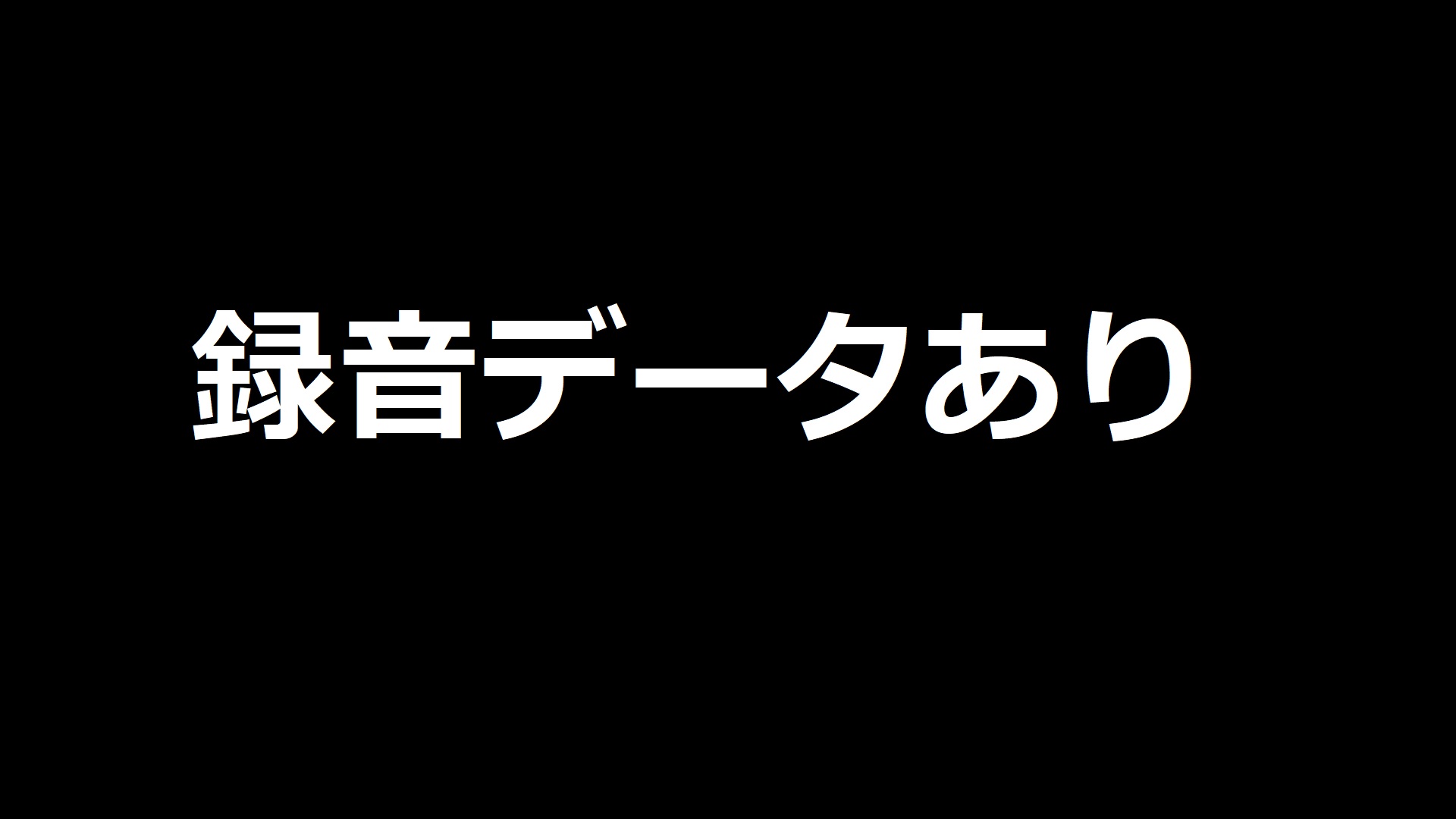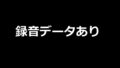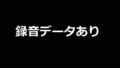事件や事故に巻き込まれた際に、人は何をどこに相談すればよいのか迷うことがある。また、保護が必要な状況と、追及すべき事件・事故の対応方法を正しく切り分けることは容易ではない。本記事では、事件・事故と保護をどのように整理し、適切な対応を取るべきかについて、実体験や法的な視点を交えながら解説する。特に、法務局や弁護士会などの相談窓口での対応を通じて得た知見をもとに、具体的なアプローチを紹介する。どのように問題を整理し、適切なサポートを得るべきか悩んでいる方にとって役立つ内容となっている。
事件・事故と保護をどう切り分けるべきか:法的対応と実体験から
- これまでは
- 保護について
- 事故(事件)について
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘禁され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
保護について
被害者は2023年2月11日から病院に行けないまでも、事件、事故、保護の件につきネットで調べ始めていた。なかなか当てはまる情報を見つけられなかったが、保護について人権の観点から、法務省の人権相談というものを見つけた。
みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)
差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局につながります。相談は、法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。
また、法務局及びその支局では、窓口において、面接による相談も受け付けています(インターネットでも相談を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。)。○受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
TEL0570-003-110
(出典:法務局HP)
実はまだこの法務省の人権相談には相談していない。理由としては、後述のインターネット人権相談受付窓口から相談フォームを使い相談したことにより完全に失念した。今後また書いていこうと思うが埼玉弁護士会の人権擁護委員会からまだ回答が来ていないことからも、この人権相談にものちのち電話をしてみようと思っている。
※2025年3月7日、電話をした。話を聞いてくれるだけ。こころの相談ダイヤルではないのだから、それでスッキリして終わりというのは”法務省”を名乗っている限り違和感しか感じなかった。
インターネット人権相談受付窓口へようこそ!
法務省の人権擁護機関では、人権相談をインターネットでも受け付けています。
相談フォームに氏名、住所、年齢、相談内容等を記入して送信すると、最寄りの法務局から後日、メール、電話又は面談により回答します。
あなたの悩みごとや困りごとについて、ひとりで悩まず、気軽に相談してください。(出典:法務局HP)
インターネット人権相談受付窓口に相談したことにより、近くの法務局からメールが来たが、「何もできない。関東管区警察局を紹介する」という内容だけであったと記憶している。その後も連絡を取ったがなしのつぶてという状況であった。
事故(事件)について
被害者は日弁連交通事故相談センターに電話をした。
公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
当センターについて 寄付について 当サイトについて 弁護士専用ページ 事務局専用ページ
0120-078325無料電話相談 平日 10:00〜19:00
日弁連交通事故相談センターは、「弁護士」が「無料」で「公正・中立」の立場で相談をうける公益財団法人です。当センターは、自動車による交通事故の民事上の法律問題に関して 1:電話相談 2:面接相談 3:示談あっせん・審査 の各事業を行っています。
当センターの6つのポイント
相談者から満足度88%と高い評価をいただいております
相談者の88%の方が「大変役に立った」もしくは「役に立った」と回答されています(令和2年度実施アンケートより)。警察や市区町村等から紹介されている安心できる相談窓口です。
当センターは、相談者の約4割(38%)の方が警察や市区町村、又は友人・知人からの紹介を受けて相談されています(令和2年度実施アンケートより)。こんなときはお気軽にご相談ください
交通事故にあったがこれから加害者とどのように交渉すればよいのか不安だ。
停車中に追突されたので責任は0:10のはずなのに、相手方の保険会社が1:9と主張してきている。納得できない。
事故の相手が任意保険に入っていなくて賠償金(慰謝料など)の交渉ができない。
相手方の保険会社が提示してきた賠償金(慰謝料など)が妥当かわからない。
相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずに困っている。
通話料・相談料無料。
月〜金の10:00〜19:00に 0120-078325へ電話をおかけください。
電話相談の詳細については、「電話相談」 のページをご参照ください。
面接相談弁護士による30分程度の無料面接相談を全国154か所の相談所で行っています。相談は原則として5回まで可能です。相談時間や予約方法等については、お近くの相談所にお電話(相談所ごとに電話番号が異なります。)にてお問い合わせください。
なお、高次脳機能障害に関する無料面接相談を本部ほか7か所の相談所で実施しています。面接相談の詳細については、「面接相談」 のページを、高次脳機能障害面接相談の詳細については「高次脳機能障害」のページをそれぞれご参照ください。示談あっせんの申込み
損害賠償の交渉で相手方と話し合いがつかないときに、当センターの弁護士が間に入り、公正・中立な立場で示談が成立するよう無料でお手伝いします。当センターではこのような示談成立のためのお手伝いを「示談あっせん」と呼んでおり、本部及び41支部で行っています。示談あっせんをご希望の方は、まず面接相談を受けていただきます。示談あっせんの申込みの詳細については、「示談あっせん・審査」 のページをご参照ください。示談あっせん
示談あっせんのお申込み後、相手方保険会社等の了承を受けたうえ、当事者双方に相談所においでいただく日時を調整します。示談あっせん当日は、当センターの弁護士が当事者双方から事情をお聞きし、適切な示談に至るよう調整を行います。示談あっせんの詳細については、「示談あっせん・審査」 のページをご参照ください。
審査示談あっせんによっても示談の合意ができない場合で、加害者がJA共済や全労済等の9共済に加入しているときは、審査の申込みをすることができます。審査では、複数人の弁護士で構成する審査委員会が適切な示談案を当事者双方に示し、被害者側が同意したときは、相手方の共済はこれを尊重することになっています。審査の詳細については、「示談あっせん・審査」 のページをご参照ください。
・電話相談は10分程度でお願いしております。
・面接相談は30分×5回まで無料です。
電話番号
03-3581-4724
住所
〒100-0013 千代田区霞が関1−1−3
弁護士会館14F(出典:日弁連HP)
被害者はこの後、まず交通事故として、日弁連交通事故相談センター、埼玉弁護士会法律相談センターの浦和と川越両方に相談をしていったと思う。
交通事故の法律相談
無料相談
埼玉弁護士会法律相談センター(浦和)※5回まで無料さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂 パークハウス1階
予約受付 : 月~金:午前9:00〜午後5:00 ※祝日を除く、
土:午前9:30〜午前11:30
相談日時 : 月~金:午後1:00~午後4:10
WEB予約 048-710-5666川越支部
川越市宮下町2-1-2 福田ビル1階
MAP
予約受付 : 月〜金:午前9:00〜午後5:00 ※祝日を除く、
土:午前9:30〜正午 午後1:00〜午後4:00
相談日時 : 水:午後1:30~午後4:00
WEB予約 049-225-4279次にあてはまる場合には、交通事故無料相談をご利用できません。
・交通事故に伴う刑事事件に関するご相談の場合
・交通事故に伴う行政処分に関するご相談の場合
・すでに代理人の弁護士を選任している場合示談あっせん
相手方と話し合いがつかない時に、弁護士が間に入り、公平・中立な立場で示談が成立するようお手伝い致します。
示談あっせんだけを申し込むことはできません。
まずは上記の無料相談を受けていただき、示談あっせんに適する事案かを弁護士が判断したうえ、適すると判断した場合に申込手続をしていただきます。示談あっせんは、現時点では埼玉弁護士会法律相談センター(浦和)でのみの実施となります。
埼玉弁護士会法律相談センター(浦和)
さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂 パークハウス1階
予約受付 : 月~金:午前9:00~午後5:00、土:午前9:30〜午前11:30
相談日時 : 月~金:午後1:00~午後4:10
WEB予約 048-710-5666埼玉弁護士会
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20
TEL.
048-863-5255(出典:埼玉弁護士会)
結果的に一番最初に電話を受けてくれた弁護士が最も適格かつ親身であったと思う。弁護士は言った「(事件)事故と保護を分けて考える様に。(事件)事故は警察に訴えかける。保護は日弁連人権擁護委員会に申し立てるように」と。この教えはずっと守り続けていたが、最後の最後、2回目の検察審査会で最後のカードとして保護を持ち出すもそれは無駄に終わった。
法テラス川越の相談も利用した。
法テラス川越
電話
0570-078313
※IP電話をご利用されている場合は、法テラス川越 (電話:050-3383-5377) へおかけください。
所在地
〒350-1123
川越市脇田本町10-10 KJビル3F
業務時間
平日 9時~17時 (土日・祝日及び年末年始を除く)
情報提供受付 平日9時~12時、13時~16時(土日・祝日及び年末年始を除く)
特に埼玉弁護士会の電話相談は、何十回利用しただろうか、どうすればいいかわからないとき、自分のおかれている状況がわからないとき、今後の見通しが立たないとき、とにかくわからないことがあったら電話をした。
「警察が動かないと弁護のしようもない」。たしかそのようなことをどの段階かは忘れたが弁護士に言われたと思う。「警察に連絡をしろ」と。
関係する法令
- 国家賠償法 第1条
- 国家賠償法 第2条
- 地方自治法 第245条の4
- 刑法 第193条
- 刑法 第194条
- 刑法 第195条
- 刑法 第197条
- 刑法 第198条
- 刑法 第258条
- 刑事訴訟法 第230条
- 行政手続法 第5条
- 行政手続法 第8条
- 行政手続法 第9条
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第1条
国家賠償法 第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、これを賠償する責に任ずる。
国家賠償法 第2条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。
地方自治法 第245条の4
普通地方公共団体は、その事務の管理及び執行に関し、法令に違反する行為があると認めるときは、是正のため必要な措置を講じなければならない。
刑法 第193条
公務員がその職務を行うに当たり、法律に特別の規定がある場合を除いて、自己又は他人の利益を図る目的で、その権限を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げたときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法 第194条
前条の罪を犯した者が、特別職の公務員であるときは、3年以下の懲役に処する。
刑法 第195条
公務員がその職務を行うに当たり、暴行又は脅迫を用いたときは、7年以下の懲役に処する。
刑法 第197条
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、5年以下の懲役に処する。
刑法 第198条
前条の罪の未遂は、罰する。
刑法 第258条
権限を有しない者が、公務員と称してその職務を行ったときは、3年以下の懲役に処する。
刑事訴訟法 第230条
何人も、犯人があったと思料するときは、告訴をすることができる。
行政手続法 第5条
行政庁は、申請に対して審査をし、理由があると認めるときは、これを許可し、又は認可しなければならない。
行政手続法 第8条
行政庁は、処分をしようとする場合において、あらかじめ相手方にその旨を通知しなければならない。
行政手続法 第9条
行政庁は、処分をする場合においては、その理由を示さなければならない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第1条
この法律は、行政機関が保有する情報の開示を求める権利を国民に保障し、その適正な実施を確保することにより、行政運営の公正と透明性を確保し、国民の理解と信頼を得ることを目的とする。
専門家としての視点
- 警察や行政機関の役割の限界と責任
- 法務局や法務省への相談対応の実態
- 弁護士との連携の重要性
警察や行政機関の役割の限界と責任
警察や行政機関は、法律の執行や市民の安全確保という重要な役割を担っているが、その対応には法的根拠と責任が伴う。警察は刑事事件を中心に活動する傾向があり、民事問題への介入は限定的とされているものの、事件性があると判断されるべき事案に対して捜査を行わない、あるいは被害届を受理しないといった行為は、職務放棄または公務員の不作為として法的責任が問われる可能性がある。行政機関についても、法令に基づいて適切な対応を行う義務があり、対応を怠った場合は地方自治法や行政手続法上の問題となりうる。単なる制度の限界として処理するのではなく、公務員による対応義務の不履行が国家賠償法第1条に該当するかを検討する必要がある。市民にとっては不満や無力感の原因となるため、制度的な限界を踏まえつつも、明確な不作為や対応の不備については法的観点からの是正が求められる。
法務局や法務省への相談対応の実態
法務局や法務省は人権問題に対する相談窓口として設置されており、差別や虐待、ハラスメントに関する相談を受ける体制を整えている。しかし、実際の対応として「関東管区警察局を紹介するのみ」「話を聞いて終わり」といった形式的対応に終始したケースでは、相談者の人権救済という本来の目的が果たされておらず、行政手続法第8条や第9条において求められる理由の通知や説明責任が果たされていない可能性がある。また、インターネット相談後に継続対応がなされなかった点についても、行政機関の職務怠慢または違法な不作為として、国家賠償法上の問題が生じ得る。名称として「法務省」を冠する機関である以上、対応の質には一定の説明責任と継続義務が求められる。法務局の対応が単なる紹介や聞き取りにとどまり、実質的な対応を拒否した場合、それは「権限を有しながら実施しない行為」であり、職務放棄として法的な評価が必要である。
弁護士との連携の重要性
問題解決において弁護士の存在は極めて重要であり、特に行政機関や警察による不作為が疑われる場合には、法的手段を講じる主体として不可欠な存在となる。弁護士は事案の全体像を整理し、民事・刑事両面からの対応を構築することが可能であるほか、行政対応が不十分な場合には国家賠償請求や告訴の準備など、実効的な手段を提案する。示談交渉や損害賠償請求、行政手続の支援などにおいても、弁護士の専門知識は不可欠である。また、行政文書の開示請求や手続義務の履行確認など、市民が個人で対応しきれない場面においても、弁護士の介入によって正当な権利の行使が可能になる。心理的負担を軽減し、制度的な壁を乗り越えるうえでも、弁護士と早期に連携を図ることは現実的かつ戦略的な選択である。
専門家としての視点、社会問題として
- 支援の断絶:制度と現実のギャップ
- 「保護」という名の隔離とその社会的影響
- 被害者の声が届かない構造の解体に向けて
支援の断絶:制度と現実のギャップ
事件や事故に巻き込まれた人々が「支援を求めるべき相手がわからない」という現実は、制度上の断絶が背景にあるといえます。警察は刑事事件に対応し、民事には介入しない、法務局は人権問題に対応するが介入権限はない、弁護士は法的対応が必要な場面で初めて動くなど、それぞれが担う役割が厳格に分かれていることは制度の安定性にとって必要である一方、現実に直面する当事者にとっては「たらい回し」の構造に映ることが少なくありません。特に「事件」か「保護」かの判断が現場レベルで曖昧である場合、警察による不当な保護措置が取られるケースも報告されており、そのような場面でどこに訴えても明確な対応が得られないことが大きな問題です。このような制度のギャップを埋めるためには、制度間の連携強化、相談体制の一元化、当事者の自己決定権を尊重する柔軟な運用が求められます。また、被害者が制度の枠組みに翻弄されることなく、自らの状況を正確に伝え、必要な支援にアクセスできるよう、専門機関側にも説明責任や対応能力の向上が求められるのです。
「保護」という名の隔離とその社会的影響
「保護」とされる行政行為が、実際には当事者の意向や実情にそぐわないまま実施される場合、それは人権上の問題をはらむ重大な事態です。特に精神的な健康や行動に関する問題を理由に保護措置がとられる際、その妥当性の判断は現場の警察官や医師に一任されることが多く、適正な審査手続や異議申し立ての余地が事実上存在しないという問題が指摘されています。保護された本人の記憶や記録が残されにくく、誰の判断によって何が行われたのかを後から検証する手段も乏しいため、不当な拘禁であってもそのままうやむやになることがあります。このような運用が続けば、「保護」という制度そのものへの不信感を社会に生み出すことになります。真に必要な支援を必要な人に届けるためにも、「保護」と「隔離」は明確に区別され、客観的かつ中立的な第三者による監査制度や情報開示の義務づけなどが急務です。人を守るはずの制度が人を傷つける道具とならないために、社会的監視の目と制度設計の見直しが求められています。
被害者の声が届かない構造の解体に向けて
事件や事故の被害者が、訴えや相談を繰り返しても制度の網にかからず、何の支援も受けられないまま放置される現実は、社会全体の構造的な問題といえます。特に加害者とされる側が公務員や大企業などの立場にある場合、情報の非対称性や組織の防衛的姿勢により、被害者の声が軽視される傾向が強まります。さらに、制度にアクセスできたとしても、そこでの対応が形式的だったり、「法律上できない」という言葉で片づけられることで、二次被害的な心の傷が残ることもあります。こうした構造を変えるには、第一に「声が届かない仕組み」がどこで発生しているのかを可視化し、制度上のボトルネックを明らかにする必要があります。第二に、各機関が持つ責任と限界を明確にし、連携する仕組みを構築すること。第三に、被害者の語りを軽視せず、記録し、継続的に支援する文化の形成です。社会が被害者に向き合う姿勢を変えることで、はじめて問題の本質に近づくことができます。「誰かが聞いてくれる」安心感こそが、制度の出発点であるべきです。
まとめ
今回の記事では、警察や行政機関の対応の限界、法務局や法務省への相談の効果とその制約、そして弁護士との連携の重要性について解説しました。警察や行政機関は法律の枠組み内でしか対応できず、その限界を認識することが必要です。法務局や法務省は、人権問題の相談窓口として重要な役割を担っていますが、直接解決に至るケースは少なく、専門的な支援が必要となる場合が多いです。こうした中で、弁護士との連携が問題解決の鍵を握ることが明らかです。弁護士は法的知識を駆使して解決策を提示し、依頼者の権利を守るために行動します。問題の本質を正確に把握し、適切な手続きを踏むためにも、早期に専門家の支援を受けることが推奨されます。これらの視点を踏まえ、多角的なアプローチを取ることが、問題の迅速かつ効果的な解決につながると言えます。