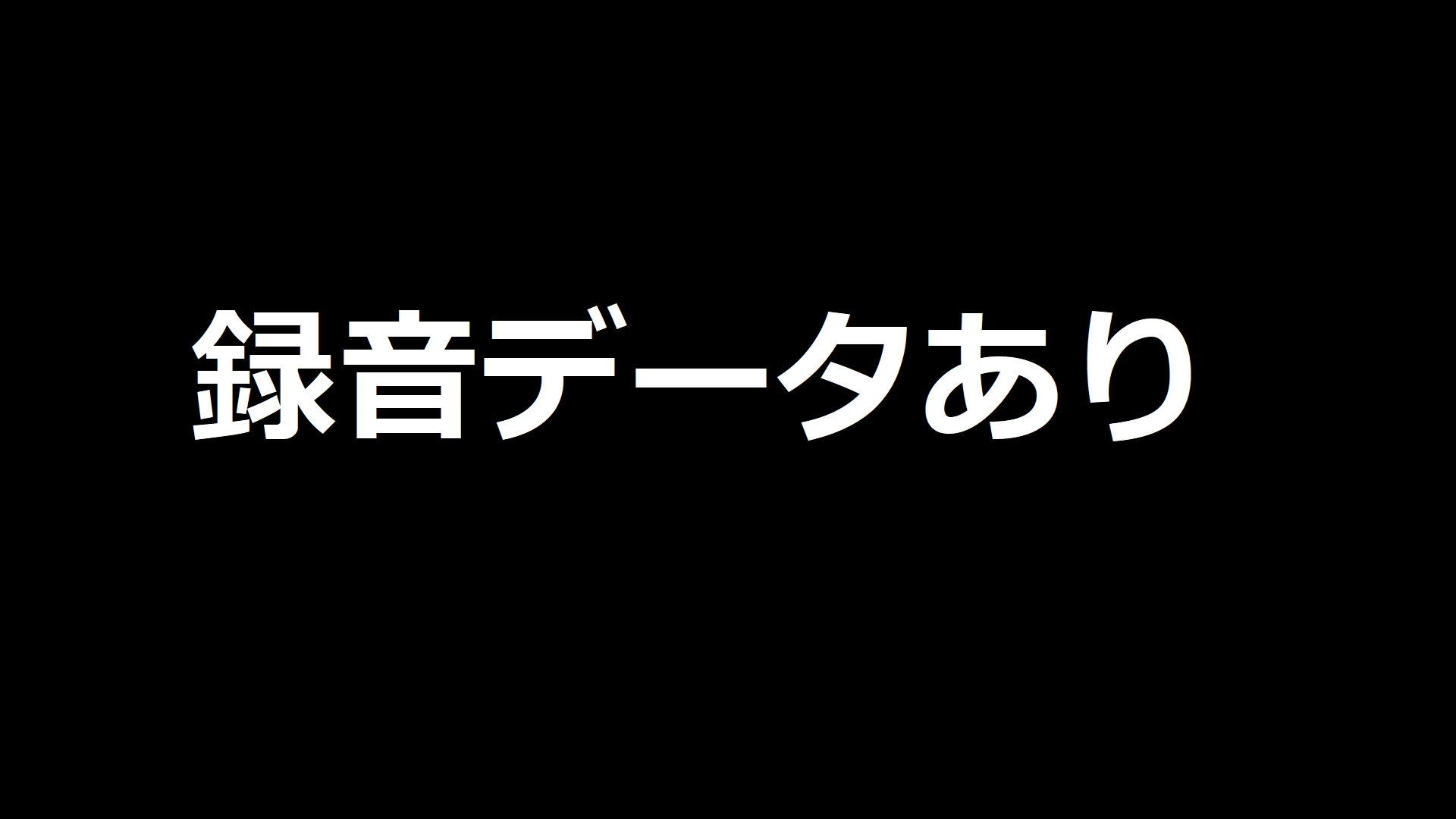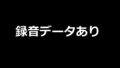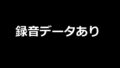鳩山町役場の課長が口にした「本人が楽になるなら、それも一つの方法だ」という発言は、単なる失言では済まされない社会的重みを持つ。これは自殺を容認する内容であり、行政職員の立場で発された以上、個人の思想ではなく制度を代表する意志として受け取られる。とりわけ精神的に追い詰められた住民にとって、その一言が引き金となる危険性は現実に存在し、社会全体が生命尊重の原則を再確認する必要がある。行政の言葉が人を追い詰めてはならない。
鳩山町役場自殺推進課?
- これまでは
- 鳩山町役場自殺推進課?
- 考察:鳩山町役場自殺推進課?
これまでは
幼少期から父のDVを受けて育ってきた。
成人してからも、パワハラやモラハラが続いていた。
社会人になり、結婚してからも、父母は家庭に介入し、家庭を混乱に陥れた。
一度は同居したものの、一年もたずに縁を切った。
やがて家庭は崩壊しかけ、そこに不本意ながら再び父母が絡んできた。
結局は離婚することになったが、さすがにそれまで人生を操られてきたこともあり、自分の人生を歩みたくて、一人で生きていこうと思った。
そこに母から「二度とそういうことは起こらないから帰って来なさい」という言葉があった。
その言葉を信用しつつも、また同じことが繰り返されるのではと警戒していた。
1年が経ち、案の定また始まった。
今回は絶対に出て行かないと心に誓っていたため、抵抗する。
抵抗に対して、父は駐在に相談した。
駐在は鳩山町役場と連携を取った。
駐在、西入間警察署、鳩山町役場は、父からの一方的な話だけで判断し、こちらの言い分を聞こうともしなかった。
鳩山町役場長寿福祉課のPSW(MHSW、精神保健福祉士)が接触してきた。
この接触は、家から出ることを促すものであり、自立支援医療の個人情報を目的外で利用するという違法行為だった。
「家を出て生活保護を受ければ、それなりの金額がもらえる」という内容だった。
すでに障害年金の受給申請は済ませており、また十分な貯金もあった。
その後の鳩山町の精神保健福祉士の行為によって、結局は父を追い出さざるを得なくなり、さらに母も出ていくことになった。
鳩山町の精神保健福祉士に不信感を抱いて関係を絶ち、その責任を追及していくと、鳩山町役場長寿福祉課長が現れた。
月に1回、半年にわたって面談を重ねるなどしたが、最終的には、それらの積み重ねを無にするような、あざ笑う態度を取った。
当時の共産党議員の仲介のもと、再び接触を続けるが、その最中・・・。
鳩山町役場自殺推進課?
話はやや遡るが、半年間にわたる面談の中で、鳩山町役場長寿福祉課長は違和感を覚える発言をした。
「孤独死とか、大丈夫か?」
背筋がぞくっとするような冷たさを感じた。
後に問い詰めてみると、さらに自殺について、
「本人が楽になるなら、それも一つの方法だ」
耳を疑った。
ここであらためて解説するほどのことではないが、個人的には尊厳死に賛成の立場だ。
無駄な延命治療は、本人にとっても、家族を含む周囲にとっても不幸でしかなく、医療機関を儲けさせるだけの行為だと感じている。
しかし、法治国家であるこの日本において、尊厳死は法的に認められていない。
法で認められていない以上、地方公共団体においても、地方公務員においても、それを是とすることは許されない。
以前、この件について他のチャンネルで言及したことがあったが、その直後、偶然のタイミングだろうか、鳩山町役場長寿福祉課が自殺予防について声明を出していた。
これは、当時の長寿福祉課長の発言が誤りであったことを、町自らが認めたことに他ならない。
さらに、この発言について忠告すべきだと感じ、電話で追及したところ、課長は非常に面倒くさそうな態度を取り、受話器に口を当てて、
「自殺しないでね〜」
と言ったのである。
完全にふざけているとしか感じなかった。
考察:鳩山町役場自殺推進課?
本件は、行政機関(鳩山町役場)の職員が、住民との継続的な面談の中で発した一連の発言と、その後の対応に関する問題提起である。特に焦点となっているのは、長寿福祉課長の発言内容と、その態度が当事者に与えた心理的影響、さらに組織としての対応姿勢である。
まず、半年間にわたる面談という継続的な関係性の中で発せられた「孤独死とか、大丈夫か?」という言葉は、明確に冷淡な発言であった。
その後の「本人が楽になるなら、それも一つの方法だ」という発言は、明らかに自殺容認の発言であり、行政職員としての発言としては極めて慎重さを欠く。
当事者は尊厳死について一定の理解を示しているが、それでもなお「法治国家である以上、行政職員がこのような発言をすることは許されない」と明確に一線を引いている点は、判断基準として妥当であると言える。
その後、当該発言を社会的に指摘した後、鳩山町役場が「自殺予防に関する声明」を出したという事実があるとされる。これは明確に問題の収拾を図ったものであり、少なくとも役場側が「自殺を容認するような言動は誤りである」と内外に示した形で、発言の問題性を認識したと見るべきである。
また、電話での忠告に対し、課長が「自殺しないでね〜」と発言した場面については、軽率さや配慮の欠如が際立っており、やり取りの中に真剣さや敬意が感じられないという印象を残している。この言動は、すでに信頼関係が揺らいでいる中での対応としては適切性を欠くと第三者からも見て取れる。
関係する法令
- 地方公務員法 第30条
- 地方公務員法 第32条
- 自殺対策基本法 第4条
- 自殺対策基本法 第6条
地方公務員法 第30条
すべての職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
地方公務員法 第32条
職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例その他の規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
自殺対策基本法 第4条
国及び地方公共団体は、自殺対策を総合的に策定し及び実施する責務を有する。
自殺対策基本法 第6条
地方公共団体は、地域の特性を踏まえて、自殺の防止及び自殺者の親族等への支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するよう努めなければならない。
専門家としての視点
- 地方公務員による自殺を容認する発言と服務規律の違反
- 行政責任者による自殺対策法令の軽視と組織的責務の不履行
- 自殺を取り巻く行政上の発言と心理的影響に関する行政倫理
地方公務員による自殺を容認する発言と服務規律の違反
地方公務員が職務中に住民に向けて発する言葉には、厳格な服務義務と倫理的責任が伴う。特に住民の生命に関わるテーマに関しては、細心の注意と配慮が求められるのは当然であり、発言の影響力は一般人とは比較にならない。地方公務員法第30条では「すべての職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」とされており、生命に関わる話題において無責任な発言を行うことはこの服務義務に明確に反する。鳩山町役場長寿福祉課の課長が述べた「本人が楽になるなら、それも一つの方法だ」という発言は、自殺を容認する発言であり、行政職員としての立場を逸脱している。地方公務員法第32条は「職員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例その他の規程に従い」と明記しており、ここに含まれる「法令」には自殺対策基本法も当然含まれる。同法第4条は「国及び地方公共団体は、自殺対策を総合的に策定し及び実施する責務を有する」と定め、第6条では「地方公共団体は、地域の特性を踏まえて、自殺の防止及び自殺者の親族等への支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するよう努めなければならない」とされている。こうした法的根拠の下では、課長の発言は法の趣旨に反し、住民の生命を守る責務を放棄したものと評価せざるを得ない。たとえ精神保健福祉士などの専門資格を有していなかったとしても、福祉行政の責任者として住民対応に当たっていた以上、専門性の有無にかかわらず、その発言は職務上の義務違反であると判断される。言葉の選択は個人の自由ではなく、公務の一環としての結果責任を伴う。
行政責任者による自殺対策法令の軽視と組織的責務の不履行
自殺対策基本法は、国および地方自治体が住民の生命を守る制度的な責務を明確に定めた法律であり、地方公共団体のすべての職員、とりわけ福祉部門の管理職にはこれに準じた行動が求められる。鳩山町役場長寿福祉課の課長が発した「本人が楽になるなら、それも一つの方法だ」という言葉は、自殺を容認する発言であり、法令に定められた行政の義務と根本的に矛盾する。自殺対策基本法第4条は「国及び地方公共団体は、自殺対策を総合的に策定し及び実施する責務を有する」と規定し、さらに第6条では「地方公共団体は、地域の特性を踏まえて、自殺の防止及び自殺者の親族等への支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するよう努めなければならない」として、住民一人ひとりに対する実践的配慮を含めた体制づくりを義務づけている。地方公務員法第32条の「法令遵守義務」と連動すれば、課長の発言は明らかに制度に違反しており、個人の価値観や見解によって正当化できるものではない。また、当該発言の後に鳩山町が「自殺予防」に関する公式声明を発表しているという事実が存在する以上、この発言が組織の方針と齟齬をきたしていたことは明白であり、職員個人だけでなく組織全体としての管理責任と内部統制の不在が問われる。さらに、長寿福祉課は高齢者・障害者・生活困窮者など自殺リスクの高い層と接点を持つ部署であるにもかかわらず、その最高責任者が自殺を容認する発言を行ったことは、該当部署全体の支援姿勢に対する住民の信頼を大きく損なう行為である。これは行政倫理以前に制度運用上の重大な違法状態を生んでおり、自治体の根幹を揺るがす問題といえる。
自殺を取り巻く行政上の発言と心理的影響に関する行政倫理
行政職員の発言は、相手が精神的に不安定な状態にある場合、想像以上に深刻な心理的影響を与える可能性がある。鳩山町役場長寿福祉課の課長が住民からの抗議に対して電話越しに「自殺しないでね〜」と冗談めかして発言したことは、公的職務の一環としての応対の範疇を完全に逸脱したものである。地方公務員法第30条では「すべての職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定されており、住民の尊厳と生命の安全を脅かすような発言は、この規定に真っ向から反する。相手が抗議の意思を持って電話をかけてきている状況下で、自殺という語を安易に冗談として用いる行為は、公共の利益を守る立場にある職員の言動として看過できない。さらに自殺対策基本法第4条および第6条は、地方公共団体に対して自殺の防止と住民支援のための施策実行を義務づけており、その趣旨に反する軽率な発言は、組織としての信頼を失墜させる。仮に課長が精神保健福祉士等の専門職でなかったとしても、福祉部署の責任者という肩書きを有する以上、発言には制度上の重みが伴い、冗談で済まされるものではない。行政行為においては、受け手の主観的な受け取り方が評価の基準となり、言葉の背景や真意は問われず、結果に対する責任が最優先される。軽率な発言が自殺の引き金となる可能性を想定しない行政態度は、重大な安全配慮義務違反であり、これは倫理ではなく制度の問題である。課長の発言はその典型であり、鳩山町役場の行政監督体制が正常に機能していなかった証拠として位置づけられる。
専門家としての視点、社会問題として
- 行政職員による無責任な発言がもたらす自殺リスクの増幅
- 地域社会における行政不信とメンタルヘルス制度の崩壊
- 制度内権力の乱用と住民の生命権軽視が生む構造的暴力
行政職員による無責任な発言がもたらす自殺リスクの増幅
行政職員の言動は、その立場に伴う権威性によって住民に強い影響を与えるが、それが命に関わる領域に及ぶ場合、その影響力は社会的なリスクとして顕在化する。鳩山町役場長寿福祉課の課長による「本人が楽になるなら、それも一つの方法だ」との発言は、自殺を容認する発言であり、ただの個人的感想や失言として処理されるべきではない。このような言葉が、社会的に弱い立場にある住民、特に精神的な危機にある者に向けられた場合、それは直接的に自殺リスクを増幅する加害性を帯びる。厚生労働省の自殺対策大綱では、すべての関係者が当事者の「生きる力を支える」姿勢を貫くことが求められており、公的機関の職員がそれに逆行する発言を行った事実は、制度の理念そのものに反している。自殺の要因は多岐にわたるが、その決定的引き金となるものの一つに「社会的な否定」「信頼の崩壊」がある。行政職員の言葉がその両方を内包していた場合、それは国家や社会からの否定と同義になりかねない。地域において、住民は行政に対して一定の信頼を前提として生活しており、その信頼のもとに相談や面談が成立している。そこで発された自殺容認発言は、事実上の精神的追い込みとして機能する可能性がある。さらに、こうした発言に対して何ら是正措置が講じられず、謝罪もなされず、懲戒も行われないとするならば、それは単なる一個人の問題を超えて、行政組織全体が自殺対策という社会的責任から逸脱していることを意味する。つまり、この問題は職員個人の資質の問題ではなく、公務組織が持つ構造的な鈍感さと安全配慮の欠如が生んだ結果であり、社会全体の生命保障に対する意識の低さが露呈した象徴的な事例である。
地域社会における行政不信とメンタルヘルス制度の崩壊
メンタルヘルス支援体制は、行政による住民支援の中核をなすべき領域であるにもかかわらず、実際の現場ではその理念と現実の乖離が極端に大きく、特に地方行政においてはその傾向が顕著である。鳩山町役場長寿福祉課の課長による自殺を容認する発言は、住民の精神的安全を破壊するものであり、制度的には支援体制の根幹を崩壊させる内容を含んでいる。自治体は住民に最も近い公的機関であり、そこに所属する職員の言動は、他の何よりも直接的に住民の信頼形成に影響する。信頼が損なわれた制度は、制度として機能しない。自殺リスクの高い者が相談する先として行政が機能しないとき、その人々は孤立し、孤立の果てに選択肢を失うという流れはすでに幾度も社会問題として顕在化している。にもかかわらず、行政の現場では言葉の重さや影響についての教育が極めて乏しく、対人対応の訓練も不十分であるケースが少なくない。そのような中で、課長という管理職にある者が、支援対象者との対応の中で発言すべきでない言葉を口にしたことは、住民のメンタルヘルスに対する行政の姿勢が形骸化していることを強く示している。厚労省のガイドラインや自殺総合対策大綱に照らしても、こうした言動は明らかに逸脱行為であり、是正の対象であるにもかかわらず、組織内で黙認され、処分も行われなければ、それは組織ぐるみの責任放棄である。住民からすれば、支援機関において命の問題が軽視されていると知った瞬間に、どのような支援の枠組みも信用することはできなくなる。これは単なる「不適切発言」ではなく、地域社会全体に対する制度的裏切りである。
制度内権力の乱用と住民の生命権軽視が生む構造的暴力
現代における構造的暴力の一形態として、制度内部の権力を持つ者が公的地位を利用して弱者に対し精神的・社会的損害を与えるという事例が増加している。鳩山町役場長寿福祉課の課長による「本人が楽になるなら、それも一つの方法だ」という発言や「自殺しないでね〜」という発言は、その軽薄さだけが問題なのではなく、制度内の権限を帯びた立場にある者が住民の生命権を軽視する言動を繰り返したことに本質がある。制度の中にいる者が、制度を背景にして非制度的なメッセージを送り出すとき、その被害は個人の主観や感情を越え、構造的抑圧として機能する。行政の職員がその地位に基づいて発言する言葉は、私人としての発言ではなく、制度の意志として受け取られるため、それが自殺を容認するものであれば、それは制度が住民の死を選択肢として黙認したと解釈されても当然である。社会において命の価値を左右できる立場にある者が軽率な発言をすることは、直接的暴力よりも深く、かつ長期的に影響を及ぼす。しかもこのような事例が何ら是正されず、行政機関内で処理されないとき、その暴力は制度の中に定着し、繰り返される土壌を形成する。住民は制度から守られるべき対象であるにもかかわらず、制度の中で傷つけられる現実がある限り、制度の正当性自体が根底から崩れるのである。これは教育や倫理の問題ではなく、構造として修復不可能な暴力の常態化を意味している。問題は一職員ではなく、制度がそれを放置していることにある。
まとめ
行政職員による「自殺を容認する発言」は、個人の言葉として済まされるものではなく、制度の信頼を根底から揺るがすものである。特に福祉を担当する部署の管理職が発言した場合、それは行政機関が住民の生命権を軽視したと受け取られ、地域社会に深刻な不信と心理的ダメージを残す。発言の背後には、専門的な教育の欠如や組織内の安全配慮体制の未整備といった構造的な問題が潜んでおり、これは個人の資質の問題ではなく、制度の構造そのものに内在する暴力性と鈍感さに起因している。住民の命を守るはずの行政が、逆にその命を危うくする言動を放置するようでは、行政の正当性も機能も根底から破綻していると言わざるを得ない。