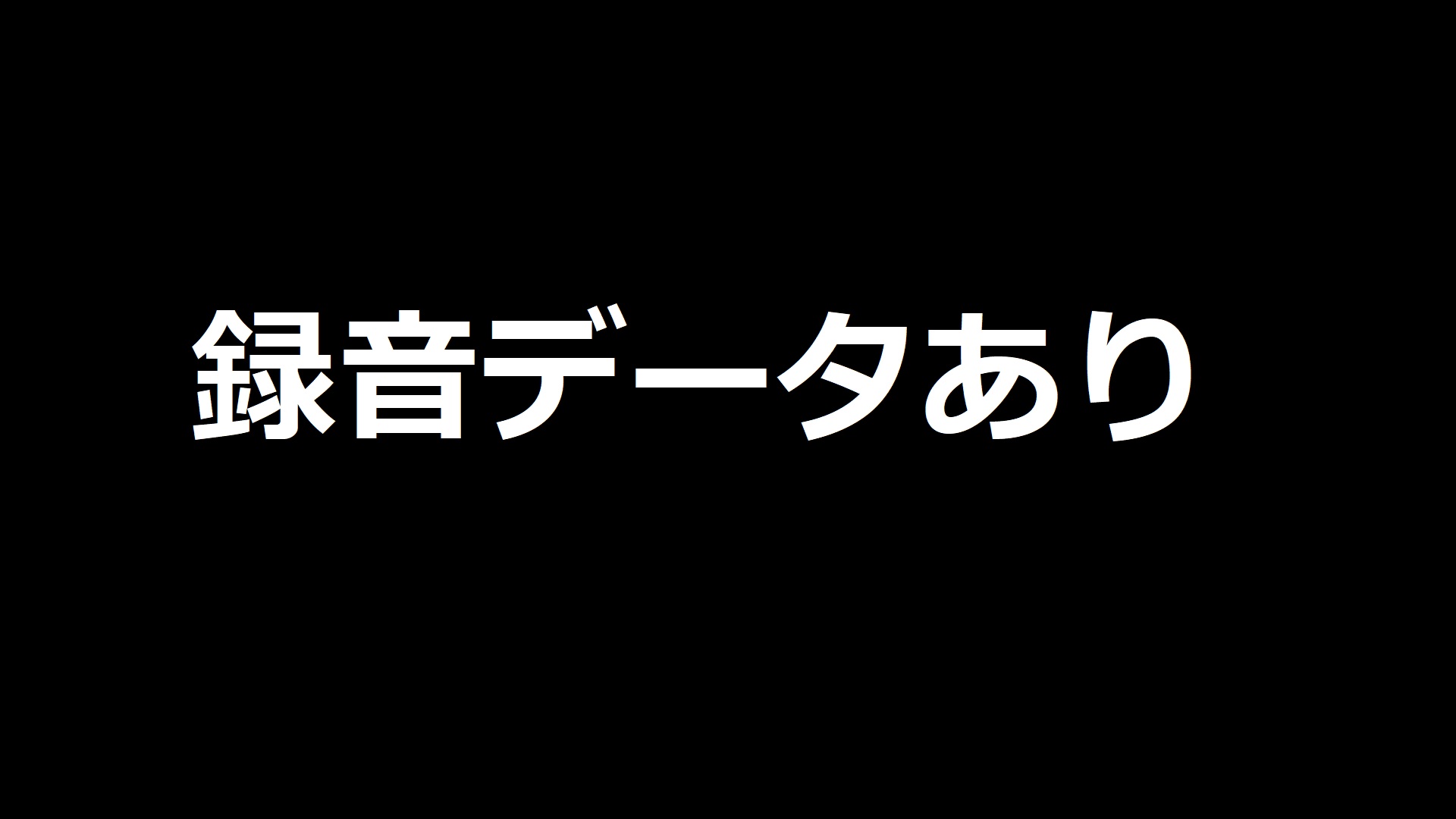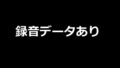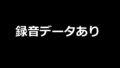警察による保護措置は、本来ならば明確な法的手続きと医学的根拠に基づいて慎重に実施されるべき制度である。しかし、現場の警察官が主観的な判断により実質的な拘禁を行う事例が存在し、それが適正手続や人権の保障を損なう危険性をはらんでいる。本記事では、東松山警察署生活安全課の対応を具体例として取り上げ、警察官職務執行法や精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との照合を通じて、制度運用の問題点と社会的影響について検証する。
東松山警察署生活安全課K氏
- 保護のためにいたのでは?
- 保護時のやり取り
- 保護は脅しの手段か?
保護のためにいたのでは?
パトカーで東松山警察署に到着した際、玄関に立っていたのは生活安全課のK氏であった。目立つ制服を着ており、背も高かったため、その姿は記憶に残りやすかった。この印象操作のような状況は、後に警察が保護を脅しの手段として使っていると感じさせるものだった。次にK氏が現れたのは、聴取室であった。そこでは、2人の刑事による事情聴取が行われていたが、聴取中に聴取室の入り口のドアは開けられており、その外をK氏が行ったり来たりして歩いているのが非常に気になった。
保護時のやり取り
最初にK氏と対面した時期については記憶が定かではないが、音声データによると、保護された後、2階の保護室に向かう途中であると思われる。そこで、被害者はK氏に対して次のように話しかけた。「これからどうなるんですか?一体、何なんですか?」
K氏はこう答えた。「お話ししている内容が、あのお話ししている内容が、自傷他害の恐れがあるということで、実際、今日お会いしたご老人の車にも手を○○ということで、一応保護という形で、まずここで休んでいただきます。それで、保健所さんの方に連絡させていただいて、保健所の職員さんとお話し…」
被害者が尋ねた。「保健所って、どこの保健所ですか?」
K氏は答えた。「ここは東松山警察署なので、東松山の保健所になります。」
被害者はさらに尋ねた。「いつですか?」
K氏は言った。「今日中に来れるんだったら、今日中に。保健所さんの都合もあるので、今日中に夜の間に来れるなら夜の間に、無理だったら明朝になります。」
廊下をそのまま一番奥まで進むと、そこにK氏が立っていて金属探知機を持っていた。被害者は金属探知機を見たことがなかったので、スタンガンか何かと思い、少し恐怖を感じた。被害者が「それは何ですか?」と尋ねると、K氏は「金属探知機です。体の中に金属が入っていないか確認します」と答えた。K氏と対面したのはそれが最後であり、事件当日及び翌日にK氏を見ることはなかった。
保護は脅しの手段か?
事件後、被害者は東松山警察署の交通課の係長に頻繁に連絡を取っていたが、ある時、保護の話をすると、係長に伝えていないにもかかわらず、K氏から被害者のスマホに直接電話がかかってきた。K氏はにこやかな雰囲気で、丁寧な話し方で被害者に言った。「あの時の私です。あの制服の私です。金属探知機を当てた私です。」丁寧でにこやかであっても、それは保護を盾にした脅しだと被害者は感じた。振り返ると、K氏は玄関に非常に目立つフォーマルな制服を着て立っていたり、聴取室の外でうろうろと歩いていたり、金属探知機を使ったりし、とても強く印象を焼き付けていた。どんなに丁寧に、にこやかに話しかけていても、その行動は、「保護というものが怖いだろ?」と脅されているようにしか感じなかった。被害者はこのタイミングが一番適切だと感じ、録音データの存在をK氏に伝えた。すると、K氏は絶句した。
関係する法令
- 警察官職務執行法第2条
- 警察官職務執行法第6条
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条
- 憲法第31条
- 民法第709条
- 刑法第194条
警察官職務執行法第2条(職務質問)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯人を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者を停止させて質問することができる。
警察官職務執行法第6条(保護の措置)
警察官は、精神に異常のある者であって、自分の保護者の監護に属しない者又は保護者が不明な者が、自分の行為によって他人の生命、身体又は財産に害を及ぼすおそれがあると明らかに認められるときは、その者を一時保護することができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条(警察官による通報)
警察官は、精神障害者であると思われる者が自傷他害のおそれがあると認めたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条(医師の診察)
通報を受けた都道府県知事は、精神保健指定医にその者の診察を行わせなければならない。
憲法第31条(適正手続の保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
民法第709条(不法行為)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
刑法第194条(特別公務員職権濫用罪)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
専門家としての視点
- 警察官による保護措置の判断における要件不備
- 保護行為に伴う適正手続の欠如と憲法違反の可能性
- 心理的威圧による不法行為構成と損害賠償責任
警察官による保護措置の判断における要件不備
警察官職務執行法第6条においては「精神に異常のある者であって、自分の行為によって他人の生命、身体又は財産に害を及ぼすおそれがあると明らかに認められるとき」に限り、警察官は一時保護を行うことができると規定されている。また精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条においては、警察官は「精神障害者であると思われる者が自傷他害のおそれがあると認めたとき」には、都道府県知事に通報しなければならないとされている。さらに第29条では通報を受けた都道府県知事は精神保健指定医に診察を行わせる義務がある。これらの法令の文言に共通しているのは、いずれも「明らかに認められる」「認めたとき」といった客観的で根拠ある判断を前提としており、警察官個人の主観的な印象や憶測による判断では不十分であるという点である。本件においては、被害者の発言や行動に対してK氏が「自傷他害の恐れがある」と判断したものの、それに医学的な裏付けや客観的診断がなされた記録はなく、警察署到着時にはすでに保護の結論ありきの対応がなされていた可能性がある。このような経緯は一時保護の法的要件を満たしておらず、仮に被害者が精神障害を有していなかった場合、その一時保護行為は違法となる可能性が高い。したがって、本件は職務執行法及び精神保健福祉法に基づく一時保護の運用要件を逸脱しており、判断の妥当性と手続の正当性が問われるべき事案である。
保護行為に伴う適正手続の欠如と憲法違反の可能性
日本国憲法第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と定め、国民の自由を制限する際には適正手続(due process)を保障している。警察官による一時保護措置であっても、その実態が拘禁・隔離に該当するものである以上、個人の自由を奪う処分として憲法31条の制約を受ける。さらに一時保護の手続に際し、医学的診断を欠いたまま実施された場合、精神保健福祉法第29条の規定に違反することになり、制度上保障されている専門的評価と公的判断を経た上での処遇という枠組みが無視されたことになる。これにより、被害者は事実上、法的根拠のないまま行動の自由を奪われた状態に置かれたことになり、実質的な違法拘禁に相当するおそれがある。また、一連の手続において適切な説明がなされていなかった場合、自己決定権及び人格権の侵害ともなり得るため、単に手続的瑕疵ではなく、憲法上の人権侵害としても重大な問題を含んでいる。保護という名目の下であっても、法的根拠のない身体的拘禁や施設への隔離が行われた場合には、その処分は違法とされるべきであり、被害者の人身の自由を侵害した警察官に対しては、国家賠償請求や違憲確認の対象となる可能性が生じる。
心理的威圧による不法行為構成と損害賠償責任
警察官の行動が一見丁寧であっても、その態度や言動が被保護者に対して強い心理的威圧を与える内容であった場合、民法第709条に基づく不法行為が成立しうる。709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、損害を賠償する責任を負う」と定める。本件では、K氏が玄関で目立つ制服姿で立ち続けたり、聴取室の外を徘徊したり、金属探知機を突きつけたり、さらには後日、私的に電話をかけてきて過去の行動を蒸し返すような発言を行っている。これらは一連の保護措置の延長としてだけでなく、被害者に対する威圧と受け取られ得るものであり、精神的苦痛を与えたという意味で人格権侵害に該当する。特に、金属探知機に関しては事前説明を行わず、被害者が「スタンガンかと思った」と感じるほど不安を抱かせた点において、説明義務違反と評価される余地がある。さらに、交通課係長とのやりとりの中で本人が何も伝えていないにも関わらず、K氏が被害者に直接電話をしてきたことは、個人情報の不適切な利用の問題にも関係し、職務上得た情報を職務と無関係に用いたとされれば、刑法第194条(特別公務員職権濫用罪)の構成要件に該当する可能性もある。このように、形式上は丁寧な対応であっても、実質的には強制性を帯び、相手の自由意思を著しく侵害する行動であった場合には、不法行為が成立し得ることになる。
専門家としての視点、社会問題として
- 保護制度の濫用がもたらす人権侵害の拡大
- 警察行政による市民監視の常態化
- 精神障害とされるリスクの社会的悪用
保護制度の濫用がもたらす人権侵害の拡大
保護措置の制度は本来、本人の安全と周囲の平穏を守る目的で設けられているが、その運用が曖昧であったり、恣意的に拡張されることで重大な人権侵害が生じる危険がある。特に警察官が現場での主観的な判断に基づいて「自傷他害の恐れがある」と断定し、強制的に保護する場合、その判断基準が公開も検証もされないまま行使されているという構造的欠陥が存在する。これは「明らかに認められるとき」という警察官職務執行法第6条の文言の曖昧さにも起因し、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条で想定されるような専門的判断や通報義務が軽視されている実態とつながっている。精神保健指定医の診断を経ずに現場の警察官が単独で保護に踏み切ることは、正当なプロセスを経ない拘禁に等しく、これは憲法第31条の適正手続保障にも反する。制度としては限定的な適用が想定されているはずの「保護」が、運用面では日常的に濫用されている場合、社会的には黙認されているが実質的な人権抑圧である。こうした傾向が放置されると、警察による保護が形式的には合法でも実態は不当拘禁という事態を招き、警察組織の自浄作用が働かない限り、被害者が記録や録音を残していなければ真相が闇に葬られる構図が常態化する。保護制度の趣旨を守りつつも、運用実態を透明化し、恣意的な適用が一切排除される仕組みの再設計が求められている。
警察行政による市民監視の常態化
警察による保護措置の行使が、治安維持という目的を超えて市民の行動規制や思想統制の手段として利用される可能性が指摘されている。たとえば、特定の人物が行政や制度に異議を唱えたり、違和感を持つ発言を行った場合、その発言内容を「不穏」「危険」「異常」と評価して記録に残し、以後の監視対象として扱う流れが制度的に構築されているとすれば、それは治安維持の範疇を逸脱した政治的・思想的な管理である。このような傾向は、被害者のように繰り返し110番通報を行っていた者に対して「通報履歴が多いから精神的に不安定である」「トラブルに巻き込まれやすい人物である」といったレッテル付けをし、それをもって保護の根拠とするケースに顕著である。問題なのは、この判断が本人への情報開示もなく、行政文書としての記録やその評価基準も一切知らされないまま進行する点にある。つまり、市民は自らがいつ監視対象とされ、どのように分類され、何を基準に保護対象とされるのかを知ることができず、防御手段を持たないという状況に置かれるのである。これは民主主義社会における情報公開制度と矛盾し、基本的人権のひとつであるプライバシー権・自己決定権の侵害にも直結する。警察行政における「記録」「監視」「保護」措置は、それぞれが独立した権限ではなく、連動しているからこそ、その正当性と透明性がより厳しく問われるのである。
精神障害とされるリスクの社会的悪用
社会において精神障害が疑われるという評価は、時にその本人の自由を制限し、社会的信用を失わせる重大な烙印として機能してしまう。その評価を警察が一方的に下す構造が存在する場合、精神障害者としてのラベリングは保護という名のもとに拘禁や排除の正当化に使われてしまう危険がある。これは障害者権利条約が定める「平等の原則」「偏見や差別の禁止」にも反し、国際的な基準から見ても著しく後退した対応である。また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条では、警察官による通報義務が明記されているが、その後の医師による診察(第29条)や適正な手続きが形骸化している場合、それは精神障害の評価を「権力による都合の良い手段」に転化させていることを意味する。さらに、対象者が実際には精神疾患を有していないにもかかわらず、過去の言動や行政への苦情、近隣とのトラブルといった要素をもとに精神的に不安定と断定される事例も報告されており、これは明確に社会的差別の構造である。精神障害を理由とする拘禁が行政側の不都合や責任回避に使われるようになると、その制度全体が信頼性を失い、真に支援を必要とする人々への制度的支援が機能不全に陥る。精神的異常の判断は極めて専門的かつ慎重であるべきであり、それを非専門家である警察官が独断的に行うことを許容する構造自体が、社会的に再検討されるべき重大な制度問題である。
まとめ
警察官による保護措置は本来、緊急かつ正当な理由に基づいて一時的に行動の自由を制限する制度であるが、現場判断に委ねられることで恣意的運用の余地が生じている。本件では、東松山警察署生活安全課K氏による保護措置が、医学的判断や客観的証拠を伴わないまま実施された疑いがあり、その手続きは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条および第29条の趣旨に反していた可能性がある。さらに、制服姿での出迎え、聴取室前での徘徊、金属探知機の提示、録音後の沈黙、直接の私的電話などの一連の行動は、心理的圧力を通じて被害者の抵抗を抑えようとする意図が疑われる。こうした対応は警察官職務執行法第6条の運用を逸脱しており、適正手続を保障する憲法第31条に照らして重大な問題を含む。保護の正当性が問われる場面においては、主観ではなく明確な手続きと客観的根拠に基づく判断が強く求められる。