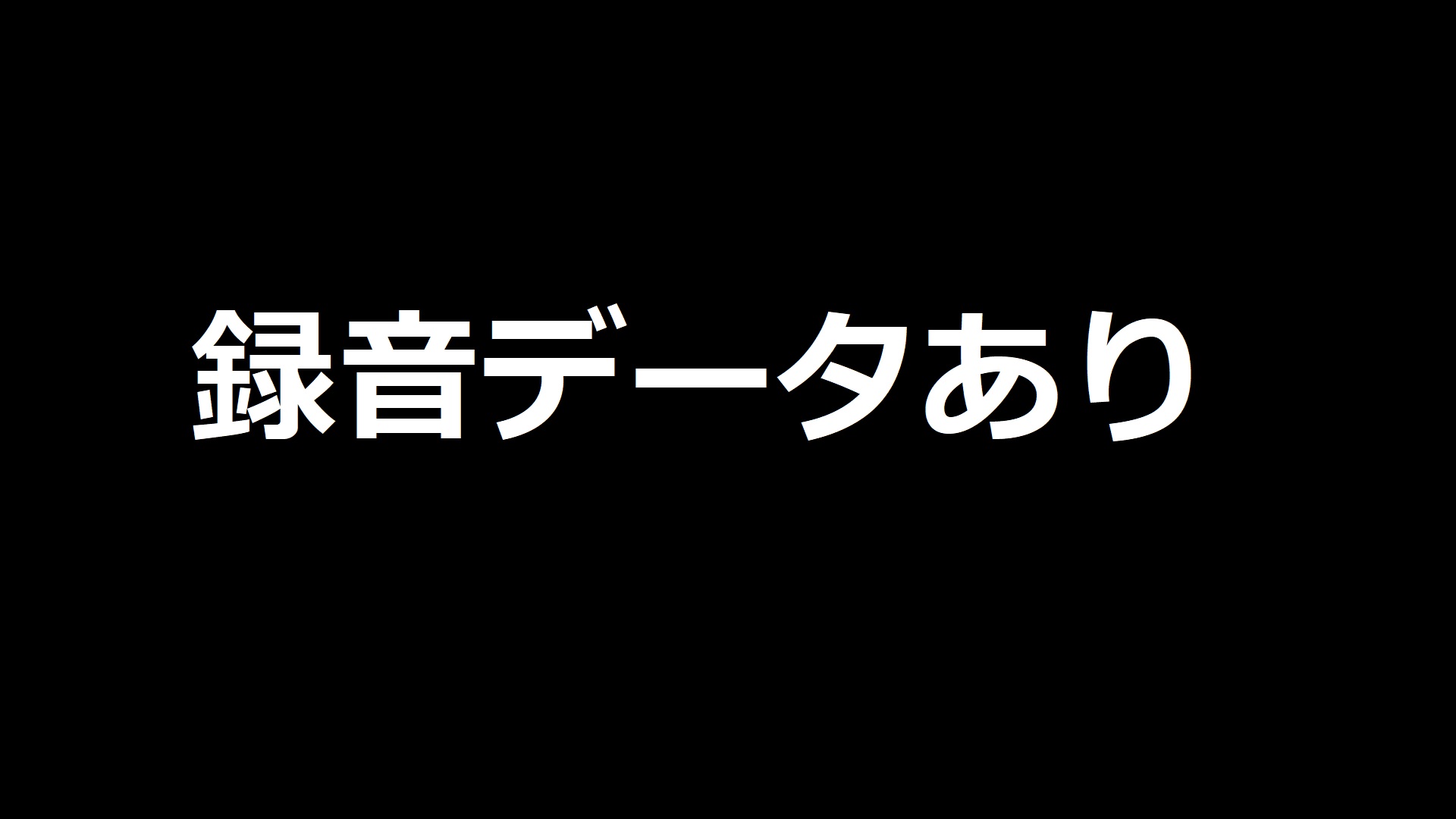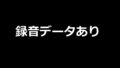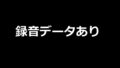警察による取り調べや事件対応において、被害者の訴えが無視され、逆に加害者の立場が優先されるような状況が実際に起きている。特に、長期間にわたる嫌がらせの訴えが軽視され、事件当日の行動だけを切り取って判断されることで、本来守られるべき市民の権利が踏みにじられる例もある。本記事では、東松山警察署の対応をもとに、取調べにおける中立性の欠如や、捜査判断の正当性、さらには組織的な責任の所在について検証し、なぜこうした事態が起こるのか、何が制度として問われるべきなのかを、具体的な発言や行動の記録を交えて明らかにする。
これまでは
2023年2月9日。
4年間にわたり、鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人からの嫌がらせが続いた末に事件が発生した。ひき逃げ事件の被害者として東松山警察署へ向かうパトカーの中で、スマートフォンの録音を開始。事情聴取の最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者は18時間にわたり拘禁され、翌日、措置入院の判断を目的に2つの病院で診察を受けたが、精神病院への入院には至らず解放された。
事情聴取の最中、東松山警察署I刑事は話の展開を強引に180度転換させようとする。
被害者を加害者に、加害者を被害者に。
被害者の主張はこうだ。
・事件には原因と前提、経緯がある
・ひき逃げである
・前提として嫌がらせがあるのだから正当防衛には当たらない
・警察が嫌がらせ通報に対して対応しなかった
・犯人は何かを隠しているから逃げた
東松山警察署I刑事の主張はこうだ
・事件はまっさらに起こるのである
・事件はその日、その時だけのことで判断すべきである
・犯人は相手に怪我を負わせても普通逃げるのであり、それはひき逃げではなく正当防衛だ
・警察署が違うと状況はまったくわからない
・警察署が違っても警察の対処は評価できる
4年間にわたる犯人の嫌がらせを受け、4回目の嫌がらせとなった事件時、動画を撮ろうと被害者は犯人のクルマに近づいた。犯人は余裕綽々にニヤつきながら運転席のパワーウィンドウをいっぱいに下げた。会話のあと、逃げる雰囲気を感じた被害者は、今後の嫌がらせの継続を防ぐために、クルマを発進させることを防ぐ目的で運転席の窓に手を入れた。犯人はクルマをフルスロットルで急発進。被害者の左手は運転席に引っかかり10メートル以上引きずられる。なんとか左手を抜き出したものの転倒し負傷。犯人の逃げ去る先はコンクリートで囲まれた、狭い電車の高架橋の下道であった。あのまま左手を抜くことができなければ・・・。
動画化:事件は”まっさら”に起こる
考察:事件は”まっさら”に起こる
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人本人による4年間にわたる嫌がらせの末に、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ搬送されるパトカーの中で、スマートフォンによる録音を開始する。だが事情聴取の場で待っていたのは、「保護」という名目による一方的な拘禁だった。身に覚えのない対応により18時間もの間拘禁され、翌日には措置入院の可否を判断するために2つの病院で診察を受けることとなる。精神病院への入院は必要ないと判断され、ようやく解放された。
取り調べの場では、東松山警察署のI刑事が強引に話の流れを反転させようとした。被害者が加害者であり、加害者こそが被害者であるかのように、事件の構図そのものを180度書き換えようとしていた。被害者は、この事件には明確な原因と前提、そして長期にわたる経緯が存在していること、そもそもこれはひき逃げ事件であること、さらに正当防衛には該当しない背景として日常的な嫌がらせの事実があることを主張した。また、これまでの通報に警察が対応してこなかったこと、そして犯人が逃走した理由は何かを隠していたからだという点も挙げていた。
しかし、I刑事は真逆の論理を展開する。事件は過去の因縁とは無関係に、まっさらに起こるものであるという立場をとり、その日の出来事はその日の文脈だけで判断されるべきだと主張した。さらに、相手に怪我を負わせた場合、人は普通逃げるものであり、それはひき逃げではなく正当防衛だとも述べた。警察署が異なれば状況は把握できないという立場をとりながらも、それでも警察の対応は評価できるのだと話をまとめた。
事件当日、4回目となる嫌がらせを受けた被害者は、犯人のクルマに近づき、動画を撮影しようとしていた。犯人は余裕の表情を浮かべながら運転席のパワーウィンドウを全開にした。短い会話ののち、逃走の気配を察知した被害者は、これ以上の嫌がらせを止めるために車の発進を阻止しようと考え、運転席の窓に左手を差し入れた。だが犯人はそのままアクセルを踏み込み、車を急発進させた。被害者の左手は運転席に引っかかり、10メートル以上引きずられた末に、ようやく手を引き抜いたものの、転倒して負傷した。逃走する車は、コンクリートに囲まれた狭い電車の高架下の道へ消えていった。あのとき、左手を抜くことができなかったらどうなっていたかは、想像に難くない。
専門家としての視点
- 刑事訴訟における取調べの中立性と誘導の限界
- 交通事故と故意の衝突における傷害罪の境界線
- 正当防衛の要件無視による捜査判断の違法性
刑事訴訟における取調べの中立性と誘導の限界
刑事訴訟法第197条は、捜査機関が犯人があると思料するときに捜査を行う権限を認めているが、これはあくまで事実に基づく客観的な疑いに限られ、恣意的な判断に基づいてはならない。また、同法第198条においても、取調べは必要があるときに限られ、取調べの手法が任意性を欠き強制的または誘導的である場合には違法性を帯びる。特に被害者とされる者に対して、明確な証拠もないまま加害者であると断定し、被疑者と同様に扱う取調べは、中立性の欠如を意味する。このような行為は、国家公務員法第98条の「法律又は命令を遵守し」職務を遂行する義務にも違反しうる。また、同法第99条が禁じる「信用を傷つける行為」に該当する可能性もある。加えて、取調べの過程において意図的に前提事実(たとえば嫌がらせの継続や通報歴)を無視し、それを事実として取り上げることを拒むような態度は、捜査の適正性を損なう。取調官は事実関係を公平に把握し、すべての背景を踏まえた上で判断しなければならず、過去の経緯を排除する姿勢は、刑事司法制度全体の信頼性を揺るがすものである。特に本件のように被害者が長期にわたり被害を訴えてきたにもかかわらず、その内容に一切耳を傾けず、むしろ加害者の立場を先に肯定するような発言を重ねることは、取調べの名の下に行われる不当な心理的圧迫と見なされる危険がある。捜査は一方に肩入れすることなく、証拠と証言を精査したうえで進められるべきであり、誤った誘導が最終的に虚偽の供述や不当な処分につながることは過去の判例にも見られる通り、厳しく戒められるべきである。
交通事故と故意の衝突における傷害罪の境界線
刑法第204条は「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」と明記しており、自動車の運転によって他人に怪我を負わせた場合でも、明確に故意または未必の故意が認定されればこの条文が適用される。また、刑法第208条の2では、危険運転致傷として「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を負傷させた者は、十五年以下の懲役に処する」とされているが、同様に極端な過失や著しい不注意も危険運転の範疇に含まれうる。今回の事案において注目すべきは、運転席の窓に人の手が入っていると知りながら、車両をフルスロットルで急発進させたという行為が、明らかに通常の過失運転を超えて危険運転、さらには故意の傷害に接近するものであるという点である。加えて、道路交通法第72条では交通事故が発生した際には「直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護する義務」が課されており、引きずった上でそのまま走り去った行為は明確にこの義務に反している。警察がこのような重大な身体的被害を伴う事件において、運転者の意図を問わず「逃げるのは普通」と発言した場合、その判断の基準自体が法令に反している可能性が高く、組織としての中立性を損ねるだけでなく、故意性を軽視する姿勢が司法判断に重大な偏りをもたらす懸念がある。故意性の有無は被害者の行動ではなく、加害者の選択と状況認識により判断されるべきであり、その場において運転者が危険を予見しながらも実行に移したならば、結果的に重大な刑法上の責任を問われることは避けられない。
正当防衛の要件無視による捜査判断の違法性
刑法第36条は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」として正当防衛を認めているが、これには三つの要件が必要である。すなわち急迫性、不正性、そして防衛の必要性と相当性である。仮に加害者が正当防衛を主張するにしても、それが成立するためには、被害者からの侵害が直ちに暴行に至る明確な危険があったか、逃れる以外に手段がなかったか、またその行為が過剰でなかったかを厳密に判断しなければならない。運転席に手を差し入れた行為があったとしても、それが急迫な不正の侵害であったとは直ちに言い切れず、また車両を急発進させるという反応が相当であると見なすには無理がある。したがってこの場面において正当防衛を一方的に認定する捜査判断は、法的要件を満たしていない段階で結論を下しており、刑事訴訟法第197条に定める適正な捜査義務に違反する。また、このような不適切な判断を示す発言を公務員が行うことは、国家公務員法第99条に違反するおそれもある。刑事手続において正当防衛が主張される場合、その判断は慎重に事実関係を精査したうえで司法機関によって行われるべきであり、捜査段階で一方的に認定されるべきではない。警察官の主観や印象に基づく断定が捜査に影響を与えた場合、その結果は被害者の権利を大きく損なうことになり、法の下の平等と適正手続の原則が形骸化する危険性を伴う。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察官による事実の歪曲がもたらす市民不信と制度の空洞化
- 「加害者優位」の構図が作られる社会的背景と行政機関の責任
- 長期的嫌がらせの軽視が引き起こす構造的暴力の固定化
警察官による事実の歪曲がもたらす市民不信と制度の空洞化
警察官が取り調べの場において意図的に事実関係を歪曲し、加害者と被害者の立場を逆転させるような対応を行った場合、それは単なる個人の不正ではなく制度全体への信頼を揺るがす重大な社会問題である。市民は警察に対して事実を公平に取り扱う機関としての期待を抱いており、その期待が裏切られたと感じたとき、通報行動や被害申告そのものが萎縮され、正義の実現から市民が自ら遠ざかることになる。特に加害者が日常的な嫌がらせを繰り返していた事実が存在し、その経緯が警察に伝えられていたにもかかわらず、それを無視したまま「事件はその場で起きた一過性のものである」とするような捜査判断がなされた場合、それは国家公務員法第99条に定める信用失墜行為に該当する恐れがある。加えて、刑事訴訟法第197条に基づき、捜査は犯人の存在を疑うに足る状況に対して行われるべきであるが、被害者が繰り返し警察に対して被害を申し出ているにもかかわらず、それを一顧だにしない姿勢は捜査機関としての職責を放棄した行為であると評価されてもやむを得ない。こうした対応が可視化されず、記録にも残らない場合、被害者は声を上げるすべを失い、制度外の手段に訴えざるを得ない状況に追い込まれる。このような連鎖が進行すれば、警察が市民からの信頼を失い、ひいては法治国家としての根幹が揺らぐことになる。事実を曲げることは一時的には捜査を「都合よく」進めることになるかもしれないが、その代償として法の下の平等と公正が損なわれ、社会の秩序がじわじわと崩壊していく。市民の安全を守るべき組織が、自ら不正義の温床になることがあってはならない。
「加害者優位」の構図が作られる社会的背景と行政機関の責任
被害者が継続的な嫌がらせを受けていたにもかかわらず、その訴えが警察に黙殺され、逆に加害者側の主張や立場が一方的に採用されるという構図は、単なる個別の判断ミスではなく、行政組織の構造的な問題を反映している。こうした加害者優位の対応が起こる背景には、担当職員や組織内における責任回避の文化、統計的な処理重視、あるいは被害者の発言の「信頼性」を恣意的に判断する偏見などが存在することが多い。また警察署が違うという理由で、過去の通報歴や被害報告が情報共有されない状態が続いているのであれば、それは明らかに刑事訴訟法第197条に反する。捜査の一貫性と連携は制度設計上当然に前提とされるべきものであり、それを破綻させている状況は行政の機能不全である。また、こうした行政の対応によって、被害者が制度から排除される構図が固定化されれば、その地域や社会全体に「声を上げても無駄だ」という諦めが蔓延する。これは国家公務員法第98条および第99条に抵触する行為を職務として容認し続けている結果であり、その責任は現場担当者だけでなく組織全体にも及ぶものである。問題の本質は「誰が嘘をついているか」ではなく、「どのように判断がなされたか」であり、その判断過程が透明でなく、過去の嫌がらせや通報の履歴を軽視し続ける行政の姿勢そのものが、社会の分断を生み出している。公的機関は市民の安全と公平の担い手であるという建前を、行動で証明できないのであれば、その存在意義は大きく損なわれている。
長期的嫌がらせの軽視が引き起こす構造的暴力の固定化
長期的かつ継続的な嫌がらせ行為は、それ自体が被害者の生活や心理に深刻な影響を与えるものであるが、行政や警察がその行為を「小さなこと」「トラブルの一種」として扱い続けることによって、社会的に見えづらい暴力が恒常化する危険性がある。構造的暴力とは、制度や慣習、行政的無関心によって人間の尊厳や安全が継続的に損なわれる状態を指す。このような暴力は刑法上の直接的な加害行為と異なり、個別の行為ごとに処罰されるわけではないが、その影響は時間とともに累積し、被害者を制度から排除する効果を持つ。被害の通報が繰り返され、それに対して何ら具体的な対処がなされないという状態は、警察および行政が公務員としての職務を果たしていない証左である。国家公務員法第98条における「職務の遂行」義務や、第99条の「信用失墜行為の禁止」は、こうした放置や軽視を明確に禁じているにもかかわらず、現場ではしばしば「事件性がない」「相手も主張している」といった形で事実上黙殺される。これにより被害者は、物理的な暴力を受けていない時点でも精神的圧迫を受け続け、警察に訴えるたびにさらに傷つけられるという悪循環に陥る。そしてこの構造的暴力を正当化する発言や判断が、取調べの場で公然となされれば、それは行政による二次加害であり、制度としての加害行為である。市民を守るはずの組織が、被害者をさらに追い詰める側に回るという構図は、制度疲労を通り越して機能破綻であり、早急な是正と制度の再設計が必要不可欠である。
“`html
まとめ
警察による取り調べにおいて、被害者と加害者の立場を意図的に入れ替えるような対応が行われると、刑事訴訟の原則である中立性や適正手続が大きく損なわれることになる。正当防衛の三要件を無視した判断、長年にわたる嫌がらせの事実を捨象した解釈、署をまたぐ情報共有の欠如など、いずれも制度的な欠陥を露呈しており、個別の職員だけではなく組織全体の姿勢が問われる。さらに、逃走行為を「普通」とする警察官の発言や、車両を用いた行為に対する正当性の認定は、法の支配そのものを脅かす深刻な問題である。構造的暴力や行政による二次被害が常態化することで、市民が制度を信頼できなくなり、社会の安全と秩序の根幹が揺らいでいく。法の公正さと捜査の適正さを回復するには、現場レベルの実態把握と制度の透明性向上が不可欠である。