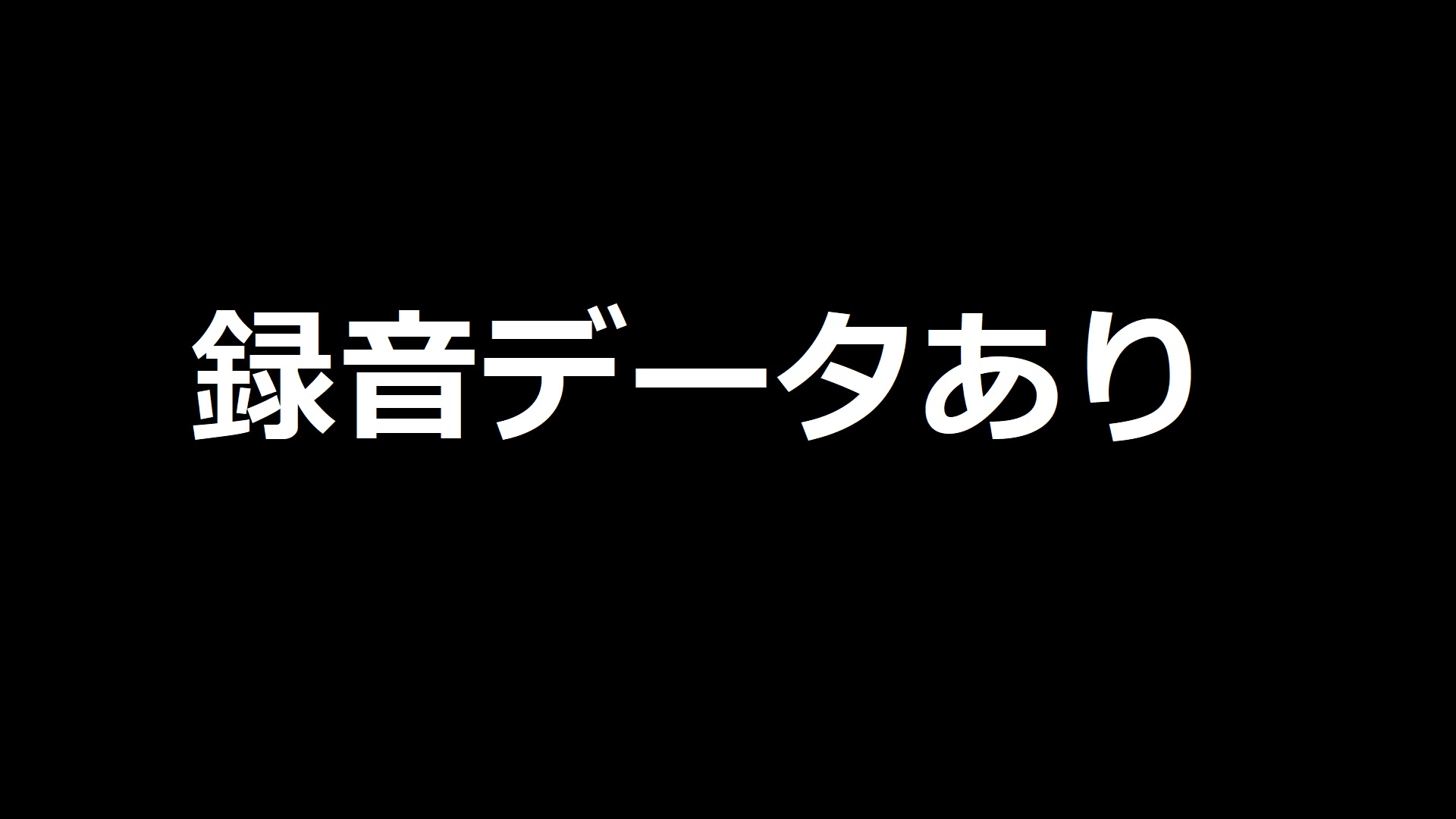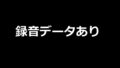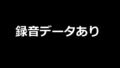高齢者が加害者となる交通事故や事件に対し、「年齢的に怖くなって逃げた」「ご老人だから仕方がない」という警察の発言が繰り返されている。ひき逃げという明確な犯人行為に対して、加害者の年齢を理由に同情的な扱いがされることは、果たして法と社会の正義に照らして正当なのだろうか。本記事では、警察や行政機関の対応の中にある法的・構造的問題を専門家の視点から明らかにする。
高齢者バイアス
- これまでは
- 動画化:高齢者バイアス
- 考察:高齢者バイアス
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による嫌がらせが4年間続いた末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの中でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者は18時間にわたって拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたが、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
東松山警察署での事情聴取中、刑事課のI刑事は、ひき逃げ事件の加害者について「ご高齢」と発言した。保護時に対応した生活安全課のK氏も「ご老人」と述べている。警察はこの事件を「高齢者が怖くなって逃げた」という構図で処理しており、ひき逃げという重大犯人を加害者の年齢によって当然の反応であるかのように位置づけている。「高齢者は怖くて逃げる」「だからひき逃げは仕方がない」という論理が前提となっており、犯人行為を事実上肯定している。
警察は最初から加害者を「犯人」と認定する姿勢を取っていない。その代わりに、被害者を精神的に問題のある人物として扱い、「保護」の名目で長時間拘束し、措置入院に持ち込もうとした。加害者の責任を免除し、被害者に責任転嫁する構造が出来上がっている。
2019年4月には、90歳の旧通産省工業技術院元院長・飯塚幸三被告が池袋で母子を死亡させる暴走事故を起こしている。高齢であっても罪が免除されることはなく、むしろ「上級国民」として特別扱いされたことへの批判が高まった。飯塚被告は事故以前に免許を返納すべきであり、私はその責任を問う遺族の署名に参加した。
動画化:高齢者バイアス
考察:高齢者バイアス
この事件で最も異常なのは、ひき逃げという明確な犯人が起きたにもかかわらず、警察が加害者ではなく被害者のほうを問題視し、精神的に不安定な人物として処理しようとした点である。しかも、加害者に対しては「ご高齢」「ご老人」といった表現を使い、「高齢者だから怖かったのだろう」「だから逃げたのだろう」といった考え方が当然のように口にされている。これは、「高齢者は恐怖心から逃げることがある」「だからひき逃げをしても仕方がない」というロジックを前提としているに等しい。つまり、加害者の行動を犯人ではなく「年齢ゆえの自然な反応」として正当化している。
警察がこうした論理に基づいて行動していたことは明白であり、被害者を守るどころか、逆に精神的におかしい人物として隔離しようとした。18時間の拘束、そして措置入院の試みは、単なる誤解や手続きミスではなく、明確に加害者を守るための手段だったと断定できる。保護という建前を使いながら、実際には警察内部の都合と判断だけで、被害者を「排除すべき存在」に仕立て上げていた。これは暴力的で一方的な権力行使である。
さらに問題なのは、この構図が単発のものではなく、社会全体に見られる傾向と重なっている点だ。2019年の池袋暴走事故でも、高齢であり社会的地位のある加害者に対して、極端に慎重な扱いがなされた。高齢者だから、元官僚だから、という理由で加害者の責任を曖昧にしようとする姿勢は、今回の事件とも地続きである。高齢であればあるほど責任を免れるという空気が、制度の中に埋め込まれている。その結果、犯人が見逃され、逆に声を上げた被害者が攻撃されるという構造が生まれている。
この事件は「たまたま判断を誤った」のではなく、「最初から加害者を守り、被害者を排除する」という方針に基づいて動いていた。警察の中にある価値観、行政の態度、社会の空気、それらすべてが結びついた結果であり、偶然ではない。これは構造的な問題である。だからこそ、こうした事実を一つ一つ明らかにし、共有し、変えていかなければならない。
憲法
- 日本国憲法 第14条
日本国憲法 第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
道路交通法
- 道路交通法 第72条
道路交通法 第72条
交通事故があった場合においては、当該交通事故に係る運転者等は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、及び道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
刑法
- 刑法 第193条(公務員職権濫用罪)
- 刑法 第194条(特別公務員職権濫用罪)
刑法 第193条(公務員職権濫用罪)
公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法 第194条(特別公務員職権濫用罪)
裁判、検察若しくは警察の職務に従事する公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、3年以下の懲役に処する。
地方公務員法
- 地方公務員法 第33条
地方公務員法 第33条
すべての職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除くほか、その職務を遂行するについて、すべての国民の利害を公平に考慮し、かつ、全力を挙げてこれを実現しなければならない。
刑事訴訟法
- 刑事訴訟法 第1条
刑事訴訟法 第1条
この法律は、刑事事件についての手続を規定することにより、適正な事実の発見と、刑罰の適用の実現を図り、もって個人の基本的人権を保障し、並びに社会秩序の維持に寄与することを目的とする。
専門家としての視点
- 高齢者であることを理由とした刑事責任の軽視は許されない
- 警察官による被疑者属性への配慮と法の下の平等の衝突
- 加害者擁護による被害者権利侵害の構造的危険性
高齢者であることを理由とした刑事責任の軽視は許されない
刑事責任の追及において被疑者の年齢が一律に考慮されるべきではなく、ひき逃げという道路交通法第72条違反の行為に対して「高齢であるから怖くなって逃げた」などの弁解を公的機関がそのまま受け入れることは、法の下の平等を保障する憲法第14条に明確に反するものである。憲法第14条はすべて国民が法の下に平等であることを定めており、いかなる年齢や地位であっても、犯人行為があった場合には同様の手続と責任追及が求められる。ひき逃げにおける「救護義務違反」は極めて重い違法行為であり、道路交通法第72条第1項により、負傷者を救護し危険を防止する措置が義務付けられている。その義務を年齢を理由に免除または軽減するような扱いは、同法の趣旨に反するものであり、あってはならない。さらに、こうした扱いが警察組織内で黙認されている場合、それは職務上の平等義務に違反し、地方公務員法第33条の職務の公正遂行義務にも違反する構造的問題をはらんでいる。仮に警察が高齢者という属性に基づいて立件や捜査を回避した場合には、刑法第193条の公務員職権濫用罪や第194条の特別公務員職権濫用罪に該当する可能性も否定できない。刑法第193条は「公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する」としており、第194条は「裁判、検察若しくは警察の職務に従事する公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、3年以下の懲役に処する」と規定している。よって、年齢を理由に犯人の責任追及を免除する構造は、明確に法秩序に対する挑戦であり、許容されるものではない。
警察官による被疑者属性への配慮と法の下の平等の衝突
警察官が取り調べや聴取の過程で被疑者に対し「ご高齢」「ご老人」などの敬称を用いる行為は、社会的に中立性を装う一方で、実質的には加害者に対する配慮や情状酌量を印象づけるものであり、刑事手続における平等原則と衝突するものである。刑事訴訟法第1条は「この法律は、刑事事件についての手続を規定することにより、適正な事実の発見と、刑罰の適用の実現を図り、もって個人の基本的人権を保障し、並びに社会秩序の維持に寄与することを目的とする」と定めており、あらゆる被疑者に対して事実に基づいた中立的対応が求められる。また、敬称の選択や属性強調によって被疑者への印象が柔らげられた場合、被害者やその関係者にとっては重大な権利侵害につながる恐れがある。とりわけ、ひき逃げという故意性または過失が明確に争点となる事件で加害者の心理的動揺や高齢による判断力低下といった主張を、そのまま捜査判断に反映する行為は、地方公務員法第33条が求める公正な職務遂行義務に違反する。警察が刑事責任における評価基準を年齢属性によって恣意的に変更することは、警察という公権力の信頼性を根底から揺るがす行為であり、正当な刑事手続を損なう違法性がある。さらに、これを組織として黙認し続けた場合には、責任の所在が曖昧になり、制度的な腐敗を招くことになる。年齢による配慮は刑の量定の段階で判断されるべきものであり、捜査・立件・認定の段階で導入されるべきではない。
加害者擁護による被害者権利侵害の構造的危険性
加害者の年齢を理由にした擁護が捜査機関内部で制度的に行われている場合、それは被害者の権利を組織的に侵害する構造となる。刑事訴訟法第1条は、適正な事実の発見と刑罰の適用を通じて個人の基本的人権を保障することを目的としており、被害者もまたその保護対象である。高齢加害者に対して「怖かったから逃げた」という主観的理由を免責の根拠として扱うことは、被害者が本来受けるべき捜査、救済、そして社会的な保護を不当に奪う行為であり、警察の組織的な判断でこれがなされる場合は、もはや個人の判断ミスではなく制度の欠陥である。さらに、こうした捜査回避の根拠が高齢という属性のみに基づく場合、それは憲法第14条の定める法の下の平等にも明確に違反する構造を持つ。被害者にとっては、加害者が誰であれ等しく法的保護を受け、加害行為について正当な捜査と裁きがなされることが保障されるべきであり、加害者擁護のためにこれを損なうことは公務員による権限の濫用として刑法第193条や第194条に抵触する可能性がある。さらに、公務員が被害者の申告や証言を軽視し、加害者保護に偏った対応を取ることは、結果として被害者の名誉、尊厳、法的利益を恒常的に損なうものであり、組織としての責任が問われる重大な人権侵害に発展する危険性がある。
専門家としての視点、社会問題として
- 高齢者による加害行為の容認構造がもたらす社会的正義の崩壊
- 行政機関による加害者擁護の常態化と被害者排除のメカニズム
- 日本社会に根付く年齢ヒエラルキーと法秩序の逆転現象
高齢者による加害行為の容認構造がもたらす社会的正義の崩壊
高齢者が加害者となった場合に、警察や行政が「ご高齢」「ご老人」といった言葉を用いてその責任を軽く扱う傾向は、加害行為に対する社会的制裁と法的制裁の両方を空洞化させる構造を生んでいる。この構造は年齢を理由とした加害者への過剰な配慮を正当化し、それにより本来法的に保護されるべき被害者の権利が著しく損なわれるという深刻な問題をはらんでいる。社会正義とは本来、加害と被害が生じた際に中立で公正な評価がなされ、加害者には責任が課され、被害者には救済と補償が与えられるという原則のもとに成立するが、「高齢者だから怖かったのだろう」「高齢者だから逃げても仕方ない」という前提が公的機関内で共有され、それが判断に組み込まれてしまうと、社会正義は根本から崩壊する。こうした構造が固定化されると、今後も年齢を理由に捜査の優先度が下がり、立件を見送る事例が続発する危険性がある。またこのような姿勢は被害者に対して「声を上げても意味がない」「相手が高齢なら泣き寝入りしろ」と暗に強いる結果となり、被害届の提出すらためらうような空気が広がることで、市民の法への信頼を著しく失わせる。警察や行政は、あくまで法に基づく公平中立な姿勢を保たなければならず、加害者が高齢者であるというだけで、その責任を相対化するような言動は許されない。高齢者に配慮が必要なのは福祉や介護の領域であり、刑事事件においては法的責任が年齢によって変動することがあってはならない。このような不公平が常態化すれば、社会全体が「年齢差別の逆転構造」に陥り、犯人に対する健全な抑止力も損なわれていく。
行政機関による加害者擁護の常態化と被害者排除のメカニズム
警察や福祉行政機関が高齢加害者に対し「怖くて逃げた」などと理由をつけてひき逃げ行為を正当化しようとする構造は、個々の判断ミスではなく、制度として加害者を保護し被害者を排除するメカニズムが根付いている証拠である。この構造は、「高齢者=弱者=保護対象」という図式を機械的に当てはめ、加害者であるにもかかわらず同情や配慮の対象として処理することにより発生する。本来、刑事事件における捜査や責任追及は加害者の年齢や地位に左右されるべきではなく、行為の重大性と法令違反の有無によって決定されるべきであるが、現実には高齢であることが一種の免責符号のように作用し、捜査対象から外れるケースが少なくない。このような傾向が行政の中で常態化すると、被害者は「訴えたことが問題」として逆に排除されるリスクに直面する。実際、被害申告後に精神的問題を疑われたり、「保護」の名目で拘束される事例が存在することは、行政の対応が加害者保護を優先し、被害者の人格や証言を軽視する方向に偏っていることを示している。これは個人の尊厳を侵害する重大な問題であり、行政の中立性と適正手続保障という原則に反する。制度が一度こうした方向で機能し始めると、それは職員一人一人の判断というよりも、組織の文化や空気として染み込み、内部からの是正が極めて困難になる。その結果、加害者は高齢であるという理由だけで責任追及を免れ、被害者は声を上げたことによって逆に社会的制裁を受けるという倒錯した構造が完成する。
日本社会に根付く年齢ヒエラルキーと法秩序の逆転現象
日本社会には年齢によって敬意や配慮を与える文化が深く根付いており、それ自体は家庭内や地域社会において調和を促す役割を果たしてきたが、この文化が公的機関の中にまで持ち込まれた場合、法秩序そのものを逆転させる作用を持つようになる。すなわち、年上の人間は多少の問題行動があっても「人生経験の長さ」「年齢的な弱さ」「精神的な負荷」といった理由で責任が軽く扱われ、逆に若年者や被害者側が「配慮に欠けた」「感情的」「問題のある人」と位置付けられる傾向がある。これがひき逃げなどの重大な刑事事件において発生した場合、加害者が高齢であるというだけで刑事責任の追及が消極的になり、被害者が本来受けるべき調査や保護、社会的支援が切り捨てられるという事態を引き起こす。このような年齢ヒエラルキーが法的判断に持ち込まれると、「高齢者に責任を問うのはかわいそうだ」「高齢者は事情を理解できなかった可能性がある」という情緒的判断が優先され、結果として法秩序に対する信頼を損ねるだけでなく、国民の間に不信感と分断を生む。法は情ではなく、行為に対して等しく適用されなければならないが、この年齢構造が制度の奥深くまで浸透している限り、形式上の平等を維持していても、実質的には著しい不均衡が生じている。結果として「高齢者であれば法を逃れられる」という空気が醸成され、社会全体に犯人抑止の意識が希薄になり、誰もが法の下に平等であるという近代国家の基本理念が形骸化してしまう。
まとめ
高齢者による加害行為に対し、警察や行政機関が年齢を理由に責任を軽く扱う傾向は、法の下の平等に明確に反し、社会的正義の原則を大きく揺るがす問題である。本来、犯人行為は加害者の年齢にかかわらず等しく裁かれるべきであり、「高齢者だから怖くなって逃げた」「高齢者だから仕方ない」といった判断を公的機関が口にし、それに基づいて立件や捜査が緩められるのであれば、それは組織ぐるみの責任回避と制度的な不公正の現れである。こうした扱いが常態化すれば、被害者は声を上げることすら許されず、逆に排除される構造が生まれる。また、日本社会に根付く年齢ヒエラルキーが、刑事手続きにまで入り込むことで、法の中立性が損なわれ、市民の信頼を著しく失わせることになる。高齢であっても法の前ではすべての人が平等であるという原則が守られなければ、刑罰の公平性は崩壊し、社会秩序の根幹が揺らぐこととなる。