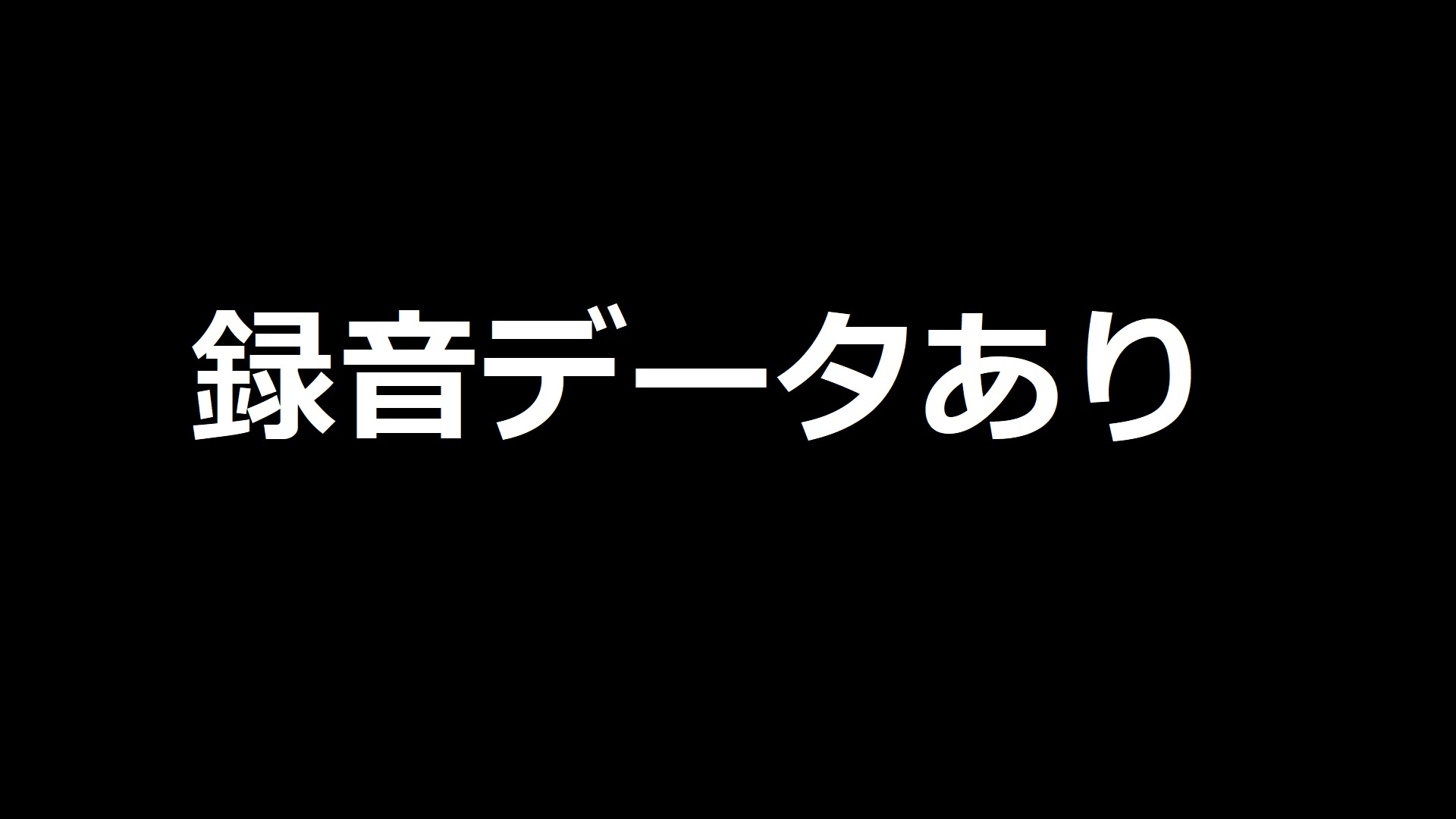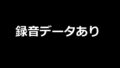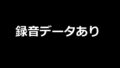被害を受けたにもかかわらず、加害者の住所が知らされず、民事訴訟も提起できない――そんな理不尽な状況が現実に起きている。東松山警察署での事情聴取を皮切りに、被害者は傷害罪として被害届を提出したものの、警察と検察はいずれも加害者の住所を明かさなかった。検察は不起訴処分とし、その理由の説明もなく、質問にも答えようとしなかった。被害者が繰り返し申し立てを行っても「不起訴相当」とされ、正当な手段で争う機会すら奪われる。この過程において被害者は、加害者が警察関係者か警察OBである可能性を疑わざるを得なくなった。透明性を欠いた対応が続くなかで、法制度の根幹である「裁判を受ける権利」が著しく損なわれている。
犯人の住所を知られたくない?
- これまでは
- 動画化:犯人の住所を知られたくない?
- 考察:犯人の住所を知られたくない?
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
事情聴取の最中、東松山警察署刑事課のI刑事は「どこの誰とかっていうのは知ってるんですか?」と発言した。被害者にとってこの言葉は非常に印象的だった。
この後、警察は被害届を受理する際に犯人の氏名や年齢は伝えるものの、住所については教えようとしなかった。この事件では傷害罪として被害届が提出され、警察が検察に送致し、検察は最終的に不起訴処分とした。被害者は検察審査会に申し立てを行ったが、「不起訴相当」と判断された。
さらに被害者は、罪状を過失運転致傷罪および救護義務違反に変更して告訴を行ったが、その件も検察で不起訴とされ、再び検察審査会に申し立てた結果も「不起訴相当」となった。
告訴の不起訴に際して、被害者は検察に対し「弁護士から、犯人の住所が分からないと民事訴訟を提起できないと言われている」として、住所を開示するよう求めたが、検察は「弁護士が決まったら、弁護士から連絡をさせてほしい」と述べるにとどまった。
被害者は、警察や検察がここまで犯人の住所を頑なに教えない姿勢に強い疑問を抱いている。さらに、実況見分の状況や検察から入手した捜査資料、ドライブレコーダーの画像などを見ても、警察は事件を軽微なものとして扱おうとしているように感じられた。検察による不起訴処分、またその理由の説明が明確になされず、質問にも応じようとしない態度を考慮すると、被害者は犯人が警察関係者、もしくは警察OBである可能性が高いと考えている。
こうした背景から、警察も検察も犯人の住所を開示したがらないのだと被害者は推測している。
動画化:犯人の住所を知られたくない?
考察:犯人の住所を知られたくない?
事情聴取の最中、東松山警察署刑事課のI刑事は「どこの誰とかっていうのは知ってるんですか?」と発言した。被害者にとってこの言葉は非常に印象的だった。
この後、警察は被害届を受理する際に犯人の氏名や年齢は伝えるものの、住所については教えようとしなかった。この事件では傷害罪として被害届が提出され、警察が検察に送致し、検察は最終的に不起訴処分とした。被害者は検察審査会に申し立てを行ったが、「不起訴相当」と判断された。
さらに被害者は、罪状を過失運転致傷罪および救護義務違反に変更して告訴を行ったが、その件も検察で不起訴とされ、再び検察審査会に申し立てた結果も「不起訴相当」となった。
告訴の不起訴に際して、被害者は検察に対し「弁護士から、犯人の住所が分からないと民事訴訟を提起できないと言われている」として、住所を開示するよう求めたが、検察は「弁護士が決まったら、弁護士から連絡をさせてほしい」と述べるにとどまった。
被害者は、警察や検察がここまで犯人の住所を頑なに教えない姿勢に強い疑問を抱いている。さらに、実況見分の状況や検察から入手した捜査資料、ドライブレコーダーの画像などを見ても、警察は事件を軽微なものとして扱おうとしているように感じられた。検察による不起訴処分、またその理由の説明が明確になされず、質問にも応じようとしない態度を考慮すると、被害者は犯人が警察関係者、もしくは警察OBである可能性が高いと考えている。
こうした背景から、警察も検察も犯人の住所を開示したがらないのだと被害者は推測している。
関係する法令
- 民事訴訟法
- 刑事訴訟法
- 刑事訴訟規則
- 国家公務員法
民事訴訟法(検察が民事訴訟に必要な住所の開示を拒否した行為)
第133条第1項
訴状には、当事者及び法定代理人を表示しなければならない。
刑事訴訟法(警察が実況見分・捜査資料で事件を軽微に扱った可能性)
第189条第2項
司法警察員は、犯人があると思料するときは、捜査をしなければならない。
刑事訴訟規則(検察が不起訴理由を説明せず、質問に応じなかった行為)
第262条の2
検察官が公訴を提起しない処分をしたときは、告訴人又は告発人に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
国家公務員法(捜査の中立性や公平性を欠いたと受け取られうる対応)
第96条第1項
職員は、その職務の遂行に当たっては、法令に従い、かつ、全体の奉仕者として公共の利益のためにこれを行わなければならない。
専門家としての視点
- 民事訴訟における住所非開示と訴権制限の問題
- 警察の捜査軽視と職務遂行義務違反の疑い
- 検察の不起訴理由非開示と告訴人の手続保障
民事訴訟における住所非開示と訴権制限の問題
民事訴訟を提起するには民事訴訟法第133条第1項により訴状に当事者及び法定代理人を表示しなければならないとされておりこれは氏名だけでなく住所の記載も要求されるため検察が被害者からの住所開示の求めに対して「弁護士が決まったら連絡をさせてほしい」とのみ応じて実質的に開示を拒否する行為は民事訴訟提起の前提条件を阻害し訴権の行使を制限している状態である本来であれば行政機関が保有する情報のうち訴訟のために必要不可欠でありかつ合理的理由のある開示請求については目的を限定した範囲内での情報提供が検討されるべきであり一律の拒否は正当化されない被害者にとっては民事上の請求権行使のために最低限必要な情報であるためその取得が不可能となることは法的保護の不全をもたらすまたこうした状態は国家公務員法第96条第1項において職員は法令に従い全体の奉仕者として公共の利益のために職務を行うべきであるとされているにもかかわらず特定の個人に関する情報保護を過度に優先し結果的に加害者側を実質的に保護するという職務の不公正性を内包しているさらに被害者にとっての民事訴訟上のアクセスが閉ざされている状況が長期にわたり放置されている場合は行政不作為と評価される可能性すらありその場合には行政救済の手段や国家賠償請求の対象としても検討されることがあるしたがって検察が民事訴訟の提起に不可欠な情報を不開示とする判断については被害者の基本的な権利とのバランスを欠くものであり司法アクセスの平等に関する重大な問題を含んでいるといえる
警察の捜査軽視と職務遂行義務違反の疑い
警察が実況見分や捜査資料において事件を軽微なものとして扱っているように見える場合その行為は刑事訴訟法第189条第2項に規定されている司法警察員は犯人があると思料するときは捜査をしなければならないという義務に反する可能性があるこの規定は捜査機関に対して中立かつ積極的な捜査義務を課しており特定の加害者に有利になるよう事件の重大性を軽視する行為は法的義務違反と解されうるまた事件の証拠として提出されたドライブレコーダー映像や実況見分の内容が明らかに被疑者側に有利な解釈や表現で構成されている場合には捜査機関が故意または過失によって事実の歪曲や過小評価を行っている懸念が生じる警察はあくまで中立の立場で捜査を行うべき存在であるにもかかわらず本件のように加害者の関係性が警察内部または退職者等とつながりがあると疑われる状況で客観的資料や証言に基づかない「軽傷」「偶然」といった構成を意図的に作り上げているとすれば刑事訴訟法だけでなく国家公務員法第96条第1項に違反する行為である同条文は職員に対し全体の奉仕者として法令に従い公共の利益のために職務を遂行すべき義務を定めており個人的つながりや組織内保身のために判断が歪められることは絶対に許容されないまたそのような判断に基づき事件が不起訴に至った場合には本来訴追されるべき行為が見逃され被害者が刑事法上の保護から排除されるという重大な法的損害を受けることになるしたがって実況見分や資料構成において事件の性質を恣意的に軽視した警察の対応は職務違反であり組織的隠蔽や職権乱用の疑いも含めて検証されるべき内容である
検察の不起訴理由非開示と告訴人の手続保障
検察官が不起訴とした際にその理由を被害者に一切説明せず質問にも応じようとしなかった行為は刑事訴訟規則第262条の2に違反するおそれがある同条は検察官が公訴を提起しない処分をしたときは告訴人又は告発人に対しその旨及びその理由を通知しなければならないと明確に規定しておりこの通知義務は単なる形式ではなく被害者に対する刑事手続上の説明責任と理解補助の役割を果たすものであるところが本件においては検察が不起訴理由を説明せずさらには被害者からの質問にも回答しなかったという点で告訴人の知る権利や手続保障が著しく軽視されている検察は行政機関であると同時に準司法機関としての性格も有しており職務執行にあたっては公正性中立性説明責任が強く求められるまた不起訴処分は裁判所による審理を経ないまま処分が確定する性質を持つためその判断が恣意的あるいは不透明であれば司法的統制を免れる結果となりかねない特に被害者が検察審査会に申し立てたにもかかわらず二度にわたって「不起訴相当」とされた背景に合理的な理由が説明されていない以上検察の初期対応から審査会の判断に至るまでの一連の流れに構造的問題がある可能性があるさらに国家公務員法第96条第1項に基づく職務遂行の在り方としてもこのような不誠実な対応は法令遵守義務に違反する行為と評価され得るしたがって不起訴理由の説明拒否および質問への無回答という検察の対応は刑事訴訟規則違反かつ行政機関としての責務放棄に該当し手続保障の不履行として厳しく問われるべきである
専門家としての視点、社会問題として
- 司法アクセス格差と制度的障壁の固定化
- 行政機関の透明性欠如と説明責任の喪失
- 法執行機関における身内保護構造の問題
司法アクセス格差と制度的障壁の固定化
加害者の住所が明かされないことにより被害者が民事訴訟を提起できず法的救済の機会を失う事態は深刻な司法アクセスの不均衡を示しているこれは制度上の条件を満たしていても実質的に裁判を起こせないという構造的障害の問題であり公正な裁判を受ける権利の侵害に直結する事態である民事訴訟法第133条第1項により訴状には当事者の表示が求められるがその住所を行政機関が一切開示しないことで民事訴訟の入り口すら閉ざされているこの状況は単なる手続き上の問題にとどまらず被害者と加害者の間に制度的な非対称性を生じさせ被害回復を目的とする民事制度の本質を損なっている行政機関が被害者に対して説明を尽くさず画一的に開示を拒絶する姿勢は訴訟を前提とした情報アクセスの平等を否定し司法制度全体への信頼を損なうものとなっているさらにこれが恒常的に行われている場合特定の立場にいる人間が事実上訴追から免れる構造を温存することとなり市民全体の法的平等という憲法上の理念とも整合しない情報の非対称性が救済の非対称性に直結している以上これは法的技術の問題ではなく明確な社会的不公正の現れであり制度改革を含む構造的対応が求められる状態にある
行政機関の透明性欠如と説明責任の喪失
検察が不起訴処分を下した際にその理由を被害者に明示せず質問にも一切応じないという対応は行政機関の説明責任の放棄を意味し現代民主主義社会における透明性原則と根本的に矛盾する検察官には刑事訴訟規則第262条の2に基づき告訴人に対し不起訴の理由を通知する義務があるが現実には理由を曖昧にしたまま処分のみを伝える例が存在するこれは被害者が手続きの正当性を確認し理解する機会を奪うものであり納得なき処分は法の支配を空洞化させるまた不起訴処分が重なりその理由が一切不明なまま検察審査会でも再び「不起訴相当」とされる構図は制度的密室性を浮き彫りにしており制度の設計意図が現実に反映されていないことを示す民主的コントロールを受けるべき行政機関が市民に対して「答えない」ことを常態化させると行政手続き全体が閉鎖的な自己完結型となりやがて外部からの信頼を失うこのような構造が正当化されれば検察判断が常に正義であるかのような誤った観念を助長し個別事案への検証も困難になる市民にとっての知る権利と説明を受ける権利は法的義務の根拠の上に成り立つ実質的保障でありそれを行政が放棄することは制度全体の正当性を危機に晒す行為である
法執行機関における身内保護構造の問題
被害者が加害者の身元に関して「警察関係者あるいはOBではないか」と疑うに至る背景には警察および検察の一貫した情報非開示や事件軽視の姿勢がありそこに組織内の身内保護構造が疑われる状況が存在しているこれは国家公務員法第96条第1項に定められた全体の奉仕者として法令に従い公共の利益のために職務を行うべき義務に真っ向から反する構造であり公的権限が私的関係や組織内部の保身のために行使されている可能性を示している特定の人物が属していた過去や関係性によって組織的に庇護される構造が存在すれば法の下の平等は崩壊するまた捜査が不十分であること実況見分が軽視されていること証拠の扱いに偏りがあることこれら一つ一つの行動が偶然ではなく意図的な方向性を持って重なっているとすればそれは組織的な隠蔽または不作為の構図に発展しうる警察や検察が一定の範囲の人間を守るために中立性を失うのであれば法執行機関としての正当性を根底から損なうものでありその行動は信頼の対象ではなく監視と検証の対象となる身内保護の傾向は一件の問題にとどまらず全国的な制度運用全体の信頼性を揺るがす社会構造の問題でありこのような傾向を制度的に放置することは市民社会全体に対する背信行為である
まとめ
警察や検察による対応の中で被害者が加害者の住所を知らされず民事訴訟が提起できない状況は民事訴訟法の実効性を損ねておりさらに捜査段階で事件が軽視され実況見分や証拠構成に恣意性が認められる場合は刑事訴訟法に定められた捜査義務や公正中立の原則に違反する可能性がある検察が不起訴とした理由を被害者に説明せず質問にも応じない対応は刑事訴訟規則が定める説明義務に反し行政の透明性と説明責任を損なうものでありまた警察や検察が一貫して加害者の身元を隠す姿勢を貫いた場合それが警察関係者やOBの保護である可能性が疑われる構造であれば国家公務員法に反する職務遂行義務違反にも該当しうるこれらの一連の対応は被害者の司法アクセスを妨げるだけでなく行政と司法への信頼を揺るがす社会的問題であり制度そのものの再点検と改善が求められる