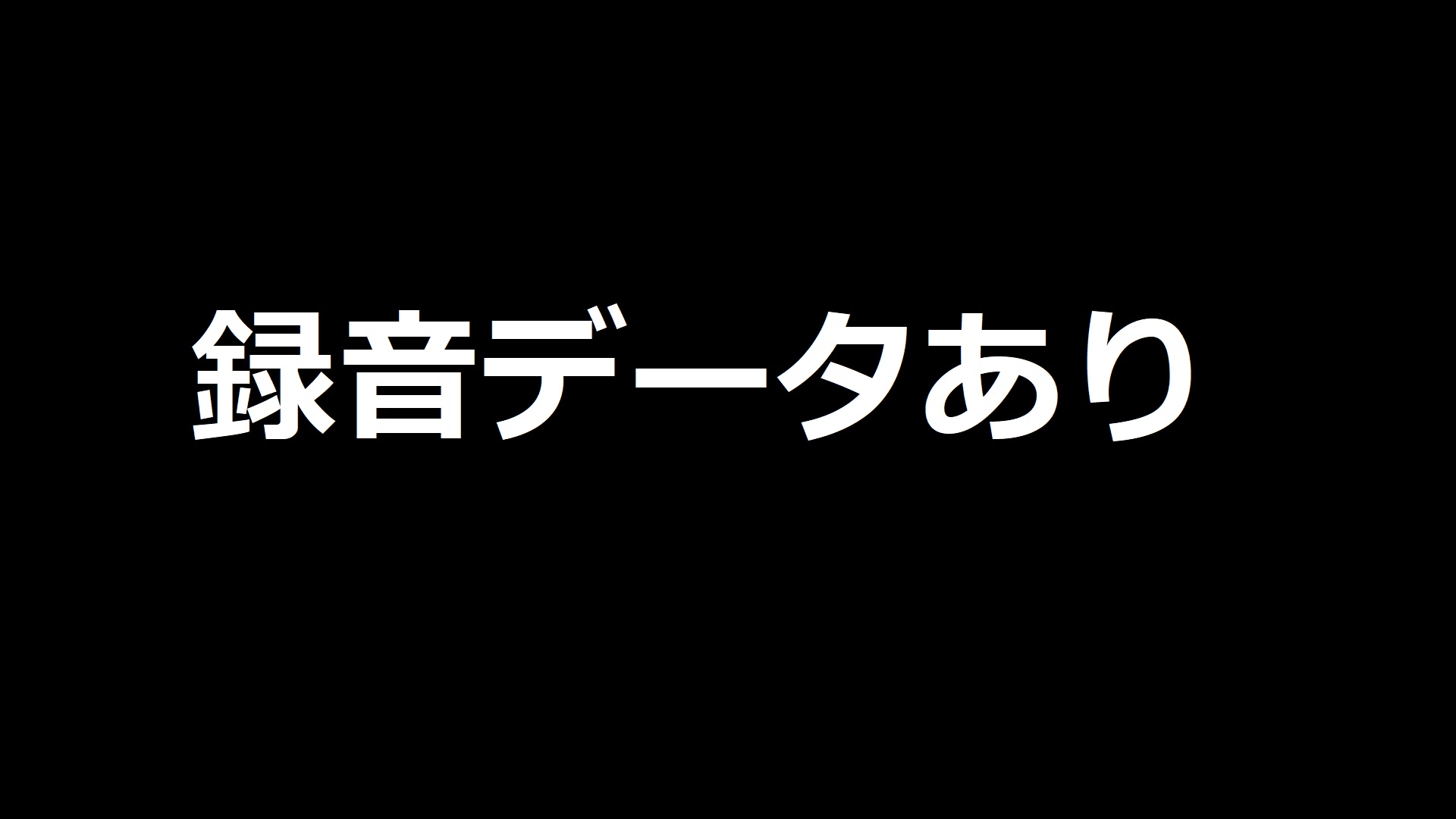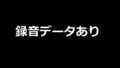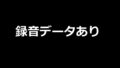「それでいいやで保護?」というテーマのもと、警察による拘束の正当性とその影響について考えます。警察官職務執行法第3条に基づく保護措置が、市民の自由や人権をどのように制限するのか、またその適正性をどう評価するべきなのか、法的視点と社会的影響を掘り下げて検証していきます。警察権限が濫用されることがないよう、どのように市民の権利を守るべきかを考えることが、今後ますます重要な課題となるでしょう。
それでいいやで保護?
- これまでは
- 動画化:それでいいやで保護?
- 考察:それでいいやで保護?
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
保護直後、被害者は東松山警察署の2階の保護室に連れて行かれ、所持品は保護された聴取室に残されたままだった。録音中のスマホもそこに残されていた。私がいない場所で軽口を叩く刑事たち、その中で東松山警察署刑事課のS刑事は「両親をやっちゃうとか言っているから、それでいいやと思って」と発言していた。
遡ること30分前、被害者はS刑事の事情聴取を受けており、S刑事の誘導尋問により両親との関係について触れ、「両親をやっちゃうかもしれない」と発言した。しかし、その発言は「可能性として」であり、「今は冷静な気持ちで、やる気はない」とも明言していた。
ちなみにこの「保護」とは、警察官職務執行法第3条に基づくものである。
警察官職務執行法
(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信じるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
要件として「応急の救護を要する」とあり、被害者は「可能性」に言及し、さらに「今は冷静で、やる気はない」と明言しているにもかかわらず、この法律は適用されるべきではない。
また、「保護」とは名ばかりであり、警察はこの警察官職務執行法第3条を悪用し、被保護者を精神病院に措置入院させることが常態化しているようだ。その理由は、両親や親戚などによる私怨で行われることが多いという。そのように措置入院させられた被保護者が正常な精神状態にある割合は、6割に達しているという。
関係する法令
- 警察官職務執行法第3条
- 刑事訴訟法第199条
警察官職務執行法第3条
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信じるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
刑事訴訟法第199条
第199条 公判前に被告人に対する拘禁が適法である場合、裁判所は必要に応じて、被告人を一時的に拘束することができる。
専門家としての視点
- 法的視点からの拘束の適正と警察官職務執行法第3条の適用
- 刑事訴訟法第199条の適用における拘束の適法性
法的視点からの拘束の適正と警察官職務執行法第3条の適用
警察官職務執行法第3条は警察官が異常な挙動または泥酔などにより自己や他人の生命身体財産に危害を及ぼすおそれがある者を発見した場合に応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由があるときには保護することができると規定しておりこの法令に基づいて行われる拘束はあくまで一時的かつ必要最小限でなければならない今回の事例では被害者が冷静であることを繰り返し明言しさらに「やる気はない」と自ら述べている点からして警察がこの条文を適用して保護名目で拘束する根拠は極めて薄いと考えられる警察官職務執行法は任意保護の要件として「異常な挙動」や「危害を及ぼすおそれ」が明白でなければならず「冷静」で「やる気はない」と言っている者に対してこの規定を使うことは法の趣旨を逸脱する行為といえるまた本人の意思確認や医学的判断を欠いたまま保護を行った場合には違法な身体拘束として憲法第31条の適正手続きの保障にも抵触するおそれがある警察がこの条文を濫用して自由を不当に制限することは許されずその拘束の正当性が問われるべきであり今回の行為が違法な行政行為として損害賠償請求の対象となる可能性も否定できない。
刑事訴訟法第199条の適用における拘束の適法性
刑事訴訟法第199条は検察官または司法警察職員が被疑者を通常逮捕する場合には裁判官の発する逮捕状により行うことを定めており逮捕の前提として犯罪の嫌疑があることと逃亡または証拠隠滅のおそれが必要とされる今回の事例において被害者が逮捕または類似の拘束を受けた経緯があるとすればその根拠が刑事訴訟法に基づいていたか否かを厳格に確認する必要がある仮に逮捕状がなく拘束が行われていた場合には任意同行や保護という名目であっても実質的に身体の自由を奪う状況が存在すれば事実上の逮捕と評価されることがありその場合刑事訴訟法第199条の要件を満たしていなければ違法な逮捕となるとされているまたこの条文は裁判官の審査を経ることで被疑者の権利保護を図る趣旨を持つためこれを経ずに行われた拘束は司法審査の欠如という重大な手続違背を含み違法性が極めて高いと評価されるさらに裁判例においても警察が任意と称して実質的拘束を行った場合違法と認定される事例が多数存在しており今回の拘束が刑事訴訟法の手続きを回避したものであるならばそれ自体が違法行為である可能性が高く正当な理由がなければ国家賠償の対象となり得る。
専門家としての視点、社会問題として
- 拘束に関する法的問題とその社会的影響
- 刑事訴訟法第199条の適用と人権保障
- 警察官職務執行法第3条の適用と市民の自由
拘束に関する法的問題とその社会的影響
拘束に関する法的問題は単なる刑事手続きの枠を超えて現代社会における人権意識や国家権力の在り方そのものに深く関わっている警察や行政機関による身体拘束が違法または不当であった場合それは単に一個人の自由を侵害するだけでなく社会全体に対して重大な不信感を生じさせるものである特に本人が冷静に意思表示をしている状況で恣意的な判断によって拘束を行えばそれは公共の利益とは無関係な職権濫用であり監視や統制の名のもとに個人の尊厳を踏みにじる行為と評価され得る拘束の適法性を支える制度設計があったとしても現場での運用が常にその理念に沿っているとは限らず実務上の逸脱が制度そのものの信頼性を損なう結果にもつながる警察官職務執行法第3条が規定するような異常な挙動や泥酔の状態においても警察官の主観に依拠しすぎれば判断が独断的となりやすく社会問題化する要因となる市民が不当な拘束に晒される危険が放置されれば司法制度への信頼低下を招きそれは民主主義の根幹を揺るがす結果となるこのような問題が社会問題として議論されるべき理由は拘束の濫用が極めて個別具体的な場面から発生する一方でそれが制度として広範な影響を及ぼすという特性を持っているからである。
刑事訴訟法第199条の適用と人権保障
刑事訴訟法第199条は被疑者の逮捕に際して裁判官の発する逮捕状によることを原則としその要件として犯罪の嫌疑と逃亡または証拠隠滅のおそれを必要とするこの法的枠組みは身体拘束という重大な人権制限を行うための厳格な条件として機能しておりその運用には厳密な司法的監視が前提とされるしかし現実には形式的な逮捕状の取得やその後の手続きにおいて人権保障の視点が後景に追いやられる場面が少なくない特に精神的に不安定と判断された人物に対して迅速に拘束を実行する場合にはその適法性と比例原則に照らした妥当性が問われるべきであるにもかかわらず実質的に本人の言動が冷静でかつ危険性が具体的でない状況においても行政的措置が刑事手続きに転化する場合がある刑事訴訟法第199条は逮捕状主義によって国家権力の濫用を防ぐ装置であるはずだが現場判断によってその意義が骨抜きにされれば制度としての人権保障は機能しなくなる個別の事案においてこの条文の適用の正否を検討することは単なる違法性の有無にとどまらずそれが社会に与える抑圧的影響をも俯瞰した評価が必要である。
警察官職務執行法第3条の適用と市民の自由
警察官職務執行法第3条は警察官が異常な挙動や泥酔などにより自己または他人の生命身体財産に危害を及ぼすおそれのある者を発見した場合に応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由があれば保護することができると定めているがその運用の広範性ゆえに市民の自由と衝突する余地が常に存在するこの条文は現場の警察官に相当な裁量権を与えている一方でその裁量が濫用された場合には本来保護されるべき市民の権利が重大に侵害されることとなる保護の名目で行われる拘束が実質的に任意性を欠いていればそれは憲法が保障する自由権への挑戦に他ならず行政権の行使に際して最も慎重でなければならない分野である冷静に意思疎通ができる者に対しても警察官が恣意的に危険性を主張し保護を強行する場合その正当性は極めて疑わしくまた社会全体としてもそのような運用が常態化すれば警察に対する信頼の失墜や不当な介入への恐怖を生み市民社会の萎縮を招く結果となる市民の自由を不当に制限する行為が慣例化することの危険性は制度そのものの正統性を揺るがす要因であり警察官職務執行法第3条の適用範囲とその実施手続きについて明確なガイドラインと外部監視が必要である。
まとめ
今回の議論では、警察官による拘束や刑事訴訟法第199条、警察官職務執行法第3条に基づく適用に関する法的な問題と、それが引き起こす社会的な影響について検討した。特に拘束の適正性は、市民の自由を保護するために非常に重要であり、不適切な拘束が人権侵害を引き起こす可能性があることを指摘した。刑事訴訟法第199条は被疑者の適法な拘束に必要な手続きとして、拘束の根拠が明確であることを求め、警察官職務執行法第3条は警察が保護措置を取るための要件を定めているが、その適用が市民の権利を不当に制限することのないよう注意が必要だ。警察の権限が適正に行使されない場合、社会に与える影響は大きく、無用な不安や信頼の喪失を引き起こすため、法的枠組みの適正な運用が不可欠である。今後、このような問題を防ぐために、法制度の透明性と市民の権利保障が一層重要になる。