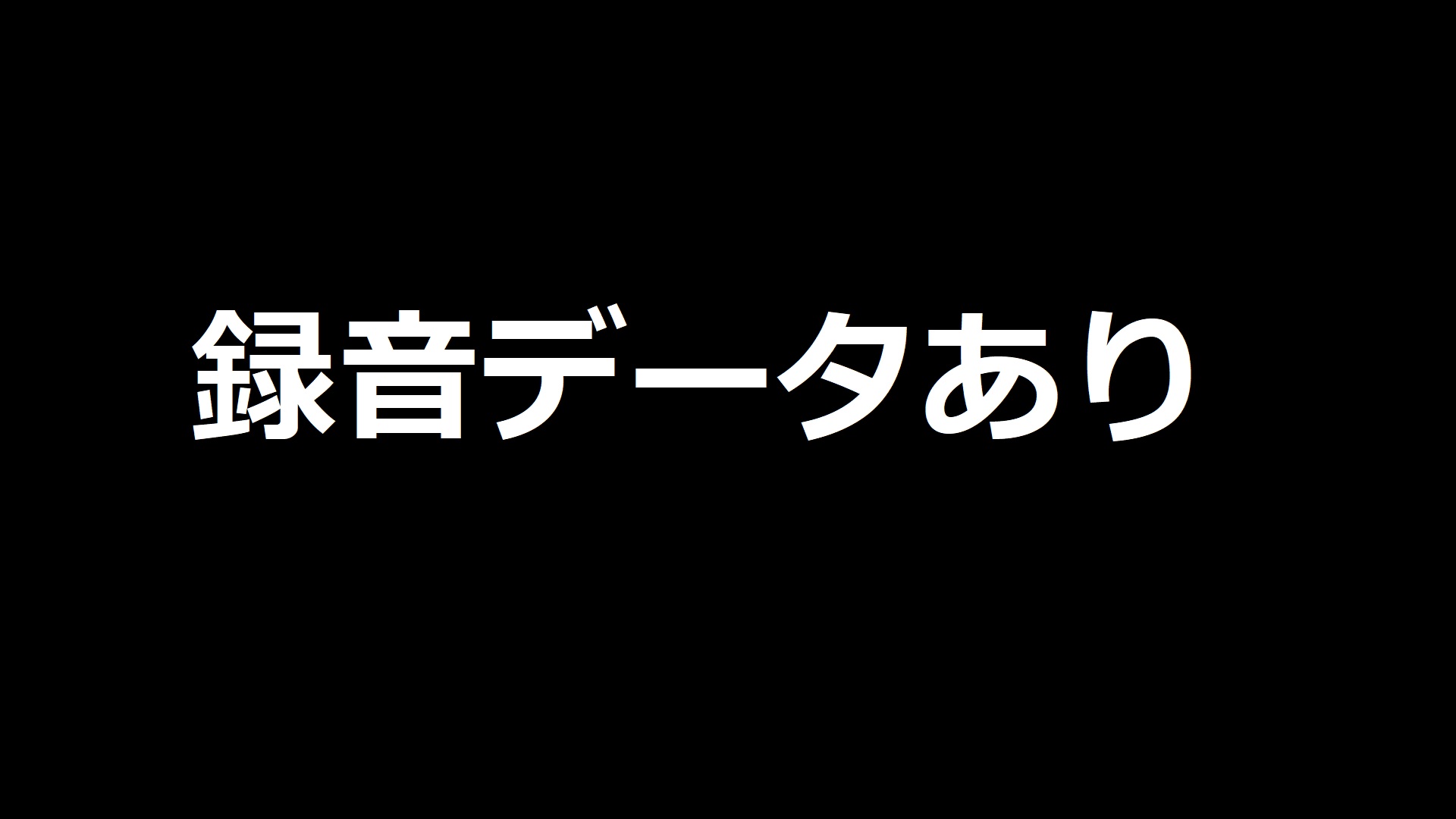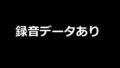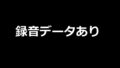保護の名のもとに行われた警察の判断は、本当に正当だったのか。東松山警察署で実際に起きた事例をもとに、保護措置の裏で進められていた事実の歪曲や内部で交わされた虚偽の発言について検証する。録音データが示すのは、手続きの正当性を欠いたまま自由を制限し、さらにその正当化のために後付けの説明が行われていた構図である。これは個別の問題ではなく、制度全体が抱える構造的課題として捉えるべき内容である。
警察の思惑
- これまでは
- 動画化:警察の思惑
- 考察:警察の思惑
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
今回は、東松山警察署生活安全課のK氏が、被害者が署に到着する前から「保護ありき」で準備を進めていたこと、2人の刑事が被害者と加害者を意図的に入れ替えようとしていたこと、その過程で多くの矛盾する話を無理に構成しようとしていたこと、さらに保護後に被害者不在の中で語られた本音の発言によって話の流れが強引に転換され、保護が不当なものであったことが明らかになっている。これらの一連の経過を記録した動画を作成しており、ここではその内容について解説する。
動画化:警察の思惑
考察:警察の思惑
今回は、東松山警察署生活安全課のK氏が、被害者が署に到着する前から「保護ありき」で対応を準備していた点、そしてその後、2人の刑事が被害者と加害者を入れ替えようとする姿勢で事情聴取を進めていた点が重要である。録音データをあらためて確認すると、刑事たちの話の持って行き方は、事実確認ではなく、被害者を加害者に仕立てること自体が目的となっており、そのために内容は場面ごとに変化し、矛盾がいくつも重なっている。相手の言葉を都合よく解釈したり、質問自体を誘導的にしたりしながら、最初から決められた方向に無理やり話を運んでいた様子がうかがえる。
さらに、保護後に被害者が不在となった場面で交わされた発言では、それまでの対応がウソであったことがわかり、筋書きに合わせて話がすり替えられていたことが明らかになる。発言内容は整合性を欠き、客観性を装いながらも、事実とのズレが顕著である。その一連のやり取りは、保護という判断そのものが正当性を欠いていたことを証明するものであり、今回その矛盾点の解明に焦点を当てる構成にした動画を作成し、ここでその内容について解説する。
関係する法令
- 刑法第193条(特別公務員職権濫用罪)
- 刑法第195条(特別公務員暴行陵虐罪)
- 刑法第220条(逮捕及び監禁)
- 刑法第158条(虚偽公文書作成及び行使)
- 刑事訴訟法第198条(取調べ)
- 憲法第31条(適正手続の保障)
刑法第193条(特別公務員職権濫用罪)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役に処する。
刑法第195条(特別公務員暴行陵虐罪)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、その職務を行うに当たり、看守等と共謀して、拘禁されている者に対し、暴行又は陵虐を加えたときは、7年以下の懲役に処する。
刑法第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法第158条(虚偽公文書作成及び行使)
公務員がその職務に関し、虚偽の公文書を作成し、又は偽造し、これを行使したときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
刑事訴訟法第198条(取調べ)
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者を取調べることができる。取調べに当たっては、被疑者の意に反して供述を強要してはならない。
憲法第31条(適正手続の保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
専門家としての視点
- 「保護ありき」の判断が職権濫用となる構造的背景
- 被害者不在での意思決定と憲法第31条違反の成立
- 立場のすり替えと刑事訴訟法198条の観点から見る取調べの問題点
「保護ありき」の判断が職権濫用となる構造的背景
被害者が警察署に到着する前から保護を前提とした準備を行っていたという状況は、刑法第193条に定める「特別公務員職権濫用罪」に該当する可能性がある。刑法第193条は「裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役に処する」と定めており、事実確認を行わずに保護措置を前提として行動していたとすれば、保護対象となった人物に本来発生しない拘束を強いたという意味で「義務のないことを行わせた」と評価され得る。また、これが組織的、計画的であった場合、職権濫用の意図が構造的に内在していたとも受け取られ、違法性の程度は高まる。さらに、このような行為は憲法第31条に抵触する可能性がある。同条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」としており、適正な手続に基づかないまま保護という名目で自由を制限した行為は、法的根拠を欠いた違憲の行為とされる。つまり、事前の事情聴取もなく、客観的な事実認定を欠いた状態で強制的な措置を進めていたとすれば、それは単なる判断ミスではなく、制度の運用を逸脱した違法行為と評価されうる。
被害者不在時の内部発言によって明らかになった保護の虚偽構成と法的責任
保護の意思決定が行われた後、被害者が不在となった場面において、警察内部で交わされた発言の内容から、それまでの説明が虚偽に基づいていたことが明らかになった場合、その発言自体が組織的な違法行為の証左となる。憲法第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と明記しており、手続上の正当性がなければ自由の制限は一切許されない。すでに保護という重大な判断がなされた後に、関係者が不在者を対象に説明の辻褄を合わせる発言を繰り返していたとすれば、それは手続が当初から不備を抱えていたことを裏付けるものである。また、その説明内容が内部文書等に記載された場合、刑法第158条に定める虚偽公文書作成及び行使罪に該当する可能性がある。同条は「公務員がその職務に関し、虚偽の公文書を作成し、又は偽造し、これを行使したときは、3月以上10年以下の懲役に処する」と定めており、後付けで合理化された保護理由を記載し、それを組織内外の判断材料として使用した時点で構成要件を満たす。重要なのは、被害者が発言不能な状況下でのみ、関係者が本音や真相を口にしていた点であり、これにより当初の判断が虚偽構成であったことが露呈する。このような事後的な正当化の言動が、むしろ違法性を強く証明する材料となる点において、法制度の趣旨に照らして看過できない。本人の言い分を封じたまま、虚偽に基づく筋書きを固めていく一連の過程は、行政の透明性および正当性の根幹を脅かす重大な問題であり、手続の適正性を欠いた組織的違法行為として扱うべき性質を有している。
立場のすり替えと刑事訴訟法198条の観点から見る取調べの問題点
被害者と加害者の立場を入れ替えるような事情聴取が行われた場合、それは刑事訴訟法第198条に反する疑いがある。同条は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者を取調べることができる。取調べに当たっては、被疑者の意に反して供述を強要してはならない」と明記しており、任意性が重視されている。つまり、取調べにおいて、誘導的な質問や前提をすり替えるような話法を用いて、被害者を加害者として位置づけるような構成で進めることは、法的には供述の強要と解され得る。また、虚偽の構図に基づいた事情聴取は、虚偽公文書の作成(刑法第158条)にもつながる可能性があり、後日それを内部記録や報告書に反映すれば、明確に違法性が問われる。さらに、そうした事情聴取が警察の組織的判断や内部の共通認識として行われていた場合、その違法性は個人の行為にとどまらず、制度運用全体に広がる問題となる。被害者に対して矛盾する説明を繰り返し、自白を引き出す形で立場を転換させるという行為は、公平な捜査を旨とする刑事手続において最も忌避されるべき違法対応であり、その法的影響は極めて重大である。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察内部の論理が市民の自由を侵害する構造的危険性
- 捜査過程における発言操作と社会的信頼の崩壊
- 保護制度の乱用が精神的被害と社会的不信を生む構造
警察内部の論理が市民の自由を侵害する構造的危険性
警察が保護を判断する際に、事実関係の確認を経ずに先に筋書きを定め、その方向に現場対応を合わせていくという運用が行われたとすれば、それは個々の過失ではなく、制度内部に組み込まれた論理的構造の問題として認識すべきである。市民の自由は憲法第13条および第31条において保障されており、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」とされている。しかしながら、現場で「保護ありき」の方向性が先行していた場合、現実には自由の制限や拘束が行われていたにもかかわらず、その正当性が事後的に構成されていたことになる。このような慣行は、個人の権利を守る制度設計を実質的に形骸化させ、市民の人権に対する組織的な軽視を内包する。しかも内部での説明や発言の整合性が優先され、記録や報告に矛盾が残っても追及されない風土が存在すれば、それは組織としての責任回避構造と表裏一体であり、誤った判断が繰り返される温床となる。このような構造を放置すれば、警察に対する市民の信頼は長期的に毀損され、行政機関全体への不信にもつながる。市民の側からは、何が「任意」で何が「強制」なのかを判断する機会すら与えられないまま、権限の行使を受けることとなり、民主社会の前提が揺らぐ深刻な問題である。
捜査過程における発言操作と社会的信頼の崩壊
警察による事情聴取の過程で、被害者とされる者が意図的に加害者として扱われるよう話の構造が作られていた場合、それは取調べの任意性を根本から覆す深刻な問題である。刑事訴訟法第198条は「取調べに当たっては、被疑者の意に反して供述を強要してはならない」と定めているが、発言の意味を誘導的に捉え、無理に論理をつなげることで事実を捻じ曲げる手法が横行すれば、もはや真実追及ではなく結論ありきの押し付けに変質してしまう。こうした取調べの現場での恣意的な解釈や、供述の一部だけを切り取った誤解を前提にした構成が公文書や報告書に反映され、それが上層部や関係機関への説明に用いられた場合、結果として市民に対する情報のねじれが生じ、最終的には社会的信頼の大きな損失となる。警察の発言が録音されていたにもかかわらず、実際の記録や説明の中でその内容が歪められていた場合、矛盾の存在は誰の目にも明らかとなり、その発言操作自体が信頼の破壊を生む。さらに、そうした対応が反復されていれば、組織の中に「事実ではなく方針に従って話を整える」という文化が固定化される。このような構造は、警察に対する社会的正当性を根本から崩し、市民との間に深い分断を生む制度的弊害を伴う。
保護制度の乱用が精神的被害と社会的不信を生む構造
本来、保護制度は緊急的に生命や身体の安全を確保するために設けられたものであり、任意である以上、本人の意思と判断に最大限の尊重が求められる制度である。しかし、今回のように事実確認を経ることなく保護措置が前提化され、さらにその対応が後付けで正当化されていた場合、本人にとっては不当な拘束と精神的打撃が加えられる形となる。これは一時的な不自由という次元にとどまらず、「自分の意見が聞かれず、勝手に判断された」という根源的な信頼喪失につながる。特に、警察署という密室性の高い空間で、本人が不在の状態において関係者だけで「筋書き」を整え直していたことが録音などにより明らかとなった場合、その不信感は深刻なトラウマへと発展しうる。さらに、制度の運用そのものに対する市民の不信が広がれば、今後本当に保護が必要な場面でも、本人が警察に関わることを避けようとする傾向が強まり、制度全体の実効性が低下する恐れがある。保護制度はその存在自体が重要であるからこそ、運用上の一件一件の信頼性と公正性が社会の根幹に関わる。行政権力の濫用によって本来守るべき制度の信頼性が損なわれるならば、それは個人の問題にとどまらず、制度の根幹を崩壊させる社会的問題として真剣に検証されなければならない。
まとめ
警察による「保護ありき」の判断が事実確認を伴わずに進められていた場合、それは組織的な職権濫用や適正手続違反の疑いを含んでいる。さらに、保護後に被害者が不在となった場面で、関係者がこれまでの対応の整合性を取るために虚偽の発言を重ねていたことが録音により確認されれば、その判断が後付けで作られた虚構であったことが明らかになる。こうした構造は、刑法第193条や憲法第31条に反するだけでなく、捜査の信頼性そのものを根底から揺るがすものである。また、虚偽の筋書きを元に事情聴取が行われ、被害者を加害者に仕立てようとする意図があったとすれば、それは刑事訴訟法第198条にも明確に反し、市民の人権を軽視した重大な問題といえる。今回明らかになった事例は、一個人の経験にとどまらず、制度の運用全体に警鐘を鳴らすものであり、社会全体としてこの構造的問題に目を向ける必要がある。