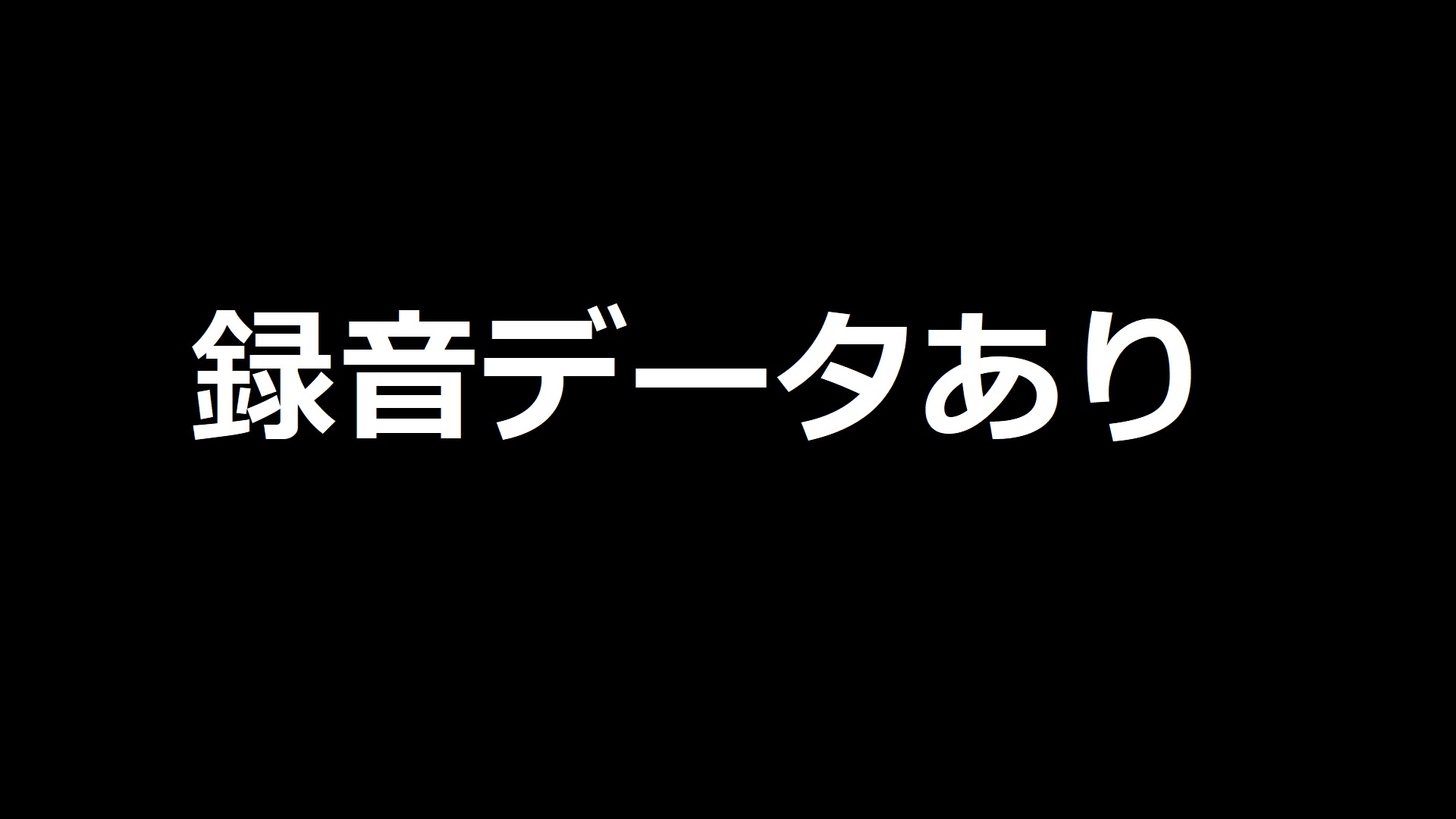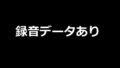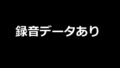公共の場において市民がスマートフォンで記録を行う行為は、違法性がない限り原則として認められている。にもかかわらず、現場に出動した警察官が「撮影をやめてください。警察官が言っていますよ」と発言することで、市民の自由が事実上制限される場面が存在する。このようなやり取りには、単なるマナーや秩序の問題にとどまらず、法的・構造的な圧力が含まれている可能性がある。本記事では、警察官による発言が市民の行動にどのような影響を与えるのか、法令と構造の両面から検証する。
警察官が言っているからなんなの?
- 経緯
- 警察官が言っているからなんなの?
- 考察:警察官が言っているからなんなの?
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定のような取り決めが交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、いつものことではあるが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
警察官が言っているからなんなの?
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
相手は「知らない」と答え、「それは役場の誰かが勝手に言ったことじゃないのか」などと口にした。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定のような取り決めは確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく、まずは言い返すことが前提のような応対。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」──お決まりの反論が続く。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
私がまず思ったのは、保護される危険性があるということだった。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしている側が一方的に「保護」という名目で排除されかねない。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを手に取った。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護という名のもとに強制的な処置へと導かれるか──それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院への入院という「お決まりのコース」が待っている。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであるとみられており、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物として慎重に扱わなければならない。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
2人目の警察官が到着した。
その警察官は、私の名前を何度も呼びかけてきて、明らかに口を開かせることを目的とした圧力的な態度をとってきた。
私は無言のまま、スマートフォンで録画を続けていたが、あまりにもしつこく名前を呼び続けてくるため、やむを得ずこう答えた。
「連携取れていますか?先ほどの警察官に話はしていますよ。」
それでも私の名前を呼び続け、何とかして発言させようとする姿勢は変わらなかった。
そこで、私は改めて明確にこう伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すると、警察官はこう返してきた。
「聞いていますよ。その上で話しかけているんです。」
さらに警察官は圧力を強めてきた。
「撮影をやめてください。警察官が言っていますよ!」
考察:警察官が言っているからなんなの?
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた家庭があった。約5年前、鳩山町役場の仲裁により、互いの家の前を通らないという紳士協定のような取り決めが交わされ、それ以降は大きなトラブルもなく平穏が保たれていた。しかし、ある日を境に隣人が再び当該家庭の前を通るようになり、関係が再び緊張を帯びるようになった。再三の抗議にもかかわらず、隣人は協定の存在を否定し、通報によって警察官が現場に到着する事態に至った。当該家庭の人物は過去に不当な保護措置を受けた経験から、録画と弁護士連絡を含む慎重な対応を選択。警察官に対して「弁護士の折り返しを待っている。それ以上のことは話さない」と明言していた。それにもかかわらず、2人目の警察官は執拗に名前を呼び、発言を引き出そうとする対応を見せた。さらに「撮影をやめてください。警察官が言っていますよ」と発言。これに対して、撮影に関する違法性の指摘や法的根拠の説明はなく、単に「警察官が言っている」という理由だけが根拠として用いられていた。現場には隣人夫婦と町内会長も同席しており、当該家庭にとっては数的不利と社会的圧力が同時にかかる構造となっていた。発言の内容ではなく、発言者の肩書きが行動の正当性を左右する場面が可視化された事例であった。
関係する法令
- 日本国憲法 第21条(表現の自由)
- 日本国憲法 第38条(黙秘権)
- 日本国憲法 第34条(弁護人依頼権)
- 警察法 第2条(警察の責務)
- 刑事訴訟法 第198条 第2項(供述の任意性)
- 刑法 第193条(特別公務員職権濫用罪)
- 刑法 第223条(強要罪)
- 国家賠償法 第1条(公務員の不法行為による損害賠償責任)
日本国憲法 第21条(表現の自由)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法 第38条(黙秘権)
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
日本国憲法 第34条(弁護人依頼権)
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、拘禁されない。
警察法 第2条(警察の責務)
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることを、その責務とする。
刑事訴訟法 第198条 第2項(供述の任意性)
取調べをする者は、被疑者の供述が任意にされたものであることを明らかにするため、必要があるときは、取調べの状況を録音し、又は録画しなければならない。
刑法 第193条(特別公務員職権濫用罪)
裁判、検察若しくは警察の職にある者又はその他の特別の職務を有する公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法 第223条(強要罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処する。
国家賠償法 第1条(公務員の不法行為による損害賠償責任)
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。
専門家としての視点
- 録画中止要請の法的限界と職権濫用
- 発言誘導と供述の任意性の崩壊
- 多人数による囲い込みと構造的圧力の法的評価
録画中止要請の法的限界と職権濫用
公共の場所における撮影行為は、日本国憲法第21条が保障する表現の自由に基づき、原則として制限されるものではない。警察官が「撮影をやめてください。警察官が言っていますよ」と発言する場合、その言葉の裏付けとなる具体的な法律的根拠が示されない限り、これは単なる要請にとどまる。しかし、肩書きを利用して命令的に伝えることで、実質的には強制に近い影響力を持つ場合、その行為は職権の逸脱と解されるおそれがある。刑法第193条(特別公務員職権濫用罪)では「裁判、検察若しくは警察の職にある者が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」に処罰されると明記されている。録画の中止を命じることが法令に基づかないにもかかわらず、肩書と場の圧力をもって義務のように受け取らせた場合、この条文に該当する可能性がある。また、警察法第2条においては「個人の生命、身体及び財産の保護」に加え、「公共の安全と秩序の維持」を責務としながらも、その活動が「適正かつ公平」であることが求められており、恣意的な指示や命令はその原則に反する。撮影行為が周囲に直接的な危険や混乱を引き起こしておらず、他者の権利を侵害していないのであれば、それを中止させる正当な理由は存在せず、警察官の一方的な発言が違法な職務執行に該当する可能性は否定できない。
発言誘導と供述の任意性の崩壊
現場で発言を控える意思を明確にしている人物に対し、警察官が名前を繰り返し呼び、発言を促し続ける行為は、憲法第38条における「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」という規定に対し疑義を生じさせる。さらに、刑事訴訟法第198条第2項においては、「取調べをする者は、被疑者の供述が任意にされたものであることを明らかにするため、必要があるときは、取調べの状況を録音し、又は録画しなければならない」と定められており、任意性の担保が不可欠とされている。仮に発言を引き出すための行動が、対象者に心理的圧迫を与えるものであり、しかもその前提として「弁護士に連絡している」「それ以上のことは話さない」との意思表示があった場合、警察官の行動は供述の自由を事実上制限する方向に作用する。このような状況で引き出された発言は、手続的に任意とは評価され難く、その後の記録や対応にも影響を与え得る。また、国家賠償法第1条は「公務員が故意又は過失により違法に他人に損害を加えたとき」において、国家が賠償責任を負う旨を定めており、仮に精神的苦痛や社会的不利益が発生した場合、違法な職務遂行としての責任が問われる構造が成立する。
多人数による囲い込みと構造的圧力の法的評価
当該事案においては、警察官2名、隣人夫婦、町内会長、隣の隣の元警察官の計5名が、1人の個人を取り囲む状況が構成されていた。こうした構造は物理的拘束を伴わずとも、社会的・心理的圧力として作用する性質を持つ。特に公務員が関与する場合、このような状況で発言や行動を求める行為は、刑法第223条(強要罪)の構成要件である「暴行又は脅迫を用いて、人に義務のないことを行わせた」状態に準ずる可能性がある。また、複数の立場者が同時に発言を促す状況では、警察官による対応が形式上は任意であっても、実質的には従わせる空気を形成している場合が多い。さらに、警察官がこの構図を利用する形で録画の中止や発言を求めた場合、刑法第193条に規定される特別公務員職権濫用罪に該当する余地がある。国家賠償法第1条の適用対象としても、こうした構造において被った精神的圧迫や名誉の侵害は、職務上の違法性と損害の因果関係が成立し得る。囲い込みが明示的な命令や拘束を伴わなくとも、結果として自由な意思決定が阻害されていれば、それは違法な圧力構造として法的に評価される。
専門家としての視点、社会問題として
- 現場対応における公的肩書の濫用と市民の萎縮
- 孤立した個人に対する構造的包囲の危険性
- 記録行為への妨害が生む透明性の欠如
現場対応における公的肩書の濫用と市民の萎縮
公共空間において「撮影をやめてください。警察官が言っていますよ」という発言が市民に与える心理的影響は、単なる要請にとどまらない。肩書のある者からの発言は、一般市民にとっては命令と等しく受け取られる場合があり、その場での拒否や無視は「不穏当な態度」「挑発的行為」とされる危険性を内包している。これは現場対応における権力の非対称性が露骨に表れる場面であり、市民が法的に許容された行為であっても、それを実行すること自体が圧力下に置かれる現実を示している。こうした態度が現れる背景には、日常業務において「迅速な処理」「騒動の回避」を優先するあまり、法的正当性よりも現場での支配力が優先される文化が存在している可能性がある。しかも、その命令が制度的に違法でないにしても、相手がその意味を正しく理解しない状況下では、法的拘束力のない要請が、事実上の強制力を持ってしまう構造がある。このような運用は、表現の自由や行動の自由を制度的に保障されているはずの市民に対して、警察がもつ権威を行使することで意思決定をねじ曲げさせる効果を持ち、権利行使を心理的に困難にさせるという意味で、権限の越権的使用と見なされかねない。現場対応で求められるのは、肩書ではなく行為の内容に法的正当性があるかどうかであり、肩書によって相手を抑え込もうとする言動は、制度の本旨に反し、組織としての信頼性を損なう温床となる。
孤立した個人に対する構造的包囲の危険性
この事例で最も象徴的なのは、当該家庭に対して隣人夫婦、警察官2名、町内会長、隣の隣の元警察官が一堂に会し、1人を取り囲む構造が形成されていたという点である。人数の多寡だけではなく、それぞれが持つ立場や社会的属性が心理的圧力として加わる構図は、制度的中立性を前提とすべき公的対応の場において深刻な問題を孕む。公務員がその場に居合わせることによって、他の関係者の発言に黙示の正当性が付与されたり、警察の権限がそのまま周囲の声に転化されるような状況が生まれた場合、法的には形式上任意であっても、実質的には発言や拒否の自由が封じられる環境となる。こうした環境では、被囲繞者が沈黙や無反応を選ぶことすら「不審」や「抵抗的態度」と解釈されかねず、本人の意図や状況とは無関係に不利な評価が積み上げられる構造がある。これは司法的な正当性以前の問題として、社会的な多数派圧力のもとで個人が自らの身を守る行為すら困難になるという社会的排除の一形態である。行政や治安機関に属する者がこのような構造の中に加わる場合、特に慎重な立場保持が求められるが、逆にその一員として加担するような振る舞いをした場合には、制度が本来保障すべき弱者保護の理念が反転し、公的制度が私的対立の道具として機能するリスクを顕在化させる。
記録行為への妨害が生む透明性の欠如
映像や音声による記録行為は、現代における市民の自衛手段として広く認知されつつある。とりわけ、過去に不当な処遇を受けたと感じる市民にとっては、録画や録音は単なる証拠保全にとどまらず、現場の力関係を可視化し、第三者評価に委ねるための極めて重要な手段となっている。これに対して「撮影をやめてください」という警察官の要請が、法的な禁止根拠の提示もなく、かつその理由が明示されないままなされるとすれば、それは記録の正当性を否定するものとしてだけでなく、透明性の確保という観点からも大きな問題を含んでいる。行政機関や治安組織の活動は、本来公開性と説明責任を前提に成立しているにもかかわらず、現場での撮影中止要請が常態化すれば、記録されない空間においてのみ特定の行為が行われる状況が温存される。これは制度全体への信頼を失わせ、結果として市民の通報回避、警察不信、沈黙の選択を招く温床となる。特に一方的な通報によって警察が出動し、かつその現場で録画行為が行われているにもかかわらず、停止が強要される構造が繰り返されれば、記録されない対応こそが常態であるという危険な前例を積み重ねることになる。記録を止めさせるなら、その場で正当性を説明できなければならず、それを欠いた中止要請は、記録を嫌う側の都合を黙認する社会構造として機能してしまう。
まとめ
この事例は警察官の言動が現場での力関係にどのような影響を及ぼすかを象徴的に示している。公道における撮影行為は原則自由であり、その自由が警察官の肩書によって圧迫される状況は、表現の自由に対する事実上の制限とみなされかねない。また、弁護士への連絡を明言して黙秘の意思を示しているにもかかわらず、それを無視するような警察官の対応は、供述の任意性を損なう恐れがある。さらに1人を取り囲むようにして複数人が加わる構造は、発言や記録といった正当な権利を心理的に封じ込める社会的圧力を生みやすい。行政機関は中立的立場を堅持しなければならず、警察官がその立場を逸脱すれば、国家賠償法や刑法による責任の対象となる可能性もある。市民が記録を通じて自衛を図る行為が、制度によって妨げられるような社会構造が常態化すれば、監視されるべき権力行使そのものが密室化し、制度への不信が深まる要因となる。この一連のやり取りは、単なる一家庭と警察の対話にとどまらず、制度と市民の関係性における警鐘として読み解くべき重要な事例である。