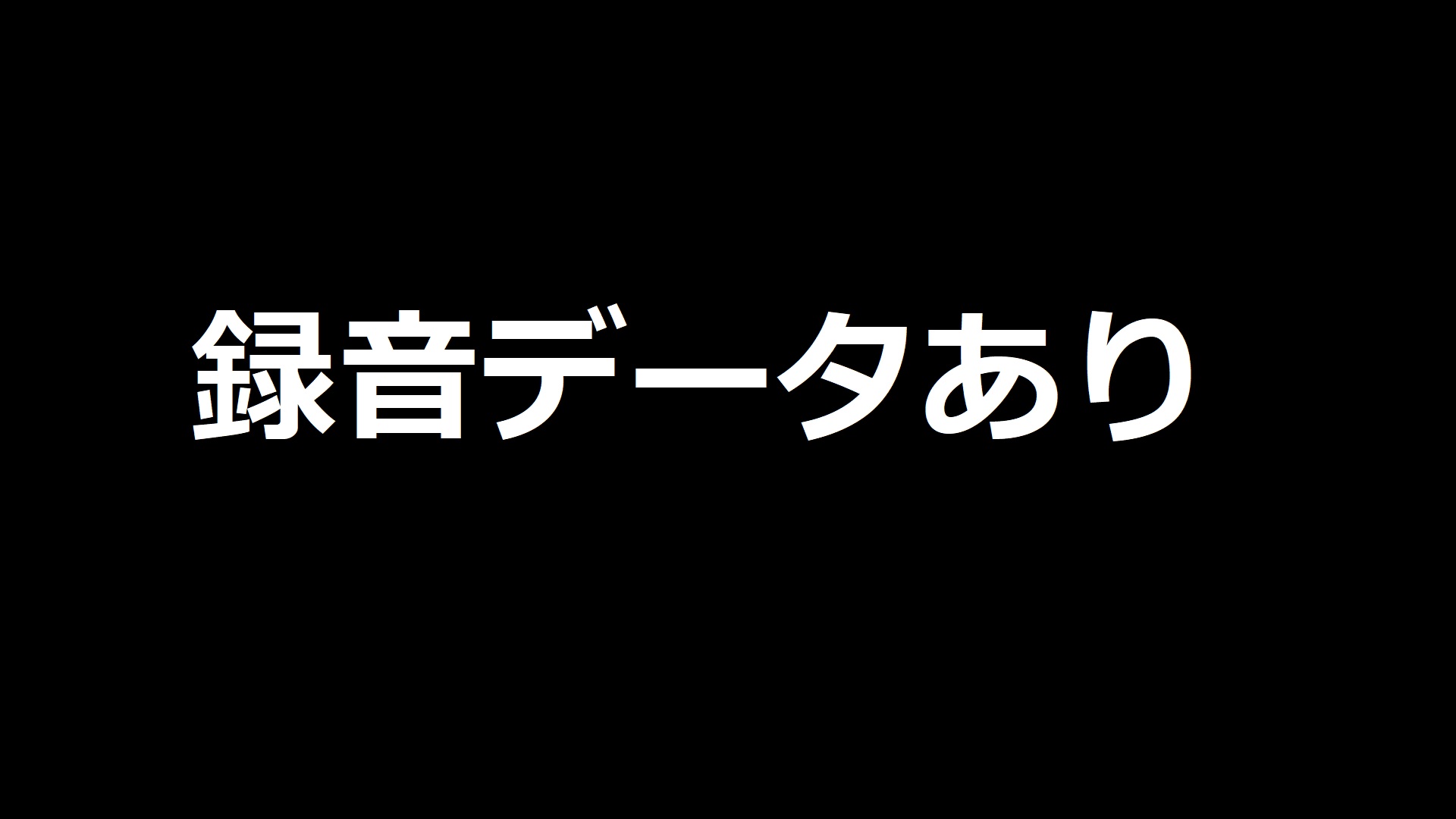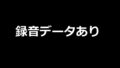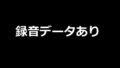犯人特定。不起訴が続く中で、刑事手続が尽きたあと、民事訴訟を見据えた動きの中でついにその身元が明らかになった。ひき逃げ、証拠隠滅、繰り返される嫌がらせ。それでも警察と検察は「不起訴」を繰り返し、救済の道を閉ざしてきた。すべての扉が閉じた先で、わずかに残された手段として動かした民事の準備が、最後の一点を射抜いた。これは、制度の隙間をかいくぐって、ついにたどり着いた「犯人確定」という結論に至るまでの記録である。
 |
犯人確定
- ひき逃げ事件と不当な保護の始まり
- 刑事事件の終結と情報発信の決意
- 民事訴訟への移行と犯人確定
ひき逃げ事件と不当な保護の始まり
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
刑事事件の終結と情報発信の決意
その後、事件は警察に、保護は日弁連人権擁護委員会へ。
事件については被害届を東松山警察署へ提出、さいたま地方検察庁熊谷支部に送検された。
さいたま地方検察庁熊谷支部A検事は「不起訴」。検察審査会に不服申し立てし「不起訴相当」。
民事訴訟へ移行しようとしていたところ、弁護士相談の弁護士から「告訴」を勧められる。
再び東松山警察署へ「告訴」。再度さいたま地方検察庁熊谷支部へ送検。担当は再びA検事。そして「不起訴」。
もう一度検察審査会に不服申し立てをするも「不起訴相当」。
ここで刑事事件としては完結した。
そのことによって、それまで考えていたこのブログ、YouTube、xでの情報発信を始めた。
民事訴訟への移行と犯人確定
そして犯人確定。
2回目の告訴の際、さいたま地方検察庁熊谷支部のA検事に対して、私が「民事訴訟を提起するから住所を教えてくれ」と求めたところ、「弁護士が決まったら、弁護士から連絡をもらえれば教える」との回答があった。
その言い方に、私はA検事が弁護士に対して何らかの圧力をかけるつもりなのだろうと感じていた。
これは、かつて事件直後に法テラス川越で弁護士に相談した際、その担当弁護士の対応に違和感を覚え、警察の圧力がかかっているのではないかと感じたときの感覚に似ていた。
私はもう何十回も弁護士会の弁護士相談をしていたから、その中で「犯人の住所は検察に聞かなくても、弁護士が弁護士会を通して確認すればわかる」と聞いていた。今回の民事の担当弁護士は「警察に聞けばすぐわかる」と言っていたし、担当弁護士が検察や警察の圧力に屈するような弁護士には感じなかったが、一応「弁護士会を通して陸運局に問い合わせてほしい」とお願いしてあった。
その連絡が2週間ほど前にあったのだ。これで犯人確定。
私が以前から「99%その人物に間違いない」と言っていた犯人が、「100%」になったのだ。
担当弁護士が作成した慰謝料請求書案に記載されていた住所を見ると、それはまさしく「犯人と思われる人物」の住所だった。
もちろん、そこは白の50系プリウスがとまっている家だ。
※なお、今回の民事訴訟については、東京の法テラスを通じて弁護士費用の免除申請をしている。正式な書類はまだ届いていないが、担当弁護士からは「ほぼ適用される見込み」との話があった。
私は精神障害者福祉手帳を所持しており、障害年金を受給していることもあって、申請の際には年金額について確認された記憶がある。
さて、検察が言う犯人の不起訴理由のひとつに「犯人が反省している」というものがある(悪質な傷害罪、救護義務違反、過失運転致傷罪、道路交通法違反、救護義務違反が、反省しているというだけで「不起訴」となるのも意味不明だが)。
その「反省している」犯人が、事件後にナンバーを交換し、さらに高齢者マークをつける。
そして2回の不起訴後に高齢者マークを外す。
さらに、私がたまたま犯人宅の前に停車していると、近づいてきて「何か用ですか?警察に通報しますよ」。
これらが、反省している人間の行動なのだろうか。
いずれにしても、「犯人確定」。これは、この2年間の葛藤の末にたどり着いた、ひとつの大きな区切りとなるものである。
今後も他の問題と並行して、今度は民事請求、民事訴訟への展開を共有していきたいと思っている。
ただし、公開することでこちらが不利になるおそれのある内容については、あえて伏せ、後日公表とさせていただくことをご理解いただきたい。
関係する法令
- 刑事訴訟法 第47条(訴訟記録の閲覧制限)
- 国家賠償法 第1条(違法な公権力の行使による損害賠償)
- 個人情報の保護に関する法律 第23条(第三者提供の制限)
- 検察審査会法 第30条(審査会の審査義務)
- 刑法 第105条(証拠隠滅)
刑事訴訟法 第47条(訴訟記録の閲覧制限)
公判の手続は、公開する。ただし、裁判所は、被告人の名誉を保護し、又は裁判の秩序を維持するため必要があると認めるときは、決定で、これを公開しないことができる。
国家賠償法 第1条(違法な公権力の行使による損害賠償)
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
個人情報の保護に関する法律 第23条(第三者提供の制限)
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
検察審査会法 第30条(審査会の審査義務)
検察審査会は、審査の申立てがあつた事件については、速やかにこれを審査しなければならない。
刑法 第105条(証拠隠滅)
自己又は他人の刑事事件に関し、証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽証をさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
専門家としての視点
- 検察による訴訟上の情報提供の制限とその限界
- 「反省している」という不起訴理由の適否と量刑判断の逸脱
- 加害者とされる者の行動と証拠隠滅罪の成立要件
検察による訴訟上の情報提供の制限とその限界
刑事訴訟法第47条は公判手続の公開を原則としつつ、必要な場合には裁判所の判断で制限することができると規定しているが、この趣旨は刑事裁判における透明性と公正性の確保にあるため、刑事手続において収集された情報を、正当な民事訴訟の準備のために利用する場面で一律に制限することは適切とは言えないと考えられる。民事訴訟の提起を前提とし、訴状の送達先として加害者の住所情報を確認する行為は、裁判所法第80条および民事訴訟法第133条の趣旨にもとづくものであり、正当な訴訟行為である。そのうえで、検察官が「弁護士を通じなければ住所は提供できない」と発言した場合、それが被害者の法的救済手段を事実上妨げる結果となるならば、国家賠償法第1条における「違法な職務行為」に該当する可能性がある。とりわけ、被害者側に代理人弁護士が未定である段階で、情報提供を拒絶または遅延させる行為が民事訴訟の提起そのものを阻害している場合には、検察の職務上の中立性を逸脱する懸念が生じる。個人情報保護法第23条は、原則として第三者提供を禁止しているが、法令に基づく場合や人の生命・身体・財産を保護するために必要である場合には例外を認めており、被害者が訴訟を提起し損害賠償を求めることは、まさに財産権の保護に該当するため、法的根拠のある提供が可能な範囲である。したがって、検察の対応が過度に慎重になり、法令上許容される範囲を逸脱して個人情報を過剰に保護している場合、それは結果として司法アクセスの阻害となりうる。
「反省している」という不起訴理由の適否と量刑判断の逸脱
検察官による不起訴処分には、刑事訴訟法第248条が定める「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重並びに情状」等を踏まえた訴追裁量が認められているが、それはあくまで合理的かつ客観的な根拠に基づいてなされるべきである。「反省している」という主観的要素だけを根拠として、傷害罪(刑法第204条)や過失運転致傷罪(自動車運転処罰法第5条)といった重大な結果を伴う犯罪を不起訴にすることは、著しく訴追裁量を逸脱する可能性がある。特に本件では、救護義務違反(道路交通法第72条)や証拠隠滅に類する行為が継続的に認められている中で、加害者側に対して処罰が一切なされていないことは、刑事司法の平等性を損ない、国家の正義執行機関としての信頼を揺るがす事態である。さらに、同一検察官が繰り返し同じ被疑者に対して不起訴を決定していることは、形式的には問題がないように見えても、検察審査会法第30条に基づく市民の審査制度を実質的に形骸化させるものであり、訴追の客観性確保という立法趣旨に反する。よって、「反省」を理由とする処分には、被害の重大性と社会的影響を十分に考慮した上で、慎重かつ透明性のある判断が求められるべきである。
加害者とされる者の行動と証拠隠滅罪の成立要件
刑法第105条は「自己又は他人の刑事事件に関し、証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽証をさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めており、これは証拠保全による司法の公正性を担保することを目的とした条文である。被疑者が事件直後にナンバーを変更したり、高齢者マークを装着・取り外す行為を行った場合、それが単なる日常的な事情変更ではなく、事件の追及や特定を免れる目的であったと認定できる場合、証拠隠滅罪の構成要件に該当する可能性がある。特に、被害者が現場確認や証拠収集を進める中で、加害者とされる人物が接近し「警察に通報しますよ」などと告げた行動は、証言封じや威圧と受け取られる余地があり、証拠保全活動に対する妨害としての評価が必要である。また、証拠隠滅罪の成立には「隠滅意思」が必要とされるが、行動の時期や文脈、被疑者が本件において起訴される可能性を十分認識していた状況下での行為であれば、その意思の存在も推認可能である。さらに、公訴が提起されていない段階でも、将来訴追される可能性が高い案件において証拠を隠滅する行為は処罰対象となるため、本件における加害者とされる者の一連の行動は、形式的に罪に問われていないだけで、刑法上の構成要件には十分接触しているといえる。
専門家としての視点、社会問題として
- 刑事処分の透明性欠如がもたらす市民の司法不信
- 加害行為の軽視と社会的制裁の不均衡
- 公的機関の対応がもたらす二次被害と制度疲労
刑事処分の透明性欠如がもたらす市民の司法不信
検察官による不起訴処分が繰り返された結果、加害行為が事実上何らの制裁も受けないまま放置されるような事態が継続すると、市民の間に司法制度そのものへの不信感が広がる。特に、反省しているという主観的事情だけを根拠に刑事処分を免れるような事案が可視化されることで、「司法とは一部の人間に有利に働くもの」という印象を一般市民に植え付けてしまうのである。これは、法の下の平等という憲法第14条の理念にも反するばかりか、法秩序全体の正当性を揺るがす深刻な社会問題である。検察官には訴追裁量が認められているが、それはあくまで合理的で客観的な根拠に基づき、市民の理解を得られるような説明責任を果たすことを前提とするものであり、起訴か不起訴かの結論だけを一方的に下す現在の運用は、市民感覚との乖離を広げる一因となっている。検察審査会制度はこうした不透明な不起訴判断に対して市民の目線を加える目的で設けられているが、今回のように2度にわたり「不起訴相当」という結果が繰り返されると、制度そのものが形骸化しているとの懸念が生じる。検察審査会が有効に機能するには、審査員に対して十分な事実資料と判断材料が提供されること、そしてその審査結果に社会的影響が伴うよう制度設計の見直しが不可欠である。現在のままでは、制度は単なるガス抜きの役割にとどまり、市民の信頼回復には程遠い状況にある。刑事司法の正統性を社会全体で維持するためには、訴追判断の透明性と理由開示を義務化する法制度の整備が求められる。
加害行為の軽視と社会的制裁の不均衡
ひき逃げや救護義務違反といった重大な交通犯罪が、実際の被害者が存在し、診断書などの証拠が揃っていながら刑事処分の対象とならないという状況は、社会的制裁の不均衡を生み出している。加害行為が軽視されると、それは同種の行為を助長するメッセージにもなりかねず、法秩序の予防的機能が失われる危険がある。特に今回のように、加害者が事件後にナンバーを交換したり、目印となる高齢者マークの着脱を繰り返すなど、外形的にみて自己の責任回避を意図した行動が存在している場合、それが刑事責任に問われることなく看過された場合には、国民全体に対して「やった者勝ち」との誤解を広める結果となる。交通犯罪は一瞬の過失で起きるとされる一方で、事故後の対応において誠実さが重視される分野であり、逃走や隠蔽行為は極めて悪質と見なされる。したがって、反省しているという一言では説明がつかない行動が重ねられた場合には、社会的にも法的にも相応の責任が問われるべきである。今回、加害者とされる人物が被害者に対して「警察に通報しますよ」と発言した点は、被害者を威圧し、監視的態度を示すものであり、被害者保護という観点からも重大な問題をはらんでいる。刑事処分を回避した加害者が社会的には保護され、被害者が継続的に恐怖や不安の中で暮らす構造は、法治国家において是正されるべき優先課題である。
公的機関の対応がもたらす二次被害と制度疲労
本件において検察の不起訴対応が繰り返され、かつ加害者とされる者への適切な対応が取られないまま時間が経過したことは、被害者にとって「司法に訴えても救済されない」という感覚をもたらし、精神的な二次被害を引き起こしている。さらに、検察が住所情報の提供を「弁護士が決まってから」と条件をつけて遅らせる対応は、民事訴訟の準備を妨げ、被害回復の機会を先送りにしている。このように、本来被害者を守る立場にあるはずの公的機関の対応が、逆に被害者を追い詰める構造を生み出している点に社会的な深刻さがある。精神的負担が長期化し、弁護士の手配や民事手続に必要な準備が遅れることで、結果として法的手続の実効性が損なわれる。制度疲労とは、制度が形としては存在していても、その目的どおりに機能しない状態を指す。検察審査会に不服申し立てを2度行っても結果が変わらず、明確な説明もないまま終結するという流れは、まさに制度疲労の現れである。加えて、こうした制度の不全に対してメディアや第三者が取り上げる機会が少ないことも、問題の可視化を妨げている。市民が法的制度に期待を持ち、適切に利用できるようにするには、行政機関と司法機関の連携強化だけでなく、説明責任の徹底と情報公開の透明化が必須である。さもなければ、被害者が制度の中で孤立し、泣き寝入りを強いられるという構造が今後も再生産され続けることになる。
まとめ
警察や検察といった公的機関の対応が適切でなかったとされる事例において、司法手続が被害者にとって真に機能しているのかを改めて考えさせられる内容である。特に不起訴処分が繰り返される中で、被害者が民事訴訟へと手段を移行しようとする過程で、情報提供が制限されたり、加害者の行動が事実上の証拠隠滅と受け取られかねない形で進行している現状は、司法制度の本質的な役割と社会的信頼性に疑問を投げかけるものである。検察の訴追判断が透明性に欠け、市民目線での合理的説明がなされない限り、制度は市民の信頼を損ねる危険性を持ち続ける。被害者が正当な手続によって加害者を訴え、救済を得るためには、情報アクセスや訴訟支援の制度がより機能的に整備される必要がある。