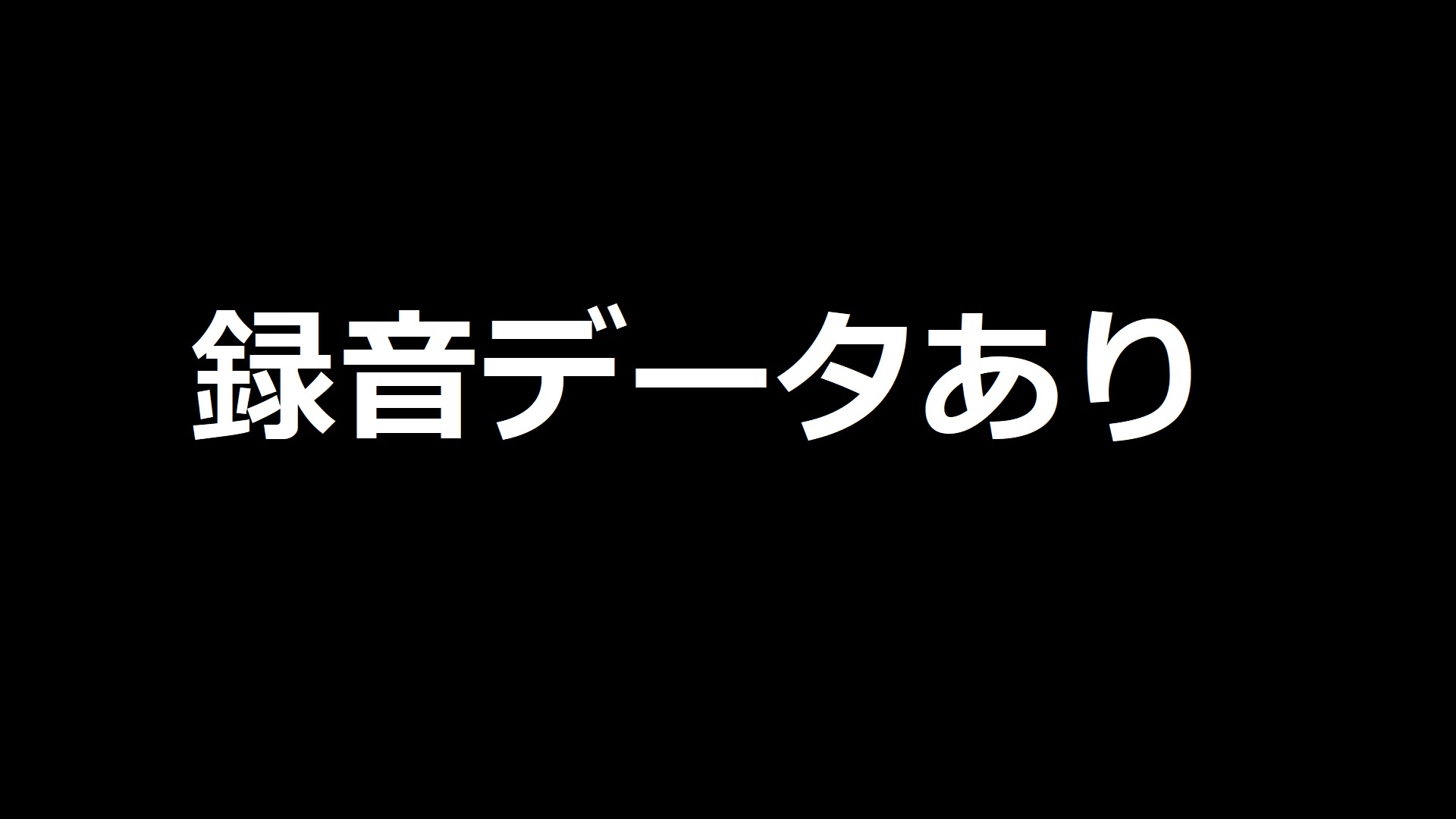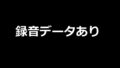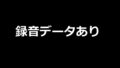家庭内の支配や暴力は個人の問題として片付けられがちだが、社会全体に影響を及ぼす深刻な課題である。特に親子間の暴力や精神的虐待は長期間にわたって継続しやすく、被害者の自立を妨げる要因となる。刑法やDV防止法に基づく対応が求められるが、家庭内の問題は外部に伝わりにくく、適切な支援を受けることが難しいのが現状である。本記事では、家庭内暴力に適用される法令や支援制度を詳しく解説し、被害者が自らの権利を守るための方法について考察する。支配構造から抜け出し、健全な生活を取り戻すためには、社会全体の認識を変え、適切な対策を講じる必要がある。
結局なに一つ変わっていない父 | 学習能力ゼロ
- これまでは
- 同居から元のパワハラ、モラハラへ
- 冷戦から「出てけ」防止へ
これまでは
2023年2月9日、4年間にわたる鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせの末事件は起きた。事件後東松山警察署で事情聴取を受け、謎の警察による不当な保護。
その背景には、父による幼少期からの虐待、DV、パワハラ、モラハラがあった。成人してからもパワハラ、モラハラは行われ、やがて被害者は結婚。新婚家庭にも干渉してくる、同居すれば1年で破綻。その後それらのことが一因となり被害者の家庭は崩壊、離婚した。
離婚後、さすがにこれ以上人生を左右されたくないと、同居を拒否するものの、母の説得により同居してしまう。ただし今回だけは「出てけ」には屈せず、家から出ていかないことを心に誓う。その後・・・。
同居から元のパワハラ、モラハラへ
最初は優しい父、しかし1年経つと父は豹変した。実はこれはお決まりのパターンで、客観的に見て兄も、というか兄こそ同じことを何度も繰り返している。「出てけ!」1年経つと「帰ってこい」、「出てけ!」1年経つと「帰ってこい」、この繰り返しである。
豹変後の父は、またパワハラ、モラハラを始める。被害者は当時ひどい鬱状態と精神的に荒れていたこともあり、すでに睡眠導入剤をアルコールで飲まないと眠れない状況にあった。
ある日、睡眠導入剤をアルコールで飲んで酩酊状態の被害者に対して、父の恫喝が始まった。理由もわからなければ、何を言っているかも理解できない。座っている被害者に対し、立った父は上からなにか大きな声で怒鳴り続けている。立ち上がることもできず、父に「やめてくれ。何を言っているかわからない」と訴え続けたが、それも1時間以上続いた。
冷戦から「出てけ」防止へ
父と被害者の冷戦状態が始まる。これまで1年で「出てけ」があったわけだが、今回被害者は「今回は絶対に出ていかない」と心に決めていたので、父の「出てけ」を多少の脅しと暴力で言わせないようにしていた。その暴力というものは父がこれまで行ってきたことからすると、ほんの5分の1の期間、ほんの10分の1の内容を行ったという程度のことである。胸倉をつかむ(父はそれを首を絞めると表現していたが)、地面に押し倒す、やったとしてもケツを蹴っ飛ばす程度のものである。その程度のことならやっても構わないというのは、それよりも酷いことをやられてきたのであるから、そういう環境にいたわけであるから、それを暴力と呼ばないのが我が家のしきたりだと考えるのも、無理がないことだと被害者は思う。ましてや母の髪の毛をつかんで家中引きずり回す父なのであるから、その程度のことをされて暴力とは呼ぶまい。
一時期雪解けを迎えたが、雪解け後1年、また「出てけ」の兆候が見られた。当然被害者は「今回は絶対に出ていかない」である。
学習しない父と繰り返される支配の連鎖
- 過去と現在の変わらぬ支配
- 同居後の生活と精神的負担
- 対立と支配からの解放の試み
過去と現在の変わらぬ支配
この家庭では、長年にわたって父による支配的な態度が続いてきた。幼少期からのパワーハラスメントやモラルハラスメントは、成人後も変わることなく繰り返され、家族の生活に大きな影響を与えてきた。結婚後もその支配は続き、新婚家庭にまで干渉が及ぶこととなった。これにより家庭は破綻し、離婚という結果を迎えた。その後、独立を試みるも、母の説得によって再び同居することとなる。しかし、今回はこれまでのように父の命令に従うことなく、家庭内での立場を維持することを決意していた。しかし、過去のパターンと同様に、最初は穏やかだった関係も時間が経つにつれ崩れ始めた。父は再び威圧的な態度を取り始め、過去の支配的な振る舞いを繰り返すようになった。「出てけ」と「帰ってこい」を繰り返す父の行動は、家庭内に不安定な環境を作り出し、精神的な負担を増大させた。これにより、家庭内の緊張は高まり、父の言動による影響がますます顕著になっていった。
同居後の生活と精神的負担
再び同居を始めた後、父の支配的な態度は時間の経過とともに強まっていった。初めのうちは表面上穏やかに接していたが、次第に威圧的な態度が見られるようになり、家庭内での空気は緊張感に満ちたものになっていった。特に精神的に不安定な状況下にあった家族に対し、父の怒鳴り声や圧力は強く影響を与えた。ある日、家族の一人が酩酊状態にあった際、父は執拗に怒鳴り続け、その行為は1時間以上にも及んだ。このような行動は精神的な負担を大きくし、家庭内での安心感を奪う要因となった。家族の中には精神的なストレスにより不眠状態に陥る者も現れ、家の中での生活はますます厳しいものとなった。家庭内での威圧的な態度は、精神的な安定を崩し、心理的に追い詰められる状況を生み出した。
対立と支配からの解放の試み
家庭内での対立が続く中、これまでのように父の「出てけ」という言葉に従わない決意が固まった。これまでのように家を出ていくことなく、父の支配に屈しないことを選択した。父の暴力的な言動に対しても、従来のように無抵抗ではなく、ある程度の反撃を行うことで、これ以上の圧力を防ごうと試みた。しかし、家族内に長年根付いた力関係は容易に崩れるものではなく、父の支配的な態度は変わることなく続いた。母に対しての暴力も再び表れ、家族の間での緊張は高まり続けた。雪解けのような一時的な和解が見られることもあったが、それは長く続くものではなかった。時間が経つにつれて、また同じ「出てけ」という言葉が繰り返される兆候が見られた。結局のところ、この家庭において父の支配構造は変わることなく続き、家族はまた同じ問題に直面することとなった。
家庭内に関する法令
- 刑法208条(暴行罪) – 身体的な攻撃が行われた場合
- 刑法222条(脅迫罪) – 威圧的な言動や脅迫的な発言があった場合
- 刑法223条(強要罪) – 「出てけ」などの言動を強制する行為
- 刑法204条(傷害罪) – 暴力によって負傷させた場合
- DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律) – 精神的・身体的暴力が継続的に行われた場合
刑法208条(暴行罪) – 身体的な攻撃が行われた場合
暴行を加えた者は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法222条(脅迫罪) – 威圧的な言動や脅迫的な発言があった場合
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処する。
刑法223条(強要罪) – 「出てけ」などの言動を強制する行為
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
刑法204条(傷害罪) – 暴力によって負傷させた場合
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律) – 精神的・身体的暴力が継続的に行われた場合
配偶者または元配偶者からの身体的暴力、精神的暴力、性的暴力を防止し、被害者の保護を目的とする法律。警察や保護施設への相談、接近禁止命令の申請などの措置が含まれる。
家庭内支配の法的課題と救済措置
- 家庭内の暴力と刑法上の責任
- 精神的虐待と脅迫罪の適用
- 強要と家庭における法的保護
家庭内の暴力と刑法上の責任
家庭内における身体的暴力は刑法208条の暴行罪に該当する可能性がある。暴行を加えた者は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされており、たとえ外傷を伴わなくても、暴行行為が確認された場合には法的責任が問われる。さらに、暴行の結果として傷害が生じた場合、刑法204条の傷害罪に該当し「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処される可能性がある。例えば、家庭内で母の髪の毛を掴んで家中引きずり回す行為は、暴行罪の典型例として認識される。これは単なる家庭内の揉め事ではなく、法律上の明確な犯人行為であるため、被害者は警察に通報し保護命令を申請することが可能である。DV防止法では、配偶者や元配偶者に対する身体的暴力を防止し、被害者の安全を確保するための措置が設けられている。特に、警察や裁判所は「接近禁止命令」や「退去命令」を発令することで、加害者による更なる暴力のリスクを軽減できる。これにより、被害者が安全な環境で生活できる法的支援が提供されることとなる。
精神的虐待と脅迫罪の適用
家庭内での怒鳴り続ける行為は、精神的虐待の一種であり、刑法222条の脅迫罪に該当する可能性がある。脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に対し、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」を科すものである。例えば、座っている者に対し立った状態で1時間以上大声で怒鳴り続ける行為は、被害者に精神的な恐怖を与える可能性が高く、犯人として扱われることがある。このような行為が継続的に行われた場合、DV防止法に基づく精神的暴力として認定される可能性もある。警察や福祉機関への相談により、加害者に対する指導や保護命令の申請が可能となる。加害者が精神的虐待を繰り返す場合、家庭裁判所は「接近禁止命令」や「退去命令」を発令し、被害者の安全確保を優先する措置を講じることができる。このように、精神的虐待は刑事・民事の両面で対応可能であり、被害者は法的手続きを通じて適切な保護を受けることができる。
強要と家庭における法的保護
家庭内での「出てけ」「帰ってこい」の繰り返しは、刑法223条の強要罪に該当する可能性がある。強要罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者」に対し、「3年以下の懲役」を科すものである。例えば、「出ていけ」と執拗に命じることは、経済的・精神的圧力を伴う場合には強要行為と見なされることがある。特に、住居に関する権利がある者に対して、暴力や脅迫を伴って退去を強いる行為は違法となる可能性がある。さらに、DV防止法に基づき、配偶者や同居家族に対する精神的圧力は法律上の保護対象となる。家庭裁判所では、保護命令の申請が可能であり、加害者が強要行為を繰り返す場合、罰則を伴う命令が出されることもある。強要罪は家庭内の問題として軽視されがちだが、法律上の明確な犯人行為であり、被害者は適切な法的手段を講じることで、自らの権利を守ることができる。
家庭内支配と社会的孤立の連鎖
- 家庭内ハラスメントの継続と社会への影響
- 精神的支配と経済的依存の問題
- 家庭内暴力と法制度の限界
家庭内ハラスメントの継続と社会への影響
家庭内ハラスメントが継続することは、被害者に深刻な影響を及ぼすだけでなく、社会全体にも悪影響を与える要因となる。特に、家庭内で繰り返されるパワーハラスメントやモラルハラスメントは、被害者の精神的健康を著しく損ない、社会的な孤立を引き起こす可能性がある。日本では、家庭内での支配的関係が長期間続くことが珍しくなく、特に高齢の親が子に対して持つ権力関係が強固な場合、被害者が逃れることが困難になるケースが多い。このような状況が続くと、被害者は仕事や社会的な関係を維持することが難しくなり、経済的自立が阻害されることで、さらに支配関係が強まるという悪循環に陥る。家庭内暴力やハラスメントが長期間放置されると、被害者の精神的健康が悪化し、うつ病や不安障害の発症リスクが高まる。これにより、社会復帰が困難になり、結果として生活保護の受給や社会的支援への依存が増加する可能性がある。家庭内での支配が継続することは個人の問題にとどまらず、社会全体における負担として顕在化するため、早期の介入と適切な法的措置が求められる。
精神的支配と経済的依存の問題
家庭内での精神的支配が続く背景には、経済的依存の問題が深く関わっている。特に、家庭の主な収入源を握る人物が支配的な立場を利用し、他の家族に対して精神的圧力をかけることで、自立を阻止するケースが多い。例えば、「出てけ」と繰り返し命じられたとしても、経済的な余裕がない限り、独立することが困難であり、その結果として支配関係が強化される。これは、精神的虐待と経済的DVの複合的な問題として捉えられるべきである。経済的に自立できないことで、被害者は住居や生活費の確保が難しくなり、結果として加害者との関係を断ち切れなくなる。この問題は、高齢化社会において特に深刻化しており、成人した子どもが親の支配から抜け出せず、精神的ストレスを抱えたまま生活するケースが増加している。経済的依存が継続すると、被害者が自身の権利を主張することが難しくなり、結果として家庭内の支配関係が強固になる。これを防ぐためには、経済的支援や自立支援の制度を強化し、被害者が適切な環境で生活できるようにすることが不可欠である。
家庭内暴力と法制度の限界
日本の法制度において、家庭内暴力に対する対応は徐々に強化されてきたものの、依然として多くの課題が残されている。DV防止法は配偶者間の暴力に焦点を当てており、親子間や兄弟姉妹間の暴力については十分な対応がなされていないのが現状である。例えば、親が成人した子どもに対して継続的に精神的圧力をかけたり、生活の自由を制限したりする行為は、明確な暴力行為として認識されにくい。そのため、被害者が警察や福祉機関に相談しても、明確な対応が取られないケースが多い。さらに、刑法においても、暴行罪や強要罪の適用には証拠が必要であり、家庭内での出来事が外部に伝わりにくい現状では、実際に処罰されるケースは少ない。特に、精神的な暴力が長期間にわたる場合、被害者が正常な判断力を失い、支配関係から抜け出すことが困難になることも問題である。このような課題を解決するためには、法律の改正や支援制度の拡充が必要であり、家庭内での暴力が単なる家庭の問題ではなく、社会全体の問題として認識されることが重要である。
まとめ
家庭内の支配や暴力は個人だけの問題ではなく、社会全体の課題として認識されるべきである。特に親子間の精神的・身体的暴力は見過ごされがちであり、法的な対応が不十分な場合が多い。刑法208条の暴行罪、刑法222条の脅迫罪、刑法223条の強要罪、DV防止法などが適用される可能性があるが、家庭内の出来事は外部に伝わりにくいため、実際に法的措置が取られるケースは少ない。経済的依存によって支配が継続しやすく、被害者は自立する手段を失い、結果として支配関係から抜け出せなくなる。社会全体で家庭内の支配構造を問題視し、被害者が適切な支援を受けられる環境を整備することが重要である。精神的虐待や暴力が容認される家庭文化を変えるためにも、法律の改正と支援制度の拡充が必要である。