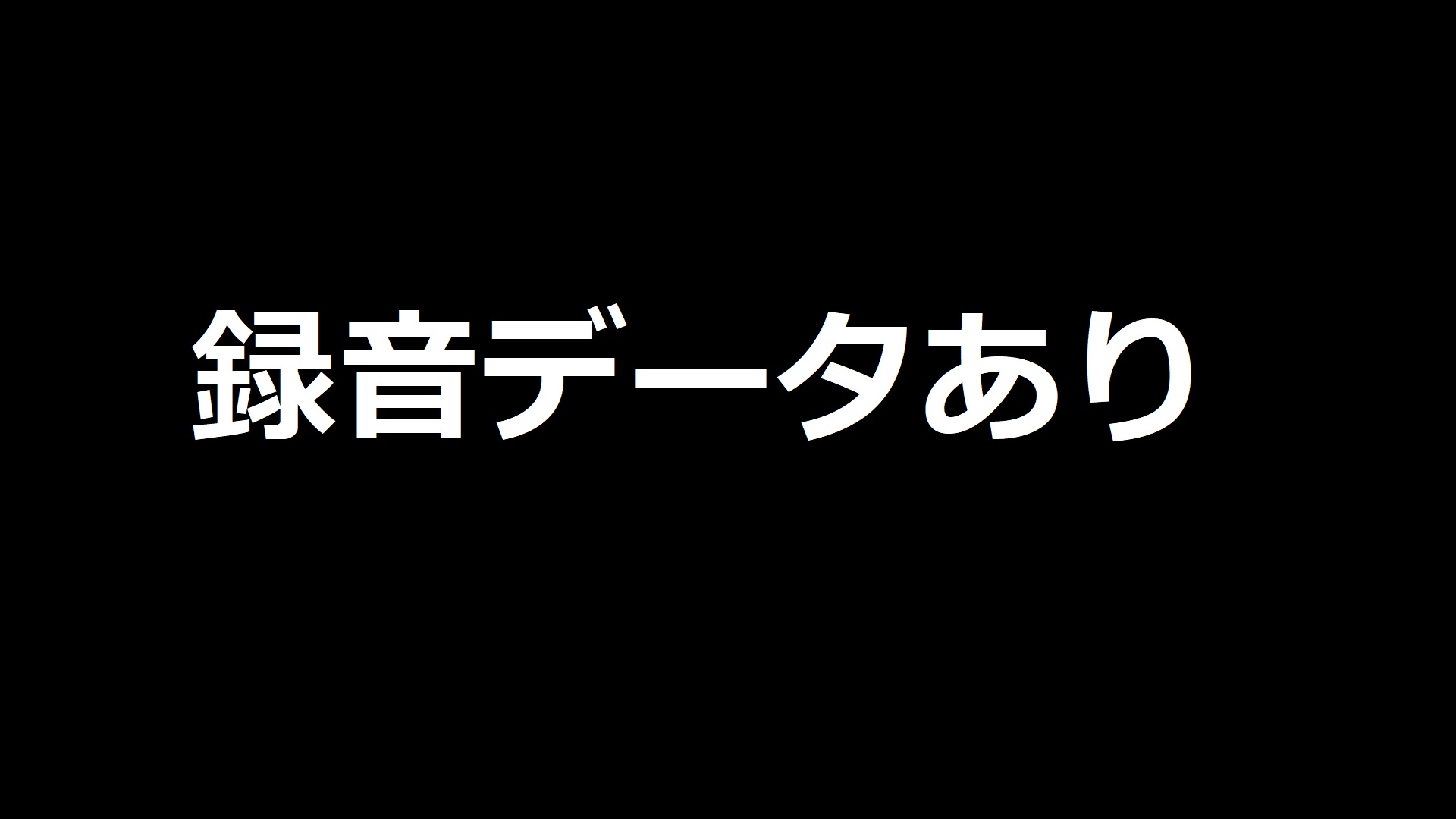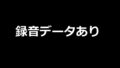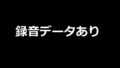DV モラハラ パワハラの実態 家庭内の支配と社会への影響
家庭内でのDV、モラハラ、パワハラは個人の問題にとどまらず、社会全体に影響を及ぼす深刻な課題です。特に自己愛性パーソナリティ障害のような心理的要因が絡む場合、被害者は長期にわたる精神的・肉体的苦痛を受け続けることになります。本記事では、家庭内の支配構造やその社会的影響について、専門的な視点から掘り下げ、法的な枠組みと共に解説していきます。
父という男
- 根っからのDV、モラハラ、パワハラ男
- 顔を殴るのではなく尻を叩くのは偽装
- 自己愛性パーソナリティ障害発覚
根っからのDV、モラハラ、パワハラ男
被害者の生まれてから一番古い記憶は、父が母にDVを行っていて、薄い壁一枚の向こうから母の泣き叫ぶ声が聞こえてきたというものだ。
被害者自身、父から虐待を受けて育った。それは被害者が肉体的に父を上回るまで行われた。
一例を出すと、父からモラハラを受けた挙句虐待に発展する。玄関でパンツを脱ぎ四つん這いになって尻を出す。40代男性、とりわけ父は筋肉質であったが、その腕力いっぱいの力で尻を叩くのだ。体は吹っ飛び、尻に激痛が走る。無理やり引きずり上げられ、2度、3度と。遠くに見える母に助けを求めても母は助けてくれない。翌日学校で朝礼に向かうために並んでいて、友達がふざけて後ろから押してくると激痛が走る。またすぐ隣に住む同級生からはその虐待の声が聞こえてきたとからかわれる。そんなことが頻繁に行われていた。
顔を殴るのではなく尻を叩くのは偽装
母の話では、小学生の頃の被害者の同級生の父親はDVを繰り返しており、警察が頻繁に来ていたという。我が家の場合は母が世間体を非常に気にする人間であったこともあって、警察を呼ぶことはなかったのだろう。
また尻を叩くというのは、普通に第三者が聞けば”躾として軽いもの”と感じるだろうが、被害者にとってはあれをやられるくらいなら顔を殴られる方がよほどマシというものであった。
そして、顔を殴る(=外観として証拠が残る)よりも尻を叩くことで、「尻を叩いた」というように印象を軽くする効果を狙ったものと考えられる。
このこと、とりわけ被害者の尻を叩く件について、西入間警察署生活安全課課長は「昔はよくありました」などと言っていた。昔だからいいわけでもなく、そもそもそういう男なのであるから、警察はそれを前提にこの我が家の問題を考えるべきなのである(とはいえ民事不介入だが)。
体罰というのは明治時代の民法により認められていた。しかしそれは国際社会からは批判され続けていた。
自己愛性パーソナリティ障害発覚
2023年2月9日、4年間の嫌がらせの末事件となった。
その後、欠かさず見ているAbema Primeの放送を見て、「これだ」と思った。
父の言動はまさに「自己愛性パーソナリティ障害」である。
家庭の中でDV、パワハラ、モラハラを行ってきた。
職場においてもパワハラ、モラハラを行っていたことは、父本人、また父の会社でアルバイトをしたことがあるという叔父からも聞いている。父などは自慢していたくらいである。
また父はクレーマーであり、例えばレストランで注文した料理が出てこないと1時間近く怒鳴り散らした上で、スタッフルームに入って行ってまでクレームを言い立てる。また例えばパソコンを購入して操作を上手くできないとなると、深夜に渡って長時間電話で怒鳴り続けるなど。
自己愛という意味であれば、彼の人生において彼を支えていたのは「早稲田出身、(小さな出版社の)編集長」であった。
関係する法令
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 児童福祉法
- 民法
- 刑法
- 迷惑防止条例
- 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
児童虐待の防止等に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、その監護する児童に対し監護及び教育を行うものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対して行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による身体的虐待を放置するなど、著しい養育の怠慢その他の保護の怠慢を行うこと。
四 児童に著しい暴言を吐き、著しく拒絶的な対応をし、又は著しく過干渉な対応をするなど、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童福祉法
(児童の権利)
第三条の二 全て児童は、その生活を保障され、愛護されるとともに、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることを保障される。
2 全て児童は、その年齢及び発達の程度に応じて、適切に養育され、教育され、及びしつけられることを保障される。
3 全て児童は、その意見を尊重され、その生活に影響を及ぼす事柄について、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見を表明する権利を有する。
民法
(親権者の権利義務)
第八百十八条 親権を行う者は、子の利益のために、その監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
刑法
(暴行罪)
第二百八条 暴行を加えた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(傷害罪)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(脅迫罪)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
迷惑防止条例(東京都の場合)
(不当なクレーム行為の規制)
第五条 正当な理由なく、公共の場で他人を著しく不安にさせる言動を繰り返した者は、六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
(事業主の措置義務)
第三十条 事業主は、労働者に対し職場におけるパワーハラスメントが行われないよう必要な措置を講じなければならない。
DV・パワハラ・モラハラと法的問題
- 家庭内での暴力と法的責任
- 自己愛性パーソナリティ障害と法的問題
- 社会での問題行動と法的責任
家庭内での暴力と法的責任
日本の法律では、家庭内での暴力(DV、パワハラ、モラハラ)に関する規定が複数存在する。DV防止法(配偶者暴力防止法)は主に配偶者間の暴力を規制する法律であるが、親子間の暴力は直接的にこの法律の適用を受けない。そのため、親による暴力は児童虐待防止法や刑法によって規制される。児童虐待防止法第2条では「保護者が児童に身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトを行うこと」を虐待として定義し、特に身体的虐待に関しては刑法第208条の暴行罪が適用される可能性がある。暴行罪は「暴行を加えた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められている。また、暴力によって傷害が発生した場合には刑法第204条の傷害罪が適用される可能性があり、「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされている。さらに、心理的虐待についても、継続的な暴言や過度な支配による精神的圧迫は刑法第222条の脅迫罪に該当する可能性がある。
自己愛性パーソナリティ障害と法的問題
自己愛性パーソナリティ障害を持つ人物は、家庭内や社会において支配的な行動をとることが多く、これが法的問題を引き起こすことがある。例えば、家庭内での極端な支配や罵倒が続いた場合、これが刑法第223条の強要罪に該当する可能性がある。強要罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して、人に義務のないことを行わせた者は、三年以下の懲役に処する」と規定されており、支配的な言動が特定の義務を強制する形となった場合、適用される可能性がある。また、家庭内での精神的虐待が極端な場合、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求が可能となる。不法行為とは「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない」とされており、家庭内での継続的な精神的苦痛が損害と認められた場合、損害賠償請求が可能となる。
社会での問題行動と法的責任
家庭内だけでなく、社会においても自己愛性パーソナリティ障害の特徴を持つ人物が問題行動を起こすことがある。例えば、クレーマー気質が極端になり、企業や店舗に対して過剰な要求を繰り返す場合、各都道府県の迷惑防止条例に違反する可能性がある。東京都の迷惑防止条例第5条では「正当な理由なく、公共の場で他人を著しく不安にさせる言動を繰り返した者は、六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされており、店舗や企業に対する過度なクレーム行為が社会的に問題視されることがある。また、職場でのパワハラについては労働施策総合推進法(パワハラ防止法)によって規制されており、第30条では「事業主は、労働者に対し職場におけるパワーハラスメントが行われないよう必要な措置を講じなければならない」と定められている。職場でのモラハラや過剰な威圧的言動が業務遂行に支障をきたす場合、事業主が適切な対応を行わなかった場合には労働基準監督署の指導を受ける可能性がある。
家庭内暴力と社会問題
- 家庭内でのDV・モラハラの社会的影響
- 自己愛性パーソナリティ障害と家庭問題
- 社会全体でのパワハラ・クレーマー行動の影響
家庭内でのDV・モラハラの社会的影響
家庭内でのDVやモラハラは単なる個人の問題ではなく、社会全体に影響を与える深刻な社会問題である。DVの被害者は精神的・肉体的に大きな傷を負い、適切な支援が受けられない場合、長期的なトラウマを抱えることになる。特に家庭内での暴力が子供の前で行われた場合、児童虐待に該当する可能性があり、児童虐待防止法第2条では「児童の心身の正常な発達を妨げる行為」として明確に規定されている。このような環境で育った子供は、将来的に暴力を容認する価値観を持つ可能性が高く、社会全体に負の連鎖を生み出す要因となる。さらに、家庭内暴力の被害者が精神的なダメージを受けることで、就労継続が困難になったり、社会的孤立を深めたりするケースも多い。これは社会保障制度への依存度を高める要因となり、結果的に経済的な負担として社会全体に影響を及ぼす。日本ではDV防止法が存在するが、配偶者間の暴力に特化したものであり、親子間の暴力や精神的虐待に対する法的保護が十分であるとは言い難い。民法第818条では「親権者は子の利益のために監護および教育を行う義務を負う」とされているが、実際には親権者による虐待行為が発覚した場合でも、行政の対応が遅れがちである。特に家庭内での精神的虐待やモラハラは、外部から把握しにくいという特徴があり、被害者が自ら助けを求めなければ問題が表面化しないことが多い。このため、社会全体として家庭内暴力やモラハラの問題をより深刻な社会課題として認識し、法制度の強化や被害者支援の充実が求められる。
自己愛性パーソナリティ障害と家庭問題
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)を持つ人物は、自己中心的な思考を持ち、他者への共感力が著しく欠如しているため、家庭内での支配的行動が問題となることが多い。特に親がNPDの場合、子供への過剰な支配、過干渉、精神的虐待が常態化しやすく、これが子供の成長や人格形成に深刻な影響を及ぼす。児童福祉法第3条の2では「すべての児童はその心身の健やかな成長および発達が保障される」とされているが、NPDの親のもとではその権利が侵害されるケースが多い。家庭内での支配構造が極端な場合、子供が自己肯定感を持てず、将来的に対人関係や社会適応に困難を抱える可能性が高まる。自己愛性パーソナリティ障害の親は、子供の成功を自己の栄誉と結びつけ、過度なプレッシャーをかける一方で、子供が親の期待に応えられないと極端に冷淡になることがある。このような環境では、子供が自尊心を形成できず、精神的なダメージを負いやすい。心理的虐待の継続は、刑法第222条の脅迫罪や強要罪に該当する場合もあるが、精神的な支配は目に見える証拠が少なく、法的措置が取りにくいという課題がある。したがって、家庭内での精神的虐待やNPDの親の支配行動に対して、社会的な認識を高めることが重要である。特に、家庭内における精神的虐待の通報制度の拡充や、子供が安全に相談できる環境の整備が求められる。
社会全体でのパワハラ・クレーマー行動の影響
家庭内だけでなく、社会においてもパワハラやクレーマー気質の問題が拡大している。特に自己愛性パーソナリティ障害の傾向が強い人物は、職場や公共の場において過剰な要求や攻撃的な言動を繰り返す傾向がある。これにより、企業や店舗の業務に支障をきたすだけでなく、従業員や一般市民に精神的負担を与える問題が発生する。労働施策総合推進法(パワハラ防止法)第30条では「事業主は職場におけるパワーハラスメントを防止するために必要な措置を講じなければならない」と規定されているが、現実にはパワハラの判断基準が曖昧であり、企業が適切な対応を取らないケースも多い。また、クレーマー行為が極端になった場合、各都道府県の迷惑防止条例によって規制される可能性がある。例えば、東京都の迷惑防止条例第5条では「正当な理由なく、公共の場で他人を著しく不安にさせる言動を繰り返した者は、六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」とされており、悪質なクレーム行為が規制の対象となることがある。さらに、近年ではインターネットを利用した誹謗中傷や威圧的行動も問題視されており、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪が適用されるケースも増えている。これらの問題を解決するためには、社会全体としてハラスメントや過剰なクレーム行為に対する認識を高め、法的規制の適用範囲を明確にすることが求められる。
まとめ
家庭内でのDVやモラハラは個人の問題ではなく社会全体に影響を及ぼす深刻な社会問題である。特に自己愛性パーソナリティ障害を持つ親の家庭では、子供が精神的なダメージを受けやすく、将来的に対人関係や社会適応に困難を抱える可能性が高まる。児童虐待防止法や児童福祉法によって子供の権利は保護されるべきであるが、精神的虐待は外部から把握しにくいため適切な介入が困難である。一方で、職場や公共の場においてもパワハラやクレーマー行為が社会問題となっており、パワハラ防止法や迷惑防止条例が適用される場合があるが、実際には対応が遅れることも多い。こうした問題を解決するためには、被害者が適切な支援を受けられる環境を整え、社会全体としてハラスメントや暴力の防止に向けた意識を高めることが不可欠である。