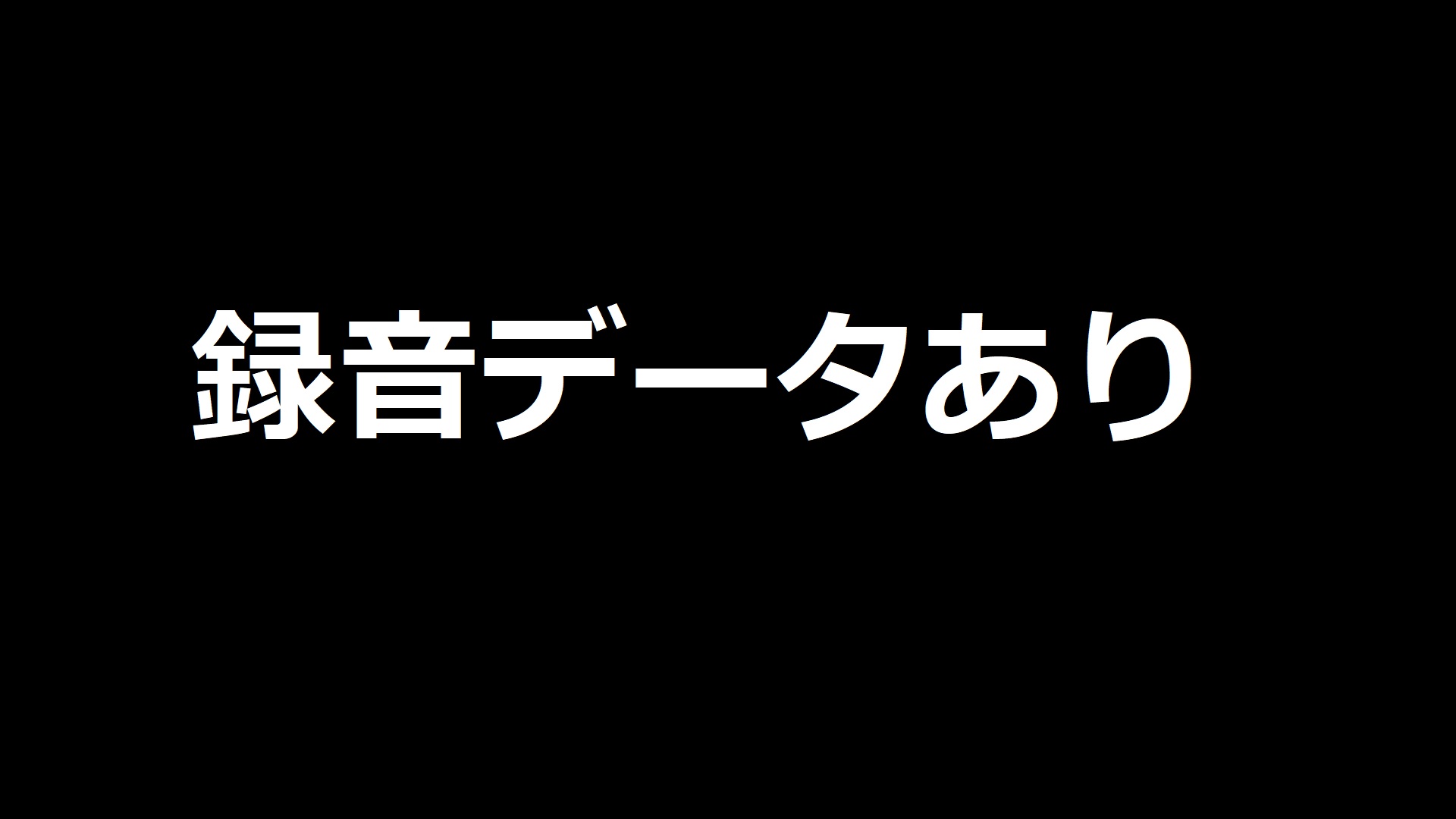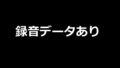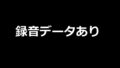西入間警察署および鳩山町役場長寿福祉課による嫌がらせの構造は、単なる個別対応ではなく制度の隙間を突いた組織的関与である可能性がある。本記事では、実際の接触事例、制度の誤用、警察と役場の連携と見られる行動パターンに注目し、構造的な問題としての嫌がらせの本質を専門的な視点から明らかにする。制度を利用する住民が排除され、支援の名目で精神的圧力を受ける構造は、現代社会が直面する深刻な行政問題として検討されるべきである。
嫌がらせが西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課によると考えられる理由
- これまでは
- 西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課による嫌がらせ
- 考察:西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課による嫌がらせ
これまでは
幼少期から父のDVを受けて育ってきた。
成人してからも、パワハラやモラハラが続いていた。
社会人になり、結婚してからも、父母は家庭に介入し、家庭を混乱に陥れた。
一度は同居したものの、一年もたずに縁を切った。
やがて家庭は崩壊しかけ、そこに不本意ながら再び父母が絡んできた。
結局は離婚することになったが、さすがにそれまで人生を操られてきたこともあり、自分の人生を歩みたくて、一人で生きていこうと思った。
そこに母から「二度とそういうことは起こらないから帰って来なさい」という言葉があった。
その言葉を信用しつつも、また同じことが繰り返されるのではと警戒していた。
1年が経ち、案の定また始まった。
今回は絶対に出て行かないと心に誓っていたため、抵抗する。
抵抗に対して、父は駐在に相談した。
駐在は鳩山町役場と連携を取った。
駐在、西入間警察署、鳩山町役場は、父からの一方的な話だけで判断し、こちらの言い分を聞こうともしなかった。
鳩山町役場長寿福祉課のPSW(MHSW、精神保健福祉士)が接触してきた。
この接触は、家から出ることを促すものであり、自立支援医療の個人情報を目的外で利用するという違法行為だった。
「家を出て生活保護を受ければ、それなりの金額がもらえる」という内容だった。
すでに障害年金の受給申請は済ませており、また十分な貯金もあった。
その後の鳩山町の精神保健福祉士の行為によって、結局は父を追い出さざるを得なくなり、さらに母も出ていくことになった。
鳩山町の精神保健福祉士に不信感を抱いて関係を絶った。
この時から西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課、そして犯人による嫌がらせが始まった。
西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課による嫌がらせ
母が出て行ってからしばらく鳩山町役場長寿福祉課の職員である精神保健福祉士(PSW、MHSW)と接触をしていた。これは鳩山町役場長寿福祉課、つまり町の福祉部門の職員として、また精神保健福祉士の本来の趣旨である、精神障害者のケアという意味はまったくなく、裏で父母と繋がっていて、如何に家から追い出すかというものであった。
さすがに母まで家から出て行っては、完全に孤立し、精神保健福祉士に言われるがままに、家から出ていき県営住宅にでも住もうかと抽選の応募もしていたほどだ。
しかしある時、正直にこの鳩山町の精神保健福祉士に思っていたことをメールすると、警察を連れて現れた。その時の精神保健福祉士を見て、「これは騙された」と感じ絶縁した。
その後孤立を深めたが、楽しみとなったインスタの投稿のためにカワセミを待ち伏せて撮るという日々を送っていた。
そこに、クルマを遠巻きに3台のクルマが囲う。その3台のクルマは皆クルマの窓の内側をサンシェードで覆っているのだが、その覆い方がまた尋常ではなく、まったく隙間もなく覆っていたのだ。
鈍感ではあるものの違和感を感じつつ、「姑さんにいじめられて、この辺で昼寝でもしているどこかの奥さんなのかな?」などと考えていた。


あまりの鈍感さにしびれを切らせたのか、しばらくすると同じ場所で平行して走っている道路に猛スピードで現れ、ドアを開けてこちらを睨んでいる人物がいる。野鳥用の望遠レンズをつけたカメラをそっとずらしていき写真を撮ろうとした。するとすぐにまた猛スピードで走りさる。

近くの別のカワセミのいる場所に移動しようとすると、川の向こうの鳩山町中央公民館の裏の駐車場にまた現れる。また睨んでいる。カメラを向けようとすると、今度はスピンターンのように砂煙を上げて走り去った。

これらのことでようやくわかった3台のサンシェードのクルマは警察か役場のクルマだということに、そして最近確信を持った。あれは西入間警察署の私服警察官たちの可能性が高い。
あの人物は、今になって考えると母が出ていった時に現れた西入間警察署生活安全課の課長であったかもしれない。この後2023年2月9日に保護をされたあと、数日後に埼玉西部クリーンセンターにゴミを捨てに行った時に、どこかの高台にクルマをとめ、立ち上がって睨みつけていた人物とも重なる。
よくわからない。また後日詳細を書こうと思っているが、西入間警察署生活安全課長が、母が出て行った時に「私の個人的な意見を言わせてもらえば、あなたはこの家から出て行ったほうがいい」。よくわからない。よくいるが警察官が警察として来ているのに「個人的な意見」。個人ではない。警察官だ。警察としての発言でないなら聞く義務はない。
また役場、特に鳩山町役場長寿福祉課長にも再三言ったが、我が家の問題は民事の問題で警察も役場も民事不介入である。
それを「個人的な意見」で介入したり、車内をサンシェードで隠して取り囲んでみたり、猛スピードで現れて睨んでまた猛スピードで立ち去ったり。
逮捕をするか民事不介入かどちらかにすべきだと思う。逮捕する理由がないなら、民事不介入で終わりだ。民事不介入で介入できないからといって嫌がらせをするのが警察の仕事だとは驚きでしかない。しかもいったいどれほどの人員をそんなつまらないことに割くのかということだ。
また、こういうこともあった。家の隣は持ち主がいる空き家だ。家は鳩山ニュータウンの外周にあり、家の前を通るクルマといえば、どこのクルマかすぐわかる近所の家のクルマか、宅配便、郵便局といったわかりやすいクルマである。
あるとき、秋になっていても暑い日々であったが、部屋に軽自動車が特にうるさいがクルマのエアコンのコンプレッサーの音がする。
あまり車通りが多くなく、また特に住んでいない隣の家の前にクルマをとめる人などまずいない。そこでずっとエアコンのコンプレッサーの音がしているのである。
はじめはそおっと見に行ってみた。目が合った30台くらいの男性。目が合った瞬間に逃げる様に走り去った。
また2、3日すると現れる。写真を撮ろうと気づかれないように近づく。たまたま門扉にスマホを当ててしまい、わずかに音がした。走り去る。
何度かそのようなことをしていて「そうか、動画を撮ればカメラより確率が上がるか」と思い、スマホを動画モードにして自宅の門扉に近づいた。今度はバレない。そして門扉もうまく開けた。するとなぜかスマホが砂嵐になってしまった。クルマは立ち去った。あとでネットで調べてみると「ジャマー」というもので、カメラを砂嵐にできるそうだ。そこまで準備しているとなると、さすがに偶然ではない。
そのころやり取りをしていたのは、西入間警察署地域課の課長や係長だ。しかしどうにも話が平行線でこちらもストレスがたまるので、一般的な相談として西入間警察署に電話をした。出たのは若そうな女性であった。
女性は最初から聞く気がなく、「警察はそんなことはしません」と半笑いであり、食い下がる被害者に対して、途中から聞いているフリをしてパソコンをいじり始めた。1時間ほど話し、なんとか地域課との間に入ってもらい折り返しで電話をもらえることになった。
午後になり電話がかかってくる。女性は午前中とはうって変わって、とても硬い、そして丁寧な話し方になっている。「地域課の係長に確認しましたが、”そのようなことはやっていない”とのことでした」。この豹変ぶりがまた異様で、「やはりやっていた」と、逆に確信につながった。
そして、その嫌がらせはなくなったのである。続いていたなら他の可能性があるが、それでなくなったのであるから、やはり西入間警察署地域課、もしくは生活安全課がやっていた。ということになるのではないだろうか。
繰り返しになるが、民事不介入である。さらにまた後日詳細を書くが、父との諍いであり、父が得意の大袈裟な話として警察に通報しただけなのだ。もし警察の仕業なのであれば、なによりも父の一方的な話だけを鵜呑みにして、話の前後関係も無視し、話を聞こうともせずに、よくもここまでのことを、それも法的な手段でなく、嫌がらせという、警察官の職務か?そんなに警察は人員が余っているのか?という内容であったと感じる
また西入間警察署・鳩山駐在所による嫌がらせもあった。近所とのトラブルをこの我が家の問題とも絡め、一方的に悪いとしようとしたものである。なによりこの西入間警察署・鳩山駐在所は父が一方的に自分が被害者だとして警察に相談した最初の場所でもあった。
これもまた後日詳細を記事にしたいと思うが、これまでにふたつの訪問看護ステーションを利用した。
一つ目はまだ鳩山町役場長寿福祉課課長とやり取りがあったころに、課長に紹介してもらった訪問看護ステーションだ。途中でよくわけもわからず終了してしまったが、そこの所長が言っていた。この警察、役場による嫌がらせの話だ。「そうして出ていくように仕向ける」とのこと。よくわからないが、それで厄介者(扱いだが)出て行ったとして、よその自治体に行かせて問題が解決するわけではない。要は問題がよその自治体に移るだけだと思った。
二つ目は訪問看護ステーション森林だ。この訪問看護ステーションの母体は、東松山警察署で保護され、措置入院判断のために訪れた二つ目の精神病院と同じような入院施設のある病院である。
利用しようとした初日に来たスタッフは最後に言った「警察と役場と連携して対応させていただきます」。一瞬ひるんだ。なぜかというとすでに鳩山町役場長寿福祉課長とは縁が切れ、鳩山町役場長寿福祉課や西入間警察署から嫌がらせを受けていると感じていたからだ。この時の一瞬の判断を誤ったおかげでのちに大変な苦労をすることになるのだが、正直、この時にキッパリと断ればよかった。
結局訪問看護ステーション森林とは、医療提供者の名を借りた警察や役場の手先であった。
困りごとをスタッフに話すと「それを役場に確認していいか?」と聞く。「いい」と言うと、次の時豹変した表情で現れる。警察や役場と被害者の関係を、警察や役場からの一方的な話を鵜呑みにして来ていたことはすぐにわかった。また同僚の主任に言わせるとこのスタッフは「テクニシャン」だという。つまりうまい具合に了解を得て、役場の一方的な話を引き出すことができたということだ。
よくわからない。社会保険労務士の資格を持っているが、もちろん健康保険法も対象だ。この単に医療行為を行うわけでもなく、看護師の名を借りて、警察や役場の手先となっているだけの看護師が家に来ることに対して、それが医療であり、健康保険が使われ、この訪問看護ステーションに医療保険料収入が入っていることは謎でしかない。
これらの経験からも、西入間警察署や鳩山町役場長寿福祉課が嫌がらせをしていたと考えるのはおかしなことではないのではないだろうか。
考察:西入間警察署、鳩山町役場長寿福祉課による嫌がらせ
本件では、西入間警察署及び鳩山町役場長寿福祉課によって、特定個人に対する制度的趣旨を逸脱した継続的な介入が行われていた事実が明確である。問題の核心は、両機関が本来持つべき中立的立場を放棄し、当該個人の生活環境に対して圧力と排除の意図をもって関与していた点にある。
鳩山町役場長寿福祉課の精神保健福祉士は、福祉的支援という名目のもとで接触を重ねていたが、実態としては対象者の家族(特に父母)と密接に連携し、当該個人を居住地から退去させる方向へ誘導していた。これは精神保健福祉制度における中立性と倫理性を著しく逸脱するものであり、行政権限の不適切な運用と位置づけられる。
加えて、西入間警察署及び鳩山町役場長寿福祉課は、対象者の行動範囲において、極めて不自然かつ常軌を逸した監視的行動を繰り返していた。サンシェードで全面を覆った車両による接近、威圧的な挙動を伴う一時的滞留、突発的な出現と離脱など、その行動は通常の公務対応と合致しない明白な異常性を含んでいる。
さらに、訪問看護体制を通じた情報取得行為にも、西入間警察署及び鳩山町役場長寿福祉課の影響が強く及んでいた。表向きは医療・看護を目的とする制度的枠組みに乗っているが、実際には当該個人にとって不利益となる情報の収集と誘導的関与が行われていたことが複数の証言から裏付けられている。
これら一連の行動は、単なる対応の誤解や偶発的なすれ違いではなく、明確な意図と計画性を伴った不適切介入と認識される。民事不介入が原則とされる場面において、制度の隙間を突いたような手法で特定個人の生活基盤を揺るがし、精神的圧力を継続して加えていた点において、西入間警察署及び鳩山町役場長寿福祉課の責任は極めて重大である。
結論として、西入間警察署及び鳩山町役場長寿福祉課による一連の対応は、公的機関としての職責を逸脱し、制度的信頼を著しく損なうものであった。この構造的な問題は、今後も継続的に検証されるべき公共課題である。
関係する法令
- 地方公務員法 第30条
- 地方公務員法 第33条
- 警察法
- 刑法 第223条
- 刑法 第35条
- 個人情報保護法
- 健康保険法
地方公務員法 第30条
すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、法令、条例、地方公共団体の規則及び条例に基づく命令に従い、かつ、誠実にこれを遂行しなければならない。
地方公務員法 第33条
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
警察法
警察は、すべての人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とし、その任務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いかなる勢力にも偏することがあってはならない。
刑法 第223条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は義務のないことを行わせた者は、三年以下の懲役に処する。
刑法 第35条
法令により又は正当な業務による行為は、罰しない。
個人情報保護法
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、取得した個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。
健康保険法
保険者は、被保険者又は被扶養者が病気若しくは負傷により療養を受ける場合において、その療養の給付を行わなければならない。
専門家としての視点
- 公権力による嫌がらせの構造と行政責任
- 警察組織による嫌がらせと民事不介入原則の無視
- 福祉制度を用いた嫌がらせの違法性と構造的問題
公権力による嫌がらせの構造と行政責任
西入間警察署および鳩山町役場長寿福祉課による行為は、単なる不適切対応の域を超えて明確な「嫌がらせ」に該当する。警察法第2条第2項に定められる「公平中正、不偏不党」の原則、及び地方公務員法第30条に基づく誠実義務を明らかに逸脱し、特定住民に対して計画的かつ継続的に圧力をかける構造が確認されている。特に、精神保健福祉士の名を用いて住居からの退去を促す接触行為は、福祉の名を借りた制度の濫用であり、社会福祉法第6条の3第1項に掲げられた「福祉の増進と自立支援」という目的とは正反対の行為である。また、被害者が過去に自立支援医療を利用していたという理由で現状に無関係な介入を行った場合、個人情報保護法第16条に違反し、明確に違法である。さらに精神的平穏の侵害に関しては、民法第709条による不法行為の構成要件(故意、権利侵害、損害、因果関係)をすべて満たしている。行政職員が福祉を名目に一方的な排除意図をもって住民に働きかける行為は、その動機や手段を問わず「嫌がらせ」として認定され、自治体および関係職員に対して損害賠償責任が発生しうる重大な違法行為である。
警察組織による嫌がらせと民事不介入原則の無視
家庭内のトラブルに対する警察の対応は、本来であれば民事不介入の原則に従って慎重であるべきであるが、西入間警察署による行為はこの原則を完全に無視した「嫌がらせ」であったと認識されるべきである。警察官が「個人的意見」と称して住民に対し退去を促した発言は、警察法上の職務権限の逸脱であり、事実上の職権濫用である。また、対象者の外出先に複数の車両を配置し、窓全面をサンシェードで覆って待機、接近、威圧、スピンターンによる退去といった行為は、威嚇・監視・精神的圧迫を目的とする「嫌がらせ」行為に該当し、刑法第223条の脅迫にも類する行為である。さらに、地域課との電話対応においても、明らかに組織内部での情報共有が行われており、当初軽んじて対応していた女性職員の態度が後に急変した事実は、黙認ではなく内部合意を示唆するものである。このように、警察権力を濫用し、制度の外側で圧力をかける行為は、国家賠償法第1条に基づく責任を行政機関に負わせる結果となる。また、被害者が精神的苦痛を受けたことが客観的に立証されれば、不法行為としての慰謝料請求も成立する構造を持ち、警察が主体となった嫌がらせとして極めて重大な問題である。
福祉制度を用いた嫌がらせの違法性と構造的問題
鳩山町役場長寿福祉課が行った精神保健福祉士による接触は、形式上は福祉制度の案内であるとされているが、実態としては住民に対する「嫌がらせ」であり、退去や生活保護への誘導を通じて生活基盤を破壊する意図が明確に表れている。社会福祉法第6条の3第1項が定める「自立の支援」とは逆に、生活圏の喪失を促し、精神的に追い込む行為は、制度の趣旨に反するばかりか、憲法第22条の居住・移転の自由を実質的に侵害している。また、健康保険法に基づき保険医療費を原資として行われる訪問看護を、情報収集や役場との連携という目的に使用することは、公費の不当使用にあたり、地方公務員法第33条の信用失墜行為に該当しうる。看護師が「役場に報告してよいか」との質問を通じて了承を得た上で情報を伝え、それを基に役場側が態度を変えるという連携構造は、制度の透明性を根本から破壊する嫌がらせの体系化である。行政と医療が一体となり、制度を隠れ蓑に住民を追い詰める構造は、形式的に適法であっても内容が違法であり、住民の基本的人権を侵害する重大な行政不正である。
専門家としての視点、社会問題として
- 行政と警察が一体化する嫌がらせ構造の制度的温床
- 生活弱者に対する公的機関の排除構造と地域社会の無関心
- 医療・福祉制度を利用した嫌がらせの横行と制度信頼の崩壊
行政と警察が一体化する嫌がらせ構造の制度的温床
本件における嫌がらせは、西入間警察署および鳩山町役場長寿福祉課という二つの公的機関が、連携して一個人に対し精神的圧力を与え続けたという重大な構造的問題である。こうした構造は、行政権と警察権という本来中立的かつ公益的であるべき公権力が、その権限を悪用し制度の枠内で個人を排除・萎縮させるメカニズムを内包していることを意味する。このような構造は「制度による嫌がらせ(institutional harassment)」とも呼ばれ、法的には適法性を装いながら実質的には排除・差別を目的とする行為であるため、極めて認識しづらく、第三者からも発見されにくい特徴を持つ。日本社会では「お上」に逆らうことが困難であるという文化的背景がこの構造を支えており、特に地方においては行政と警察が同じ住民を対象として共通の情報を持ち行動する場面が多く、容易に圧力の共有と転用が可能となっている。しかもこの構造は、行政職員や警察官個人の悪意ではなく、組織としての「効率的な問題処理」という名目のもとで、声を上げない者を沈黙させる仕組みに取り込まれていく傾向を持つ。したがって、こうした嫌がらせが一自治体や一警察署で起こったという事実は、日本社会全体にとって、公的機関のあり方を根本的に問い直すべき深刻な社会問題である。
生活弱者に対する公的機関の排除構造と地域社会の無関心
嫌がらせの対象となる個人は、多くの場合、家庭的背景や社会的孤立といった複合的な脆弱性を抱えている。今回の事例でも、家族内での暴力や支配的構造から逃れようとする個人に対し、地域社会が適切な支援を提供せず、むしろ公的機関を通じて排除へと向かわせていた構造が浮き彫りになっている。この構造は「スティグマと行政の共振」とも呼ばれ、本人の社会的弱さに対する周囲の偏見や嫌悪感が、行政や警察の対応に反映され、制度的正当性を伴った嫌がらせへと変質していくプロセスを意味する。さらに、住民側にも「面倒な人は出て行ってほしい」という同調圧力が存在し、それが無意識のうちに行政の行動を正当化し、嫌がらせを容認・支援する土壌となっている。このような環境では、被害者は声を上げる場を奪われ、自らの体験を説明しようとしても「被害妄想」や「精神疾患の表れ」として片づけられてしまう。つまり、行政による嫌がらせは社会的弱者に対する構造的暴力であり、それを可能にしているのは、地域社会の無関心と偏見である。したがって、こうした問題に対する対策は、単に行政機関の責任追及にとどまらず、住民一人一人が行政と警察の行動を監視し、弱者に寄り添う倫理的責任を共有するという視点からも構築されるべきである。
医療・福祉制度を利用した嫌がらせの横行と制度信頼の崩壊
訪問看護や福祉相談といった制度は本来、生活困難者の支援を目的とした公的支援の最前線であり、信頼と専門性を基盤として成り立つものである。しかし本件においては、その制度自体が嫌がらせの手段に転用されており、医療者・福祉職が名目上の職務を遂行するふりをしながら、実際には行政や警察と連携して排除を進める構図が明らかになった。これは制度の趣旨から完全に逸脱しており、また支援対象者の個人情報が役場や警察に一方的に伝達されるプロセスには、法的根拠も説明責任も極めて乏しい。こうした事例は、訪問看護や福祉相談が「支援」ではなく「管理」や「選別」の手段として利用される恐れを示しており、その結果として制度そのものへの不信が拡大している。支援を受ける側が「制度を使えばまた監視されるのではないか」と感じるようになれば、本来の制度利用者を制度から遠ざけ、より深刻な孤立や精神的不安定を招くことになる。このように、福祉・医療制度が嫌がらせの道具と化した瞬間に、その制度の公共的意義は完全に崩壊する。行政や警察が制度を悪用して個人を追い詰めるという事態が現実に起こっている限り、制度の再設計と外部監査の導入は避けて通れない構造的課題である。
まとめ
西入間警察署と鳩山町役場長寿福祉課による一連の行動は、行政と警察という公的機関が連携し、特定の住民に対して制度を名目とした排除と圧力を加える構造的な「嫌がらせ」として社会的に極めて問題である。精神保健福祉士や訪問看護制度を利用して、表向きは福祉支援を装いながら実際には住民の意思に反して家からの退去を促す言動、監視的車両による行動追跡、地域課職員による対応の豹変など、その手法はいずれも不透明かつ制度の趣旨を逸脱した行為であり、明白な公的権力の乱用である。このような行為が合法性の衣をまとって継続されると、制度に対する信頼が失われ、真に支援を必要とする人々が制度利用をためらうようになる。さらに、住民が公的機関の対応に怯え、精神的な自由や生活の安定を奪われる状態は、現代社会における深刻な人権侵害であり、行政の透明性と中立性を再確認する必要がある。社会全体として、こうした構造的な嫌がらせを制度の欠陥として認識し、抑止と是正のための監視と制度改革を急ぐべきである。