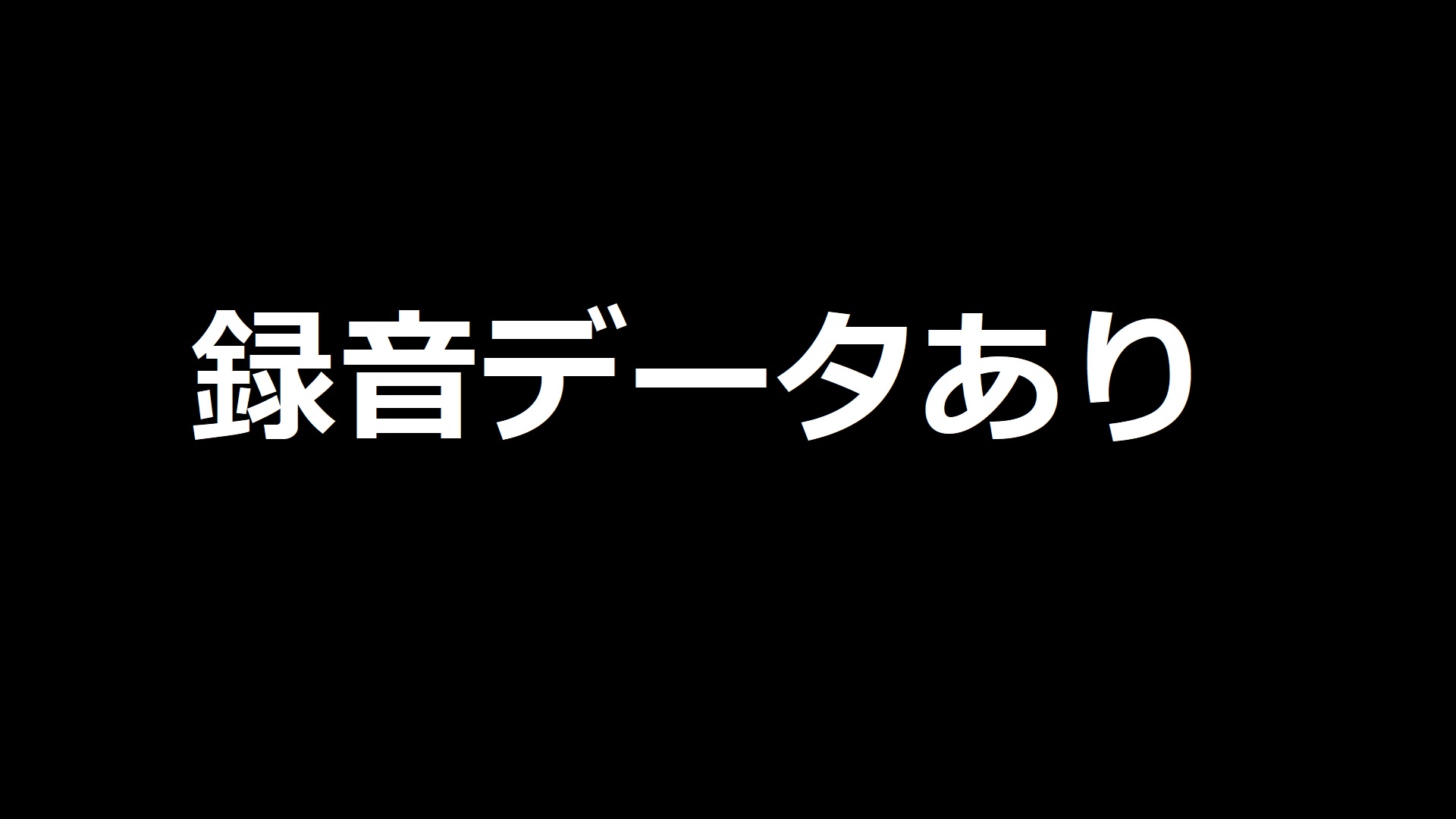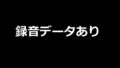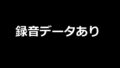鳩山町長寿福祉課において、住民対応の中で発せられた「堂々巡りだよね」「ぷっ、笑っちゃったw」という発言は、制度的な問題として深刻な意味を持つ。これらは単なる言葉遣いの問題ではなく、住民の訴えを軽視し、対話を閉ざす態度として表れており、公務員の職務上の義務と責任に関わるものである。発言が放たれた背景には、地方行政に特有の内部文化や縦割り体制、住民との関係性の固定化がある。行政に求められるのは、対話を重ねる姿勢と、制度の透明性であり、こうした発言が公的空間で容認されるようであれば、制度の信頼そのものが崩れる。この記事では、発言の言語的構造と社会的影響を専門的に分析し、制度と市民の関係における健全性の再構築を問う。
「堂々巡りだよね」「ぷっ!笑っちゃったw」
- これまでは
- 「堂々巡りだよね」「ぷっ!笑っちゃったw」
- 考察:「堂々巡りだよね」「ぷっ!笑っちゃったw」
これまでは
2023年2月9日、4年間およぶ鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせの結果、ひき逃げ事件に発展し、被害者は被害者として東松山警察署に行った。東松山警察署に向かうパトカーの中でスマホの録音を始めた。事情聴取中に謎の警察による不当な保護(警察官職務執行法第3条)。18時間拘禁された挙句、2つの精神病院に措置入院判断のために連れていかれ、結果的には開放された。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせが行われた理由としては、幼少期からの父によるDV、パワハラ、モラハラがあり、離婚後「これ以上人生を狂わされたくない」という思いから同居を拒否するも、母からの「二度とそのようなことは起こらない」との言葉を信じて、また「今度は何があろうと絶対に家から出ていかない」と心に決める。
同居をはじめてしばらくすると、相変わらずはじまる父のパワハラ、モラハラ。「出ていかない」ための抵抗により、父は警察、役場を利用して追い出そうとする。
鳩山町役場長寿福祉課、精神保健福祉士の不手際により、父の目論見を知った被害者は父を家から追い出す。
精神保健福祉士の行動はその後も不審極まりなく、やがて母も去ることとなる。
ひとり残された被害者は一時、精神保健福祉士を唯一の頼りとするが、やがてその目論見が自己の、所属組織、さらには警察へのアピールであったことを知る。
精神保健福祉士の対応について追及を強めるため、省庁を含むあらゆる関係機関に対して問い合わせを行った。
2周すると現れたのは鳩山町役場長寿福祉課長。
責任を追及すべく、月に一度、半年間にわたって面談を重ねた。
面談自体に悪い印象はなかった。ただ、毎回別れ際に、背中に“舌を出しているような雰囲気”を感じた。
6回が過ぎ、そろそろ明確な謝罪を受ける頃だと感じ、電話でそれを課長に伝えた。すると、課長の口からは信じがたい言葉がこぼれた・・・。
「堂々巡りだよね」「ぷっ!笑っちゃったw」
面談時とは違い、話が噛み合わない。
何を言っても、言い返すのが仕事であるかのように、小学生の口喧嘩のような返答が返ってくるだけだった。
そして、ついに課長の口から出たのは、
「堂々巡りだよね」
さらに、
「ぷっ、笑っちゃったw」
被害者は、鳩山町長寿福祉課長の指示のもと、精神保健福祉士の不手際により多大なストレスを受け、結果として家庭は崩壊した。
父母側から考えても、もっともらしい不法行為に加担させられた挙句、長年ローンを払ってきた終の棲家を追われる羽目になったのだ。
この不適切な発言を繰り返す、田舎町の役場の課長によって。
考察:「堂々巡りだよね」「ぷっ!笑っちゃったw」
この一連のやりとりを第三者の立場から俯瞰的に捉えると、地方行政における権力の私物化、説明責任の放棄、そして対話の破綻が浮き彫りになる。
まず、面談時の態度と電話対応の乖離に注目すべきである。面談中は一応の礼節や対面の抑制が働いていたが、電話口ではその仮面が剥がれ、相手を軽んじるような発言が露骨に現れている。「堂々巡りだよね」「ぷっ、笑っちゃったw」といった発言は、対等な対話の放棄であり、問題解決の意志が完全に欠如している態度を示している。
このような言動は、単なる失言ではなく、制度の中で力を持つ側がそれを正当化するために用いる、いわば“言語による優位の誇示”である。発言者が役場の課長であり、かつ問題の根源に指示的立場で関与していたという事実は、この問題を単なる人間関係の衝突として済ませることを許さない。
また、精神保健福祉士の不手際が引き金となった被害者側の家庭崩壊や、父母が不本意なかたちで居住権を失ったという構図は、単なる一個人の不満ではなく、地方行政による生活破壊として捉えられる。行政職員が「加担させる」という構造的暴力を経て、被害者家族が崩壊に追い込まれていく様は、責任の所在が曖昧なまま進行する制度的不条理の典型例といえる。
田舎町の役場という、閉じた人間関係と上下構造の中で、課長のような人物が無反省なまま不適切な言動を繰り返す背景には、行政内部の監視機能の欠如と、外部からの批判を“敵視”する体質がある。ここで問題なのは、発言そのものの軽薄さではなく、それを無批判に許容する組織の構造である。
つまりこの事例は、行政機構における説明責任と倫理意識の欠如が、住民の人生をどれほど深く傷つけるかを端的に示している。問題は言葉遣いや態度だけではない。そこに潜む制度的暴力性と、役職者による関係支配の構図こそが、最も根深く、また看過すべきでない本質である。
関係する法令
- 地方公務員法
- 国家賠償法
- 民法
- 障害者基本法
地方公務員法(第33条)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
国家賠償法(第1条)
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、これを賠償する責に任ずる。
民法(第709条)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
障害者基本法(第4条第2項)
何人も、障害者であることを理由として、正当な理由なく差別的取扱いをしてはならない。
専門家としての視点
-
- 行政職員による「堂々巡り」の発言が示す責任回避構造
- 公務中の嘲笑発言「ぷっ、笑っちゃったw」にみる信用失墜行為の法的性質
- 住民対応における軽侮的発言がもたらす人格権侵害の構造
行政職員による「堂々巡り」の発言が示す責任回避構造
地方自治体における行政職員の発言は、私人の発言と異なり職務執行行為として制度の一部とみなされるため、その内容が持つ意味は常に公的責任を伴う。「堂々巡りだよね」という発言は一見、会話が平行線をたどっている状況を指摘しているかのように見えるが、住民からの真摯な訴えに対してこのような表現を用いることは、実質的に対話を打ち切り、問題を処理しない構えを示すものである。このような言葉が公務中に発せられた場合、それは住民に対して制度が向き合う姿勢を欠いたものとして、職員としての品位保持義務に違反する言動と評価される可能性がある。地方公務員法第33条は「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と規定しており、対応の打ち切りを暗示する発言はこの条文に照らして信用失墜行為とみなされ得る。また、「堂々巡り」という語には、話が無意味に繰り返されているという否定的評価が含まれており、それを行政側から発することは、住民の意見を初めから価値のないものと見なす態度の表明となる。これにより住民が精神的苦痛を受けた場合には、民法第709条の不法行為規定により「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、その損害を賠償する責任を負う」とされており、賠償請求の対象となる構成が成立し得る。よってこの種の発言は、単なる不適切対応ではなく、制度が本来果たすべき説明責任や対話姿勢を放棄したものであり、住民の訴えを制度的に排除する意図を含むものとして重大な社会的・制度的問題を内包する。行政職員が住民との対話において応答を閉ざすような発言をすることは、制度の正当性そのものを損なう結果をもたらすため、厳密に評価されるべきである。
公務中の嘲笑発言「ぷっ、笑っちゃったw」にみる信用失墜行為の法的性質
公務員が業務中に発する一つ一つの言葉は、単なる個人の感情表現ではなく、行政機関としての立場を背負ったものと解釈されるため、社会的意味は極めて重大である。「ぷっ、笑っちゃったw」という発言は、住民との対話において発せられた場合、相手の発言や存在そのものを嘲笑する意図を含むものとして認識されやすく、これが行政職員の口から発せられたという点において、職務上の品位保持義務違反として扱われる。地方公務員法第33条はそのような事態を未然に防ぐために、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定めている。したがって、住民が真剣に訴えている場において「笑っちゃった」という発言がなされた場合、その言動は職務行為の一環としての不適切対応と見なされ、当該地方自治体の職務執行体制全体に対しての不信を招く根拠となる。また、この発言によって相手方が精神的苦痛を受けたとすれば、国家賠償法第1条が適用され得る。すなわち「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、これを賠償する責に任ずる」とされており、公務中の嘲笑発言が違法行為と認定された場合には、町側が賠償責任を負う構成が成立する。さらに民法第709条に照らせば、個人としての不法行為責任も追及可能であり、同時に障害者基本法第4条第2項「何人も、障害者であることを理由として、正当な理由なく差別的取扱いをしてはならない」に抵触する場合には、発言が合理的配慮を放棄したものとして別の法的責任も問われる。従って、この「笑っちゃった」という発言は、単なる軽口ではなく、公務中に行われた信用失墜行為・人格権侵害・差別的対応といった複数の法的評価軸で精査される必要がある。
住民対応における軽侮的発言がもたらす人格権侵害の構造
住民に対する行政職員の発言が「堂々巡り」や「ぷっ、笑っちゃったw」のような形式をとる場合、それは相手の話をまともに取り合わず、精神的に切り捨てる態度を内包しており、法的には人格権侵害の構成を持つ。人格権とは、民法上保護される最も基本的な非財産的利益であり、名誉、信用、精神的平穏などがこれに含まれる。民法第709条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と明記されているが、この「法律上保護される利益」には、前述の人格的価値が当然含まれる。行政機関の窓口で精神的苦痛を与える発言が繰り返された場合、その行為は私的な感情の発露ではなく、「制度による言語的暴力」としての構造的責任を問われる。とくに福祉部署においては、弱者に寄り添うべき義務が強く求められるため、その立場からの嘲笑・侮蔑・軽視は、社会的影響の大きさにおいて通常の不法行為よりも重い評価を受ける傾向がある。人格権を侵害された住民が訴訟を起こした場合、精神的損害に対する慰謝料の支払い義務が生じる可能性があり、それが国家賠償法第1条の構成要件に合致すれば、町に対する損害賠償請求へと拡張される。このような軽侮的発言が行政職員の立場から繰り返される環境は、自治体内部におけるコンプライアンス体制の崩壊を意味し、信頼の回復には組織的見直しと制度的再構築が不可欠である。
専門家としての視点、社会問題として
-
- 行政窓口における「堂々巡り」発言が生む対話遮断と市民排除
- 「笑っちゃったw」という公務員の嘲笑が象徴する制度的侮辱
- 地方行政の内部文化としての軽視とその構造的再生産
行政窓口における「堂々巡り」発言が生む対話遮断と市民排除
「堂々巡りだよね」という発言は一見、議論が同じところをぐるぐる回っているという事実認識の表明に見えるが、行政窓口における住民応対においてそれを発することは、実質的に対話の打ち切り宣言に等しい意味を持つ。つまり、訴えの核心に対する検討意欲を放棄し、住民の言葉を「無意味な反復」と決めつけて処理しようとする姿勢がそこに表れている。このような応対は、行政サービスが住民の声に基づいて調整されるべきものであるという原則を否定するものであり、事実上の市民排除行為に他ならない。特に地方自治体においては、人口規模が小さく、窓口担当者と住民との距離が近いため、このような発言が制度全体への不信につながりやすい。さらに、「堂々巡り」という言葉の持つ冷笑的ニュアンスが、訴える側の精神的負担を増大させることは明らかである。これは一方的な評価の押し付けによって話を終わらせようとする言語的な暴力であり、形式的には問題提起に応じているように見せながら、実質的には思考停止と排除のメッセージを送る行為である。こうした態度が繰り返されることは、行政機関における相談制度や対話空間の形骸化を招き、結果的に苦情の制度的吸収機能が失われ、紛争の激化や住民の孤立を招くことになる。言葉を通じて行政にアクセスしようとする住民に対して、行政側が「堂々巡り」と断じることは、民主的制度の根幹である相互理解のプロセスを一方的に閉ざす行為であり、深刻な社会的問題である。
「笑っちゃったw」という公務員の嘲笑が象徴する制度的侮辱
「ぷっ、笑っちゃったw」という言葉は、一見すれば軽い冗談や個人的な感情の発露に過ぎないように聞こえるが、行政職員が公務中に住民に対してこのような言葉を口にすることは、その背後にある制度的権力と優越的立場を背景にした侮辱行為とみなされる。この種の発言は、住民との信頼関係を一瞬で破壊するものであり、単なる不適切発言ではなく、制度的正当性の根幹を揺るがす行為である。とりわけ、相談や苦情申し出の場において、住民が自身の経験や被害を訴えている最中にこのような嘲笑的表現が発せられた場合、それは「おまえの訴えは笑いものだ」という意思表示として受け取られる。つまり、発言そのものが制度による否認、軽視、排除を体現する。地方行政においては、しばしば職員と住民の関係が固定化し、内部的な優越感が未処理のまま温存されていることが多く、こうした言動が無意識に行われる場合もあるが、それは許容されるべきではない。制度は中立性と公平性を保つことが求められるが、「笑っちゃったw」という言葉が放たれた瞬間、その制度は中立者の立場を放棄し、住民に対して優越的な立場からの評価を下したことになる。これは精神的な攻撃行為であるだけでなく、行政が提供する相談機能そのものの正当性を否定するものである。こうした言動が自治体内で黙認された場合、他の職員による追随や同様の言語態度の拡散を引き起こし、組織としての倫理基盤の崩壊に直結する。ゆえに「笑っちゃったw」という一言は、公務員個人の態度という範囲を超え、組織文化の問題、ひいては制度が住民をどのように扱うかという根本的課題を露呈させる象徴的発言である。
地方行政の内部文化としての軽視とその構造的再生産
「堂々巡り」や「ぷっ、笑っちゃったw」という発言は、個人の資質に帰する問題ではなく、地方行政組織における住民軽視の文化が構造的に再生産されている実態を示している。こうした発言が現場で自然に出てくる背景には、住民を制度の対象としてではなく、処理すべき厄介な存在として捉える意識が浸透していることがある。行政の内部では、形式的な応対マニュアルや法令遵守は重視されても、住民との対話において本当に求められる傾聴・理解・共感といった態度は軽視されがちである。特に少人数自治体においては、職員同士の相互監視が機能せず、内部での発言や態度が野放しになりやすいという構造的問題がある。その結果、住民の訴えに対して「またか」「話が長い」「対応するだけ無駄」といった感情が内面化され、それが言語化されたものが「堂々巡り」や「笑っちゃった」といった発言である。このような態度は、新たに採用された職員にも継承され、職場内での共通言語として定着していく。つまりこれは、個人の不適切対応という範囲を超えた、組織全体の問題として認識されるべきである。行政がこうした構造を放置すれば、住民の行政離れや不信感の固定化を招き、地域における制度そのものの正当性が揺らぐことになる。よって、「堂々巡り」や「笑っちゃったw」といった発言を許容する土壌そのものが、重大な社会的課題であり、監査、議会、外部監視機関などによる可視化と是正措置が不可欠である。
まとめ
行政職員の発言である「堂々巡りだよね」「ぷっ、笑っちゃったw」という言葉には、単なる不適切応対という次元を超えて、制度そのものが市民をどう扱っているかという深い問題が潜んでいる。これらの発言は、対話を打ち切る口実であり、住民の真剣な訴えを軽視し、制度的に排除する言語的手段として機能する。公務員が公務中にこのような言葉を発することは、単なる一職員の態度ではなく、その背後にある組織文化や行政の内面構造を映し出すものである。とくに地方自治体においては、住民との距離の近さが制度の柔軟性や対応力の鍵となるが、逆に内輪化や形式化が進行すると、こうした軽侮的言動が常態化しやすくなる。行政機関は制度の顔であり、住民にとっての最前線である以上、その一言一言が制度の正当性を体現する。だからこそ、こうした発言が公的空間で放たれたとき、それは制度全体の信用を失墜させ、行政機関の存在意義を自ら損なう結果につながる。