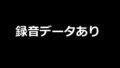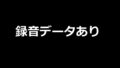地方行政の窓口で発せられる言葉が、時に住民の生死や尊厳に深く関わることがある。特に福祉の現場では、職員の一言が支援にも加害にもなりうる中、制度の名の下で語られる発言がいかに当事者を追い込むかは、あまりにも軽視されてきた。「本人が楽になるならそれも一つの手だ」と語った長寿福祉課長の言葉は、単なる失言ではなく、制度的加害の象徴である。本記事では、その背景にある行政構造、法令との関係、そして社会的責任について明らかにしていく。
本人が楽になるならそれも一つの手だ
- これまでは
- 本人が楽になるならそれも一つの手だ
- 考察:本人が楽になるならそれも一つの手だ
これまでは
2023年2月9日、4年間およぶ鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせの結果、ひき逃げ事件に発展し、被害者は被害者として東松山警察署に行った。東松山警察署に向かうパトカーの中でスマホの録音を始めた。事情聴取中に謎の警察による不当な保護(警察官職務執行法第3条)。18時間拘束された挙句、2つの精神病院に措置入院判断のために連れていかれ、結果的には開放された。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせが行われた理由としては、幼少期からの父によるDV、パワハラ、モラハラがあり、離婚後「これ以上人生を狂わされたくない」という思いから同居を拒否するも、母からの「二度とそのようなことは起こらない」との言葉を信じて、また「今度は何があろうと絶対に家から出ていかない」と心に決める。
同居をはじめてしばらくすると、相変わらずはじまる父のパワハラ、モラハラ。「出ていかない」ための抵抗により、父は警察、役場を利用して追い出そうとする。
鳩山町役場長寿福祉課、精神保健福祉士の不手際により、父の目論見を知った被害者は父を家から追い出す。
精神保健福祉士の行動はその後も不審極まりなく、やがて母も去ることとなる。
ひとり残された被害者は一時、精神保健福祉士を唯一の頼りとするが、やがてその目論見が自己の、所属組織、さらには警察へのアピールであったことを知る。
神保健福祉士との関係を遮断すると、西入間警察署、鳩山町長寿福祉課、犯人による嫌がらせが始まる。
一方、精神保健福祉士の行動を追及し始めた被害者は、省庁を含むあらゆる組織に問い合わせを行い、やがて二巡目で鳩山町長寿福祉課長にたどり着く。
被害者は長寿福祉課長と6ヶ月に及ぶ面談を重ねるが、その面談の最中・・・。
本人が楽になるならそれも一つの手だ
面談を重ねる中で、長寿福祉課長は一旦はこちらの正当性を認めたかに見えた。
そんな中、気になる発言があった。
「孤独死とか、大丈夫か?」
しかも、その言い方には背筋が凍るような冷たさを感じた。
一時的な長寿福祉課長の裏切りを乗り越え、再び電話でやり取りをするようになった。
どうしてもあの一言が頭から離れなかった被害者は、課長に確認する。
すると、あろうことか課長の口から発せられたのは、
「本人が楽になるならそれも一つの手だ」
という信じがたい一言だった・・・。
考察:本人が楽になるならそれも一つの手だ
被害者と長寿福祉課長との間で複数回にわたり面談が行われる中、課長は一度は被害者の主張の正当性を認めたかのような対応を見せた。しかしその最中、「孤独死とか、大丈夫か?」という発言があった。この発言は、形式上は安否確認のようにも見えるが、被害者は「孤独死をされては迷惑だ」という含意を感じ取り、役場職員、福祉課長としてあるまじき冷たさを覚えた。
のちに電話での対話が再開された際、被害者はその発言について課長に確認を行った。すると課長は、「本人が楽になるならそれも一つの手だ」と述べた。
この発言は意図的かつ明確に発せられたものであり、行政職員、特に福祉を担当する立場として不適切である。被害者が受けた印象や状況を含め、この一連の言動は記録として正確に保持されるべきものである。
関係する法令
- 地方公務員法
- 国家賠償法
- 刑法
- 厚生労働省設置法
- 社会福祉法
地方公務員法(第32条)
職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
地方公務員法(第33条)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
国家賠償法(第1条)
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、これを賠償する責に任ずる。
刑法(第193条)
公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げたときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法(第61条)
他人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
厚生労働省設置法(第4条第1項)
厚生労働省は、国民生活の安定及び向上を図るため、国民の福祉の増進、社会保障の充実並びに保健、医療及び労働に関する施策の企画及び実施を総合的に推進することを任務とする。
社会福祉法(第3条第1項)
全て国民は、無差別平等の原則の下に、必要な福祉サービスを等しく受けることができる。
専門家としての視点
- 地方公務員による発言と服務規律の明確な抵触
- 行政対応における国家賠償法上の違法行為の構成要件
- 刑法上の職権濫用および教唆構成の観点からの検討
地方公務員による発言と服務規律の明確な抵触
地方公務員法第32条は「職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定し、さらに第33条においては「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない」とされている。本件における長寿福祉課長の発言「孤独死とか、大丈夫か?」および「本人が楽になるならそれも一つの手だ」という言葉は、被害者の心理的状況を踏まえたうえでの行政対応として、福祉行政の担い手がとるべき発言ではなく、明らかに上記条文に違反するものである。これらの発言が一対一の対話の中で発せられたものであり、正式な見解や声明でなかったとしても、発言者が地方公共団体の課長職という公的な立場にあり、職務に付随する権限を背景として行動していた以上、その言動には常に公務員法上の服務規律が適用される。特に福祉という人命や生活の維持に直結する分野においては、言葉のひとつひとつに対する責任の重みは極めて大きく、公的立場からの不用意な言及は直ちに「信用失墜行為」として問われうる。したがって、当該発言が私的感想の範囲であったか否かにかかわらず、当該職員が公務員としての地位にある限り、服務義務違反としての評価は免れない。このような事案では、単なる内部指導ではなく、第三者機関による調査や処分検討が本来求められる枠組みとなる。
行政対応における国家賠償法上の違法行為の構成要件
国家賠償法第1条は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、これを賠償する責に任ずる」と明記している。本件における長寿福祉課長の発言群が被害者に深刻な精神的影響を及ぼし、生活上の支障や不安、孤立感の増大を招いた場合、それが「損害」として認定される余地は十分にある。特に福祉課長という職位は、一般の住民から見れば信頼を前提とした行政窓口の代表であり、その発言のひとつひとつが「職務行為」として捉えられるのが通例である。仮に課長本人が「一般論として述べた」「私的な感想であった」と反論したとしても、その発言が職務上のやり取りの一環であった以上、法的には「職務執行中の行為」として扱われ、職責に基づく損害発生があれば自治体が賠償責任を問われる構造にある。さらに、精神的損害については民法上の慰謝料請求と同様に取り扱われるため、発言の内容が具体的に被害者の自尊心や安全感、将来展望に影響を及ぼしたことが客観的資料や証言などにより立証されれば、国家賠償法第1条に基づく請求が法的に成立し得る。また、本件のように支援を求めて行政に接触した結果、逆に心理的ダメージを受けたケースは、いわゆる「公的加害」としての意味合いが強く、自治体側の説明責任が極めて重い。制度の信頼性確保のためにも、組織的な検証と対応が不可欠である。
刑法上の職権濫用および教唆構成の観点からの検討
刑法第193条は「公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げたときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する」と定めており、公務員が行政的優位性を背景に住民の行動や思考に実質的な影響を及ぼした場合、その発言や行為は職権濫用として違法性を問われうる。また、刑法第61条においては「他人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する」と規定されており、意図的な誘導行為や選択肢の提示が一定の条件下で教唆罪の構成要件に該当する可能性がある。本件における「本人が楽になるならそれも一つの手だ」という発言が、たとえ明示的な指示でなかったとしても、受け手の心理状態や状況、会話の流れ、発言者の権威性などを総合すれば、事実上の示唆または容認として機能する構造を持つ場合、刑法上の問題を生じさせる余地がある。特に福祉職という、対象者の心理的・生活的脆弱性を理解した上で支援する立場にある職員が、選択誘導に近い言葉を口にすること自体が構成要件該当性の検討対象となりうる。仮に直接的な因果関係や実行行為がなかったとしても、発言の内容・立場・影響力を踏まえれば、教唆または幇助の観点からの精査が必要であり、刑法上の適用可否を第三者機関が判断する必要性がある。
専門家としての視点、社会問題として
- 行政福祉現場における精神的暴力の構造的放置
- 公務員発言の社会的影響と住民の信頼毀損
- 孤立と制度的不作為が生む二次的加害
行政福祉現場における精神的暴力の構造的放置
本件に見られる長寿福祉課長の発言は、その内容において直接的な物理的暴力を伴っているわけではないが、精神的・心理的影響という点で明確なダメージをもたらしている点に注目する必要がある。とりわけ「孤独死とか、大丈夫か?」や「本人が楽になるならそれも一つの手だ」といった発言は、社会的孤立の状態に置かれた住民に対し、行政側から暗に拒絶を伝えるような言葉として機能しうる。こうした言葉の背後にあるのは、制度の中に埋め込まれた構造的無関心であり、それは個人の資質による問題として処理されがちだが、実際には行政福祉機構全体に共有された態度の一端である。住民が行政に相談を求めた時点で、すでに一定の社会的・心理的負荷がかかっていることは前提であるべきであり、その中で「支援の仮面をかぶった突き放し」が生じることは、事実上の精神的暴力に他ならない。しかもそれが個室での会話、非公開の面談という密室的構造の中で行われるため、記録も残らず検証もされにくく、被害者側だけが証言と記憶に頼らざるを得ない状況となる。これは、いわゆる「制度的暴力」として国際的にも議論されている問題の一部であり、行政手続きのなかに隠蔽されたかたちで潜在している構造的加害である。今後の対応としては、福祉現場における言動に関する職員教育の抜本的見直しと、面談等のやり取りを記録・開示可能なかたちで保存する仕組みの構築が不可欠である。個人の問題として処理される限り、この構造は温存され続け、同様の被害が再生産されるリスクが高い。
公務員発言の社会的影響と住民の信頼毀損
行政職員の発言は、単なる個人の言葉ではなく、その背後に組織と制度を背負っていることを社会的に理解しなければならない。特に地方自治体における福祉担当者の言葉は、対象者にとっては生活と生命に直接関わる意味を持ち、それゆえに一言一句が重大な影響を及ぼす。本件で示された「本人が楽になるならそれも一つの手だ」という言葉が、事実である以上、その責任の所在は行政組織としても問われるべきであり、これは単なる「言葉の選び方」の問題に矮小化してはならない。こうした発言は、単に当該被害者個人への影響にとどまらず、地域住民全体に対する行政への信頼感を毀損する行為である。行政機関にとって「言葉」は制度の顔であり、制度の最前線で交わされる言葉の質は、そのまま行政機能の質と捉えられる。特定の弱者層、特に精神的・社会的に孤立した住民に対する発言は、単なる失言ではなく、「制度の意思」として解釈される可能性すらある。行政が中立性や公平性を謳うのであれば、言葉の中立性や影響評価についても明確な指針を設け、言葉による加害が発生した際には適切な説明と回復措置がなされる仕組みが必要である。自治体ごとにこうした評価機構が存在していない現在、被害者が個別に発言の記録や追及を行わざるを得ない構造は極めて非効率であり、構造的放置に近い状態を生んでいると言える。
孤立と制度的不作為が生む二次的加害
被害者が行政機関に支援を求めた背景には、すでに長期的な孤立や社会的排除が存在していると考えられる。こうした状況下で、福祉行政の担当者から突き放すような発言がなされることは、第一の被害に対する「二次加害」に他ならず、社会的には制度的不作為による被害再生産と呼ばれる事象である。本来、社会福祉制度はこのような孤立を解消するために存在しているにもかかわらず、現実にはその制度が機能不全に陥り、さらなる孤立と心理的損傷を深める役割を果たしている構図が存在する。「本人が楽になるならそれも一つの手だ」という発言が口をついて出る現場においては、もはや支援を必要とする個人の尊厳や生存権が、制度の前提として認識されていないことを意味している。これは単に一自治体の課題にとどまらず、日本の福祉行政全体に内在する構造的問題であり、統計に表れない数多くの孤立死や制度外死の根底にこの構造が関与している可能性がある。社会全体として、孤立者に対するアプローチを制度の内側にきちんと取り込む設計を持たない限り、このような「静かな加害」は今後も見えないかたちで続いていく。行政機関が担うべきは制度の運用にとどまらず、制度の存在意義そのものを住民の尊厳と共に維持する姿勢であり、個人の資質や感情によって制度が歪む構造を放置することは、国家的責任の回避に等しい。
まとめ
地方自治体の福祉担当者による発言が、制度的に許容されない内容であった場合、その影響は個人の心理的ダメージにとどまらず、行政全体の信頼性を揺るがす深刻な問題であると言える。「本人が楽になるならそれも一つの手だ」という発言が公務員の立場から発せられた事実は、支援を求める住民に対し制度が加害者となる構造を浮き彫りにしており、精神的暴力や制度的不作為の側面を帯びる。しかもこの発言が一般論として語られた以上、個人ではなく組織の姿勢そのものが問われることになる。現場の言葉一つが命に関わる重みを持つ福祉の場面において、言動の適切さを確保する体制が不在であるならば、それは制度設計そのものの欠陥である。行政には、住民の尊厳と安心を守る責任がある以上、こうした事例を通じて、言葉による行政加害を制度的に予防・記録・検証できる仕組みを整備することが不可欠であり、組織的対処が求められる段階に来ている。