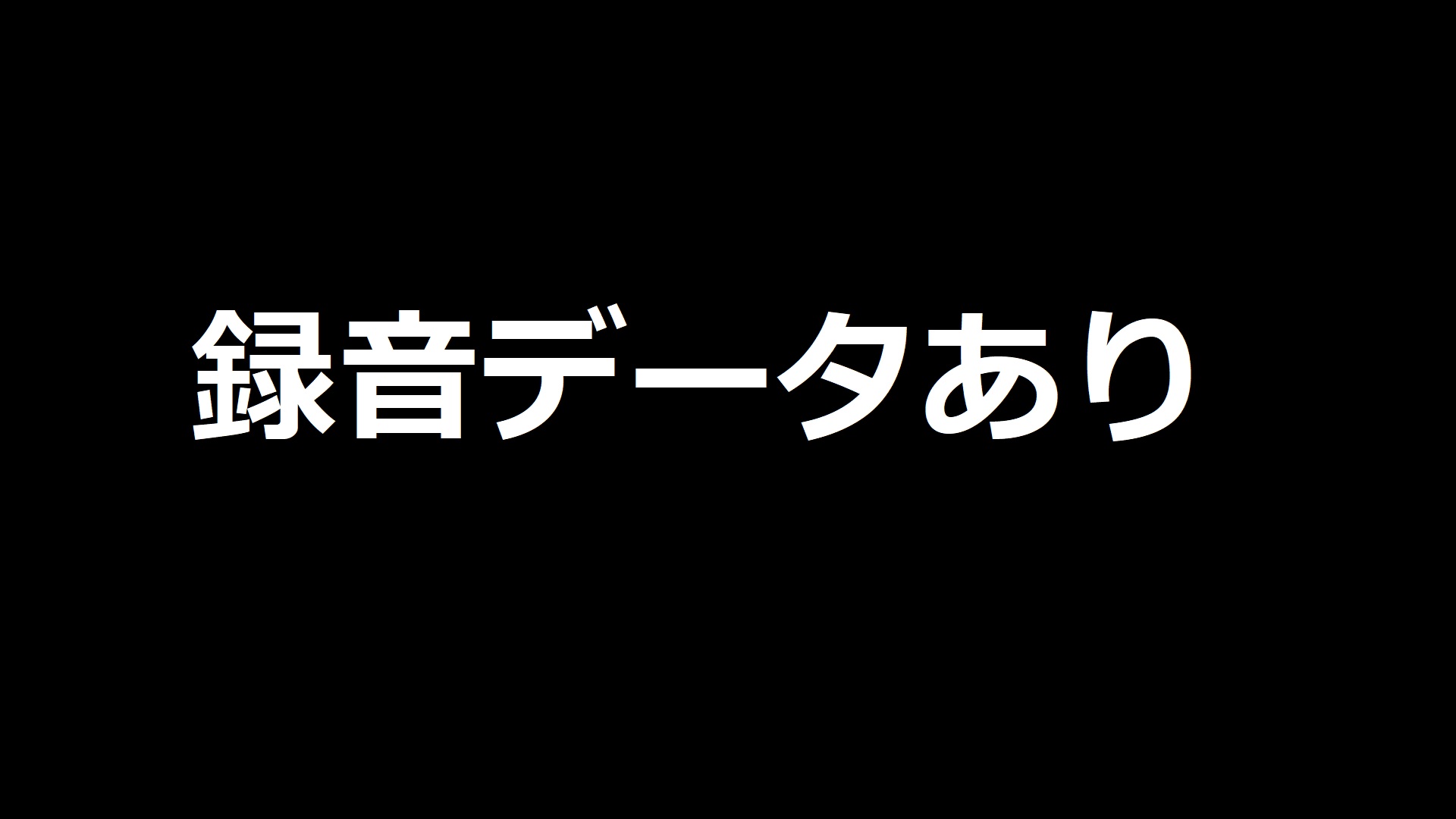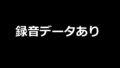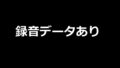警察は市民の安全を守る存在であるはずだが、実際にはその権限を濫用し、被害者を加害者として扱うケースが後を絶たない。今回の事例では、被害者が繰り返し通報を行ったにもかかわらず、警察は適切な対応をせず、最終的には被害者を保護という形で処理した。これは公務員職権濫用に該当する可能性があり、司法機関全体の信頼を揺るがす問題である。警察の対応に潜む矛盾と市民の権利侵害について検証する。
私、保護されました。
- 保護に至る経緯
- 保護時の会話(録音アリ)
- 保護の理由とされる「手を入れた」「両親に手をだす」の真相
保護に至る経緯
2023年2月9日、4年間にわたり鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による執拗な嫌がらせが続いた末に、ついにひき逃げ事件へと発展した。被害者は東松山警察署に向かい、事情聴取を受けることとなった。しかし、警察は事件の背景にある長年の嫌がらせや犯人の行動を一切考慮せず、「事件をその日、その時だけで判断しろ」といった理不尽な対応を取り、被害者の証言を封じるような姿勢を示した。刑事たちは、事件の経緯や動機、犯人の行動について真剣に取り合うことなく、被害者の行動のみを問題視し、加害と被害を逆転させるような誘導を行った。
保護時の会話
保護の理由とされる「手を入れた」「両親に手をだす」の真相
警察の取り調べでは、刑事が被害者に加害者の立場を考えるよう強要した。車内でスマホを見ていた際に突然ドアの近くに立たれ、手を入れられた場合どう感じるかと質問し、被害者が状況次第だと答えると、刑事は「普通は逃げる」と一方的に決めつけた。被害者が「自分なら110番通報をする」と主張すると、刑事は通報よりも逃げることを正当化し、警察の役割を自ら否定する矛盾した発言を繰り返した。被害者が事件をひき逃げとして扱うべきではないかと問いただすと、刑事は「ひき逃げにもなり得るが正当防衛の可能性もある」と曖昧な説明を行った。被害者が「ではひき逃げだ」と指摘すると、刑事は正当防衛を持ち出し、加害者の行為を擁護する姿勢を見せた。被害者が過去の110番通報で警察が迅速に加害者を特定し、注意を行ったと報告した点について追及すると、警察は矛盾を指摘されることを避け、過去の対応についての説明を拒否した。さらに、話題は煽り運転へとすり替えられた。別の刑事は、車の窓を開けた状態で手を入れる行為が煽り運転に該当すると主張し、被害者を加害者扱いする論法を展開した。被害者がこれまでの経緯を説明しようとすると、刑事は一切聞く耳を持たず、事件の背景を無視して今回の行為だけを問題視した。警察は、被害者が特定の車両を意識し過ぎていると決めつけ、何度もつきまとわれていた事実を認めようとしなかった。被害者が繰り返し110番通報しても警察がまともに対応せず、結局何の解決も得られていない現状を指摘すると、警察はまともな反論すらせず、注意を行ったはずの車両が再び現れた事実についても一切説明をしようとしなかった。被害者に対しては執拗に疑念を向け、問題の本質には一切踏み込もうとしない警察の姿勢は、被害者の保護ではなく、加害者の擁護に終始しているとしか思えない対応だった。
関係する法令
- 刑法 第193条(公務員職権濫用罪)
- 刑法 第230条(名誉毀損)
- 刑法 第208条(暴行罪)
- 刑法 第222条(脅迫罪)
- 刑法 第239条(虚偽告訴罪)
- 道路交通法 第72条(交通事故の場合の措置)
- 道路交通法 第117条(ひき逃げの罰則)
刑法 第193条(公務員職権濫用罪)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法 第230条(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法 第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法 第222条(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法 第239条(虚偽告訴罪)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴又は申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
道路交通法 第72条(交通事故の場合の措置)
交通事故を起こした者は、直ちに車両等を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等の措置を講じなければならない。
道路交通法 第117条(ひき逃げの罰則)
道路交通法第72条の規定による措置を講じなかった者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
警察の対応と法的問題点
- 警察の矛盾した対応と公務員職権濫用
- ひき逃げの適用基準と警察の解釈
- 煽り運転の定義と警察の歪曲
警察の矛盾した対応と公務員職権濫用
警察の取り調べでは、被害者が自身の訴えを伝える過程で、刑事が加害者の立場を強調し、被害者に不当な負担をかけた。刑法第193条(公務員職権濫用罪)では、公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した場合、2年以下の懲役または禁錮に処すると定められている。被害者が110番通報を行い、加害者の特定と警察の対応を求めたにもかかわらず、警察は一貫性のない対応を続け、事件の真相を明らかにする責任を放棄した。刑法第239条(虚偽告訴罪)は、人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴または申告を行った場合、3月以上10年以下の懲役に処するとしているが、警察の供述が一貫しないことが被害者の立場を弱め、加害者の責任追及を困難にしている。警察は被害者に対し、加害者の心理を考えるよう要求し、事件の本質をすり替えたが、刑法第230条(名誉毀損罪)は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者に対して3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すと定めており、被害者に対する警察の発言が不当な印象操作を含んでいた可能性がある。さらに、警察は通報内容と実際の対応が矛盾している点について適切な説明を行わず、過去に注意を行ったはずの車両が再び現れた事実を認識しながらも、加害者を特定したとする供述を撤回することなく、曖昧な説明を繰り返した。
ひき逃げの適用基準と警察の解釈
警察は被害者に対し、ひき逃げとしての認定について曖昧な態度を取り、正当防衛の可能性を持ち出して加害者の行為を擁護した。道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)では、交通事故を起こした者は直ちに車両を停止し、負傷者を救護し、道路の危険を防止する措置を講じなければならないと規定されているが、警察は加害者が事故後に適切な救護措置を取らなかった点を軽視した。また、道路交通法第117条(ひき逃げの罰則)では、救護義務を怠った者に対して10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるが、警察はこれを適用するどころか、被害者に非があるかのような態度を取り続けた。さらに、刑法第208条(暴行罪)は、暴行を加えた者に対し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すと定めているが、加害者が車で急加速し、被害者を引きずった行為が暴行に該当する可能性を警察は考慮しなかった。被害者が警察の対応に矛盾があることを指摘し、過去の通報時には迅速に加害者を特定していた点を問うと、警察はこの矛盾に対して明確な説明をせず、被害者の疑念を払拭しようとしなかった。
煽り運転の定義と警察の歪曲
事件の経緯の中で、警察は話題を煽り運転の問題にすり替え、被害者を加害者であるかのように誘導した。道路交通法第117条の2(煽り運転の罰則)では、他の車両に著しい危険を生じさせるような運転を行った者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定められているが、警察は被害者の行動が煽り運転に該当するかのような印象操作を行った。刑事は、窓を開けた状態で手を入れる行為が煽り運転と見なされる可能性を指摘し、被害者が加害者を追跡していたのではないかという前提で話を進めたが、これは事実に基づかない推測に過ぎない。警察は被害者が特定の車両を意識しすぎていると決めつけ、何度もつきまとわれていた事実を軽視した。被害者が110番通報を繰り返しても、警察はまともに対応せず、結果的に加害者の行為を黙認する形となった。刑法第222条(脅迫罪)は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者に対し2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとしているが、警察が加害者の行動を放置し続けたことで、被害者が脅威を受け続けた状況を是正することはなかった。警察は注意を行ったはずの車両が再び現れた件についてもまともな説明をせず、警察は注意を行ったはずの車両が再び現れた件についてもまともな説明をせず、最終的には被害者を加害者扱いし、強制的に保護する形で対応を終えた。
警察の職権濫用と市民の権利侵害
- 警察の恣意的な対応と公正性の欠如
- 被害者が加害者にされる構造的問題
- 司法機関による権力の乱用と人権侵害
警察の恣意的な対応と公正性の欠如
日本の警察機関は本来、市民の安全を守るべき存在であるが、実際にはその職権を恣意的に運用し、不公正な対応を行うケースが散見される。特に、通報者が適切な対応を求めたにもかかわらず、警察が加害者側の視点を優先し、被害者を追及する姿勢を示すことが問題となっている。今回のケースでは、被害者が繰り返し110番通報を行い、ストーカー行為やつきまとい行為に対する対処を求めたにもかかわらず、警察は通報を軽視し、加害者への対応を取らなかった。刑法第193条(公務員職権濫用罪)では、公務員がその職権を濫用して不当な行為を行わせた場合に刑事罰が科されると規定されているが、警察はこの法規定を無視するかのように、被害者ではなく通報者を疑う姿勢を示した。また、警察は以前の通報時に「加害者を特定し、注意した」と報告していたが、実際には加害者が再び現れており、警察の対応が虚偽であった可能性も否定できない。刑法第239条(虚偽告訴罪)では、人に刑事処分を受けさせる目的で虚偽の告訴を行った場合、3月以上10年以下の懲役に処すると定められているが、警察が被害者に対し一貫して加害者の立場を擁護する姿勢を取っていたことから、恣意的な法運用が行われていた疑いが強い。さらに、刑法第230条(名誉毀損罪)では、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者に対し3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるが、警察が被害者を不当に貶めるような言動を行った場合、これに該当する可能性もある。警察が市民の安全を守るのではなく、事件の背景を無視し、特定の側に有利な対応を取ることは、公正な捜査の原則に反し、市民の基本的人権を侵害する重大な問題である。
被害者が加害者にされる構造的問題
日本の警察機関においては、被害者が適切な法的救済を受けるどころか、逆に加害者として扱われるという問題が根深く存在する。今回の事例では、被害者が執拗なつきまといを受け、これに対して110番通報を繰り返していたにもかかわらず、警察は加害者の行動を放置し、逆に被害者を加害者として扱う姿勢を示した。道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)では、事故を起こした者が負傷者を救護しなかった場合、刑事責任が問われるが、警察はこの規定を適用せず、ひき逃げの加害者の行動を正当化するような対応を取った。さらに、道路交通法第117条(ひき逃げの罰則)では、事故後に必要な措置を取らなかった者に対し、10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるが、警察は加害者にこの規定を適用せず、被害者の行動ばかりを問題視した。刑法第208条(暴行罪)では、暴行を加えた者に対し2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されると定められているが、加害者が車で急加速し、被害者を引きずった行為について警察は適切な捜査を行わず、不問に付す態度を取った。さらに、被害者がこの問題を追及しようとすると、警察は話題を煽り運転にすり替え、被害者が車両を追いかけていたかのような印象を与えた。これは、警察が事件の本質を歪曲し、不当な捜査によって被害者を加害者として扱う構造的な問題の典型例であり、市民の法的権利を大きく損なうものである。
司法機関による権力の乱用と人権侵害
警察が恣意的な捜査を行う背景には、日本の司法機関全体における権力の乱用が関係している。今回のケースでは、警察が加害者の行動を正当化する一方で、被害者に対しては執拗に疑念を向け、最終的には保護するという形で権力を行使した。刑法第222条(脅迫罪)では、人の生命や身体、名誉に対して害を加える旨を告知し脅迫した者に対し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるが、警察が被害者に対して執拗な取り調べを行い、精神的圧力をかけたことがこの規定に該当する可能性もある。さらに、警察が特定の証拠を無視し、事件の全容を歪曲する形で進めた捜査は、公正な司法手続の原則に反するものであり、市民の権利を侵害する重大な問題である。刑法第193条(公務員職権濫用罪)では、公務員がその職権を濫用して市民の権利を侵害した場合、刑事罰が科されるとされているが、警察の対応はまさにこの条文に該当する行為である。最終的に、警察は被害者の訴えを無視し続け、加害者に対する適切な措置を取ることなく、権力を行使して被害者を保護するという形で事件を収束させた。このような対応は、市民の権利を著しく損なうものであり、司法機関の不正義を示す典型的な事例である。
まとめ
警察の対応には多くの問題があり、被害者が適切な保護を受けるどころか、加害者とみなされるケースが後を絶たない。今回の事例では、被害者が繰り返し110番通報を行いながらも警察は加害者を特定せず、むしろ被害者を疑いの目で見たことが問題である。ひき逃げや暴行の事実がありながら、警察は適切な措置を取らず、法の公平性が疑われる結果となった。また、警察は事件の本質を歪曲し、被害者を精神的に追い詰める形で取り調べを進め、最終的には保護という形で事件を収束させた。これは公務員職権濫用に該当する可能性があり、司法機関のあり方にも疑問を投げかける。本来であれば被害者を守る立場であるべき警察が、その責務を果たさず、加害者の行為を容認するような対応をとることは、市民の安全を脅かす重大な社会問題である。