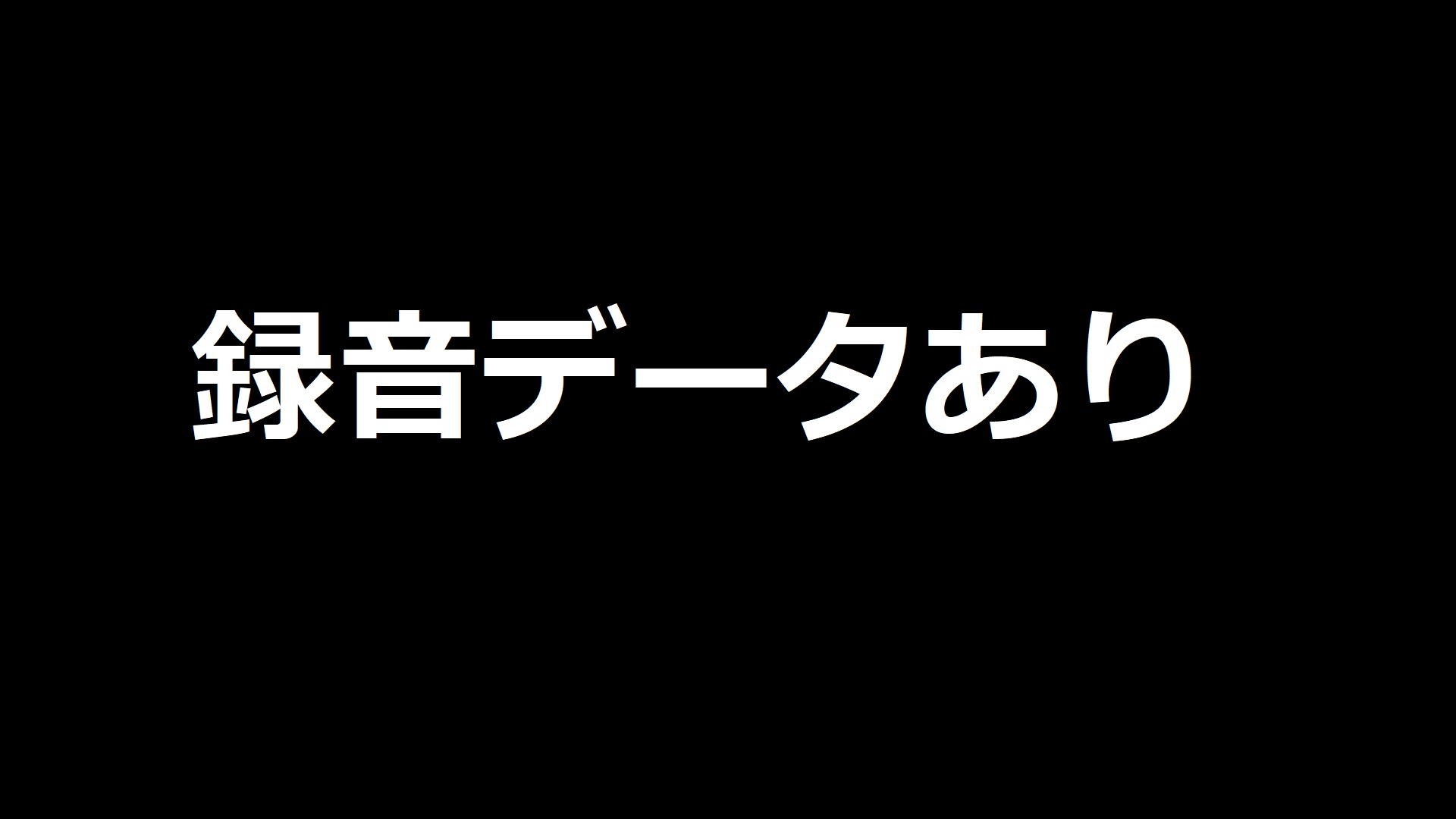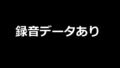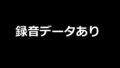煽り運転という言葉が世間に浸透し、厳罰化の流れとともにその対象行為が注目されている。しかし本来、煽り運転とは道路交通法に基づき「車両の運転者による通行妨害行為」として定義されており、運転していない歩行者に適用されるものではない。ところが、ある事件において、歩行者である被害者に対して警察が「煽り運転を行った」とする発言を行い、結果的に不当な扱いを受けた事例が存在する。このような構成要件の誤認は、冤罪や人権侵害の温床となりかねず、社会全体に対する重大な警鐘でもある。本記事では、煽り運転の定義を確認しつつ、今回の事例がなぜ法的に不適切なのかを検証し、警察対応の問題点を明らかにしていく。
歩行者がクルマに煽り運転
- これまでは
- 動画化:歩行者がクルマに煽り運転
- 考察:歩行者がクルマに煽り運転
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
東松山警察署での事情聴取中、被害者がひき逃げの定義について話していたところ、刑事課のS刑事は「煽り運転」という指摘をした。つまり、歩行者である被害者が、クルマを運転していた犯人に対して「煽り運転」を行ったという主張である。
担当弁護士が言うには、「クルマの運転席に手を入れる行為は犯人ではない」とのことであり、また仮に被害者に過失があったとしても、専門家の見解によれば過失相殺は10対90、悪くても20対80程度になるという。
このような状況を踏まえると、被害者が事情聴取中に「保護」(警察官職務執行法第3条)されたことや、犯人が傷害罪について不起訴となり、ひき逃げ(道路交通法違反および救護義務違反)についての告訴も不起訴処分となった事実は、極めて不可解である。
動画化:歩行者がクルマに煽り運転
考察:歩行者がクルマに煽り運転
東松山警察署での事情聴取中、被害者がひき逃げの定義について説明していた際、刑事課のS刑事は「煽り運転」という指摘を行った。歩行者である被害者が、クルマを運転していた加害者に対して「煽り運転をした」とするものであり、前提からして意味不明である。通常「煽り運転」は運転中の車両同士において成立するものであり、歩行者による行動がこれに該当するとは考えにくい。状況を理解せずにこのような言葉を使ったのであれば、発言の重みを疑わざるを得ず、仮に意図的であったとすれば、被害者の行動を歪めて解釈しようとする意志があったとすら受け取れる。
また、担当弁護士が言うには「クルマの運転席に手を入れる行為自体は犯人ではない」とされており、万が一、被害者に一部過失があったとしても、交通に関する専門家の見解では過失相殺の割合は被害者10、加害者90、どれだけ悪く見ても20対80程度が妥当とのことである。
このような前提を踏まえると、そもそも被害者が事情聴取の最中に「保護」という形で身柄を確保される必要があったのか、非常に疑問が残る。さらに、加害者が傷害罪について不起訴となり、ひき逃げに関しても告訴されたにもかかわらず不起訴処分とされたことは、常識的な感覚からかけ離れており、不可解としか言いようがない。
関係する法令
- 道路交通法第117条の2
- 道路交通法第108条の2の2
- 刑法第208条
道路交通法第117条の2
車両等の運転者が第70条(安全運転の義務)の規定に違反して著しく交通の危険を生じさせたときは、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
道路交通法第108条の2の2
公安委員会は、他の車両等の通行を妨害する目的で、当該他の車両等の通行を妨害する行為として政令で定めるものを反復して行った者に対し、当該者の運転免許を取り消す処分をしなければならない。
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
専門家としての視点
- 煽り運転の法的定義と対象者の明確な区分
- 歩行者による煽り運転が成立しない理由の検討
- 警察による違法な構成要件の拡張適用について
煽り運転の法的定義と対象者の明確な区分
煽り運転に該当する行為は、道路交通法の改正により明確に定義されており、同法第117条の2第2号では「第70条(安全運転の義務)の規定に違反して著しく交通の危険を生じさせたとき」は五年以下の懲役または百万円以下の罰金とされる。さらに、同法第108条の2の2では「他の車両等の通行を妨害する目的で、当該他の車両等の通行を妨害する行為として政令で定めるものを反復して行った者」に対して免許取消処分を科すべき義務を公安委員会に課しており、この政令に基づく違反行為としては、車間距離を著しく詰める行為、急な割込み、幅寄せなど、すべて車両を運転している者による運転操作が前提となっている。従って、法令上煽り運転の主体となり得るのは「車両等の運転者」に限られ、歩行者による一切の行動は対象に含まれていない。煽り運転に関する報道や司法判断でも同様の見解が踏襲されており、例えば2020年の東名あおり運転事件判決では、被告人が自車を運転しながら通行の妨害を繰り返した事実が問題とされ、歩行者が起こした行為が「煽り運転」として立件された例は存在しない。したがって、「歩行者による煽り運転」という構成自体が法律上成立せず、今回の東松山警察署のS刑事による「煽り運転」という指摘は、法的要件から完全に逸脱しており、違法な法令解釈であると言わざるを得ない。
歩行者による煽り運転が成立しない理由の検討
歩行者が運転中の車両に接近したり声をかけたり、場合によっては運転席に手を差し入れる行為を行ったとしても、それが煽り運転に該当するかどうかは、まず煽り運転という概念が何を対象としているかを明確にしなければならない。道路交通法における煽り運転の要件は、車両等の運転者が他の車両等の通行を妨害する目的で特定の運転操作を繰り返し、結果として交通の危険を生じさせることにある。これは道路交通法第117条の2および第108条の2の2に規定されており、いずれも「運転者」が主体であることを明記している。つまり、歩行者はそもそも「運転者」ではなく、対象外である。また、仮に歩行者の行動が不適切であったとしても、それは煽り運転ではなく別の法的評価、例えば刑法第208条の暴行罪や刑法第130条の住居侵入罪、または道路交通法上の横断禁止違反などによって検討されるべき問題である。したがって、歩行者の行為に対して「煽り運転」という法的評価を与えることは、論理的にも法的にも破綻しており、今回の件のように被害者をそのように扱ったことは、重大な人権侵害や捜査手続上の違法性を招くものである。
警察による違法な構成要件の拡張適用について
法の運用において警察が構成要件を不当に拡張して適用することは、刑事司法制度における重大な逸脱であり、警察官によるそのような行為は違法性を帯びる。刑法において処罰対象となる行為は、構成要件に該当することを前提としており、構成要件を満たさない事実に対して犯人性を主張することは認められない。煽り運転の構成要件はすでに明確であり、道路交通法第117条の2や第108条の2の2により、対象は「車両等の運転者」に限られることが法律上の要件である。警察がこの解釈を逸脱し、歩行者による行動を煽り運転と見なすことは、構成要件の無理な拡張であり、法的根拠のない対応である。警察は行政機関である以上、法律に基づいた権限の行使が求められ、違法な法解釈による捜査・拘束は国家賠償法第1条にもとづく違法な公権力の行使に該当しうる。したがって、今回のように歩行者である被害者の行為を「煽り運転」として指摘した東松山警察署の対応は、構成要件の誤解釈という次元を超え、違法な捜査行為として厳しく問題視されるべき事案である。
専門家としての視点、社会問題として
- 煽り運転の概念の誤用がもたらす社会的な混乱
- 警察による印象操作が市民の信頼を損なう構造
- 被害者が加害者化される構図と人権侵害の拡大
煽り運転の概念の誤用がもたらす社会的な混乱
煽り運転は社会的に強い非難の対象となっており、重大な交通犯人として報道や司法においても厳しく取り扱われているが、その「煽り運転」という言葉が本来の意味を逸脱して拡大解釈されることで、社会的な混乱を引き起こしている。法律上、煽り運転とは道路交通法に基づくものであり、車両を運転する者が他の車両に対して危険な運転操作を繰り返し、通行を妨害することを指す。この前提を無視して、歩行者による行為までも「煽り運転」として処理しようとする動きは、法の解釈を根底から揺るがす重大な問題である。今回のように、歩行者である被害者が加害者の車両に接近したという理由で「煽り運転をした」と警察が判断することは、明確な定義と対象者の枠組みを逸脱しており、結果として無実の市民が冤罪の対象となる恐れを生む。言葉の持つイメージの強さゆえに、実際の法的構成要件を確認することなく安易に「煽り運転」と断定する風潮が強まれば、法的根拠のない処罰や社会的制裁が横行することとなる。社会全体が感情や印象によって刑事的評価を行うようになれば、言葉の暴走が法の秩序を崩壊させ、誰もが任意のタイミングで処罰の対象とされる危険な社会に変質していく。
警察による印象操作が市民の信頼を損なう構造
警察による捜査や発言には重大な社会的影響力があり、その発言内容は時としてメディアに取り上げられ、公的な見解として受け止められることが多い。こうした中で、歩行者に対して「煽り運転」という法的に矛盾する指摘を行う行為は、警察が本来果たすべき法の番人としての役割から逸脱しており、印象操作によって特定の人物を社会的に貶める危険な行動である。市民は警察の言葉を一定の信頼をもって受け取る傾向があるが、その言葉が制度的裏付けのないものであった場合、警察組織全体の信用を著しく損なうこととなる。特に今回のように、明確に被害者とされる立場の者が警察によって「加害者」として扱われる事例は、警察の判断が事実よりも都合や印象に基づいているのではないかという深刻な疑念を社会に与える。こうした事例が続けば、警察に協力すること自体が市民にとって危険を伴う行為と認識され、通報・証言・協力といった基本的な協働関係が崩壊し、治安維持の基盤が脆弱化する。つまり、警察による不適切な言動は個別の冤罪被害にとどまらず、国家と市民の信頼関係そのものを根底から崩す社会的問題である。
被害者が加害者化される構図と人権侵害の拡大
今回の事案において最も深刻なのは、ひき逃げ事件の被害者が、警察によって「煽り運転の加害者」として扱われたという構図である。本来であれば被害者として救済されるべき立場にある人物が、不当な法解釈と偏った捜査のもとで逆に責任を負わされ、精神的・肉体的拘束を受けるという状況は、近代国家の刑事司法制度においてあってはならない。被害者に対して責任転嫁が行われる構図は、組織の体面維持、捜査の都合、あるいは特定の意図に基づいて説明されることがあるが、いかなる理由があろうとも、そのような扱いが人権侵害であることは明白である。日本国憲法第13条は「すべて国民は個人として尊重される」と規定し、第31条では「何人も法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と明記されている。これらの基本的人権の保障は警察活動にも当然及ぶものであり、捜査の名の下に恣意的な拘束や法的評価のすり替えがなされるのであれば、それは国家による暴力の行使に他ならない。加害者を庇い、被害者に責任を負わせる構造が一度許されれば、それは制度的正義の崩壊を意味し、社会の中で誰もがいつ被害者から加害者へと転落するかわからない不安定な状態を招く。
まとめ
煽り運転という言葉が社会に定着し厳罰化が進む中で、その定義と適用範囲についての理解が曖昧なまま拡大解釈される傾向が見受けられる。特に今回のように、歩行者である被害者に対して警察が「煽り運転を行った」とする発言を行った事例は、煽り運転の本来の法的定義を無視した極めて異常な対応である。道路交通法における煽り運転の要件は「車両を運転している者」に限られ、歩行者が対象となる余地は法令上存在しない。このような不適切な適用は、被害者の立場を不当に貶め、加害者との立場を逆転させる危険をはらんでいる。また警察による誤った構成要件の運用は、市民の人権を脅かし、冤罪や不当な拘束につながる重大な社会問題である。法令の正確な運用と警察の慎重な対応が、社会の信頼を維持するうえで不可欠である。