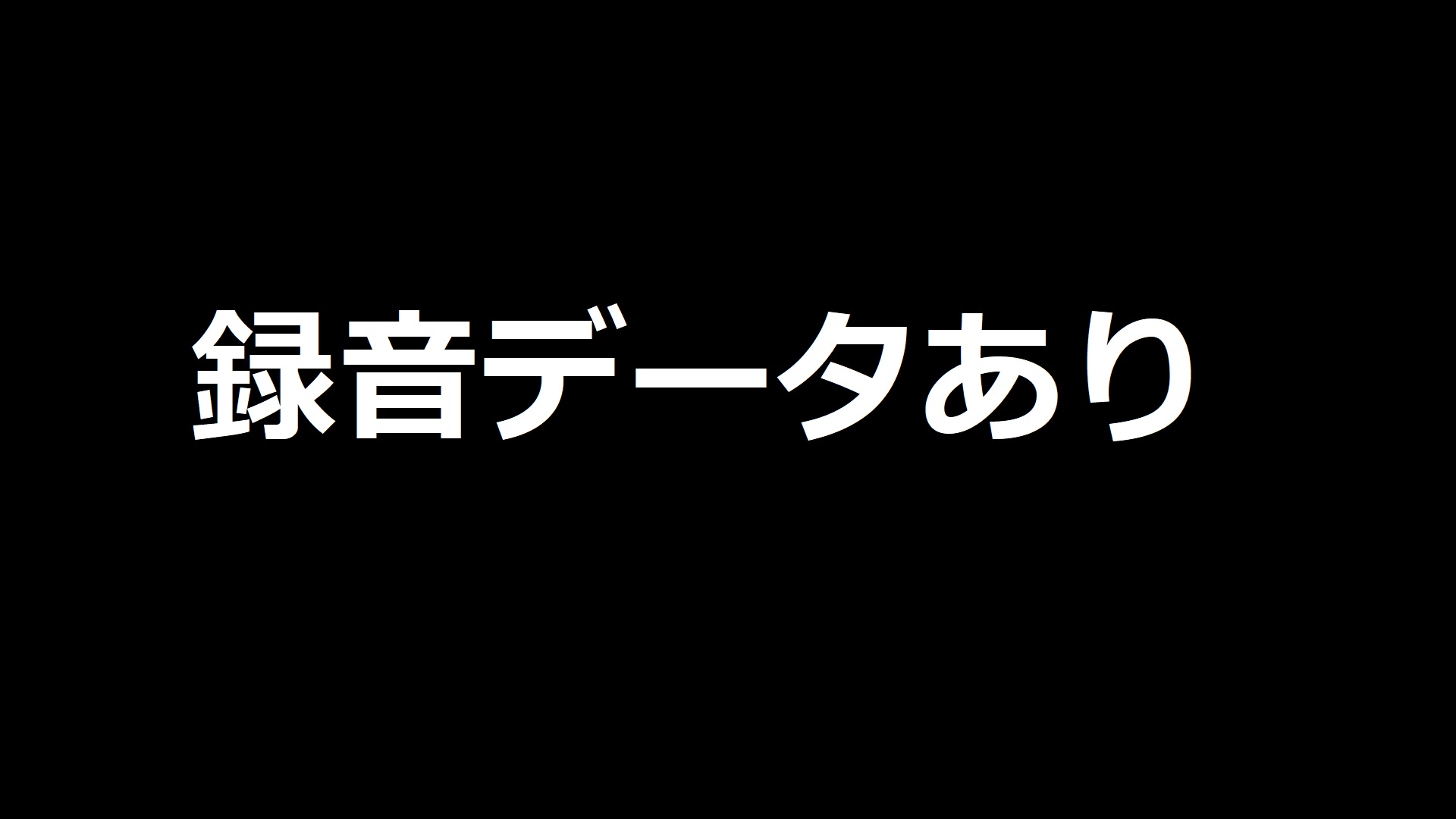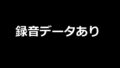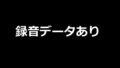ひき逃げ被害者がなぜか警察に保護された―その理由を問うと即答できなかった。警察はその後「自傷他害の話をしていたから」と説明したが、その場で根拠を示せなかった時点で警察官職務執行法第3条の適用条件を満たしていたとは考えにくく、説明責任が果たされていない可能性が高い。保護の形式を取りながら、実質的には理由のない拘束が行われた疑いがある事例として、警察の判断と手続の正当性を問い直す必要がある。
保護の理由は?
- これまでは
- 動画化:保護の理由は?
- 考察:保護の理由は?
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
東松山警察署刑事課の刑事に保護された直後、保護に立ち会っていた生活安全課のK氏に対して「保護とは何か」「なぜ自分が保護されたのか」と質問したが、K氏は明確な説明をすることができなかった。ようやく口にした説明は、「自傷他害の話をしているから」という理由であった。
そもそも東松山警察署には、ひき逃げ事件の被害者として同行していた。事情聴取の過程では誘導尋問が行われ、被害者であるにもかかわらず加害者へと扱いが転じ、事件の経緯やきっかけ、理由が一切無視されたまま加害者とされた。さらに、その場で発した言葉を根拠として保護されたが、警察官職務執行法第3条が定める「急迫の危険」には該当しない内容であり、保護の要件を満たしていないにもかかわらず、保護の理由とされた。
動画化:保護の理由は?
考察:保護の理由は?
東松山警察署の刑事課に所属する刑事によって保護された直後、同席していた生活安全課のK氏に対して「この保護とは何なのか」「なぜ自分が保護されたのか」と尋ねたが、K氏はすぐに答えることができず、説明も曖昧だった。しばらくして口にした理由は「自傷他害の話をしているから」というものであった。
しかし、そもそも自分はひき逃げ事件の被害者として警察署に同行していた。事情聴取の場では、会話の流れを操作するような誘導的な質問が繰り返され、被害者であったはずの立場が次第に加害者のような扱いへと変化していった。事件の発端や経緯、これまでのやりとりなどは一切考慮されず、表面的な言葉だけを根拠として処理が進められた。そして、聴取の途中で発したいくつかの発言を理由に、「警察官職務執行法第3条に基づく保護が必要だ」とされ、強制的に保護という形を取られたが、当該法条の適用要件である「急迫の危険」には全く該当していなかった。それにもかかわらず、形式的な理由付けによって保護が正当化されたのである。
関係する法令
- 警察官職務執行法 第3条
- 警察官職務執行法 第1条
- 行政手続法 第8条
警察官職務執行法 第3条
警察官は、精神錯乱その他の理由により自己又は他人に害を及ぼすおそれがある者を発見したときは、その者に対し必要な保護を行うことができる。
警察官職務執行法 第1条
この法律は、警察官がその職務を執行するに当たって必要な事項を定めることにより、その職務の適正な運用を図り、もって公共の安全と秩序の維持に資することを目的とする。
行政手続法 第8条
行政庁は、申請に対する処分又は不利益処分をする場合には、当該処分の理由を示さなければならない。
専門家としての視点
-
- 警察官が保護理由を即答できない状況が示す職権濫用の構造
- 警察官職務執行法第3条の適用条件とその逸脱の実態
- 形式的正当化による不当な保護と行政手続法違反
警察官が保護理由を即答できない状況が示す職権濫用の構造
保護を受けた直後に生活安全課のK氏に対して「なぜ自分は保護されたのか」と問うたところ、K氏が即答できなかったという事実は、警察官が職務執行において必要な根拠と判断の過程を持たず、最初から「保護する」という結論だけを目的化していたことを示す明確な証拠である。警察官職務執行法第3条では「警察官は、精神錯乱その他の理由により自己又は他人に害を及ぼすおそれがある者を発見したときは、その者に対し必要な保護を行うことができる」と定めているが、「害を及ぼすおそれがあるかどうか」はあくまで具体的かつ客観的な危険を伴う状況において判断されるべきである。K氏が即座に明確な説明をできなかったという事実は、その判断がなされていなかった、あるいは存在しなかったことを示しており、実際には条文の条件を満たさないにもかかわらず保護を強行したという構図を浮かび上がらせる。これは警察官職務執行法第1条に定める「職務の適正な運用を図る」目的に反する行為であり、明確な根拠と要件を欠いたまま警察権限を行使したことになる。また、行政手続法第8条では「不利益処分を行う場合にはその理由を示さなければならない」とされており、警察による保護は実質的な身体拘束に該当する以上、当該手続に関して理由を即座に明示できなければならないにもかかわらず、これがなされなかったという点でも手続法上の重大な違反が認められる。結局のところ、K氏の即答不能はその場における判断の空白ではなく、そもそも「理由なき保護」という違法な職権濫用が事前に決定されていたことの反映であり、形式的正当性の仮面をかぶった実質的不当処分であったといえる。
警察官職務執行法第3条の適用条件とその逸脱の実態
警察官職務執行法第3条の条文においては「精神錯乱その他の理由により自己又は他人に害を及ぼすおそれがある者」に限定して保護の権限が認められているため、その適用には常に明確かつ具体的な根拠が要求されるにもかかわらず、本件においては、被保護者本人からの質問に対して生活安全課のK氏が即答できなかったという重大な手続上の欠落が存在する。このことはすなわち、現場での判断として「害を及ぼすおそれがある」という認定が具体的な観察や根拠にもとづいてなされたわけではなく、あらかじめ保護するという方向性が先に決定されており、そこに後から理由を当てはめた結果である可能性が極めて高いことを意味している。このような運用は、本来個別具体的に判断されるべき要件の検討を経ずに権限行使が行われたことを示しており、同法の趣旨を逸脱している。また「おそれがある」という文言が広義であることを逆手に取って、実質的に急迫性や明確な危険性が存在しない場合であっても、警察側が保護を行うための建前を後付けで作るという実務運用が常態化しているとすれば、それは警察権限の濫用に他ならない。警察官職務執行法は、その条文上も運用上も、あくまで「必要な保護」に限定されており、その必要性の判断は合理的かつ客観的に説明可能であることが不可欠であるにもかかわらず、即答できないという事実は、適用判断がなされていなかったか、もしくは判断自体をしていなかったことの証左であり、条文の運用基準が著しく逸脱していた証拠である。
形式的正当化による不当な保護と行政手続法違反
警察官が職務執行の中で行う「保護」は、形式上は警察官職務執行法第3条に基づく正当な措置として装われているが、実際には事実上の拘束処分である以上、その運用には厳密な根拠と理由の明示が不可欠である。行政手続法第8条は「行政庁は、不利益処分をする場合には、処分の理由を示さなければならない」と定めており、これは警察による保護行為に対しても当然に適用される。今回の事案では、保護された本人から「なぜ保護されたのか」という明確な質問がなされたにもかかわらず、現場にいた生活安全課のK氏が即答することができなかったという事実が明らかになっており、これはすなわち、保護という重大な処分が実行された時点で、法的根拠と理由が整っていなかったことを意味する。つまり、この保護は理由が存在しなかったか、あったとしても不明確かつ不適切なものであり、適法な行政行為とは言えない。また、警察官職務執行法第1条が定める「職務の適正な運用」の理念にも反しており、手続面と実体面の双方で法令違反が認められる状態である。このように、警察が理由のない保護をあらかじめ決定し、その後に形式的な理由づけを行うという手法は、法治行政の原則に反し、国民の権利を不当に侵害するものであり、制度全体の信用性を損なう結果を招くものである。
専門家としての視点、社会問題として
- 「保護ありき」の警察運用がもたらす信頼喪失と市民の萎縮
- 説明責任を果たせない警察組織とその構造的背景
- 理由の後付けによる処分の横行と法治主義の形骸化
「保護ありき」の警察運用がもたらす信頼喪失と市民の萎縮
今回の事例は、警察官が保護措置を執行する際に必要な理由や状況確認を経ることなく、最初から「保護する」という結論だけを前提として動いていたことが明確に示されており、その場で本人から「なぜ保護されたのか」と問われたにもかかわらず、即答できずに後から理由をでっち上げたという対応は、単なる手続き上の不備ではなく、制度の根幹を揺るがす重大な社会問題である。警察官職務執行法第3条は、明確に「精神錯乱その他の理由により自己又は他人に害を及ぼすおそれがある者」に限定して保護を認めており、これは警察が個人の自由を一時的に制限する強い権限であることから、適用には厳格な基準と客観的判断が求められるにもかかわらず、実際にはその判断を伴わず、形式的に保護を進めるケースが少なくない。こうした「保護ありき」の対応が横行すると、警察による任意聴取や対応の場面が、すでに結果を決めたうえで進められる恣意的な場と化し、市民は警察に対して合理的な対応を期待できなくなり、結果的に不信感と萎縮を生む。これは単なる現場レベルの対応ミスではなく、制度的な運用の中で警察権が無自覚に拡張されていることの表れであり、特に精神的・感情的に揺れている状態を示す発言がすぐに「自傷他害の恐れ」として処理される傾向がある中で、弱い立場の人間ほど警察による恣意的な保護の対象とされやすくなる構造が存在する。こうした構造の放置は、表現の自由や人格権を制約する重大な結果を生み、社会全体として警察との対話や協力が困難となる恐れがあるため、制度の透明性と説明責任の確立が不可欠である。
説明責任を果たせない警察組織とその構造的背景
警察官が保護という重大な措置を執行したにもかかわらず、その理由を即答できないという状況は、組織として説明責任を軽視する体質が根付いていることを示しており、これは単なる個人の対応力の問題ではなく、制度的に説明を後回しにする文化が存在していることの証左である。行政手続法第8条は「不利益処分を行う場合にはその理由を示さなければならない」と明記しており、警察による保護措置も実質的な身体拘束である以上、この説明責任は免れることができないにもかかわらず、現場でのやりとりにおいては曖昧な対応が常態化しており、形式的な言い訳で片付ける傾向が強い。今回のように、K氏が明確な根拠や判断の説明を即座に示すことができず、後になって「自傷他害の話をしていた」と抽象的な理由を述べた事例では、実際の判断プロセスが存在しなかったか、極めて曖昧だったことが疑われ、警察内部において手続の正当性や法的要件を検証する仕組みが機能していないことが明らかである。こうした運用がまかり通ると、警察組織全体が外部に対して説明責任を果たさない体制となり、市民に対する信頼は失われるばかりか、不当な処分が繰り返される温床ともなる。本来、警察権は強大であるからこそ、その行使に際しては厳格な法令遵守と説明責任が不可欠であるにもかかわらず、理由の即答ができないという単純な事実が、組織的な無責任構造を露呈させており、この体質が是正されない限り、今後も同様の不当な保護や処分が繰り返される危険性がある。
理由の後付けによる処分の横行と法治主義の形骸化
警察による保護措置が、実際には事前に理由や判断が存在しないまま行われ、処分が下された後に形式的な理由が後付けされるという運用が常態化すれば、それは法治主義の根幹を揺るがす重大な社会問題である。今回の事例においても、K氏が保護の直後に本人からの質問に答えられず、のちに「自傷他害の話をしていた」と説明したことは、まさに処分理由を後から当てはめる典型であり、これは警察官職務執行法第3条が要求する「害を及ぼすおそれ」に基づいた判断を欠いた対応であるばかりか、行政手続法第8条に反している。理由の後付けは、法の名を借りた実質的な違法行為であり、その都度都合の良い言葉を選んで法令に形式的に合わせるという方法が許されるようになれば、あらゆる処分が恣意的に行われうることになり、国家権力の乱用を誰も止められなくなる。特に警察の対応は市民の日常生活に直接的な影響を与えるため、その一つひとつの判断に厳密な検証と正当性が求められるが、理由のない処分が事後的に「整合性を持った説明」に書き換えられることで、外形的には合法に見えてしまう構造は極めて危険である。法治主義とは、恣意を排し、すべての権力行使に法的根拠と説明を要求する原理であるが、理由の後付けが常態化すればこの理念は形だけのものとなり、法に従って処分されるという保障は完全に空洞化する。このような運用を放置することは、市民の権利保護を危うくし、国家権力の暴走を助長する土壌を形成するため、緊急の是正が必要である。
まとめ
東松山警察署で行われた保護措置において、生活安全課の警察官K氏が保護の理由を問われた際に即座に明確な回答ができなかったという事実は、警察官職務執行法第3条の適用条件を満たしていない保護を無理やり正当化しようとした構図を浮き彫りにするものである。本来であれば「精神錯乱その他の理由により自己または他人に害を及ぼすおそれがある者」でなければ適用されない条文を、あとから「自傷他害の話をしているから」という理由で形式的に当てはめた対応は、明らかに理由の後付けであり、行政手続法第8条に定められた説明責任を果たしていない。また、警察官職務執行法第1条が求める職務の適正な運用からも逸脱しており、警察権限の濫用、そして手続きの正当性の欠如という重大な問題を含んでいる。本人が保護に疑問を持ちその理由を問うたにもかかわらず、その場で明確な説明ができなかったという事実そのものが、「はじめから保護ありき」で動いていたことの証拠であり、法の形式を借りた実質的な違法行為と捉えざるを得ない。