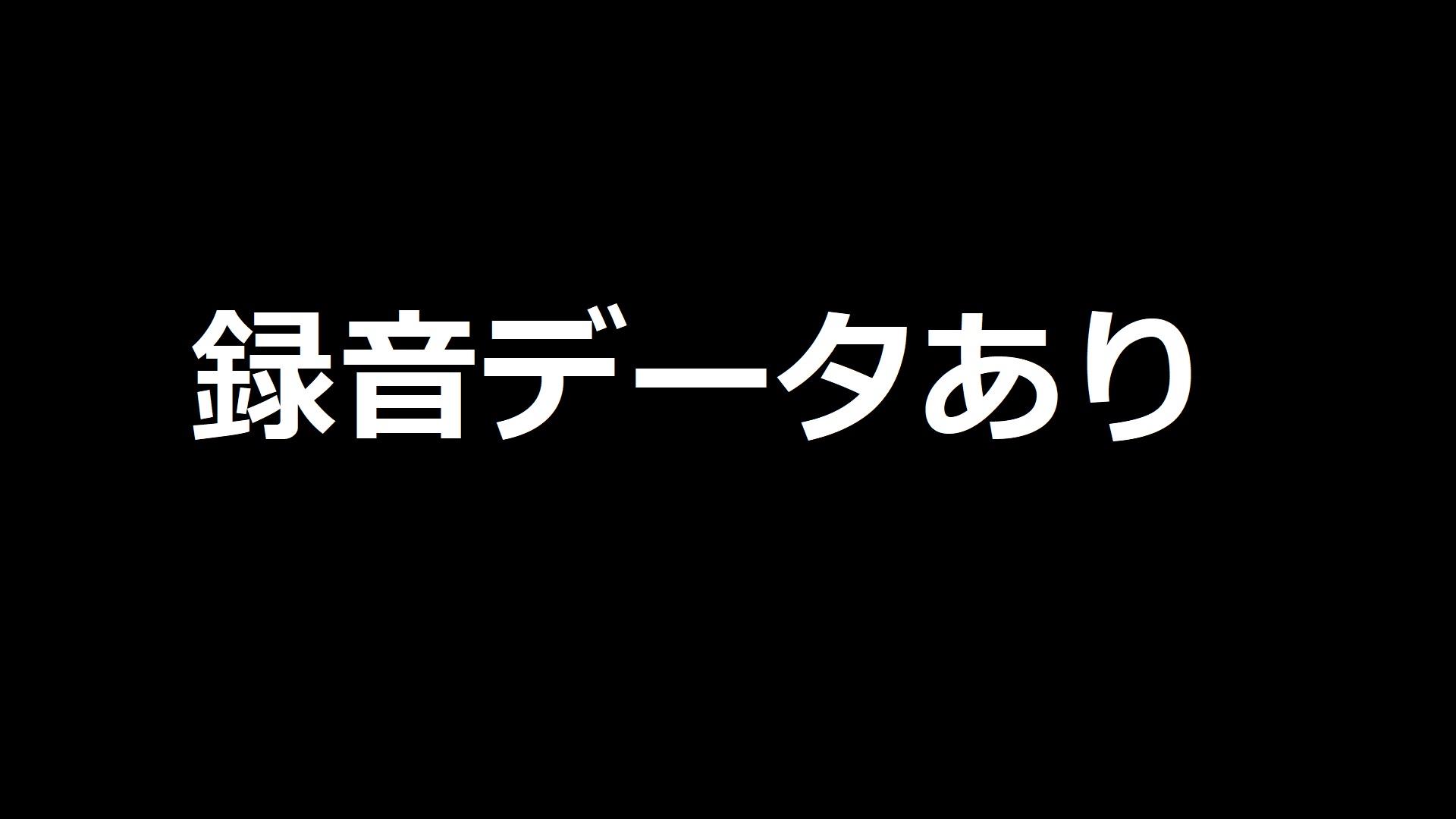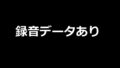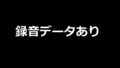警察が保護措置を適用する際、本来の目的である応急救護の枠を超え、個人の自由を不当に制限するケースが指摘されている。特に、被害者が事情聴取として警察署に呼ばれたにもかかわらず、実際には保護目的であった場合、警察官職務執行法第3条や刑事訴訟法第198条との整合性が問われる。さらに、警察官が職務権限を利用し、被害者に対して威圧的な対応を行った場合、強要罪や特別公務員暴行陵虐罪が成立する可能性がある。本記事では、警察の保護措置がどこまで正当性を持つのか、法的な観点から詳細に検討していく。
事件現場から東松山警察署へ パトカーにて
-
- これまでは
- 動画化:事件現場から東松山警察署へ パトカーにて
- 考察:事件現場から東松山警察署へ パトカーにて
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘禁され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
動画化:事件現場から東松山警察署へ パトカーにて
考察:事件現場から東松山警察署へ パトカーにて
4年間に及ぶ鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による嫌がらせは、ついにひき逃げ事件へと発展した。被害者は110番と119番に通報し、東松山警察による実況見分が行われた。その後、パトカーで東松山警察署に連れて行かれることになった。これまでの鳩山町役場長寿福祉課や西入間警察署との経緯を踏まえ、被害者はパトカーの中でスマホの録音を開始していた。この後、警察署での事情聴取が行われ、その後謎の警察による保護を受けることになった。被害者は18時間にわたって拘禁され、翌日、措置入院の判断を目的とした診察が2つの病院で行われ、精神病院に入院させられそうになったが、最終的に解放された。
関係する法令
-
- 警察官職務執行法
- 刑事訴訟法
- 犯人捜査規範
- 刑法
警察官職務執行法
第3条(保護)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱または泥酔のため、自己または他人の生命、身体または財産に危害を及ぼすおそれのある者
二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者(本人がこれを拒んだ場合を除く。)
刑事訴訟法
第198条(取調べ)
検察官、検察事務官又は司法警察員は、被疑者を取り調べることができる。
犯人捜査規範
第1条(目的)
この訓令は、刑事訴訟法その他の法令に従い、捜査の適正を確保し、もって人権の保障と社会公共の秩序維持との調和を図ることを目的とする。
警察官職務執行法
第2条(質問)
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯人を犯し、または犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、もしくは既に行われた犯人について、その事情を知っていると認められる者を停止させて質問することができる。
刑法
第223条(強要罪)
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して、人に義務のないことを行わせた者は3年以下の懲役に処する。
刑法
第195条(特別公務員暴行陵虐罪)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、その職務を行うに当たり、被拘禁者又はその他の者に対し、暴行を加え、若しくは陵虐したときは、7年以下の懲役に処する。
専門家としての視点
- 警察の保護措置とその適用の問題点
- 警察による「任意同行」と人権侵害の境界線
- 公務員の権限濫用と法的責任
警察の保護措置とその適用の問題点
警察官職務執行法第3条では、警察官は異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断し、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を保護しなければならないと規定されている。しかし、実際の運用では「保護」の名目で正当な理由なく個人の自由を制限するケースが散見される。刑事訴訟法第198条では、検察官、検察事務官または司法警察員が被疑者を取り調べることができるが、被疑者と認定されていない者に対する事情聴取はあくまで任意でなければならない。したがって、被害者が事情聴取の名目で警察署に連行されながら、実際には保護目的であった場合、任意性の担保がなされず、人身の自由を不当に制限された可能性がある。さらに、犯人捜査規範第1条では捜査の適正を確保し、人権の保障を図ることを目的としているため、警察の事前の計画に基づく待機や、保護を前提とした対応は適正な捜査といえない場合がある。これらの規定を踏まえ、警察の保護措置が適法に行われたかどうかは、実際の適用状況に照らして厳格に検証されるべきである。
警察による「任意同行」と人権侵害の境界線
警察官職務執行法第2条は、警察官が異常な挙動や犯人の疑いがある者を停止させて質問することを認めているが、これはあくまで任意のものであり、強制力を伴うものではない。しかし、警察が「任意」と称しながら実質的に強制的な同行を求めたり、保護という名目で人を拘禁した場合、人身の自由を不当に制限する行為となる。刑法第223条では、生命、身体、自由、名誉または財産に害を加える旨を告知して、人に義務のないことを行わせた者は強要罪に問われると規定されている。警察官が威圧的な言動や暗黙の圧力をかけて同行を求めた場合、法的には強要行為とみなされる可能性がある。また、犯人捜査規範第1条は捜査の適正を求めており、警察の対応が任意性を確保していなかった場合、規範の趣旨に反する。被害者が自発的に応じたのではなく、警察が実質的に従わざるを得ない状況を作り出していたならば、これらの法令に違反していた可能性が高い。
公務員の権限濫用と法的責任
公務員がその職権を濫用し、不当に個人の自由を制限した場合、刑法第195条(特別公務員暴行陵虐罪)が適用される。これは裁判官、検察官、警察官がその職務を行う際に被拘禁者またはその他の者に対して暴行や陵虐を加えた場合に適用され、7年以下の懲役が科される。K氏が警察官の立場を利用し、にこやかな雰囲気でありながら、事実上の脅しをかけたとするならば、職務権限を逸脱した行為と評価される可能性がある。警察法第2条では、警察の責務として公平・公正な職務遂行が求められており、特定の意図をもって特定の個人に圧力をかける行為は、この規定に違反する可能性がある。さらに、国家公務員法第99条では公務員の守秘義務が定められているが、警察官が職務上の情報を利用し、個人的な目的で威圧的な連絡をした場合、公務員としての職務を逸脱したものと判断される可能性がある。公務員の権限濫用は個人の基本的人権に関わる問題であり、その責任を問われるべきである。
専門家としての視点、社会問題として
-
- 警察による「保護」の濫用と人権問題
- 任意同行の強制性と司法の透明性
- 公務員による権限濫用の社会的影響
警察による「保護」の濫用と人権問題
警察官職務執行法第3条は警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断し、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由がある者を保護することを認めているが、実際にはこの規定を利用し強制的に身柄を確保する事例が発生している。特に、保護の対象者が自己の保護ができない者であることが要件であるにもかかわらず、判断が恣意的に行われることが問題視される。刑事訴訟法第198条では検察官、検察事務官、司法警察員が被疑者を取り調べることができると規定されているが、事情聴取目的で呼び出しながら実際には保護が目的であった場合、説明と実際の対応が異なり、個人の人権を不当に制限する結果となる。犯人捜査規範第1条は捜査の適正を確保し人権の保障を図ることを目的としており、警察の対応がこの趣旨に沿わない場合には違法な職務執行となる可能性がある。特に保護を名目にした拘禁が犯人者としての扱いと実質的に変わらない状況を生み出していることが問題視されており、これが人権侵害に当たるとの指摘がある。
任意同行の強制性と司法の透明性
警察官職務執行法第2条では警察官が異常な挙動をしている、または犯人を犯し、もしくは犯そうとしていると疑われる者に対して停止させ質問することができるとされているが、実際にはこの権限が拡大解釈され任意同行が事実上の強制措置となっている場合がある。刑法第223条では生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して、人に義務のないことを行わせた者は強要罪に問われると規定されているが、警察官が「任意」と称しながら拒否が事実上不可能な状況を作り出した場合、強要に当たる可能性がある。犯人捜査規範第1条では捜査の適正が求められており、被害者が自発的に応じたわけではなく、警察の事前計画に基づき保護が前提とされていた場合、適正な職務執行とは言えない。任意同行と称しながら実態は強制的な拘禁であった場合、司法手続きの透明性が損なわれ、国民の信頼を著しく低下させる要因となる。
公務員による権限濫用の社会的影響
公務員がその権限を濫用し、国民の自由を制限した場合、刑法第195条(特別公務員暴行陵虐罪)が適用される。この法律は裁判官、検察官、警察官がその職務を行う際に被拘禁者またはその他の者に対して暴行や陵虐を加えた場合、7年以下の懲役を科すとしており、公務員の職権濫用に対して厳格な対応を求めている。警察法第2条では警察の職務は公平かつ公正に行われなければならないと定められており、職権を利用し市民に圧力をかける行為は警察法の趣旨に反する。また、国家公務員法第99条では公務員には職務上知り得た秘密を漏洩してはならないとされているが、K氏が警察官の立場を利用し被害者に対し警察の対応の正当性をアピールするような発言を行った場合、公務員の権限を濫用した可能性がある。公務員が職権を利用し市民に対して影響を与えようとする行為は、社会全体に不信感を与え、警察の公正性そのものを揺るがす要因となる。
まとめ
警察による保護措置が本来の目的を超えて運用されることで、個人の自由が不当に制限される問題がある。警察官職務執行法第3条は応急の救護を要する者を保護することを定めているが、実際には被害者として事情聴取に応じるつもりが、意図しない形で身柄を拘禁される事例が発生している。また、犯人捜査規範第1条は適正な捜査と人権保障を求めているが、警察が事前に計画的に保護を実施することで、本人の意思とは無関係に拘禁されることがある。警察官職務執行法第2条では異常な挙動がある場合に質問できるとされているが、犯人者ではない人物に対し、待ち伏せのような形で保護を前提に行動した場合、その適法性が問われる。さらに、警察官が職務の範囲を超えて威圧的な連絡を取る行為は、刑法第223条の強要罪に該当する可能性があり、特別公務員暴行陵虐罪の適用が検討されるべき事例も存在する。これらの問題を踏まえ、警察の職務執行には明確な基準が求められ、権限の濫用を防ぐための監視体制を強化する必要がある。