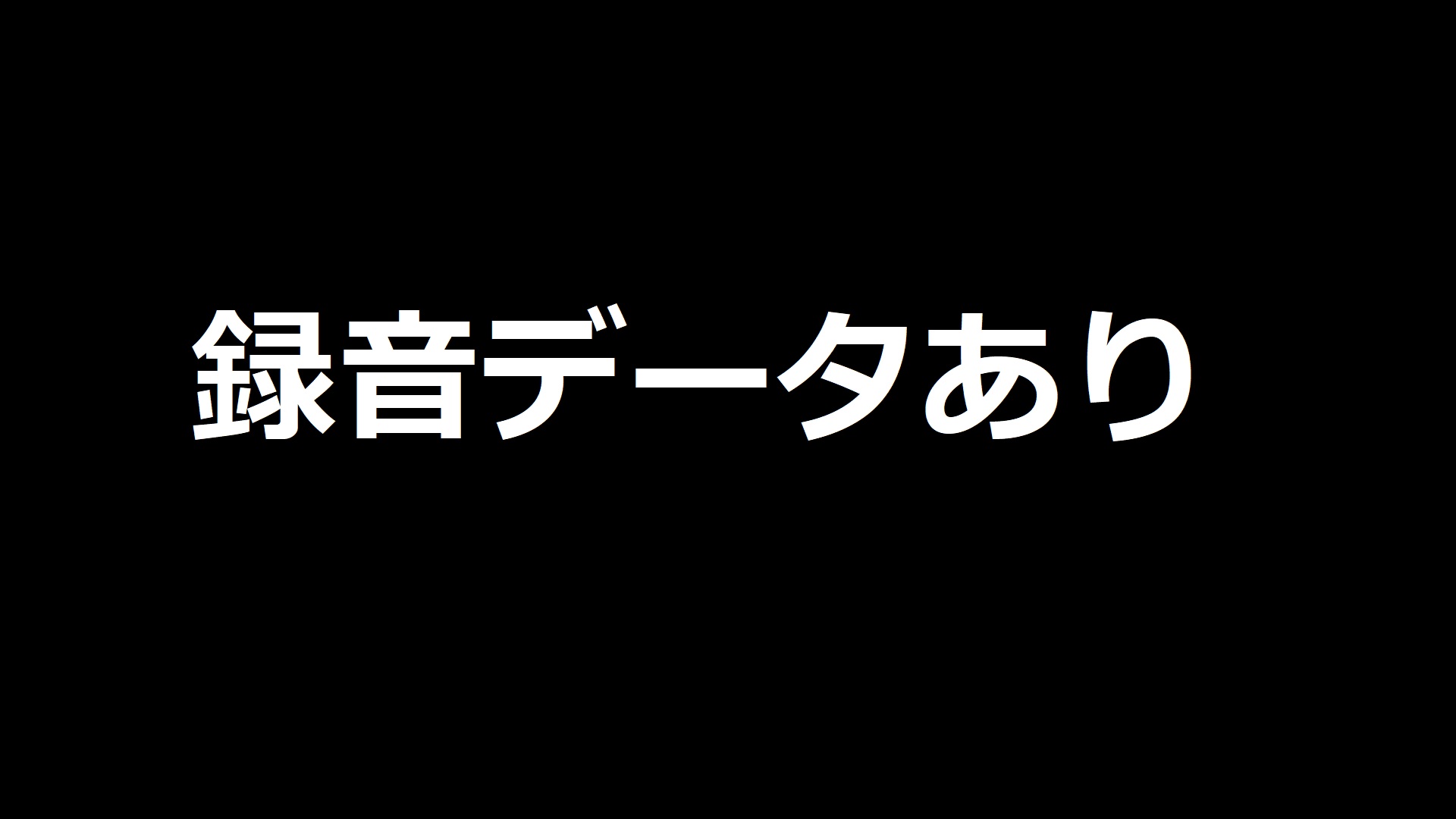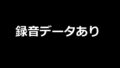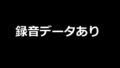警察署の事情聴取における誘導尋問や構図操作の問題は、司法制度の公平性と市民の信頼に直結する重大な社会問題である。ひき逃げ事件の現場で、被害者が加害者として扱われる事例が明るみに出たことで、取調べの任意性や中立性が否定される懸念が高まっている。刑事訴訟法第319条第1項や国家公務員法第99条、地方公務員法第33条に基づき、公務員としての中立性と誠実性が求められる一方で、実際には取調官が職権を濫用し、事実の捻じ曲げを試みるケースが報告されている。これにより、刑法第194条、刑法第156条、さらには刑法第195条や第172条に抵触する可能性が指摘される。今回の検証では、警察の事情聴取における構図操作が、いかにして制度全体の信頼を損ない、市民の権利侵害につながるかを明らかにし、透明性の向上と制度改革の必要性について詳しく論じる。
ひき逃げ犯は被害者?
- これまでは
- 動画化:ひき逃げ犯は被害者?
- 考察:事件は”まっさら”に起こる
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による嫌がらせが4年間続いた末、事件が発生した。ひき逃げ事件の被害者として東松山警察署へ向かうパトカーの中で、スマートフォンによる録音を開始。事情聴取の最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者は18時間にわたって拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたが、精神科病院への入院とはならず、最終的に解放された。
その東松山警察署での事情聴取中、刑事課のI刑事は、ひき逃げ事件の被害者を加害者に、加害者を被害者にすり替えようとする誘導尋問を行った。おそらく、犯人は警察OBなのだろう。I刑事は話を無理にすり替えようとする過程で、思わず本音を口にしてしまう。加害者を「被害(者)」と、うっかり言い間違えてしまったのである。
動画化:ひき逃げ犯は被害者?
考察:ひき逃げ犯は被害者?
2023年2月9日。鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして加害者とされる人物による、4年にわたる嫌がらせの末に、ひき逃げ事件が発生した。この日、被害者は東松山警察署に向かうパトカーの中でスマートフォンの録音を開始する。それは、自身の身にこれから起こることを記録しておくべきだという、直感に近い判断だったのかもしれない。
事情聴取が始まって間もなく、被害者は自ら望んでいない「保護」の対象とされ、不自然な形で警察の介入を受けることになる。その結果、18時間にも及ぶ拘束を受け、翌日には措置入院の可否を判断するため、2つの病院での診察を経るが、精神科への入院措置はとられず、解放される。この一連の流れは、事前に何かしらの計画がなければ成立し得ないようにも見える。
とりわけ異様だったのは、東松山警察署での事情聴取における刑事課のI刑事の対応である。I刑事は、ひき逃げの被害者をまるで加害者であるかのように扱い、反対に加害者を被害者として扱おうとする。尋問の内容には、明らかな誘導が含まれていた。事実の逆転を図ろうとするI刑事の姿勢は、単なる誤解や誤認では説明できない。そこには明確な意図があり、その背後には“加害者を守らねばならない理由”が存在するように思える。
I刑事は、取り調べのなかで不用意に口を滑らせる。加害者のことを「被害(者)」と、明確に言い間違えたのだ。これは、口調のミスというよりも、意識の奥に潜む本音が一瞬、言葉として現れてしまったのかもしれない。加害者を守ろうとする強い意志、そして被害者を貶めようとする構図。その背景には、加害者が警察関係者、あるいはOBであるという仮説が浮かび上がる。関係機関とのつながりが事件の構図を歪めた可能性は、無視できない。
関係する法令
- 刑事訴訟法 第319条第1項
- 国家公務員法 第99条
- 地方公務員法 第33条
- 刑法 第194条(特別公務員職権濫用罪)
- 刑法 第156条(虚偽公文書作成罪)
- 刑法 第195条(特別公務員暴行陵虐罪)
- 刑法 第172条(虚偽告訴等)
刑事訴訟法 第319条第1項
被告人の自白が、任意にされたものでないときは、これを証拠とすることができない。
国家公務員法 第99条
職員は、その信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
地方公務員法 第33条
職員は、勤務時間及び職務上の注意義務を遵守し、その職務を誠実に遂行しなければならない。
刑法 第194条(特別公務員職権濫用罪)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法 第156条(虚偽公文書作成罪)
公務員がその職務に関して虚偽の文書又は図面を作成し、又は虚偽の内容の文書若しくは図面を保存したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
刑法 第195条(特別公務員暴行陵虐罪)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、その職務を行うに当たり、逮捕若しくは拘禁されている者又はその他その監護に係る者に対して、暴行又は陵虐の行為をしたときは、7年以下の懲役に処する。
刑法 第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の事実を申し出、又は告訴し、若しくは告発した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
専門家としての視点
- 取調べにおける任意性の確保と誘導尋問の境界
- 公務員の中立性義務と構図操作の違法性
- 精神的陵虐と取調べ方法の限界
取調べにおける任意性の確保と誘導尋問の境界
刑事訴訟法第319条第1項は「被告人の自白が、任意にされたものでないときは、これを証拠とすることができない」と明記しており、取調べにおける供述が強制や誘導の結果であれば証拠能力を失うことになる。この原則は被疑者に限らず、参考人や通報者に対しても実質的に類似の配慮が求められるべきであり、捜査機関が自らの都合に沿うような事実の組み換えを意図して尋問を行った場合、その手続き自体が違法と評価される余地がある。たとえば警察官がひき逃げ事件において、本来の被害者に対して加害者の立場を押しつけようとし、反対に加害者を被害者扱いするような誘導を行った場合、それは事実に反した構成を無理に認めさせる試みであり、任意性を根本から否定する行為といえる。またこのような事情聴取が録音・録画されておらず、可視化されていない状況であれば、被害者が後に抗議を行っても警察側にとって有利な供述内容のみが調書化されてしまう危険がある。したがって、取調べの任意性を制度的に保障するためには、単に暴力や脅迫がなかったという形式的判断に留まらず、取調官の言動の流れや意図、質問の文脈そのものを検証する必要がある。意図的な事実操作が取調べの中に含まれていた場合、それは単なる証拠排除の対象にとどまらず、刑法第194条に規定される特別公務員職権濫用罪や、刑法第156条の虚偽公文書作成罪の構成要件にも該当する可能性がある。特に取調べの結果として作成される供述調書が虚偽の内容に基づくものであれば、その文書の作成行為自体が刑罰の対象となる。よって、取調べの適正性を確保することは、単に手続の透明性という範囲を超え、刑事司法制度全体の信頼性に直結する問題である。
公務員の中立性義務と構図操作の違法性
警察官を含む公務員には、その立場において中立性と誠実性が法的に求められており、これは国家公務員法第99条にある「職員は、その信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」という規定に明示されている。また地方公務員であれば、地方公務員法第33条により「職員は、勤務時間及び職務上の注意義務を遵守し、その職務を誠実に遂行しなければならない」とされ、個人的な関係性や組織内の利害関係に基づいて職務を遂行してはならないことが定められている。ひき逃げ事件のような重大な案件において、警察官が事件の当事者に対し、意図的に立場を入れ替えるような構図で事情聴取を行ったとすれば、その行為は中立性義務に明確に反する。たとえば加害者が警察OBであるなどの事情がある場合、警察内部での「身内意識」や「忖度」によって事実の捻じ曲げが行われたならば、それは国家の法執行機関の根幹を揺るがす背信行為である。さらに、そのような操作の結果として、無関係な人物に刑事責任を転嫁するような内容で公文書が作成された場合、これは刑法第156条に規定される虚偽公文書作成罪が成立する可能性がある。また、構図のすり替えを通じて本来の被害者に違法な供述を強要した場合、刑法第194条の特別公務員職権濫用罪にも該当しうる。つまり、公務員が中立性を欠き、法的根拠のない事実操作を行うことは、職務上の倫理違反にとどまらず、刑事罰の対象となる違法行為である。
精神的陵虐と取調べ方法の限界
刑法第195条に定められた特別公務員暴行陵虐罪は、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、その職務を行うに当たり、逮捕若しくは拘禁されている者又はその他その監護に係る者に対して、暴行又は陵虐の行為をしたとき」に適用されるが、ここでの「陵虐」には身体的暴力だけでなく、精神的・言語的圧力を含む広い概念が含まれている。事情聴取の場面で、被害者が精神的に圧迫されるような誘導や攻撃的な言動を受けた場合、それが警察官の職務中の行為であれば本罪に問われる余地がある。特に、すでに被害者として扱われるべき立場にある者が、正当な理由なく加害者扱いされ、人格を否定されるような言動を受ければ、それは精神的陵虐として違法性が問われる。また、供述をねじ曲げられた結果として、虚偽の犯人事実を申告したことにされれば、刑法第172条の虚偽告訴等にもつながり得る。たとえば警察が、ある人物にひき逃げの加害者であるかのような自白を無理に引き出し、実際にはその人物が被害者だった場合、その供述内容をもとに他者が処罰を受ければ、誘導した警察官は刑法上の責任を負う可能性がある。取調べの限界とは、単に時間や手段に関する問題ではなく、精神的圧迫をどこまで許容できるかという「人権の境界線」に関わる問題である。したがって、精神的陵虐を排除するためには、制度的に可視化・録音が義務化されるべきであり、捜査機関の言動を法的に監視する機能が不可欠である。
専門家としての視点、社会問題として
- 取調べにおける構図操作がもたらす司法不信の拡大
- 公権力と身内意識が生む構造的加害
- 取調べの可視化と市民社会の監視機能の必要性
取調べにおける構図操作がもたらす司法不信の拡大
警察による事情聴取において被害者と加害者の立場が恣意的に転換される事例は、市民に対する法の公正性への信頼を根底から揺るがす重大な問題である。とりわけひき逃げ事件のように、物理的・精神的被害を受けた者が警察署に出向き、そこで自身が加害者のような扱いを受ける事態が発生すれば、市民は正当な保護を期待して通報や出頭するという行動自体をためらうようになる。これは結果的に犯人の潜在化や、真の被害者の孤立を招くこととなり、社会全体の治安維持にも悪影響を与える。警察組織がその捜査において加害者を庇う意図を持ち、事実認定を歪曲するような誘導尋問を行った場合、国家権力の濫用に他ならず、個人の尊厳と自由を脅かす不当な介入となる。特に背景に加害者が警察OBであるなどの事情が含まれる場合、組織内部の保身や隠蔽体質が捜査の公正性を著しく損なっていることを示しており、それが一部の問題ではなく構造的なものと認識され始めれば、社会全体に司法制度そのものへの不信が広がる。こうした信頼の崩壊は一朝一夕で修復できるものではなく、結果として冤罪や見逃された犯人の温床ともなり得る。さらに、供述のねつ造や事実のすり替えが調書や捜査資料として公文書化されていく過程では、虚偽公文書作成罪や特別公務員職権濫用罪といった刑事罰に該当する可能性もあるにもかかわらず、実際には内部で処理され表面化しないことが多く、これが警察への過剰な裁量と監視不足を浮き彫りにする。市民が警察を恐れ、捜査を信頼できなくなる社会は、法治国家としての機能を著しく低下させるため、構図操作のような行為は単なる一警察官の逸脱行為として片づけてはならず、制度的監視と組織的透明性の欠如が生み出す重大な社会問題と位置づけられるべきである。
公権力と身内意識が生む構造的加害
警察という組織が本来果たすべき役割は、被害者の保護と事実の究明であるが、現実には加害者が警察関係者やその周辺にいる場合、身内意識が働き、事実の認定に偏りが生まれることがある。こうした構造的な身内意識は、被害者の立場を無視し、加害者に有利な事情聴取や処理が行われる原因となり、結果として被害者が二重の被害を受ける構図を生み出す。これが発生する背景には、警察という組織における上下関係や内部統制の強さ、ならびに外部からの監視が機能していない現状がある。ひき逃げ事件で本来の被害者が加害者として扱われるような事態が発生するのは、個別の刑事の判断ミスではなく、組織全体が持つ暗黙の同調圧力や、警察内部での利害調整の結果である可能性が高い。これは、いわば構造的な加害行為であり、個人の責任だけに還元することはできない。たとえば刑法第194条の特別公務員職権濫用罪は、職権を濫用して人に義務のないことを行わせた場合に適用されるが、実際にこの罪が適用される事例は極めて稀であり、警察官に対する刑事的責任追及が困難な制度的構造もまた、問題の根深さを物語っている。さらに、こうした構図が容認されている限り、被害者が声を上げても「被害申告をすることでさらに立場が悪くなる」という自己検閲が働き、正当な救済すら受けにくくなる。したがって、公権力に対する独立した外部の監視機構が不可欠であり、内部の処分や隠蔽体質に依存する運用では、市民の安全も人権も保障されない状態が恒常化するおそれがある。
取調べの可視化と市民社会の監視機能の必要性
取調べの可視化は、警察による事情聴取の透明性を確保し、違法捜査や供述の誘導を未然に防止するうえで不可欠である。近年、日本においても一部の重大事件に限り取調べの録音・録画(可視化)が導入されているが、制度としては限定的であり、対象事件も範囲も狭い。これでは、被害者が加害者として扱われるような構図のすり替えや、誘導尋問が行われた場合の証拠保全が十分に担保されない。特に、加害者が警察関係者などの公的立場にある場合、組織的な忖度や隠蔽が介在する余地があり、その中で可視化されていない取調べが行われた場合、外部からの検証が極めて困難になる。つまり、警察という強大な権限を有する組織の内部に対して、市民社会がチェックを及ぼす機構が欠けている現状が、構図操作や誘導を許容してしまっているといえる。さらに、取調べの過程で録音・録画がされていなければ、後日、当事者が虚偽の内容に異議を唱えても、その内容の真偽を検証する手段がないため、一方的に警察の記録が優位とされる構造が存在する。このような情報非対称の状態は、刑事手続における公平性を損ない、冤罪や不当な処分を生む温床となる。また、可視化とともに市民による外部監視委員会や第三者機関による取調べ立会制度の導入など、抜本的な制度改革が求められる。警察内部の自浄作用に依存するのではなく、社会全体が監視し是正する構造を持たなければ、取調べにおける不正は繰り返される。よって、取調べの可視化は単なる技術的手段ではなく、市民の権利と法の公正性を守るための社会制度そのものであり、警察行政における説明責任を果たさせる根幹となる。
まとめ
警察による事情聴取の過程で、被害者が加害者として扱われるような構図の転換が行われた場合、それは取調べの任意性を根底から否定するものであり、刑事訴訟法第319条に抵触する可能性がある。また、加害者を守る意図が背景にあるとすれば、国家公務員法第99条や刑法第194条などにも触れるおそれがある。こうした構造的な問題は一個人の逸脱行為ではなく、警察組織内部の身内意識や隠蔽体質、そして監視機能の不在によって引き起こされる社会的課題である。取調べの可視化と外部による独立監視の必要性は急務であり、制度の見直しと透明性の確保がなされなければ、被害者の人権は今後も容易に踏みにじられることになる。市民の信頼を回復するためには、警察という権限機関が自らを律し、常に法のもとで中立かつ誠実に行動する姿勢が求められている。