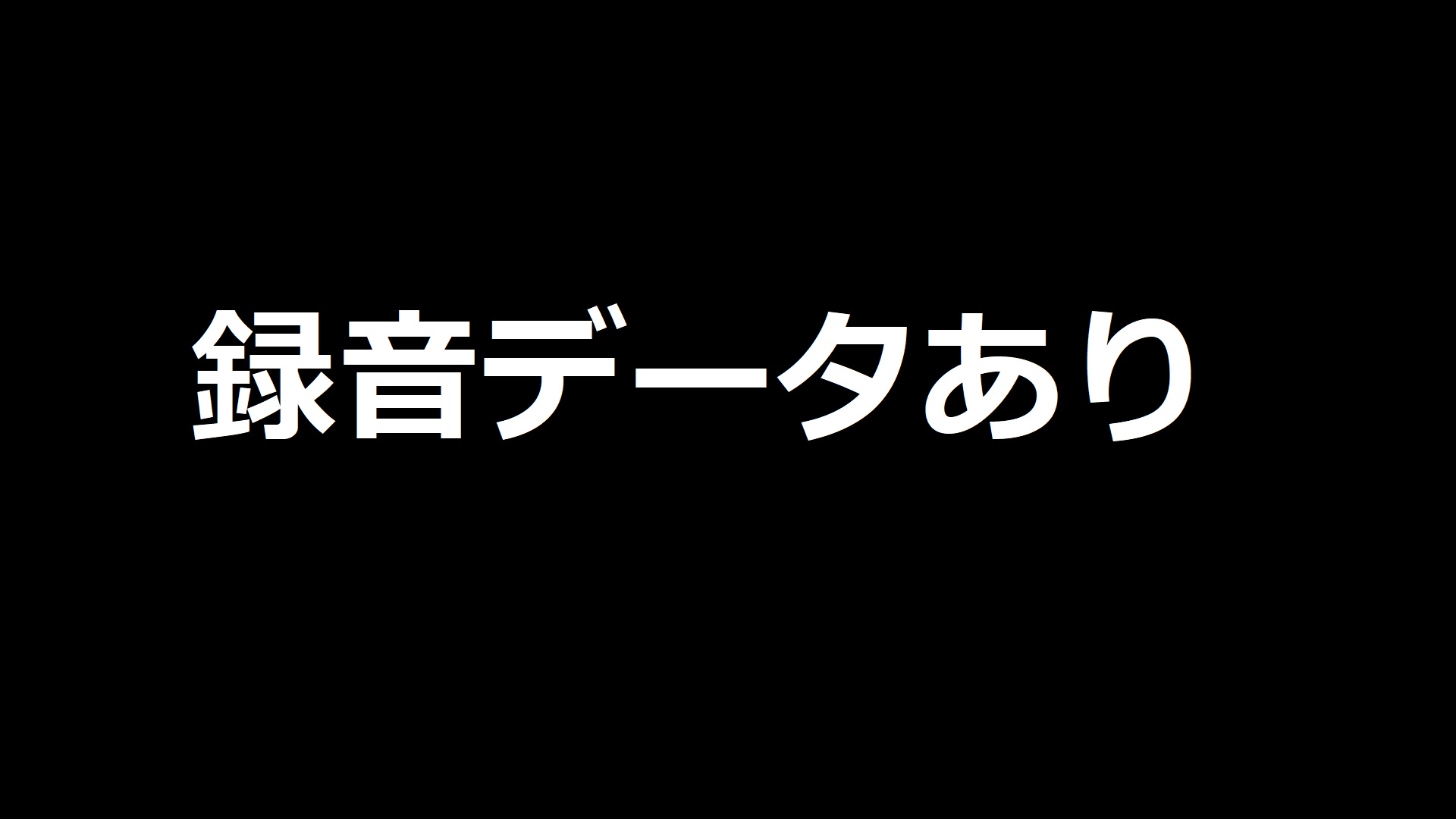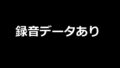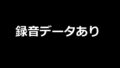警察の捜査は公正であるべきだが、現実には権力の濫用や不適切な対応が問題となるケースがある。特に、被害者の証言が軽視され、加害者が保護されるような状況では、法の公正性が損なわれる。本記事では、東松山警察署における被害者対応を事例として、刑法第195条や犯人捜査規範第61条、国家公務員倫理法の視点から問題点を分析し、警察権力の適正な運用の必要性について考察する。
警察は被害者とケンカする
- これまでは
- 動画化:警察は被害者とケンカする
- 考察:警察は被害者とケンカする
これまでは
2023年2月9日。
4年間にわたり、鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人からの嫌がらせが続いた末に事件が発生した。ひき逃げ事件の被害者として東松山警察署へ向かうパトカーの中で、スマートフォンの録音を開始。事情聴取の最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者は18時間にわたり拘禁され、翌日、措置入院の判断を目的に2つの病院で診察を受けたが、精神病院への入院には至らず解放された。
保護直後、被害者が2階の保護室に向かう中、録音中のスマホは聴取室に残る。そこで被害者を嘲笑する。さらにI刑事は「だいぶケンカしたんだけど」と笑いながら言っている。
そもそも、刑事がひき逃げ事件の事情聴取中に被害者とケンカをするというのは通常考えられないことだ。しかし、録音データを振り返ると、それに相当するやりとりが確認された。
事件の経緯やきっかけを詳細に説明する被害者に対し、I刑事は「まっさらに」事件をその日、その時だけで考えろと求めた。つまり、事件の経緯やきっかけが明確になると、犯人による嫌がらせが原因でトラブルが発生し、最終的に犯人がひき逃げ事件を起こしたという構図が浮かび上がる。その結果、犯人がほぼ一方的に悪いことが明白になってしまう。
I刑事は、おそらく警察OBである犯人を庇う意図があったのだろう。そのため、事件の経緯やきっかけ、つまり嫌がらせの事実を無視し、「まっさらに」その日、その時の出来事だけで判断しようとしたということだ。
I刑事の話の建付けはこうだ。高齢者が車を駐車していたところ、知らない人物が突然現れ、運転席の窓に手を入れた。つまり、犯人が被害者に絡まれたという状況になる。そのような行為をされたら「普通、逃げる」。だからひき逃げにもなるが、正当防衛に当たり、被害者が一方的に悪いということだ。
被害者が訴える警察および犯人の嫌がらせについて、I刑事は「被害者の思い込み」だと断定した。一応体裁上、「加害者にしたいのではない」と否定しつつ、実際には加害者を被害者に、被害者を加害者に転換するよう誘導尋問を行っている。
事件に至るまでの嫌がらせ被害に対する110番通報と西入間警察署の対応についても、I刑事は「ここは東松山警察署だからわからない」という論理を展開しつつ、西入間警察署の対応を擁護するという矛盾した話をしている。
最終的に、被害者がI刑事の話の矛盾点や、西入間警察署および犯人の行動の矛盾を指摘すると、I刑事は反論できなくなる。
これを「ケンカした」と表現するなら、「ケンカはしたが論破された」が正しい表現なのではないだろうか。
動画化:警察は被害者とケンカする
考察:警察は被害者とケンカする
I刑事の対応は不可解だ。保護直後、被害者が2階の保護室へ向かう間、録音中のスマホは聴取室に残された。その場で刑事たちは被害者を嘲笑し、I刑事は「だいぶケンカしたんだけど」と笑いながら話している。
そもそも、刑事がひき逃げ事件の事情聴取中に被害者と「ケンカをする」など通常では考えられない。しかし、録音データを振り返ると、そう捉えられるやりとりが確認された。
事件の経緯やきっかけを説明する被害者に対し、I刑事は「まっさらに」事件をその日、その時だけで考えろと求めた。だが、経緯が明確になれば、犯人が嫌がらせを繰り返し、それが原因でトラブルが発生し、最終的にひき逃げに至ったことが明白になる。つまり、犯人がほぼ一方的に悪いという結論になる。I刑事は、警察OBである犯人を庇う意図があったのではないか。だからこそ、嫌がらせの事実を無視し、事件の経緯ではなく「その瞬間」だけを切り取って判断しようとしたのだ。
I刑事の主張はこうだ。「高齢者が駐車中、突然知らない人物が現れ、運転席の窓に手を入れた。つまり、犯人が被害者に絡まれたという状況になる。そんなことをされたら普通は逃げる」。だから、ひき逃げではあるが、正当防衛に当たり、被害者が一方的に悪いという理屈だ。
また、被害者が訴える警察や犯人による嫌がらせについても、I刑事は「被害者の思い込み」だと断定した。一応、「加害者にしたいわけではない」と否定しつつ、実際には加害者を被害者に、被害者を加害者に仕立て上げるように誘導尋問を行っている。
さらに、事件に至るまでの嫌がらせ被害に対する110番通報や西入間警察署の対応についても、「ここは東松山警察署だからわからない」と言いつつ、西入間警察署の対応を擁護するという矛盾した主張を展開している。
最終的に、被害者がI刑事の話の矛盾点や、西入間警察署および犯人の行動の矛盾を指摘すると、I刑事は反論できなくなる。
これを「ケンカした」と表現するなら、「ケンカはしたが論破された」というのが正確ではないだろうか。
関係する法令
- 刑法第195条(特別公務員暴行陵虐罪)
- 犯人捜査規範第61条(被害の届出の受理)
- 国家公務員倫理法
刑法第195条(特別公務員暴行陵虐罪)
公務員がその職務を行うに当たり、被疑者などに暴行・凌辱・加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役または禁錮に処する。
犯人捜査規範第61条(被害の届出の受理)
被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
国家公務員倫理法
国家公務員が職務を行うに当たり、倫理原則を遵守し、職務の公正性と国民の信頼を確保することを目的とする。
専門家としての視点
- 公務員の職務濫用と刑法195条の適用
- 犯人捜査規範61条と警察の義務違反
- 国家公務員倫理法と警察官の行動規範
公務員の職務濫用と刑法195条の適用
公務員がその職務を行うに当たり、権限を濫用し被害者に不当な対応を取ることは、刑法195条に抵触する可能性がある。刑法195条では、公務員が被疑者などに対し暴行・凌辱・加虐の行為をした場合、7年以下の懲役または禁錮に処すると定められている。I刑事が被害者の事情聴取中に嘲笑し、正当な訴えを無視して誘導尋問を行い、被害者を加害者として扱おうとした行為は、特別公務員暴行陵虐罪に該当する可能性がある。また、被害者がI刑事の矛盾を指摘し、論破した際に反論できなくなったことからも、警察が一方的な立場を強要し、被害者の権利を侵害していた疑いがある。さらに、加害者の背景が警察OBである可能性を考慮すると、I刑事が公正な捜査を行っていないことが明白であり、これも刑法195条の適用対象となる可能性がある。
犯人捜査規範61条と警察の義務違反
犯人捜査規範第61条は、被害の届出をする者があった場合、事件が管轄区域のものであるかを問わず、警察がこれを受理しなければならないと定めている。しかし、I刑事は「ここは東松山警察署だから西入間警察署の対応はわからない」と述べ、被害者の通報内容を軽視した。この発言は犯人捜査規範61条に明確に反しており、適正な捜査義務を怠っていることになる。また、被害者が事件の経緯や加害者の嫌がらせを説明したにもかかわらず、I刑事が「まっさらにその日その時だけを考えろ」と要求したことも、事件の背景を適切に考慮せず、被害者の証言を軽視した対応である。警察の捜査は公正であるべきであり、被害届の受理を拒否することや、不当に誘導尋問を行うことは、適正な捜査を妨げる行為である。I刑事の行動は、犯人捜査規範61条の義務違反にあたり、適正な捜査を行わなかった責任を問われる可能性がある。
国家公務員倫理法と警察官の行動規範
国家公務員倫理法は、公務員が職務を遂行する際に倫理原則を遵守し、公正な対応を行い、国民の信頼を損なわないよう求めている。しかし、I刑事は被害者の訴えを「思い込み」と断定し、加害者の立場を擁護するような誘導尋問を行った。これは、国家公務員倫理法の趣旨に明確に反している。また、「加害者にしたいわけではない」と一応体裁を整えつつ、実際には加害者と被害者の立場を入れ替えるような尋問を行っていたことからも、公正な職務遂行義務に違反していると考えられる。さらに、I刑事が警察OBである加害者を庇う目的で、事件の経緯を無視し、その場限りの判断を求めたことは、倫理原則の重大な違反である。警察官は公正な捜査を行い、被害者の立場を守る責務があるが、I刑事の行動はこれに反し、倫理法の観点からも問題がある。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察の職務濫用と人権侵害のリスク
- 犯人捜査における適正手続の形骸化
- 公務員倫理と警察組織の透明性の必要性
警察の職務濫用と人権侵害のリスク
警察官が職務権限を濫用し、不当な対応を取ることは、法治国家において深刻な人権侵害を引き起こす要因となる。刑法第195条では、公務員が被疑者などに対し暴行・凌辱・加虐の行為を行った場合に処罰されると規定されているが、現実にはその適用が限定的であり、警察内部での監督機能が機能していない場合、事実上の職務濫用が黙認される状況が生じる。今回の事例では、I刑事が被害者に対し嘲笑や誘導尋問を行い、正当な訴えを軽視する態度を取ったことが問題視される。さらに、警察OBである加害者を庇う形で公正な捜査を行わなかった点は、組織ぐるみの偏向対応の可能性を示唆しており、司法の公正性に対する重大な疑念を生じさせる。このような職務濫用が放置されると、警察の信頼性が損なわれ、被害者が正当な救済を受けられない構造が固定化される恐れがある。
犯人捜査における適正手続の形骸化
犯人捜査規範第61条では、警察は被害の届出を管轄に関係なく受理する義務を負うと定められている。しかし、I刑事は「ここは東松山警察署だからわからない」と発言し、被害者の訴えを事実上無視した。このような対応は、適正手続の原則が守られていない典型例であり、警察の裁量によって法の適用が恣意的に運用される危険性を示している。適正手続とは、すべての捜査が公平かつ透明性をもって行われるための基本原則であり、警察の恣意的な判断によって証言の信用性が左右されることは許されない。しかし、実際には、被害者が不当な誘導尋問を受けたり、証言が無視されることで、適正手続の形骸化が進んでいる現状がある。今回のケースでは、I刑事が事件の経緯を軽視し、「まっさらに」その日だけで考えろと強要した点も、警察による証拠の恣意的な取捨選択の危険性を示しており、組織的な問題として検討すべきである。
公務員倫理と警察組織の透明性の必要性
国家公務員倫理法は、公務員が職務を遂行する際に公正性を確保し、国民の信頼を損なわないことを求めている。しかし、I刑事の行動は、被害者の訴えを「思い込み」と断定し、加害者の立場を擁護するような誘導尋問を行ったことで、公務員としての倫理基準を逸脱している。また、警察内部において、特定の立場の人物を庇うことが黙認される文化がある場合、倫理違反が組織的に行われるリスクがある。警察組織の透明性が確保されていないと、捜査の公平性が担保されず、国民の警察に対する不信感が増大する要因となる。特に、日本の司法制度においては警察の捜査権が強く、適正手続が確保されなければ、権力濫用が日常化する恐れがある。そのため、警察官の倫理違反を防ぐためには、独立した監視機関の設置や、捜査過程の可視化が求められる。今回のI刑事のケースも、倫理規範が機能せず、公務員の義務が果たされていない例であり、警察のあり方そのものを問う社会問題といえる。
まとめ
警察の職務濫用や不適切な捜査手法は、被害者の権利を著しく侵害するだけでなく、法治国家としての信頼を損なう重大な問題である。刑法第195条は公務員による暴行や虐待を禁止し、犯人捜査規範第61条は被害届の受理義務を定めているが、これらが守られない場合、法の公正さが失われる。I刑事の対応は、被害者の証言を軽視し、加害者を庇うような姿勢が見られた点で大きな問題を抱えている。また、国家公務員倫理法が求める公正な職務遂行も果たされておらず、警察内部の監督機能の不備が浮き彫りになった。警察権力の乱用を防ぐためには、外部監視機関の設置や捜査手続の透明化が必要であり、適正な手続きを確保するための法改正や運用改善が求められる。今回のケースを通じて、公権力による不当な扱いを防ぐためには、被害者が自身の権利を正しく理解し、法的知識を持つことが重要であるといえる。