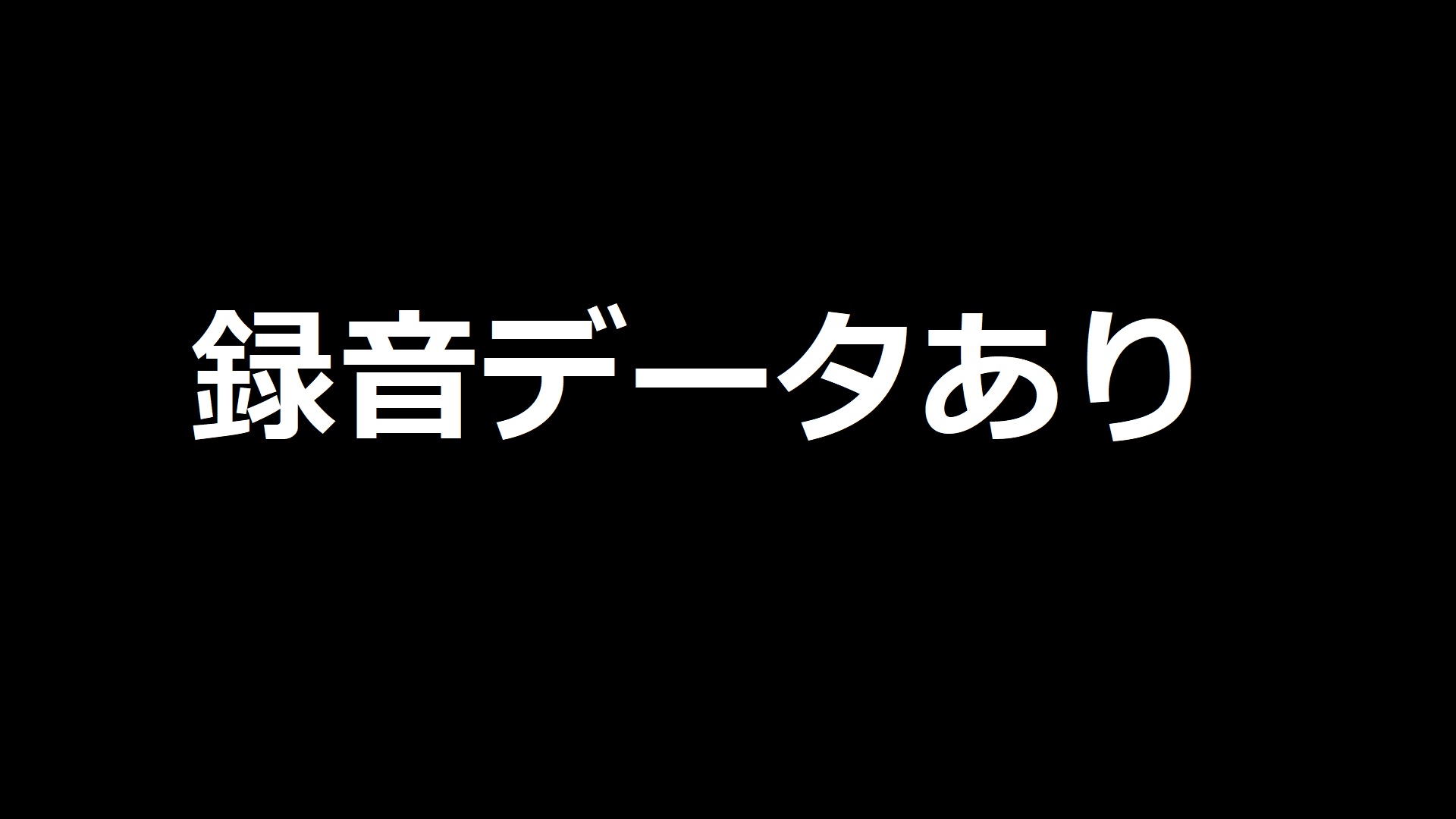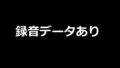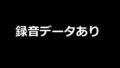埼玉県で発生した本件では、明らかに負傷している人物が救急搬送されることなく、「保護」という名目で警察施設に収容された。本人は「私、今ケガしてるんですよ」と繰り返し訴えたにもかかわらず、応急処置すら行われず、消毒液の用意もない状態であった。こうした対応がなぜ行われたのか、制度運用上の問題と現場判断の実態を検証し、警察・救急・司法の各対応に潜む構造的課題を明らかにする。
私、今ケガしてるんですよ!
- これまでは
- 動画化:私、今ケガしてるんですよ!
- 考察:私、今ケガしてるんですよ!
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
東松山警察署での事情聴取および保護後の音声データを確認すると、被害者は怪我をしていると繰り返し訴えているにもかかわらず、その怪我に対する適切な処置や対応は一切行われていないことが明らかである。
事故の状況は、4年間にわたって嫌がらせを続けていた犯人によるものであり、事故は4回目の嫌がらせが行われた際に発生した。あまりの執拗さに耐えかねた被害者は犯人の車に近づいた。犯人は自らパワーウィンドウを最下部まで下げ、ニヤニヤとした表情で余裕を見せていた。やがて同乗していた女性が発車を促した。被害者はこのままでは嫌がらせが終わらないと判断し、発車を阻止するため左手を運転席側の車内に差し入れ、同時に右手のスマートフォンで110番通報を行った。
するとフルスロットルで急加速してクルマを発車させた犯人。被害者の左手は運転席に挟まり、急加速のクルマに引きずられる。するとフルスロットルで急加速してクルマを発車させた犯人。被害者の左手は運転席に挟まり、急加速のクルマに引きずられる。被害者はしばらく走りながら耐えるが、クルマのスピードは上がっていく。死の危険を感じた被害者は必死に左手を運転席から抜き出す。10メートル以上並走したスピードに耐えられず転倒する被害者。
負傷箇所は、左腰打撲、左手首捻挫(全治6ヶ月)、左肩捻挫、そして数か所に及ぶ出血を伴う傷であった。119番通報で駆けつけた救急車の隊員は、「コロナ禍」を理由に「搬送してもかえって負担になる」と被害者に伝えた。この説明は時期的に見ても妥当な内容であったと思われるが、救急隊員の態度からは、警察の意向が何らかの形で影響していたような雰囲気も感じられた。
東松山警察署での事情聴取。ダウンジャケットを自分で脱ぐこともできず、腰の痛みで一人では歩けない状態であったにもかかわらず、そのまま保護された。
そして、保護後には保護の内部規定により脱がなければならないダウンジャケットやパーカーを、被害者は痛みのため一人で脱ぐことができなかった。それにもかかわらず、警察官たちは保護室に入り込んでまで脱がそうとした。出血の手当てのために消毒液を求めても、「用意していない」と言うばかりだった。
そもそも、それだけの負傷をしている人間を本当に保護する必要があるのだろうか。仮に怪我人を保護するというのであれば、最低限の救急処置ができるよう救急箱のひとつも用意しておくべきではないのか。
動画化:私、今ケガしてるんですよ!
考察:私、今ケガしてるんですよ!
そもそも、打撲や捻挫に加え、出血を伴う傷まである状態の人間を「保護」という名目で移動させ、管理することが妥当だったのかという疑問が残る。本人はダウンジャケットを脱ぐこともできず、歩行も困難な状態であり、明らかに通常の生活動作さえできない怪我人である。そのような状態にもかかわらず、病院への搬送ではなく保護という選択をとったことは、明確な説明が求められる対応だと思われる。また、保護する以上は最低限の医療対応が可能であるべきだが、出血に対して消毒液ひとつ準備されていないというのは、対応として非常に不十分であり、安全配慮を欠いていると言わざるを得ない。怪我人を扱っているという認識が本当にあったのか、その姿勢自体が問われる状況である。
関係する法令
- 刑法第208条(暴行罪)
- 刑法第218条(保護責任者遺棄罪)
- 刑法第199条・203条(殺人未遂罪)
- 国家賠償法第1条
- 医師法第17条
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法第218条(保護責任者遺棄罪)
老年、幼年、身体又は精神の障害により自己の身辺を保護することのできない者を扶助する責任のある者がこれを遺棄したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法第199条・203条(殺人未遂罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。自殺の未遂罪は、罰する。
国家賠償法第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。
医師法第17条
医師でなければ、医業をしてはならない。
専門家としての視点
- 警察による負傷者への不適切な対応と保護責任者遺棄罪の該当性
- 救急隊による搬送拒否と医師法第17条の潜在的違反
- 急発進による引きずり行為と殺人未遂罪の成否
警察による負傷者への不適切な対応と保護責任者遺棄罪の該当性
警察が明らかに負傷している者を保護という名目で連行し、適切な医療措置を講じなかった場合、刑法第218条に定められる保護責任者遺棄罪に該当する可能性がある。条文では「老年、幼年、身体又は精神の障害により自己の身辺を保護することのできない者を扶助する責任のある者がこれを遺棄したときは、三月以上五年以下の懲役に処する」と定められており、身体の自由が明らかに制限され、医療行為を必要としているにもかかわらず放置する行為は「遺棄」とみなされ得る。警察は公的権限のもと被保護者の身体拘束や管理を行う立場にあり、いったん保護した以上はその安全と健康を維持する義務が発生する。また、国家賠償法第1条は「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる」と定めており、医療的配慮が欠如していた場合には警察の職務上の過失責任が問われ、国に対して損害賠償請求の対象となる。負傷者が自ら衣類を脱げない、歩行できない、痛みを訴えているといった客観的状況が確認できるにもかかわらず、医師による診断や処置に回さず保護のみを継続した場合、責任の所在は明確に問われる構成となっており、刑事責任と民事責任が併存する典型例となる可能性が高い。
救急隊による搬送拒否と医師法第17条の潜在的違反
救急隊が搬送を要請された際、医学的判断をもって搬送を見送る行為は極めて慎重に扱われるべきであり、特に「搬送しても負担になる」という発言が救急隊員の独自判断によるものであった場合、医師法第17条が定める「医師でなければ、医業をしてはならない」に抵触するおそれがある。救急隊員は医師ではなく、現場で診断や治療方針を決定する権限を有していない以上、医学的根拠をもって搬送の必要性を否定することは許されない。あくまでも救急隊の役割は、容態の悪化を未然に防ぐための迅速な搬送にあり、病院での医師による判断に委ねることが原則である。また、搬送を拒否した結果として被害者の状態が悪化し、治療の遅延や損傷の拡大が生じた場合には、救急隊の職務上の過失として、国家賠償法第1条の賠償責任が問われる可能性もある。救急現場における判断は緊急性を要するものではあるが、専門資格を有しない者が患者の処遇を最終判断することは、明確に医師法の趣旨に反する行為であり、行政的にも刑事的にも問題視される構造を持っている。特にコロナ禍を理由とした搬送見送りであっても、医学的裏付けのない発言が直接処置の有無を左右したのであれば、その違法性は否定できない。
急発進による引きずり行為と殺人未遂罪の成否
被害者の手が運転席に入っていることを明確に認識したうえで、加害者がフルスロットルで車を急発進させ、被害者が10メートル以上引きずられる結果となった事案については、刑法第199条と203条に基づく殺人未遂罪の構成要件に該当し得る。刑法第199条は「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」と規定し、第203条では「未遂罪は、罰する」と明記されている。被害者が「死の危険を感じた」と証言し、車のスピードが上がっていく中で逃れようとして左手を抜き、最終的に転倒したという状況は、生命に対する危険が現実のものとして存在していたことを示している。加害者が被害者の左手の挟まりを認識していたのであれば、その状態で急加速すれば重大な結果が生じることを予見できたはずであり、それにもかかわらず車を発進させた行為は未必の故意による殺意の存在を肯定する材料となる。特に、被害者が複数の怪我を負い、意識的に逃れようとしているにもかかわらず加害者が制止せず加速を継続した場合、その危険行為の故意性が強く評価される。単なる過失傷害ではなく、明確な故意または未必の故意に基づく殺人未遂罪として立件される可能性が十分にある構造である。
専門家としての視点、社会問題として
- 「保護」の名のもとに行われる人権の軽視と制度疲労
- 現場判断に委ねられすぎた救急対応の限界と制度的課題
- 継続的嫌がらせ行為から発展する暴力の構造と司法の対応の遅さ
「保護」の名のもとに行われる人権の軽視と制度疲労
本件のように、負傷者であるにもかかわらず「保護」という行政手続きを理由に警察施設に収容された事例は、制度としての「保護」の運用が人権を軽視する方向へと傾いていることを示している。行政機関が個人の生命・身体の保全よりも、制度の運用効率や組織内部の手続きを優先する場合、保護という名目で個人の自由が不当に制限される構造が生じる。保護を受ける者が重篤な怪我を負い、自力で動くこともままならず、応急手当も受けられない状況に置かれることは、行政が想定している「保護」の目的とは明らかにかけ離れている。これは個別の運用ミスではなく、制度疲労そのものであり、現行の保護制度が社会的弱者の救済ではなく、しばしば統制手段として利用されている実態を露呈している。医療措置が必要な者に対して医療機関への搬送よりも拘束的手段を選んだことは、警察組織内での医療判断の軽視や、医療と警察の連携不足といった制度的脆弱性を明確に示している。そもそも「保護」とは生命の危機や身体の安全に対する脅威から一時的に守ることが目的であるべきであり、その結果として傷病者が悪化するのであれば本末転倒である。制度運用の現場では、形式的な規定に従うだけでなく、現場の状況に即した柔軟かつ人権を尊重した対応が求められているが、実際には現場の判断が制度の隙間に埋没し、適切な救済が行われていない事例が少なくない。社会全体として「保護」という概念を再定義し、制度設計と運用の両面において見直しが必要である。
現場判断に委ねられすぎた救急対応の限界と制度的課題
救急現場では迅速な判断と行動が求められるが、その一方で、現場の救急隊員に過度な判断責任を委ねる構造は重大な制度的問題を孕んでいる。とりわけ本件のように、「搬送してもかえって負担になる」といった趣旨の発言が救急隊からなされた場合、救急車の出動目的と相反する対応が現実に行われていることになる。救急隊は医師ではなく、診断権限を持たない立場であるにもかかわらず、医療的な必要性を現場で最終的に判断してしまう実態は、制度の限界を示している。特に感染症流行期など特殊な状況下では、搬送判断が曖昧になりやすく、現場の対応が属人的になりがちである。制度的には、感染リスクや病床逼迫を考慮する必要があったとしても、明確な負傷がある者に対して応急処置も搬送も行わないという選択肢が許容される状況は極めて不適切であり、救急対応体制そのものの見直しが求められる。全国的に見ても、傷病者が明らかな怪我を負っているにもかかわらず搬送を断られる事例は報告されており、制度的にも現場に過剰な判断を負わせないための明確な基準整備や指針の共有が不可欠である。こうした事例を放置すれば、救急制度への信頼が損なわれ、必要なときに適切な支援を受けられないという社会的不安が広がることになる。
継続的嫌がらせ行為から発展する暴力の構造と司法の対応の遅さ
本件では、加害者が4年にわたる嫌がらせを継続し、最終的に急発進によって被害者を引きずる重大な身体被害を引き起こしているが、この構図は単発的な暴力ではなく、継続的な精神的・物理的ハラスメントの延長として暴力が顕在化する典型的な事例である。近年、ストーカーや嫌がらせ行為が重大事件に発展するケースは全国的に増加しており、初期段階での警察や司法による介入の遅れが被害の深刻化を招いている。被害者が「命の危険を感じた」として110番通報するほどの緊急性があったにもかかわらず、加害者はその場で強引に車を発進させ、被害者の左手を挟んだまま引きずったという事実は、通常の運転行為では説明がつかない。これは個人間のトラブルとして片付けられるべきものではなく、組織的・制度的な警察の対応の遅さが背景にあると考えられる。嫌がらせ行為が繰り返されている時点で警告・接近禁止措置が取られていれば、重大な結果には至らなかった可能性がある。司法制度がこうした継続的な加害構造に対応しきれていない実情は、制度そのもののアップデートを求める声として社会的に認識される必要がある。個人の通報や訴えが形式的に処理され、重大化してから初めて動き出すような現状は、被害者保護という観点からも明らかに不備がある。
まとめ
今回の事例は、明らかに負傷した人物が適切な医療処置を受けることなく「保護」という名のもとで拘束され、結果として人権が軽視されている実態を浮き彫りにしている。警察の対応には保護責任者遺棄罪や暴行罪が視野に入る行動が見られ、救急隊についても医師法に抵触するおそれのある判断がなされた可能性がある。また、犯人による急発進は殺人未遂罪に相当する可能性があり、司法の対応が十分に機能していないことが社会的にも大きな問題である。制度疲労や判断の属人化によって、安全と正義が揺らいでいる現状を正面から捉え、見直しを迫る必要がある。形式の維持が人命より優先される現場がある限り、再発の危険性は常に潜んでいる。