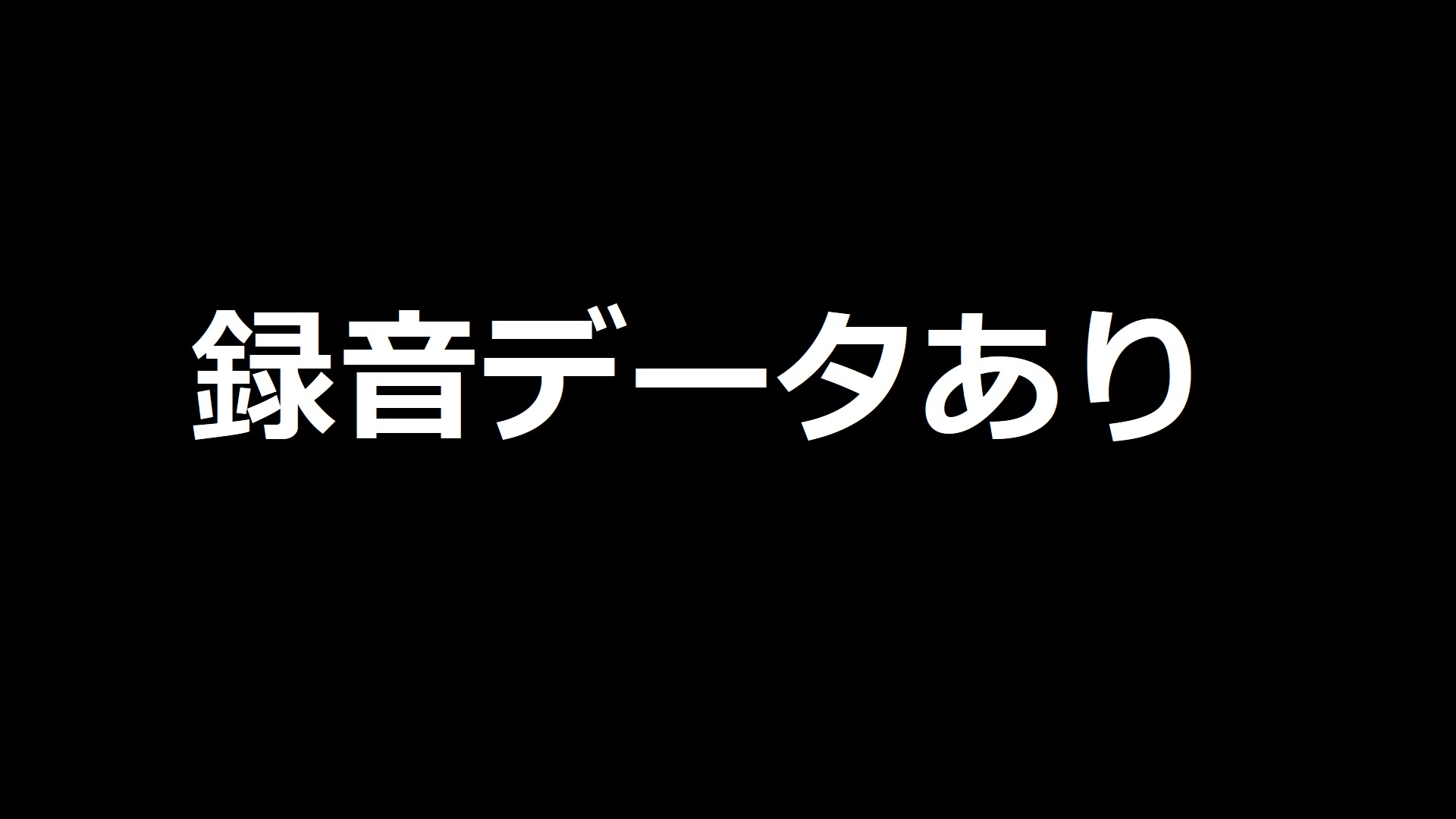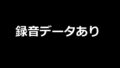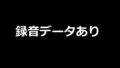警察による精神障害者の保護という名目で行われる措置が、本人の理解を伴わず、知らぬ間に精神病院への入院手続きに発展する事例がある。表面上は任意であるかのように振る舞いながら、実際には裏で措置入院の準備が進められている構造は、制度の透明性と説明責任の欠如を浮き彫りにしている。本記事では、警察の「休んでいてください」という対応が持つ法的問題と社会的影響について、関係法令をもとに検討し、その背景にある制度的な課題を明らかにする。
休むなどという気楽なことか?
- これまでは
- 動画化:休むなどという気楽なことか?
- 考察:休むなどという気楽なことか?
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
保護の後、その保護が措置入院の判断、そして精神病院への入院につながるルートとして機能している状況にもかかわらず、警察官たちは「(保護室で)休んでいてください」とだけ告げる。これは普通に考えれば、一定の時間が経過すれば解放されると被保護者が感じても不思議ではない。そして刑事たちは、その後の結果が精神病院への入院となることをすでに知っているはずである。こうした対応の背景には、その場で錯乱して暴れたり大声を出したりするのを防ぐ意図があるとも考えられる。また、精神病院への入院手続きをより円滑に進めるためという目的もあるかもしれない。いずれの場合でも、被保護者に対して明確な説明を行わないまま進めれば、保護者にとっては先の展開がまったく見えない状態となり、“騙された”と感じても無理はない状況である。
動画化:休むなどという気楽なことか?
考察:休むなどという気楽なことか?
被保護者に対して「休んでいてください」とだけ伝え、今後の経過について一切説明を行わない対応は、極めて一方的であり、本人の理解や納得を得る姿勢が欠けている。保護された本人にとっては、ただ保護室で時間を過ごせば解放されるものと思い込むのが自然であり、その期待を裏切るように突然精神病院への入院へと手続きが進むのは、極めて不透明で不安を伴う。警察側がその結果をすでに把握していながら何も説明せず、穏便にことを運ぼうとする姿勢には、錯乱や混乱を避けたいという配慮もあるのだろうが、だからといって本人の理解を無視してよい理由にはならない。本人からすれば、説明もなく知らぬ間に話が進んでいく状況は「騙された」と感じるに十分であり、その感覚はむしろ当然の反応である。行政機関の対応として、最低限の説明責任すら果たされていないこのような手続きの進め方は、制度の正当性以前に、人としての接し方の問題を突きつけていると言える。
関係する法令
- 行政手続法 第4条(公正の確保)
- 行政手続法 第5条(理由の提示)
- 民法 第709条(不法行為)
- 刑法 第220条(逮捕及び監禁)
- 憲法 第31条(法定手続の保障)
- 憲法 第34条(不当な拘禁の禁止)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29条(措置入院)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38条(応急入院)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条(警察官による通報等)
行政手続法 第4条(公正の確保)
行政機関は、処分をするに当たっては、公正に、かつ、誤りがないようにしなければならない。
行政手続法 第5条(理由の提示)
行政庁は、処分をしようとする場合には、当該処分の理由を示さなければならない。
民法 第709条(不法行為)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
刑法 第220条(逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
憲法 第31条(法定手続の保障)
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法 第34条(不当な拘禁の禁止)
何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、拘禁されない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29条(措置入院)
精神障害者であって、自傷他害のおそれがある者については、都道府県知事は、二人以上の指定医の診察の結果に基づき、当該精神障害者を指定病院に入院させることができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第38条(応急入院)
精神障害者であって、急速を要し、かつ、本人の同意を得ることができないときは、精神科病院の管理者は、医師一人の診察に基づき、七十二時間を限り、当該精神障害者を入院させることができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第45条(警察官による通報等)
警察官は、精神障害者と認められる者が保護を要すると認めたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
専門家としての視点
- 措置入院前の警察対応における説明義務の法的構造
- 警察による黙示的拘束と刑法220条の適用可能性
- 精神保健福祉法と行政手続法における適正手続の交差点
措置入院前の警察対応における説明義務の法的構造
精神保健福祉法に基づく措置入院は、本人の意思に基づかない強制的な医療介入であり、その適用は極めて慎重かつ適法に進められなければならない。とくに保護段階において警察が本人に対し「休んでいてください」とのみ伝え、今後の流れや入院の可能性を一切説明しない対応は、行政手続法第4条が定める「公正の確保」、および第5条の「理由の提示」に反する行為と評価できる。行政手続法第4条には「行政機関は、処分をするに当たっては、公正に、かつ、誤りがないようにしなければならない」と明記され、第5条では「行政庁は、処分をしようとする場合には、当該処分の理由を示さなければならない」とされている。措置入院は処分に相当する重大な公権力行使であるため、手続的説明を回避することはこれらの条文に違反する。また、説明を欠いたまま本人を意図的に誤認させるような対応は、民法第709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する不法行為にも該当する可能性がある。さらに、精神保健福祉法第45条では「警察官は、精神障害者と認められる者が保護を要すると認めたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない」と規定しており、その過程においては行政行為としての正当な手続保障が要求される。説明のないまま進められる措置入院の準備は、結果的に精神障害者の人権を制約する行為であり、正当性を確保するには明確な情報提供と意思形成の機会が不可欠である。このような観点から、警察による曖昧な言動が制度全体の信頼性を損ないかねない重大な手続違背を構成する点を強調しなければならない。
警察による黙示的拘束と刑法220条の適用可能性
警察官が被保護者に対し「休んでいてください」と伝えつつ、実際には外出も解放も許されず、精神病院への入院手続きが裏で進行している場合、その状況は実質的拘束であり、形式的には自由があるように見えても、本人が退室する自由を認識できない構造となっている。このような黙示的な拘束状態が存在すると認定される場合、刑法第220条の「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」という条文が適用される可能性がある。本人の明確な同意なく移動を制限し、心理的・物理的に閉鎖された空間に留め置くことは、「監禁」に該当しうる要素を満たしている。さらに、本人が拘束の認識すら持てない状態に置かれているという点で、事実上の自由剥奪が行われていると評価されれば、違法性は極めて高い。憲法第34条も「何人も、理由を直ちに告げられ、かつ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、拘禁されない」と規定しており、保護名目での実質的拘束がこれに抵触する可能性もある。さらに、行政手続法上の通知義務を果たさずに進められる入院措置の準備が裏で進行していたとなれば、本人にとっては一切知らされないまま自由を奪われている状態であり、その構造は刑法220条と憲法第34条の観点から重大な問題をはらんでいる。警察による保護行為が、本人の意思形成を妨げ、手続保障を回避する手段として機能している場合には、それはすでに公権力の濫用とみなされ、違法拘束として刑事的責任が問われる余地がある。
精神保健福祉法と行政手続法における適正手続の交差点
精神保健福祉法における措置入院制度は、本人の自由を制限しうる重大な行政処分であるため、その実施においては行政手続法上の適正手続との整合性が極めて重要である。精神保健福祉法第29条には「精神障害者であって、自傷他害のおそれがある者については、都道府県知事は、二人以上の指定医の診察の結果に基づき、当該精神障害者を指定病院に入院させることができる」と定められており、その前提となる警察による保護行為は、行政手続としての第一段階に該当する。また第45条には「警察官は、精神障害者と認められる者が保護を要すると認めたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない」と明記され、これは法的義務としての行為であるから、行政機関としての警察が行う処分的行為である。行政手続法第4条と第5条が求める「公正な処分」「理由の提示」は、この通報・保護過程にも適用されると解されるべきであり、したがって警察官が「休んでいてください」とのみ告げて、それ以上の情報を一切提供しないまま精神病院への措置入院判断が裏で進むような運用は、行政手続法に違反している可能性が高い。また、憲法第31条は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ」ないことを保障しており、措置入院が事実上の自由剥奪であることを考えれば、事前に十分な説明と手続的保障がなされない対応は、違憲性をも伴う可能性を持つ。精神保健福祉法と行政手続法の双方にまたがるこの問題は、警察による現場対応が単なる誘導ではなく、結果的に重大な人権制約へと直結するプロセスであることを踏まえ、制度全体の再検証が求められる領域である。
専門家としての視点、社会問題として
- 非公開の手続きによる精神医療の密室化と社会的透明性の欠如
- 警察の「保護」名目による自由制限と市民感覚の乖離
- 精神障害をめぐる偏見と制度運用の歪みが生む二次被害
非公開の手続きによる精神医療の密室化と社会的透明性の欠如
精神保健福祉法に基づく措置入院制度は、そもそも本人の意思とは無関係に進行しうるという性質を持ち、その運用が外部から検証不可能な状態で進められる場合、社会全体としての監視機能が働かなくなる。警察官が現場で「休んでいてください」と伝えたまま、裏では医師による診察と措置入院の準備が進行している構造は、行政としての透明性がまったく確保されていない状態である。このような事例が積み重なると、精神医療と行政による強制的処分の線引きが社会的に曖昧になり、任意のように見せかけた拘束が事実上の強制入院へと転化する。問題は、こうしたプロセスが第三者による評価や記録を伴わずに閉鎖的に行われている点にある。日本の制度上、措置入院は都道府県知事の権限であり、精神保健福祉法第29条によって「二人以上の指定医の診察」が条件となっているが、現実には現場の警察と医療機関の関係性や運用上の便宜によって、手続きの内容が本人や家族にすら十分に伝えられないまま進められる。これは制度の理念に反し、手続の正統性を確保できない状態である。制度の性質上、問題が発覚するのは手続きがすべて終了した後であり、本人の声が外部に届きにくいという構造的弱点がある。そのため、保護から入院に至る一連の流れが可視化されていないことが、社会問題として深刻であり、制度改革や外部監査の必要性を強く示している。
警察の「保護」名目による自由制限と市民感覚の乖離
市民が日常的に接する警察の対応において、「保護」という言葉は一般に優しさや援助といった肯定的な印象を持って受け取られるが、実際にはこの名目で本人の自由が制限される事態が多く存在する。精神障害の疑いがある人物に対して警察が行う保護行為は、精神保健福祉法第45条に基づく行政的判断であるが、現場ではその説明が十分になされることなく、本人はただ「落ち着いてください」「休んでください」と伝えられるのみである。市民感覚としては、それが医療機関への強制的入院につながるとは思いもよらないものであり、これは重大な説明不足である。さらに警察官が結果的に自由の剥奪を伴う行為を行っているにもかかわらず、任意性を装って対処するケースが恒常化すれば、それは刑法220条における監禁行為と社会的に認識される危険性を持つ。こうした手続きの非対称性が蓄積されると、警察と市民との信頼関係が根本から損なわれ、正義の実現に対する疑念が広がる。制度としては法律に基づく正当な行為であるとしても、現実の対応が不透明であり、説明責任を果たさないまま本人を病院に送るという運用が続く限り、法の下の平等や自由の理念が形式だけのものとなる。こうした警察対応の実態と市民の認識との乖離こそが、制度そのものへの不信感を生む最大の要因であり、社会全体で見直すべき重要課題である。
精神障害をめぐる偏見と制度運用の歪みが生む二次被害
精神障害という診断や疑いのもとに行われる行政処分は、対象者に対する社会的レッテルや偏見を強化しやすいという特性がある。本人の行動が一時的であった場合でも、警察により「精神的に不安定」と判断された時点で、その情報が医療機関や行政に共有され、結果的に入院や診断につながることは、本人の将来に深刻な影響を与える。精神保健福祉法第29条による措置入院は、明確な自傷他害の危険があると診断された場合に限られるが、実際の運用では警察官の主観的判断や現場の状況が強く反映される傾向がある。また、入院に至らなかったとしても、保護されたという事実が記録に残ることで、以後の生活や就労、福祉申請に影響を与える可能性がある。こうした背景には、精神障害に対する社会的なスティグマ(差別的認識)が根強く存在し、制度運用そのものがその偏見を補強してしまっているという構造的問題がある。さらに、保護された本人が事後に異議申し立てをしようとしても、すでに「精神的に不安定な人物」という印象が形成されているため、その主張が信用されにくく、結果として二次被害が常態化してしまう。精神障害を理由とした自由の制限は、本人の尊厳を根底から揺るがすものであり、本来は厳格な証拠と正当な手続によって行われるべきであるにもかかわらず、現場の恣意的運用が黙認されている現状は、法制度そのものの信頼を損なう深刻な社会問題である。
まとめ
警察による精神障害者の保護対応が、本人に対する十分な説明を欠いたまま進められ、そのまま措置入院へと移行してしまう現状は、精神保健福祉法や行政手続法の理念を無視した制度運用であるといえる。表面的には任意のように見せかけつつ、実際には自由を制限する処分が裏で進行している構造は、刑法や憲法が保障する人身の自由や適正手続の原則とも矛盾する。精神障害という診断が本人の社会的信用や将来に与える影響の大きさを考慮すれば、こうした不透明な行政対応は重大な社会問題であり、透明性と説明責任を徹底する制度改正が必要である。警察と医療が連携して対応すること自体は重要であるが、その前提として本人の権利と尊厳を守る仕組みが機能していなければならない。