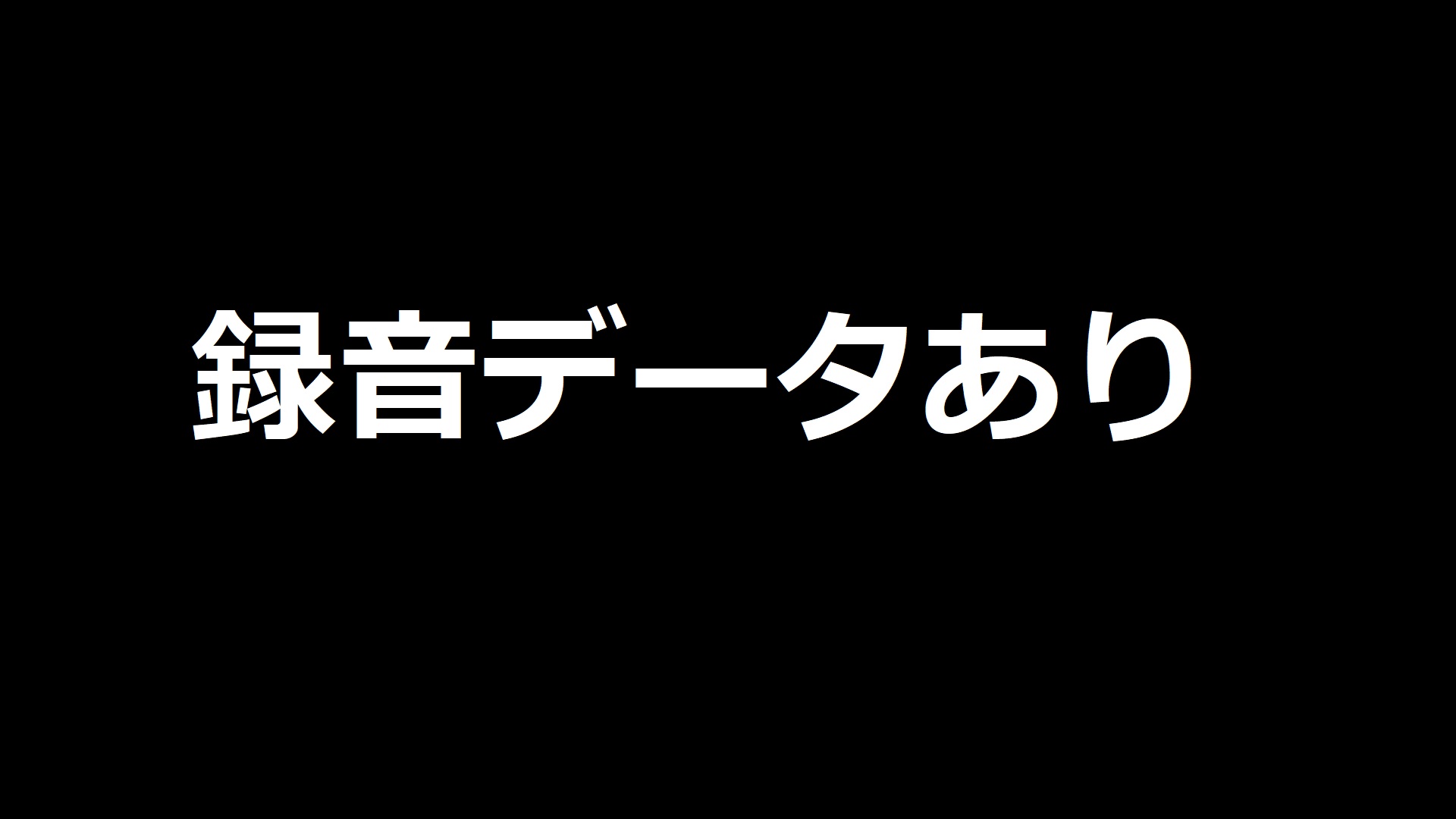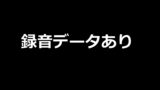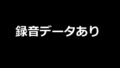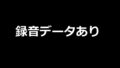警察官が公務中に撮影されることについて、最高裁平成29年6月1日判決は「公務中の公務員の行動は、原則としてプライバシーの対象とはならない」と明示しており、撮影を一律に制止する法的根拠は存在しないとされている。しかし現場では今なお、警察官自らがこの原則を理解しながらも「撮影やめてください」と圧力をかける事例が発生している。本稿では、こうした対応がなぜ生じるのかを検証し、撮影を通じた市民の正当な記録行為と、警察組織内での情報共有や現場対応の実態とのギャップについて深掘りする。
警察官は知っていた。公務で撮影されても文句を言えないことを
- 経緯
- 警察官は知っていた。公務で撮影されても文句を言えないことを
- 考察:警察官は知っていた。公務で撮影されても文句を言えないことを
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定のような取り決めが交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、いつものことではあるが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
相手は「知らない」と答え、「それは役場の誰かが勝手に言ったことじゃないのか」などと口にした。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定のような取り決めは確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく、まずは言い返すことが前提のような応対。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」──お決まりの反論が続く。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
私がまず思ったのは、保護される危険性があるということだった。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしている側が一方的に「保護」という名目で排除されかねない。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを手に取った。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護という名のもとに強制的な処置へと導かれるか──それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院への入院という「お決まりのコース」が待っている。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであるとみられており、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物として慎重に扱わなければならない。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
警察官は知っていた。公務で撮影されても文句を言えないことを
その後、もう一人の警察官がパトカーで現れ、隣人夫婦、町内会長、若い警察官の集団に加わった。しばらくすると、2人目の警察官がこちらに近づいてきた。
情報が正しく伝わっていなかったのか、私がスマホで録画している様子に気づいた警察官は、
「ちょっとお話いいですか?」
「あっ、撮影ダメです」
「警察官の・・・、あの・・・、撮影やめてください」と話しかけてきた。
この言い方を聞くと、この時点でこの警察官は理解していたはずである。
警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”。
その後マウントを取って現場の支配権を強引に握ろうとする警察官は、スマホを手で遮って圧力をかけてくる。
名前を連呼して、黙秘の意志を明確に示しているのにも関わらず、口を開かせようとする。
さらに、警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”知っていながら、「撮影やめてください」「撮影やめてください」と義務のない”命令”で圧力を強める。
やがて、仕方なく二度目の主張をした。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
警察官は“公務で撮影されても文句を言えないことを”知っていた。
その後、現場の支配権を強引に掌握しようとする警察官は、スマートフォンを手で遮るような動作を見せながら圧力を加えてきた。名前を何度も呼び続け、黙秘の意思表示が明確にされているにもかかわらず、執拗に発言を引き出そうとした。
さらに、“公務で撮影されても文句を言えないことを”知っていながら、「撮影やめてください」「撮影やめてください」と義務のない”命令”で圧力を強める。
やむなく二度目の主張をした。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません」
警察官は“公務で撮影されても文句を言えないことを”知っていた。
関係する判例および法令
- 最高裁判例 平成29年6月1日 第三小法廷決定(平成28年(あ)第1733号)
- 警察官職務執行法 第5条
- 刑事訴訟法 第198条 第2項
- 警察法 第2条 第2項
最高裁判例 平成29年6月1日 第三小法廷決定(平成28年(あ)第1733号)
公務中の警察官の姿を市民が撮影することは、特段の支障がない限り正当な行為であり、これを一律に制止する法的根拠はないとされている。この判例は、表現の自由および監視の自由の一環として、公共の場での記録行為の正当性を明確に支持するものである。
警察官職務執行法 第5条
警察官は、正当な理由がある場合を除いては、その職務の執行に当たり、人に危害を加えてはならない。
刑事訴訟法 第198条 第2項
被疑者は、取調べに対して供述を拒むことができる。
警察法 第2条 第2項
警察は、個人の権利と自由を保護するとともに、公共の安全と秩序を維持する責務を負い、そのための業務運営は適正かつ効率的に行われなければならない。
専門家としての視点
- 警察官の撮影に関する判例と現場対応の矛盾
- 撮影妨害と市民の記録権の衝突
- 情報共有の欠如が生む圧力的対応の構造
警察官の撮影に関する判例と現場対応の矛盾
本件の核心は「警察官が公務中に撮影されても文句を言えないこと」という原則に対し、現場警察官がこれを理解しながらも圧力的な言動に出たという点にある。平成29年6月1日の最高裁判決(最判平成29年6月1日刑集71巻6号605頁)は、報道関係者が公務中の警察官を撮影する行為について、公共の関心事であり、その必要性や手段が相当であれば許容されると明示している。この判例は、撮影行為が原則として違法でないことを示し、特に公務中の職務執行に関しては市民の記録権が優越する可能性を含んでいる。それにもかかわらず、本件では「撮影ダメです」「やめてください」と警察官自らが撮影を抑圧しようとし、記録の自由に対して義務なき命令を繰り返している。これは判例に反するだけでなく、警察法第2条が定める「公正かつ中立の立場を保持し、その責務を誠実に遂行しなければならない」という規範にも反している。警察官が自身の法的立場を理解した上であえて圧力を加えているとすれば、それは市民に対する心理的威圧であり、公権力の逸脱として看過できない。また、この対応が警察内部で共有されていたとすれば、個人の問題にとどまらず、組織全体の対応指針の欠如を示している。
撮影妨害と市民の記録権の衝突
警察官が市民による撮影に対して圧力をかけた場面では、市民の記録権と公権力の行使との間に明確な緊張関係が存在する。市民には公共の場所で公務中の警察官を撮影する自由があり、それは憲法21条に保障された表現の自由の一部であると解されている。この権利は、警察の違法または不適切な職務執行を監視・記録するために極めて重要であり、民主主義社会におけるチェック機能として認められている。ところが、今回のように「撮影やめてください」と繰り返す警察官の行為は、市民が合法的に行使している自由に対して不当な制限を加えるものであり、その実態は職務命令でもなく、法的拘束力を欠いた個人的な要請にすぎない。これを強引に押し付けることは、結果的に市民の記録行為を萎縮させ、警察に対する透明性を損なう行為となる。刑法104条の2(特別公務員職権濫用罪)や国家賠償法第1条の適用余地も議論される場面であり、仮に撮影を妨害することで市民に損害が生じた場合には、国家賠償の対象となりうる。加えて、判例上も公務員の撮影に対する制限は極めて限定的にしか認められておらず、例えば平成28年7月8日東京地裁判決(平成25年ワ第30447号)では、撮影行為を制止する明確な法的根拠が存在しない限り、それを妨げる行為は違法であるとされた。つまり、市民の撮影を排除するためには明確な法的根拠と必要性が求められるのであり、それを欠いた今回の対応は、違法性を問われる余地を持っている。
情報共有の欠如が生む圧力的対応の構造
本件では、複数の警察官が現場に到着し、それぞれが異なる対応をとったことが記録されているが、その背景には警察内部における情報共有の欠如、あるいは共有の形骸化があると考えられる。先に到着した警察官には「弁護士と連絡を取っており折り返しを待っているため、これ以上は応じない」という意思が明確に伝えられていたにもかかわらず、後に現場へ来た警察官はそれを無視して再び接触を図っており、現場での対応方針の不統一が露呈している。警察法第2条に定められた「適正かつ効率的な職務執行」は、内部の情報伝達と連携が前提である。これが行われていない場合、執行の正当性が損なわれ、市民に対する不要な圧力となって表出する。本件においても、撮影状況や黙秘の意志が共有されていたはずであるにもかかわらず、再度の接触と撮影妨害が行われた点は、現場警察官が組織内での情報連携を軽視していたか、または共有されていながら無視した可能性を示唆している。特に警察官が「聞いています」と発言していることから、単なる伝達ミスではなく、情報の扱いに対する意識の欠如または意図的な軽視があったとも考えられ、これは市民との信頼関係を損なう重大な問題である。組織内での適切な連携体制が構築されていない場合、同様の圧力的対応が他の現場でも再発する可能性が高く、これは単なる個別事案にとどまらず、制度的課題としての検証が求められる。
“`html
専門家としての視点、社会問題として
- 公務中の撮影に対する警察官の認識と対応の矛盾
- 記録の自由と圧力的現場対応の交錯
- 制度的連携不全と組織的問題の顕在化
公務中の撮影に対する警察官の認識と対応の矛盾
本件で最も注目すべきは、警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”理解していたとみられるにもかかわらず、現場で繰り返し「撮影やめてください」と発言し、実質的に市民の記録行為を抑制しようとした点である。警察官が撮影されることを認識しながら、それに対して義務のない”命令”のような口調で圧力をかける行為は、法的根拠を欠いた介入として、警察法第2条に定められる「適正な職務の遂行」に反している。また、このような行動は市民の表現の自由(憲法第21条)を侵害するおそれがある。さらに、平成28年7月8日東京地裁判決(平成25年ワ第30447号)では、公共の場における警察官の撮影を制限する明確な法的根拠がない限り、それを妨げる行為は違法であると判示された。この判例は、現場での記録行為が原則として認められるべきという司法の立場を明示しており、今回の事案における警察官の発言と行動はその流れに明確に逆行するものである。警察官がその法的立場を知りつつ、発言の選択を誤ったことが事実であれば、これは市民に対する誤導であり、同時に警察組織全体の信頼性を揺るがす深刻な問題である。
記録の自由と圧力的現場対応の交錯
市民がスマートフォン等を用いて公共の場で警察官の職務執行を記録することは、違法行為の抑止や行政の透明性を担保する手段として重要な役割を果たしている。これに対し、今回のように警察官が身体を寄せてきてスマホを手で遮る動作を行い、録画の継続を精神的に困難にさせるような圧力を加えることは、単なる要請を超えて記録権の侵害とみなされかねない行為である。刑法第104条の2は、特別公務員がその職権を濫用して人に義務のないことを行わせた場合の違法性を規定しているが、今回のように法的義務のない「撮影中止」を執拗に求めたことは、当該条文に抵触する可能性をはらむ。特に、弁護士への連絡を通じて黙秘権の行使が示されていた中での再接触は、対応の一貫性を欠き、法的手続きに対する不敬を示す対応と解釈されうる。市民の側に記録行為の権利がある以上、それに対する圧力的言動は慎重に取り扱われなければならず、警察官の現場での振る舞いが市民の信頼や安心感を損なう要因となる点を見過ごしてはならない。
制度的連携不全と組織的問題の顕在化
今回の事案では、複数の警察官が同一の現場に居合わせたにもかかわらず、それぞれの対応が統一されておらず、弁護士連絡済みの情報が共有されていなかったか、共有されていても対応に反映されていないという事実が確認されている。警察法第2条は「迅速かつ的確な職務の遂行」を求めており、これは情報共有を前提とした内部連携の徹底を意味している。市民との対応において現場の警察官が情報を正確に把握せず、前任者と異なる対応を行うことは、市民にとって混乱と圧力をもたらし、最終的には対応そのものの信頼性を損なう原因となる。仮に2人目の警察官が、すでに伝えられていた対応方針を無視して新たな接触を試みたとすれば、それは単なる個人の問題ではなく、警察組織内の情報管理と命令系統の不備がもたらした制度的問題であるといえる。組織としての警察が現場での言動に対して責任を持つ体制を構築していない限り、同様の事案は繰り返される可能性が高く、これは単なる過誤では済まされない構造的課題として、厳しく問われるべきである。
まとめ
本件において最大の問題は警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”理解していたにもかかわらず現場で市民に対して繰り返し「撮影やめてください」と圧力を加えた点にあるこの言動は法的根拠を欠いており記録行為を実質的に妨害するものであり表現の自由や記録の自由に対する抑圧として強く非難されるべきであるさらにすでに弁護士連絡中という明確な意思表示がなされていたにもかかわらず別の警察官が新たな接触を試みるなど警察内部での情報共有や連携体制が極めて不完全であったことが露呈した撮影されることの法的正当性を認識しながらも現場で圧力的に振る舞うという行為は個人の逸脱ではなく組織的な認識の甘さや対応指針の未整備を示しており市民の信頼を損ねる根本的な原因となっている司法判断によって保障された権利が警察実務においてないがしろにされる現状は社会全体の透明性と法の支配の観点から極めて重大な問題である。