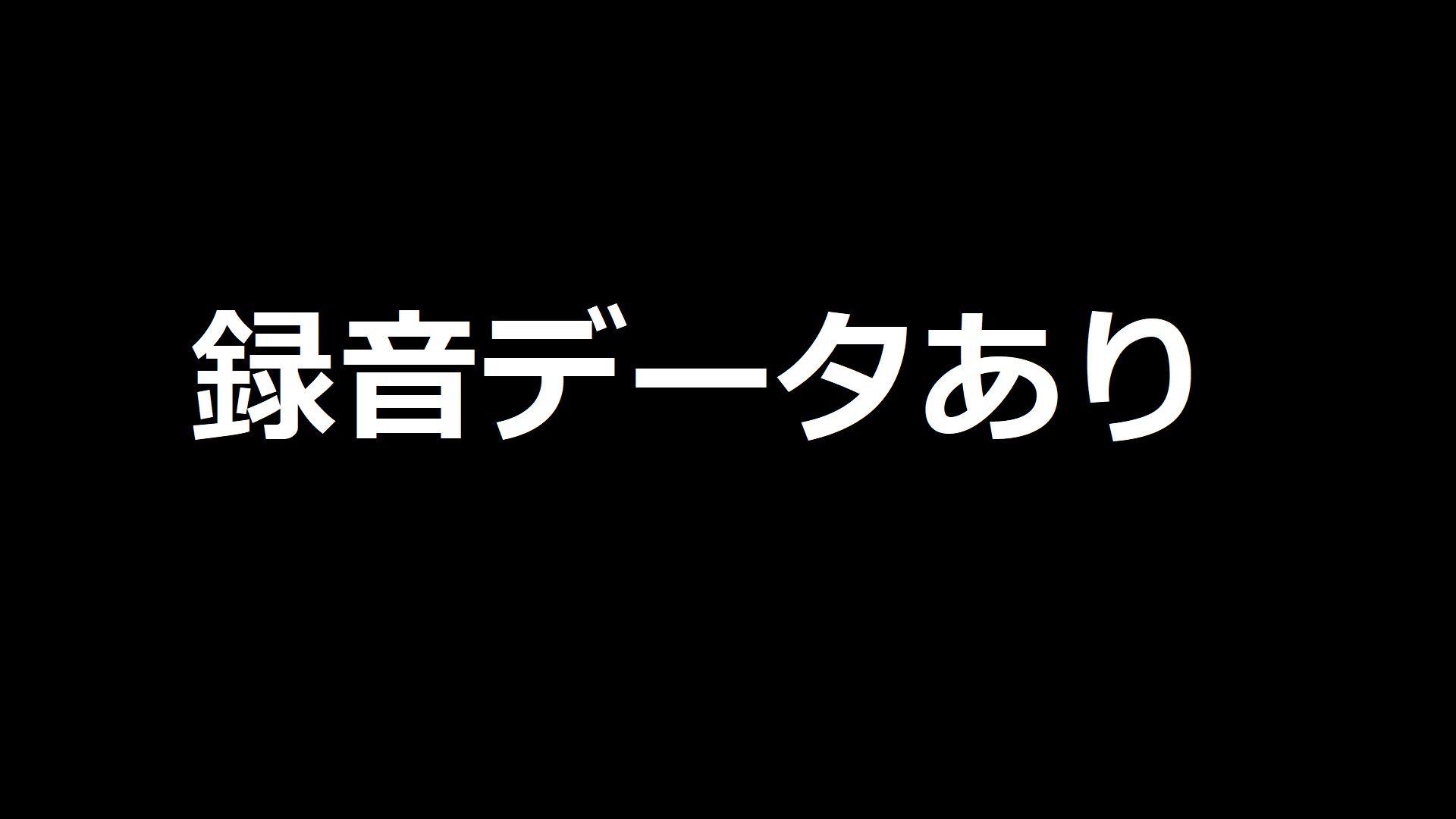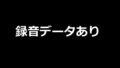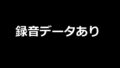スマートフォンは今や個人の生活すべてが詰まった私的空間であり、その中身を他人が無断で覗くことは重大なプライバシーの侵害にあたる。ところが、実際の捜査現場では、警察官が裁判所の開示命令や令状もなく被害者のスマホ画面を確認しようとする場面が存在している。このような行為は、刑事訴訟法が定める適正手続に反するばかりか、捜査機関による心理的圧力の行使としても問題視されるべきである。本記事では、ある事案をもとに、スマートフォンのぞき込みという行為がどのような法的・社会的問題を孕んでいるのかを、条文と実務の観点から明らかにしていく。
これまでは
2023年2月9日。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署、そして犯人による4年間にわたる嫌がらせの末、ひき逃げ事件が発生した。被害者は東松山警察署へ向かうパトカーの車内でスマートフォンによる録音を開始し、同署で事情聴取を受けた。その最中、身に覚えのない「保護」を受け、警察による不当な対応が行われた。被害者はおよそ18時間にわたり拘束され、翌日、措置入院の判断を目的として2か所の病院で診察を受けたものの、精神科病院への入院には至らず、最終的に解放された。
事情聴取の最中、事件当時に被害者が撮影しようとしていた動画の話題になる。動画の有無が気になって仕方がない様子の東松山警察署刑事課I刑事は、被害者が説明している最中にも関わらず、その話を遮ってまで「動画が残っているか」と問いかけてくる。被害者は念のためスマートフォンの中身を確認するが、I刑事はそのスマートフォンの画面を必死に覗き込もうとする。スマートフォンは極めて私的な情報の集積であり、他人に見せたくないというのが被害者の当然の感覚である。それにも関わらず、I刑事は「何か見られて困るものでもあるのですか?」と詰め寄る。スマートフォンの中身を見るには、本来であれば裁判所の開示命令が必要なはずである。
動画化:動画があると困る?
考察:動画があると困る?
事情聴取の最中、事件当時に被害者が撮影しようとしていた動画の話題が出る。東松山警察署のI刑事は、その動画の有無に異様なまでの関心を示し、被害者が状況を説明している最中にも関わらず、その話を遮ってまで「動画が残っているか」と問いかけてきた。被害者は念のためスマートフォンの中身を確認するが、そのスマートフォンの画面をI刑事は必死に覗き込もうとする。スマートフォンには日常の記録、個人的な会話、感情のメモなどが蓄積されており、見せることに抵抗を感じるのは自然な反応である。それにも関わらず、I刑事は「何か見られて困るものでもあるのですか?」と詰め寄る。これは、あたかもスマホを見せたくないのは被害者側にやましいことがあるからだと言わんばかりの態度だった。
だが、実際に「困る事情」があったのは警察の側ではなかったか。もしその動画が残っていたならば、事件の瞬間が客観的な映像として記録されており、それによって被害者の証言が裏付けられるだけでなく、加害者の行動が明白に可視化されることになる。それはつまり、警察にとって不都合な証拠となる可能性を意味していた。というのも、その事件に関して、警察は加害者に対してなぜか一貫して擁護的な態度を取り続けており、被害者の主張は軽んじられていた。もし動画が存在し、それが加害者にとって不利な内容であったならば、警察はもはや加害者を守ることができなくなる。動画の存在は、擁護の前提そのものを崩壊させる脅威だったのである。
だからこそ、I刑事は動画の存在に過剰なほど神経質になり、確認を急ぎ、そして覗き込み、被害者の抵抗を言葉で封じようとした。形式的には強制ではないが、その実、圧力をかけてスマートフォンの中身を把握しようとする姿勢は、正当な手続きとはかけ離れている。本来であれば、こうした個人の端末内情報を確認するには裁判所の開示命令が必要なはずであり、被害者が自発的に開示する義務など存在しない。それを理解していながら、あえて「自主的に見せた」という体裁をとることで、警察としての責任を曖昧にしつつ、都合の悪い情報の存在を消し去ろうとしたようにも見える。問題は、こうした姿勢が誰を守ろうとしているのか、そして誰の真実を潰そうとしているのか、という点である。
刑事訴訟法
- 刑事訴訟法第218条(捜索及び差押え)
- 刑事訴訟法第222条(差押えに関する準用)
- 刑事訴訟法第99条(証拠書類等の提出命令)
- 刑事訴訟法第197条第1項(捜査)
- 刑事訴訟法第1条(目的)
刑事訴訟法第218条(捜索及び差押え)
捜索又は差押えは、裁判官の発する令状によりこれを行う。
刑事訴訟法第222条(差押えに関する準用)
第二百十八条の規定は、押収すべき物を提出させるための差押えについて準用する。
刑事訴訟法第99条(証拠書類等の提出命令)
裁判所は、必要と認めるときは、書類若しくは物を提出すべきことを命ずることができる。
刑事訴訟法第197条第1項(捜査)
検察官、検察事務官及び司法警察職員は、犯人があると思料するときは、犯人の発見及び証拠の収集をするため、必要な捜査をすることができる。
刑事訴訟法第1条(目的)
この法律は、刑事事件に関する訴訟手続を規定し、もって事案の真相を明らかにし、かつ、適正な手続の下に正義を実現することを目的とする。
専門家としての視点
- 刑事訴訟法218条とスマートフォン画面のぞき込みの法的問題
- 開示命令なしの情報取得は適正手続に反する
- 警察による心理的圧力と同意の任意性
刑事訴訟法218条とスマートフォン画面のぞき込みの法的問題
スマートフォンは単なる物的証拠ではなく個人の行動履歴や思考、プライバシーに関する情報を広範に含む電子的記録媒体であり、その中身の確認は刑事訴訟法上の捜索または差押えの手続きに該当する行為であると専門家は位置付ける。刑事訴訟法第218条は「捜索又は差押えは、裁判官の発する令状によりこれを行う」と明記しており、令状なしにスマートフォンの中身を確認する行為は本来許されない。さらに刑事訴訟法第222条は「第二百十八条の規定は、押収すべき物を提出させるための差押えについて準用する」としており、被害者のスマートフォンに対して内容確認を求める行為も、裁判所の令状を要する差押えに準ずると解釈されるべきである。刑事訴訟法第99条においても「裁判所は、必要と認めるときは、書類若しくは物を提出すべきことを命ずることができる」と規定されており、個人の端末に保管された証拠の提出も本来は裁判所の命令を必要とする制度的枠組みの中にある。したがって、令状や開示命令を経ずに警察がスマートフォンの画面を覗き込もうとする行為は手続き的にも実質的にも刑事訴訟法の規定を逸脱しており、適法性に重大な疑義がある。刑事訴訟法第1条はこの法律の目的を「刑事事件に関する訴訟手続を規定し、もって事案の真相を明らかにし、かつ、適正な手続の下に正義を実現することを目的とする」と定めており、手続きを無視した捜査行為は法の趣旨そのものを損なうものである。
開示命令なしの情報取得は適正手続に反する
スマートフォンの中にある情報は非常に広範でかつ私的であり、それを第三者が閲覧するには厳格な手続きが求められる。刑事訴訟法第218条に基づく令状主義は、国民のプライバシーを守るための防波堤であり、捜索または差押えを行う際は必ず裁判所の発する令状が必要である。さらに第222条により、任意提出を求める差押え行為についても同様の手続きが求められることが明記されている。これに反して警察官がその場で、被害者に「動画が残っているか」と迫り、スマートフォンを確認するよう強いる行為は、外形的には任意の確認に見せかけながら、実質的には令状なき捜索と同義である。また刑事訴訟法第99条が定めるように、本来証拠の提出は裁判所の命令によってなされるべきものであり、個人に直接的な提出圧力を加えることは許されない。こうした行為は刑事訴訟法第1条が定める「適正な手続の下に正義を実現する」という原則に反する。捜査の目的が正当であっても、手続が適法でなければその捜査自体が違法とされるというのが現代刑事司法制度の大前提であり、これを無視した行為は違法収集証拠排除法則の対象となりうる。警察実務においては適法性の確保が最優先されるべきであり、今回のような事案では明確に逸脱行為が存在していたと評価できる。
警察による心理的圧力と同意の任意性
刑事訴訟法の手続において「任意の提出」や「任意の協力」がしばしば重要視されるが、その任意性が真に自由意思に基づくものであったかは極めて重要な評価要素である。たとえば刑事訴訟法第197条第1項では「検察官、検察事務官及び司法警察職員は、犯人があると思料するときは、犯人の発見及び証拠の収集をするため、必要な捜査をすることができる」と定めているが、この「必要な捜査」は法の定める枠組みの中で行われることが前提であり、個人の自由を侵害する手段であってはならない。スマートフォンの中身を見せるか否かは極めてセンシティブな判断であり、警察官から「何か見られて困るものでもあるのですか?」と詰問されることは、法的義務がないにも関わらず心理的な強制力を生み出す。表面的には任意でも、その内実が実質的な強制であるならば、その取得された情報や協力は違法とみなされる可能性がある。さらに、刑事訴訟法第218条および222条の令状主義と準用規定は、そうした強制の濫用を防ぐために存在する制度であり、この枠組みを無視して心理的圧力で情報を引き出す行為は、制度趣旨を完全に損なう。刑事訴訟法第1条が掲げる「適正な手続による正義の実現」は、まさにこうした逸脱を防ぐために存在しており、捜査機関はこの原則に従わなければならない。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察による情報収集とプライバシーの境界
- 被害者が加害者のように扱われる構造的問題
- スマートフォンという私的領域への無理解
警察による情報収集とプライバシーの境界
警察による情報収集活動が社会において必要なものであることは言うまでもないが、その過程でどこまで個人の私的領域に立ち入ることが許されるのかという線引きは極めて重要である。今回の事案では、被害者が事情聴取の最中に自身のスマートフォンを確認しているところを、東松山警察署のI刑事がその画面を覗き込もうとし、さらに「何か見られて困るものでもあるのですか?」と発言している。これは単なる質問というより、見せないことが不自然であるかのような心理的圧力を与える行為であり、事実上の強制に近い。スマートフォンは現代人にとって手帳、日記、通信記録、写真アルバム、位置情報履歴、健康管理データなど、あらゆる個人情報の集積体であり、その内容を見られることは人間としての尊厳にかかわる。こうした機器の中身を捜査機関が確認するには、令状による手続きを経る必要があるという法的原則があるにもかかわらず、その原則が曖昧にされ、なし崩し的に警察が情報にアクセスするような実務が常態化してしまえば、市民のプライバシー保護は形骸化する。刑事訴訟法第218条は「捜索又は差押えは、裁判官の発する令状によりこれを行う」と明記しており、第222条もこれを差押えに準用すると定めている。つまり、仮にスマートフォンを被害者が手にしていたとしても、その内容を第三者である警察官が確認しようとする行為は、捜索または差押えに準じた行為とされ、裁判所の関与が必須となる。令状なしの情報収集は、単なる違法行為というだけでなく、社会全体の信頼関係を損ねる深刻な問題として捉えるべきである。
被害者が加害者のように扱われる構造的問題
被害者として警察に事情を説明している立場にもかかわらず、発言を遮られ、さらにスマートフォンの中身を執拗に確認されるという行為は、被害者がまるで加害者のように扱われる構造を露呈している。警察の姿勢が「協力しないのは怪しい」「見せないのはやましい」といった前提に基づいている場合、それは証拠収集ではなく疑念の押し付けであり、刑事手続の公正さを損なう要因となる。実際に、今回の事案では、I刑事が被害者の説明中にもかかわらず話を遮り、「動画が残っているか」と繰り返し確認し、その後に画面を覗き込もうとした上で、見せたくないという態度を取る被害者に対し「何か見られて困るものでもあるのですか?」と発言している。こうした対応は、被害者の人格や信頼を否定するものであり、精神的圧迫や不信感を助長する。そもそも被害者が証拠としてスマートフォンの情報を警察に提供する義務はなく、任意性の原則が貫かれるべきであるにもかかわらず、心理的な圧力をかけて「自ら提出した形」に持ち込もうとする姿勢は、法制度の濫用に等しい。刑事訴訟法第1条が目的として掲げる「適正な手続の下に正義を実現する」という原則に照らしても、今回のような対応は捜査の正義を逸脱した構造的な問題であり、警察の職務行為として強く再検討されるべきである。
スマートフォンという私的領域への無理解
スマートフォンは現代において単なる通信手段ではなく、生活のあらゆる側面が詰め込まれた「個人の分身」とも言える存在である。写真、動画、通話履歴、SNSのやりとり、検索履歴、健康アプリ、決済記録などが1台の端末に集約されており、その中身を他人が無許可で見ようとする行為は、家の中を勝手に物色されること以上に強い侵襲性を持つ。それにもかかわらず、今回のように警察官が被害者のスマートフォンの画面を覗き込み、さらに「見せないこと」自体を不自然視する発言を行うという事例は、スマートフォンが持つプライバシーの重みを理解しない組織的体質の表れである。刑事訴訟法第218条および第222条が捜索・差押えにおける令状主義を規定しているのは、まさにこうした個人領域への介入を厳しく制限するためであり、たとえ捜査の必要があっても手続を経ることが求められている。これらの規定を無視し、場当たり的に画面を確認しようとする行為は、警察が法的根拠よりも現場対応を優先させるという誤った判断をしている証左であり、社会的にも重大な問題を孕む。市民の側が「見せないのはやましいことだと思われる」と感じてしまうほどの空気が現場にあるならば、それは捜査権限の濫用であり、法の支配に対する組織的な挑戦とみなされても仕方がない。現代社会において、スマートフォンに対する捜査の在り方は、単なる技術論ではなく人権論としての位置づけが必要である。
まとめ
スマートフォンの画面を警察官が覗き込むという行為は、現代の私的空間に対する無理解と手続き軽視の象徴であり、刑事訴訟法218条や222条が定める令状主義を根本から逸脱する行為である。とくに被害者が自ら端末を確認するという行為に対して、警察が一方的に割り込んで中身を覗こうとする場面は、法的根拠のない事実上の捜索行為に等しい。令状なしで情報を確認しようとする行為は、たとえその場の空気が任意であるかのように見えても、実質的には心理的圧力による強制であり、適正手続から逸脱している。スマートフォンは単なる物証ではなく、個人の生活や感情が集積された私的領域であり、そこへの無許可の介入は憲法上のプライバシー権とも深く関わる。警察が令状なしに内容を把握しようとすることは、被害者の信頼を損なうばかりか、法制度そのものの正当性にも疑念を生じさせる。社会全体がこのような実務の問題を可視化し、手続きの厳格な運用を求めることが今後の課題である。