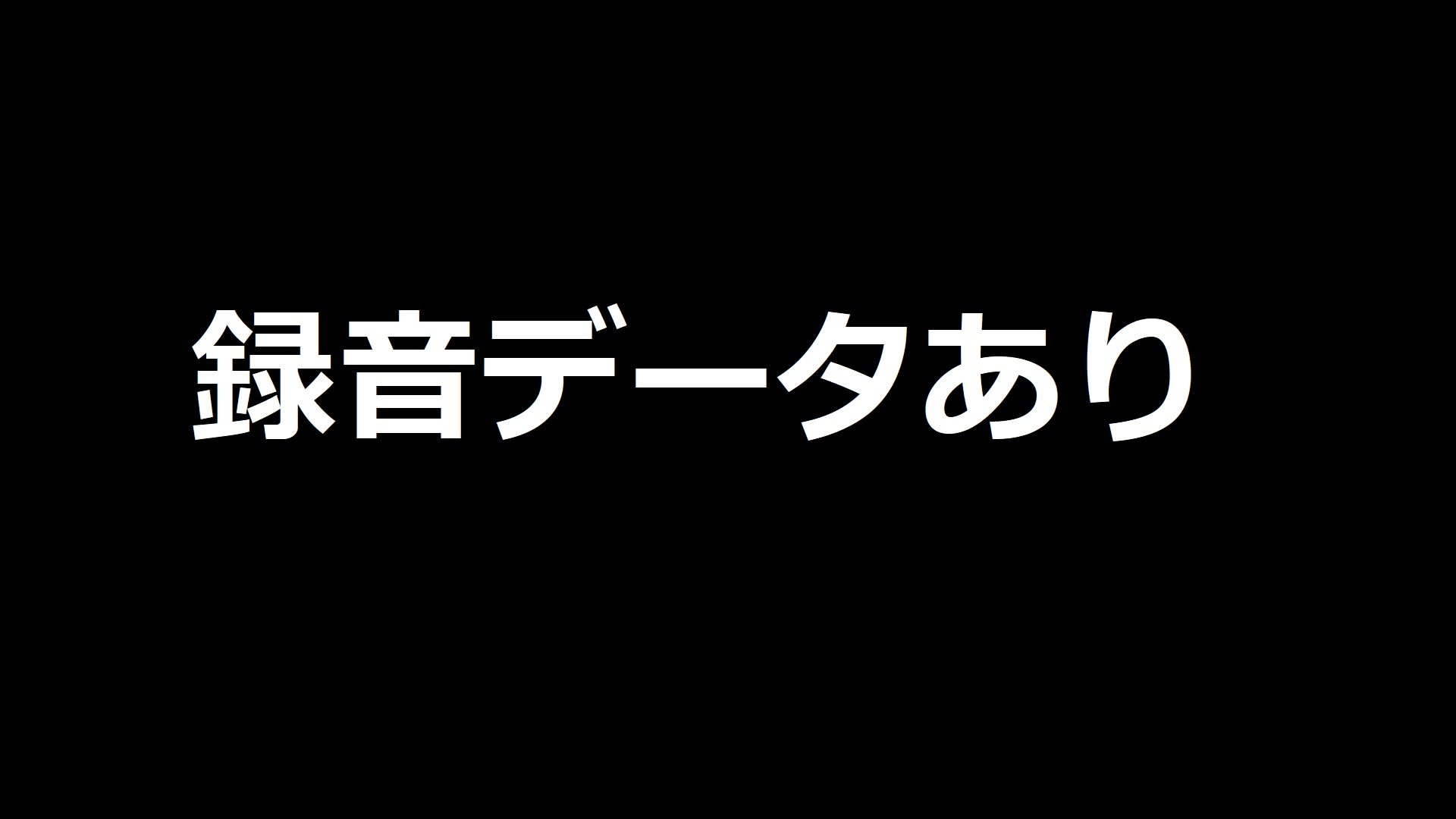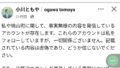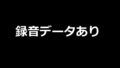ひき逃げ事件の被害者が警察署で保護名目の拘束を受けた事例は、市民社会に深刻な疑問を投げかけている。本来守られるべき立場である被害者が自由を奪われ、加害者が釈放されるという不均衡な対応は、警察権限の運用が制度趣旨から逸脱していることを示している。この構造は人権侵害につながり、市民の信頼を損なう重大な社会問題として検証されるべきである。
ひき逃げの被害者を警察署に拉致-埼玉県警東松山警察署
- 嫌がらせがついに殺人未遂事件に発展
- ひき逃げの被害者を警察署に拉致-埼玉県警東松山警察署
- 考察:ひき逃げの被害者を警察署に拉致-埼玉県警東松山警察署
嫌がらせがついに殺人未遂事件に発展
2023年2月9日、埼玉県東松山市元宿1丁目
4年間、西入間警察署、犯人、鳩山町長寿福祉課による嫌がらせが続いていた。
事件直前には、その嫌がらせはさらにエスカレートしていき、被害者が講じたさまざまな防御策をもってしても、それを防ぐことは難しくなっていた。
被害者がどのように歩行ルートを変えても、先回りして現れる西入間警察署、犯人、鳩山町長寿福祉課。
「次こそは、犯人を動画で撮ってやろう」と心に決めていた。
そこに現れた犯人のクルマ。すでに4年間に4回目の同一車両、同一ナンバー。
遠目からズームにして犯人のクルマを画像撮影。動画モードにして近づく。
犯人は余裕であった。ニヤニヤと笑っている。
運転席の犯人。助手席の女性(夫人ではない)。
2人とも70歳代と思われたが(事件時、犯人76歳)、どちらも黒々としたパーマのかかった、明らかにそれとわかるかつらを被っていた。
犯人は、パワーウィンドウを一番下まで下げる。
被害者は話しかける。
「いつもつけてますよね。一体何をやってるんですか?」
犯人は答えた。
「ポケモ~ン!」
助手席の女性が犯人に言う。
「あなた、もう行きましょうよ」
被害者は、逃げられる危機感を感じ、右手のスマホで110番通報(この時点で録画は終了してしまった)。
左手を運転席に入れ、犯人が発車できないようにした。
そこでまさかの急発進。
犯人の運転席に絡まった左手。10m以上引きずられる。
必死に左手を運転席から抜き出す。
被害者は堪えきれなくなり、アスファルトの上に転倒。負傷。
犯人のクルマは、東武東上線高架橋下の下道路に向かい、タイヤを鳴らしながら右折していった。
その高架橋下の下道路は、コンクリートで固められた非常に狭い道路であり、もし腕を抜きだすことができなければ、間違いなく死亡していただろう。
ひき逃げの被害者を警察署に拉致-埼玉県警東松山警察署
事件後、被害者は110番通報、119番通報をした。
そこに現れたのは東松山警察署刑事課。
負傷した状態で実況見分を行い、やがてパトカーで東松山警察署へと連れて行かれた。
東松山警察署では事情聴取が行われ、やがて被害者は刑事たちによって保護された(警察官職務執行法第3条)。
警察官職務執行法第3条とは、
警察官職務執行法第3条
(保護)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
保護とは、警察署の留置場の一番奥にある保護室に入れられることである。保護室は透明感のある硬質プラスチックの板で仕切られ、その内部には格子状の鉄網が張り巡らされている。
言ってみれば、形態に若干の違いはあるものの、実質的には留置場と同じである。
また、逮捕とは異なり、食事は与えられず、常時警察官の監視を受けている。
拘束の後(被害者の場合は18時間)、二人の医師の診断を受け、措置入院として精神病院の隔離病棟に入れられる。
刑事はその保護理由として、
「加害者のクルマに手を入れたから」
と言った。
しかし、これはおかしい。
東松山警察署はのちに、この事件を加害者を犯人とする傷害事件として扱っているのである。
- 加害者のクルマに手を入れた被害者を保護(拘束)。
- 被害者に傷害を負わせた傷害罪、さらに救護義務違反(いわゆるひき逃げ)を犯した加害者を釈放。
これは、犯人が警察OBの防犯ボランティアであり、被害者に執拗に嫌がらせを行っていて、それが事件に発展し、東松山警察署はその事件の隠蔽を図ったからである。
被害者は度重なる嫌がらせに耐えかね、犯人のクルマに近づいた。犯人自ら全開にした運転席側のパワーウィンドウ。被害者は110番通報をするとともに、犯人がクルマを発車できないように、腕を車内に入れたのである。
事情聴取中、どうして事件が起こったのか、被害者が犯人のクルマに近づいた理由、犯人とのやり取り、その結果事件となり、どのように転倒し負傷したのかを詳細に刑事に説明したにもかかわらず、悪質な傷害事件・ひき逃げ事件の犯人は釈放され、被害者は「保護」という扱いになったのである。
考察:ひき逃げの被害者を警察署に拉致-埼玉県警東松山警察署
保護時に刑事が口にした「加害者のクルマに手を入れたから」という説明は、事件全体を歪める決定的な言葉であった。本来、被害者の行為は加害者の執拗な嫌がらせに終止符を打つため、これ以上逃走を許さないために取られたものであり、必死の行動にすぎない。被害者は「手を入れている状況でクルマを発進させれば重大な事故になる。だから発進するはずがない」と考えていた。それは、相手の理性に依拠した極めて人間的な判断であった。にもかかわらず加害者はあえて発進し、被害者は転倒し負傷したのである。
しかし、刑事の一言はこの背景を切り落とし、被害者の行動は単なる「危険行為」と見なされる根拠とされた。その結果、複雑な経緯や防御的な判断は無視され、「危険な行動をした人物」という印象だけが残された。
さらに矛盾しているのは、その後の警察の対応である。東松山警察署はのちに、加害者を犯人と認定し、傷害事件・ひき逃げ事件として扱っている。つまり、警察自身が後に明らかにした「加害者の違法行為」と、保護時に根拠とされた「被害者の行動」は正面から食い違っている。
この「加害者のクルマに手を入れたから」という一文は、事実の連鎖を単純化し、被害者を加害的に見せる効果を持つ。執拗な嫌がらせの経緯も、防御としての必死の判断も、加害者の暴力性も、すべてかき消され、表面だけが切り取られた。その結果、被害者は「保護」という名目のもとに拘束され、加害者は釈放された。
俯瞰すれば、この場面は加害と被害の立場を逆転させる言語操作であり、組織にとって都合のよいストーリーを作るための装置として働いている。事件の本質は「手を入れたから」ではなく、「手を入れた状態で発進したから」であるにもかかわらず、警察は意図的に前半だけを強調し、後半を消し去ったのである。
この一言に凝縮されているのは、事実の切り取り方ひとつで被害者が加害者に変換されるという逆転構造であり、事件の異常性を端的に示す核心部分だといえる。
関係する法令
- 警察官職務執行法(第3条)
- 地方公務員法(第33条)
警察官職務執行法(第3条)
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
地方公務員法(第33条)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
専門家としての視点
- ひき逃げ被害者を保護名目で拘束することの法的構造。
- 加害者釈放と被害者拘束が示す警察対応の不均衡。
- 保護措置の運用がもたらす人権侵害の危険性。
ひき逃げ被害者を保護名目で拘束することの法的構造
ひき逃げ事件の被害者が警察官職務執行法第3条を根拠に保護名目で拘束された事実は制度の本来趣旨から外れたものである。警察官職務執行法第3条は「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して」危険を及ぼすおそれがあると判断された者を対象としているが、被害者は加害者による行為により傷害を受けた立場であり、犯罪被害者として取り扱われるべきであったにもかかわらず、保護室に入れられ自由を奪われた。この措置は形式上は保護であるが、実質的には逮捕に類似する強制力を伴っており、刑事訴訟法上の逮捕手続を経ないまま権利が制限された点で問題がある。被害者が被疑者と同様に扱われたことは、警察権限の運用における大きな矛盾を示している。
加害者釈放と被害者拘束が示す警察対応の不均衡
本件において東松山警察署は被害者を保護室に入れ、十八時間に及ぶ拘束を行った。一方で加害者は傷害罪、ひき逃げに相当する行為をしたにもかかわらず、釈放されている。この不均衡な対応は警察の中立性を欠くものである。地方公務員法第33条が定める信用失墜行為の禁止に照らせば、市民からの信頼を著しく損なう行為であり、警察組織の存在意義そのものを揺るがす。本来ならば救護義務違反を含む重大事件として加害者を捜査し責任を追及すべきであったにもかかわらず、逆に被害者が拘束され加害者が解放される構図は、市民の法的保護を否定し、司法制度への信頼を失墜させる。
保護措置の運用がもたらす人権侵害の危険性
保護という名目で行われた措置は実質的には逮捕に匹敵する自由制限であった。保護室は留置場と同様の環境で、外部との連絡が制限され、食事の提供もなく、常時警察官の監視下に置かれる。さらに二人の医師の診断を経て措置入院へと移行する流れが存在しており、一度保護されれば裁判手続を経ることなく長期間自由を奪われる。刑事訴訟法に基づく逮捕であれば、弁護士選任権や裁判所による審査といった保障があるが、保護にはそれがなく、不服申し立ての手段もない。このような構造は被害者にとって著しい不利益であり、事件処理の透明性を欠いた警察権力の行使は市民の人権侵害へ直結する。警察官職務執行法第3条の適用が今回のように濫用されれば、被害者救済どころか権利侵害の温床となる。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察権限の適用が本来趣旨を逸脱する構造。
- 被害者拘束と加害者釈放が示す不均衡。
- 保護措置運用の社会的影響と信頼失墜。
警察権限の適用が本来趣旨を逸脱する構造
ひき逃げ被害者が保護名目で拘束された事例は制度の趣旨を大きく逸脱している。本来警察官職務執行法第3条は精神錯乱や泥酔によって自己や他人に危害を及ぼすおそれのある者を一時的に保護する規定である。しかし実際には犯罪被害者である人物に適用され留置場同様の保護室に収容され自由を奪った。このような運用は形式的には保護であっても実質的には逮捕と同質の強制力を伴うものであり刑事手続を経ることなく権利を制限する点で重大な問題をはらむ。被害者を加害者と同列に扱うような処遇は警察権限の逸脱を示しており制度設計の根幹を揺るがす。
被害者拘束と加害者釈放が示す不均衡
事件の経緯を詳細に説明した被害者が十八時間にわたり拘束される一方で加害者は解放された。この不均衡な対応は市民の目から見れば公正さを欠き警察の中立性に深刻な疑問を投げかける。負傷した被害者が自由を奪われる一方で加害者が責任を問われない構図は市民感覚とかけ離れており被害者保護の理念に反する。地方公務員法第33条は信用失墜行為の禁止を規定しており不公正な対応は組織全体の信頼を損なう行為と評価される。警察組織に求められるのは法の下での公平な対応であるがその根幹を裏切った結果社会に対する説明責任が一層重くのしかかる。
保護措置運用の社会的影響と信頼失墜
保護という名目で行われた拘束は実際には弁護士選任権もなく外部との連絡も断たれ食事の提供もない過酷な環境で行われた。さらに医師の診断を経れば措置入院へ移行する可能性も高く一度対象とされれば長期間の自由制限に発展する危険を含む。このような仕組みが被害者に向けられた場合市民社会における人権保障の基盤が揺らぎ制度全体への信頼が大きく損なわれる。地方公務員法第33条が定める信用失墜行為の禁止の観点から見ても今回の対応は市民の信頼を裏切るものであり権力の行使がいかに濫用的に見えるかを示している。保護が本来の救済ではなく人権侵害の手段と化す危険は社会問題として看過できない。
まとめ
ひき逃げ被害者が警察官職務執行法第3条を根拠に保護名目で拘束された事例は制度の趣旨を逸脱しており、実質的には逮捕に匹敵する強制力を伴うものであった。被害者が十八時間にわたり保護室に収容された一方で加害者は釈放されるという対応は公正さを欠き、市民から見れば著しい不均衡である。このような措置は地方公務員法第33条が定める信用失墜行為の禁止に照らしても市民の信頼を大きく損なう行為に当たり、警察組織全体の存在意義を揺るがす結果をもたらす。保護という名目の下で弁護士を呼ぶこともできず、外部との連絡も遮断され、食事も与えられない状況に置かれることは人権侵害に直結し、市民社会の基盤を危うくする。今回の事例は警察権限の濫用がどのようにして被害者をさらに傷つけ、信頼を失墜させるかを示すものであり、制度の透明性と適正運用の必要性を強く突きつけている。