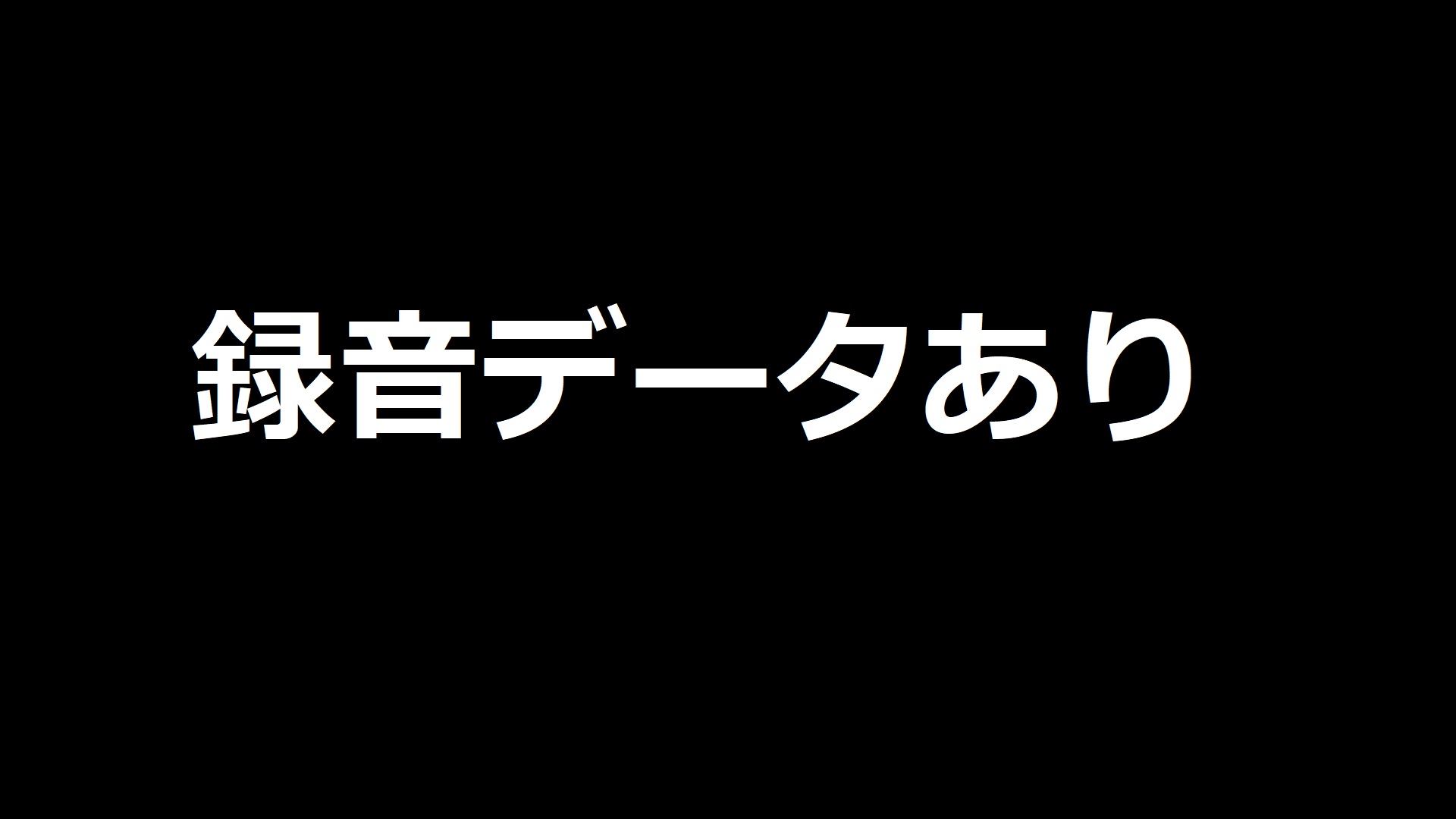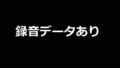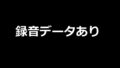2023年2月、東松山警察署による一連の対応は、被害者に大きな困難をもたらした。当初は交通事故として扱われていた事案が、実況見分や新たな情報によって事件性が明らかになるまでには、警察による不誠実な対応や圧力と受け取れる言動があった。保護という名目で18時間にわたり拘禁されたことや、生活安全課による圧力、さらには捜査過程における警察内部の対応の不透明さは、被害者としての立場を一層複雑にした。本記事では、これらの出来事を記録し、被害者として感じた警察対応の課題と、事件の進展について検証するものである。
東松山警察署の不誠実な初期の対応
- なしのつぶての東松山警察署にしつこく食い下がる
- 保護については生活安全課K氏で脅し
- 交通課による2度目の実況見分により事故ではなく事件へ 刑事課へ移送
なしのつぶての東松山警察署にしつこく食い下がる
被害者はまだ保護時の心の傷が癒えなく、また保護に対する恐怖心から東松山警察署に電話をすることをためらっていたが、なんとしてでも被害者として救済されたい、保護の不当性を晴らしたい、そんな気持ちで東松山警察署に連絡をしたのだと思う。
対応は基本的に一貫して東松山警察署交通課事故係係長。電話をして「折り返す」というので、待っていても連絡はない。先述の地域の法務局からメールで教えられた関東管区警察局に連絡をする。
関東管区警察局
埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館
電話 048-600-6000
担当者は非常にコミュニケーションの難しい人だったが、なんとか訴えかける。すると東松山警察署交通課事故係係長から電話が来る。また電話をする。折り返しの電話は来ない。関東管区警察局に電話をすると東松山警察署事故係係長から電話が来る。3回それを繰り返した。
あるとき東松山警察署交通課事故係係長と話していて、保護をされた話をすると、電話を切り、電話がかかってくる。
保護については生活安全課K氏で脅し
東松山警察署生活安全課K氏だ。「どうも、あの時の被害者です。制服を着ていた被害者です。金属探知機を持っていた被害者です」非常ににこやかに、丁寧な口調でありながら、被害者は感じた「脅しだ」と。つまり「あの時保護されて辛かったでしょ?精神病院に入院させられそうになって怖かったでしょ?」その目的であったかと思った。事件、事故現場からパトカーに乗って東松山警察署についたとき、パトカーの中から、あの目立った、見たこともないフォーマルな制服を着ていたり、事情聴取中に聴取室の外をウロウロと歩いていたり、最後には金属探知機を当てて印象づける。と被害者は考えている。
次の瞬間、生活安全課K氏は電話で絶句した。
「あの時の録音データがあるんです」
別に正しいことを行ったのであれば絶句する必要はないのである。
被害者は録音データの存在を伝えたからだと考えているが、それから少しづつ東松山警察署交通課事故係係長が話を先に進め始めた。その前に録音データについて、「公開してはいけない」旨の3つほどの法律を伝えられた。しかしそれはGoogle検索ですぐに、公開してはいけないのは警察側であって、被害者であったり市民側の話ではないことがわかり、東松山警察署交通課事故係係長にそのことを伝えた。
交通課による2度目の実況見分により事故ではなく事件へ 刑事課へ移送
東松山警察署交通課事故係係長はもう一度実況見分を行いたいという。被害者はすぐに”脅しだ”と感じた。とにかく事故をなかったものにしたいという東松山警察署の思惑を感じる。あの日2023年2月9日、東松山警察署の聴取室で事情聴取を受け、事件、事故の内容を話したところ保護されたのである。実況見分に行くということは、そこで事件、事故の状況を説明するということだ。それは聴取室での事情聴取と同じわけで、また保護をされる可能性も十分ある。
東松山警察署交通課事故係係長はこの頃になると、初期のおとぼけぶりからやや被害者を急かすような雰囲気になる。被害者は一応「保護の可能性」について係長に聞いた。東松山警察署交通課事故係係長によると、「今あなたと話していても被害者はなぜ保護されたのかわからない。今回の2回目の実況見分で保護するということはない」と言っていた。被害者は埼玉弁護士会の電話相談や法テラスの相談、東松山保健所など考えうるすべての連絡先に聞き「保護されないか?」を確認した。すべての連絡先で、結局かなわなかったが、「同行してもらえないか」という確認も取った。
事件、事故現場へ向かう。
まず早めに行って小型隠しカメラを設置した。確かな記憶ではないが、スマホ2台、タブレット1台、ボイスレコーダー1台というフル装備。すべての録音が開始されていることを確認した。
先について神社で待つ。
やがてクルマが現れ、交通課らしい制服を着た2名の警察官が降りてきた。被害者が近づくと東松山警察署交通課事故係係長はその方向から現れると想像していなかったのか、驚いたような顔つきをしていた。もう一人は若手のF氏。
何よりも東松山警察署交通課事故係係長が知りたかったのは、”犯人が被害者の手に気づいていたか、いなかったか”。気づいていれば故意。故意であれば事件であり担当は刑事課。気づかなければ過失。過失であれば事故であり担当は交通課。とのことだった。
※ちなみにこのことも被害者が「事件、事故」と表現している理由の一つだ。
パトカーではない警察の車両を事件、事故の発生現場にとめて、係長が乗る。リクライニングをいっぱいに倒し、被害者が手を入れる。
係長はそのまま前を向き「見えますよね」と言った。つまり犯人は特に意識をしなくても被害者の手が見えていたということだ。ちなみに被害者の記憶では、犯人は明らかに顔を向けて被害者の手を見た。犯人の顔色が変わったことを覚えている。
係長が「保護はしない」ということであったので、事情聴取の時と同じように、犯人に4年前から嫌がらせをされていたと言う話をしたが、係長は聞こうとはしなかった。
今考えてみると検察から入手した資料には事件当日の実況見分の写真があったことからこの実況見分が必要であったのかは疑問が残る。
ここでもう一つ疑問が生じる。事件、事故時に被害者は110番をしたのだが、その際110番の担当警察官に「ひき逃げです」と伝えている。しかし真っ先に来たのは東松山警察署刑事課のS氏である。
係長によると「ひき逃げは事故」とのこと(しかしのちに傷害罪でも救護義務違反は成立すること知る)。
また東松山警察署交通課事故係係長と電話連絡をする日々が続いた。初期の関東管区警察局に連絡をしないと電話をしてこないという不誠実さからは進展がみられ、約束の電話はかかっては来ないものの、電話をして不在であれば折り返しの電話はかかってくるようになった。
「署内で対応を検討中(刑事課と交通課)」とのことだった。
やがて係長から刑事課が担当することを告げられる。
被害者はこのことさえ”脅し”と感じていた。保護をしたのは東松山警察署刑事課の刑事だI刑事とS刑事。その刑事課が担当するというのだ。係長から「刑事課に電話をするように」と言われた。しかし刑事課は定時内しか電話を受け付けておらず、すぐにその場で刑事課と話をすることはできなかった。
被害者は逆にそれが脅しであるのであればと思い、東松山警察署の窓口受付時間の直前に、東松山警察署の近くまで行き、そこで電話をして「今すぐ行く」ということをやろうと思った。東松山警察署に電話をしてみると刑事課につないでくれたが、担当のT刑事がいないとのことで、T刑事から折り返し電話をするとのことだった。どのタイミングであったか、どういう状況であったか覚えていはいないが、その刑事課とのはじめのやり取りの中で刑事課のS刑事が出たことがあった。
S刑事は保護されたときの事情聴取の時とうって変わり、非常に丁寧かつ低姿勢であった。
またそのやり取りの中で先述のT刑事と違うT刑事とたまたま話す機会があったが、その際に「自分から近づいたんでしょ?」などと言われた。自分から近づいたからなんだと言うのだろうと疑問に感じた。自分から近づいた、また犯人に危害を加えようとしたのではなく、これまで4年間にわたり行われてきた嫌がらせを防ぐためにクルマの発進をとめるために手を入れたのだ。現に左手を入れ、その右手でスマホで110番をし、その110番は犯人に10メートル以上引きずられた際に吹き飛び、それでも110番通報の電話はつながっていたのだ。このT刑事も東松山警察署としての誤魔化し、また西入間警察署も含めた誤魔化しに加担しようとしての発言だったのだろうか。
結局こういう目にあって、何十人もの弁護士と話をしていくと、こういった司法というものにも自然と詳しくなっていく。結局最終的には裁判官の判断だ。被害者が近づいたり、手を入れたという行為が悪く過失相殺となっても、悪くて2対8、1対9、さらに手を入れた行為がまったく悪くないという弁護士もいる。
つまり最終的には裁判官の判断。手前で言えば検察が犯人を起訴とするか不起訴とするかである。警察など所詮検察の指示通りに捜査をすすめるだけで、何かを判断するというものではない。
疑いがあり逮捕ということができても、その後の判断は警察官ではない。その逮捕が誤りであったとしても何の咎めも受けない、
また逮捕さえできないとなると保護ということになるのだろうが、それはそもそも警察官職務執行法第3条に則ったものであるのかどうかという問題だ。
ただし今回の被害者がそうだが、保護という制度も知らず、警察官職務執行法第3条も知らず、わけのわからないうちに保護、18時間拘禁されて、2人の医師の措置入院判断、しかも当時の主治医は警察に丸め込まれ、東松山保健所の方が口添えをしてくれなければ精神病院に入院させられていたということも現実としてあるということは言っておきたい。
警察官の発言に関する法令
- 刑事訴訟法第47条(捜査の秘密)
- 国家公務員法第100条(守秘義務)
- 個人情報保護法第23条(第三者提供の制限)
- 憲法第13条(個人の尊重)
- 刑法第223条(強要罪)
- 国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)
刑事訴訟法第47条(捜査の秘密)
公判の開廷前は、捜査に関する書類その他の物件はこれを公開してはならない。但し、公益上の必要その他の事由により相当と認められる場合は、この限りでない。
国家公務員法第100条(守秘義務)
職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども、同様とする。
個人情報保護法第23条(第三者提供の制限)
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。ただし、以下の場合はこの限りではない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難なとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
憲法第13条(個人の尊重)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。
刑法第223条(強要罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対する害を加える旨を告知して人を脅迫し、又は暴行を用いて義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
専門家の視点
- 録音データの公開禁止についての発言
- T刑事の「自分から近づいたんでしょ?」との発言
録音データの公開禁止についての発言
警察が「録音データを公開してはいけない」と主張した点について、以下の法律が関係していると考えられる。
まず、刑事訴訟法第47条(捜査の秘密)には、捜査中の情報を公開することが事件の解明を妨げる場合に守秘義務が課される旨が規定されている。ただし、これは警察内部での秘密保持に適用されるものであり、市民が録音したデータの公開を直接禁止するものではない。次に、国家公務員法第100条(守秘義務)は、警察官を含む公務員が職務で知り得た秘密を漏洩することを禁じているが、市民側には適用されない。
さらに、個人情報保護法第23条(第三者提供の制限)は、個人情報を第三者に提供する際の制限を定めているが、これも被害者自身が自ら公開する録音データには適用されない。
以上から、警察が録音データの公開を違法と主張する場合、その法的根拠は警察内部の情報管理に関するものに限られ、市民の権利を制限する根拠とはならない。この発言が被害者に誤解を与えた場合、不適切な制約を課した可能性が指摘される。
T刑事の「自分から近づいたんでしょ?」との発言
T刑事の「自分から近づいたんでしょ?」という発言は、被害者に責任を転嫁する意図があると受け取られかねない問題発言である。この発言は被害者支援の観点から適切ではなく、法律上の観点からも以下の問題が考えられる。
まず、憲法第13条(個人の尊重)には「すべて国民は個人として尊重される」と規定されており、被害者が受けた嫌がらせや損害を軽視するような言動はこの精神に反している。また、刑法第223条(強要罪)は「暴行または脅迫を用いて人に義務のないことを行わせる行為」を禁じている。今回の発言は、被害者に過剰な心理的負担を与え、自身の行動が原因であるかのように受け取らせる意図がある場合、これに近い性質を持つ可能性がある。
さらに、警察官としての職務倫理に照らしても不適切である。国家公務員法第99条(信用失墜行為の禁止)は、公務員の職務執行における信頼性を損ねる行為を禁じている。T刑事の発言は、被害者が安心して捜査に協力する環境を損なう結果を招く可能性があり、これに抵触する懸念がある。被害者に責任を転嫁する発言は、適切な捜査を阻害し、被害者の権利侵害にもつながりかねない。
東松山警察署とは?完全ガイド
- 概要
- 歴史
- アクセス
概要
東松山警察署は埼玉県東松山市に位置し、地域の治安維持を担う重要な警察機関である。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までであり、土日祝日は基本的に受付業務を行っていない。この時間帯内に各種手続きを行う必要があるため、市民は事前にスケジュールを確認し、時間に余裕を持って訪れることが推奨される。主な業務には遺失物の届け出、各種証明書の発行、運転免許証の記載事項変更手続き、犯人被害の相談対応、交通違反の反則金納付などが含まれる。東松山警察署では来庁者がスムーズに手続きを行えるよう案内窓口を設けているが、混雑する時間帯には待ち時間が発生する可能性があるため、比較的空いている時間帯を狙って訪問するのが望ましい。また、事件や事故などの緊急対応は24時間体制で行われており、一般の受付時間とは異なるため、緊急時には110番通報または直接警察署に連絡することが必要である。受付時間外においても、一部の相談や手続きについては警察署の電話窓口で対応できる場合があるため、事前に確認するとよい。
歴史
東松山警察署の歴史は古く、地域の治安維持と安全確保を目的として設立された。埼玉県内の警察署の中でも、比較的早い時期に整備された警察機関の一つであり、長年にわたり地域住民の安心・安全を支えてきた。設立当初は小規模な警察機構としてスタートしたが、東松山市の人口増加と都市化の進展に伴い、管轄区域が拡大し、それに対応する形で業務内容も拡充されていった。特に昭和後期から平成にかけては交通事情の変化に伴い、交通違反の取り締まり強化や交通安全啓発活動が積極的に行われるようになり、交通事故防止のための取り組みが強化された。近年では、デジタル技術の導入により一部の手続きが効率化され、住民の利便性向上が図られているが、受付時間に関する課題は依然として残っている。警察署の歴史の中で、災害時の対応や犯人抑止のための施策も進められており、特に東日本大震災後には防災対策の強化が求められ、地域住民との連携を強化する取り組みが進められた。今後も警察署の役割は変化し続けるが、地域社会の安全を守るという使命は変わることなく続いていく。
アクセス(日本全国各地主要都市より)
①航空機でのアクセス
- 北海道(新千歳空港):新千歳空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 東北(仙台空港):仙台空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 北陸(小松空港):小松空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 中部(中部国際空港):中部国際空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 近畿(関西国際空港):関西国際空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 中国(広島空港):広島空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 四国(松山空港):松山空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 九州(福岡空港):福岡空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 沖縄(那覇空港):那覇空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 東武東上線で東松山駅へ
②新幹線でのアクセス
- 北海道(新函館北斗駅):新函館北斗駅 → 東京駅(東北・北海道新幹線)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 東北(仙台駅):仙台駅 → 東京駅(東北新幹線)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 北陸(富山駅・金沢駅):富山駅・金沢駅 → 東京駅(北陸新幹線)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 中部(名古屋駅):名古屋駅 → 東京駅(東海道新幹線)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 近畿(新大阪駅):新大阪駅 → 東京駅(東海道新幹線)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 中国(広島駅):広島駅 → 東京駅(東海道・山陽新幹線)→ 東武東上線で東松山駅へ
- 九州(博多駅):博多駅 → 東京駅(東海道・山陽新幹線)→ 東武東上線で東松山駅へ
③電車でのアクセス
- 東京駅 → JRで池袋駅 → 東武東上線に乗り換え → 東松山駅
- 首都圏各地からも東武東上線利用でスムーズに東松山へ
- 埼玉県内からなら車やバスも選択肢豊富で意外と行きやすい
- 休日は急行や快速を上手く使うと時短できるよ
④バスでのアクセス
- 東松山駅 → 松山神明町(路線バス)→ 徒歩約13分
まとめ
本記事では、警察官の発言や行動に関連する法律を検証し、その適法性と問題点を明らかにした。録音データの公開禁止に関する主張は、警察内部の守秘義務や情報管理の観点から説明されるべきものであり、市民側に適用される法的根拠がないことが確認された。このような誤解を招く発言は、市民の正当な権利行使を妨げる恐れがある。また、T刑事の「自分から近づいたんでしょ?」との発言は、被害者の責任を不当に追及するものであり、憲法第13条や国家公務員法第99条に反する可能性がある。
これらの問題点を通じて、警察が職務を遂行する際に被害者の心理的負担を軽減し、信頼を構築する姿勢が求められることが明らかになった。被害者の権利を尊重し、公正な捜査を進めるためには、適切な対応が重要であるといえる。