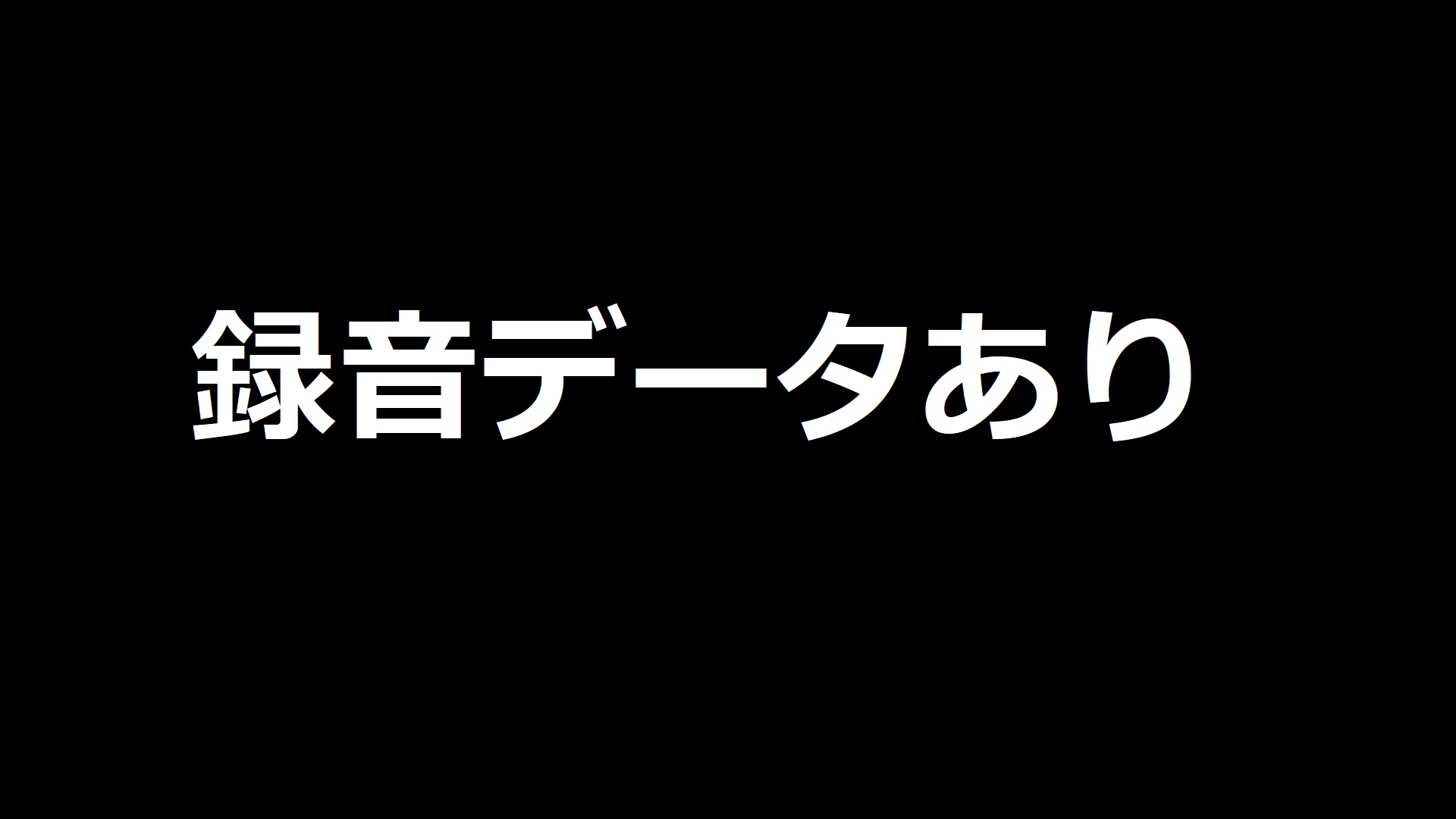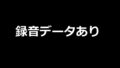警察官が黙秘の市民に対し繰り返し「話し合い」を強要する行為は、憲法第38条における自白強要の禁止、刑事訴訟法第197条第1項が定める暴行・脅迫の禁止、刑事訴訟法第34条による弁護人依頼権の保障および警察官職務執行法第2条の職権濫用禁止、さらに憲法第31条に掲げる適正手続保証という複数の法規制に抵触する可能性がある。このような取調べ慣行は被疑者の自主的意思を著しく損ない、心理的負担を増大させるだけでなく、司法制度全体への信頼を根底から揺るがす深刻な問題を孕んでいる。本稿では具体的な法令抵触の論点を明示し、取調べの録音録画義務化や外部監視委員会設置などの制度改革案を提示して、被疑者権利の確実な保障と捜査手続の透明性向上を図る方向性を検討する。
黙秘の市民に話し合いを強要する圧力警察官
- 経緯
- 黙秘の市民に話し合いを強要する圧力警察官
- 考察:黙秘の市民に話し合いを強要する圧力警察官
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定が交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
隣のご主人は「知らない」と答えた。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定は確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく夫人は言い返さないと気が済まない。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう、お決まりの反論が続く。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしているこちらが不当、不法な保護される危険性がある。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを持ってきた。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護され、精神病院への強制入院へ向かうか。それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院へ入院させられる。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであり、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物と考えないと危険である。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉を発したり、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
その後、もう一人の警察官がパトカーで現れ、隣人夫婦、町内会長、若い警察官の集団に加わった。しばらくすると、2人目の警察官がこちらに近づいてきた。
情報が伝達されているはずなのに、私がスマホで録画している様子に気づいた警察官は、
「ちょっとお話いいですか?」
「あっ、撮影ダメです」
「警察官の・・・、あの・・・、撮影やめてください」と話しかけてきた。
この言い方を聞くと、この時点でこの警察官は理解していたはずである。
警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”。
その後マウントを取って現場の支配権を強引に握ろうとする警察官は、スマホを手で遮って圧力をかけてくる。
黙秘の市民に話し合いを強要する圧力警察官
警察官同士で連携が取れていないのか、すでにはじめの警察官に「黙秘」を伝えているのにも関わらず、警察官は口を開かせようと強引に話しかけてくる。
なんで”おまわりさん”の話を聞かないのに、あなたの話を一方的に言うんですか?
(黙秘だからです)
お話にならないじゃないですか。話し合いにしましょうよ。
(「黙秘する」と言っています。この「話し合い」はここで初めて出た言葉であるが、最後まで「話し合い」をする前提とされている)
(仕方なく)「私は今、弁護士と連絡を取っていて、弁護士の連絡を待っています。私は何もしゃべる気はないです。弁護士と話をしたいのならしてください。以上です。それ以上何もしゃべりません。」
「弁護士を通して話してくださいって言うんじゃ、その弁護士からの電話はいつ来るんですか?それがわかんないとお話にならないですよね?」
(弁護士から電話があれば、貴方が弁護士と話すだけです。「それ以上は話しません」と言いました)
(相手方の家に入って、しばらくして警察官①と警察官②が出て来る)
弁護士さんからの連絡はなさそうですか?お話し合いって言うのは?
(「話し合い」と言ったのは貴方です。私は言っていません)
弁護士さん通してじゃなきゃできないんでしょ?
(「弁護士と話せ」と言っただけで、弁護士を通して「話し合い」をするとは言っていません。「話し合いにしましょうよ」と言ったのは貴方です)
連絡来ないですか?話し合いにならないですか?できないんですね?
(「弁護士と話せ」と言っただけで、弁護士を通して「話し合い」をするとは言っていません。「話し合いにしましょうよ」と言ったのは貴方です)
話し合いで今日来たんでしょ?
(誰がどこから「話し合いで来た」んですか?私であれば、私の家の前です。貴方であれば、私は黙秘しています)
でも結局○○さん話さないから、
(「黙秘する」と言いました)
話し合いにならないんで
(話し合いをするとは言っていません。「話し合いにしましょうよ」と言ったのは貴方です)
会話の流れを見ると、
1)警察官①に黙秘を伝える。
2)警察官②が、警察官①と連携が取れていて、黙秘の意志を把握しながら、黙秘の市民に話しかける。
※連携が取れているなら、市民は黙秘であることを認識している。黙秘であることを認識した上で、黙秘の市民に話しかけている。
3)警察官②は、黙秘の市民に「話し合い」を要求。
※黙秘であるから「話し合い」はできない。それなのに「話し合い」を要求している。
4)黙秘の市民が、たまりかねて、再度黙秘を伝える。
※警察官①と連携が取れているのであれば、黙秘の意志は伝わっている。黙秘なのに再度黙秘の意志を表明せざるを得なくなっている。もはや黙秘ではない。
5)警察官②は、それでも「弁護士からいつ連絡が来るか」と詰め寄る。
※当然黙秘なので話さない。黙秘の意志を認識しながら話しかける、質問をする。
(相手方の家に入って、しばらくして警察官①と警察官②が出て来る)
6)警察官②は、弁護士から連絡があったかを確認する。
※あればスマホを渡すし、なくても黙秘だから話さない。
7)警察官②は、「弁護士から連絡が来ないなら、話し合いにならないか?」と尋ねる。
※弁護士から連絡が来てないから黙秘。「話し合い」というのは警察官②の提案でしかない。
8)警察官②、「話し合いで今日来たんでしょ?」
※何を言っているのかわからない。「話し合い」は警察官②が提案しただけ。市民が「今日来た」ということなら、市民の家の前である。警察官②が「今日来た」というなら、警察官②が「話し合い」と思っているだけで、市民は「話し合い」などと一言も言っていない。
9)警察官②、「でも結局○○さん話さないから」
※終始一貫黙秘の意志を表明しているし、現に黙秘している。
10)警察官②、「話し合いにならないんで」
※黙秘の意志を表明しているし、「話し合い」は警察官②が提案しただけ。
考察:黙秘の市民に話し合いを強要する圧力警察官
このやりとりは、警察官が2名登場し、うち1名に対してはすでに市民が黙秘の意思を伝えている状況から始まっている。その後、別の警察官が市民に対して改めて言葉をかけ、「話し合い」を前提とした対話を求める展開となる。市民は再度、黙秘の意思を明確にし、「弁護士と連絡を取っている」「それ以上話すつもりはない」と発言しており、その後も一貫してその立場を変えていない。一方で警察官は「お話にならないじゃないですか」「話し合いにしましょうよ」「弁護士からの連絡はいつ来るんですか」などの表現で会話を試み、弁護士との連絡状況を繰り返し尋ねている。その後、現場での活動としては警察官が一時的に相手方の家屋内に入り、再び出てきた際にも同様のやりとりが繰り返されている。警察官は「話し合いで今日来たんでしょ?」という発言を行い、黙秘を続ける市民に対して「結局話さないから」「話し合いにならない」と述べており、終始「話し合い」を基準とした対応を続けている。これに対して市民側は、「話し合い」と言い出したのは警察官であり、自分はその前提に立っていないという立場を一貫して保持している。会話全体を通じて、警察官側は「話し合い」という言葉を中心に行動を進め、市民側は黙秘と弁護士との連絡待ちを根拠に応じないという構図が継続している。双方の前提が一致しないまま、対話の形だけが繰り返され、実質的な進展や意思の共有は見られない状況となっている。
関係する法令
- 日本国憲法第38条
- 刑事訴訟法第34条
- 刑事訴訟法第197条第1項
- 警察官職務執行法第2条
- 日本国憲法第31条
日本国憲法第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。自白は、これを強要によって得たときは、証拠とみなされない。
刑事訴訟法第34条
逮捕又は勾留された被疑者は、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。この場合において、司法警察職員は、正当な理由がなければ、弁護人の助力を受ける機会を奪ってはならない。
刑事訴訟法第197条第1項
司法警察職員は、暴行又は脅迫を加えて被疑者から供述をさせ、若しくは供述を修正させ、又はこれを抑留し、若しくは抑止し、その他自己に不利益な供述を強要するような行為をしてはならない。
警察官職務執行法第2条
警察官は、その職権を行使する場合において、法令の定める職権を逸脱し、又は濫用してはならない。
日本国憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命、自由又は財産を奪われない。また、刑罰は、法律の定める手続に従わなければ科せられない。
専門家としての視点
- 警察による黙秘権尊重の欠如がもたらす問題点
- 弁護人依頼権軽視の法的影響
- 威圧的取調べと職権濫用の法的評価
警察による黙秘権尊重の欠如がもたらす問題点
警察官が市民からの黙秘を繰り返し無視し「話し合い」を強要する行為は、憲法上保護された自由権の一角を成す黙秘権を侵害するものである。日本国憲法第38条は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。自白は、これを強要によって得たときは、証拠とみなされない。」と規定し、取調べ時におけるいかなる強制的手段も許されないことを明確に定めている。黙秘権の本質は被疑者・被告人が自己の利益を自ら判断する自主性を担保する点にあり、一度明示された黙秘の意思を無視して執拗に質問や説得を続けることは、自白強要と同視し得る違法行為である。取調べの適正性を規定する刑事訴訟法第197条第1項も「司法警察職員は、暴行又は脅迫を加えて被疑者から供述をさせ、若しくは自供述を修正させ、又は抑留し、若しくは抑止し、その他自己に不利益な供述を強要するような行為をしてはならない。」と明記しており、威圧的かつ執拗な呼びかけは厳格に禁止されている。これらの規定に照らし合わせると、警察が黙秘を明示した市民に対して「黙秘だから話し合いができない」という理屈を放棄し、一方的に「話し合い」を要求し続ける行為は、自白や供述を強要する違法な取調べ手法と評価され得るものである。これにより、捜査機関への不信感を招き、適正手続の根幹を揺るがす深刻な問題を生じさせる。
弁護人依頼権軽視の法的影響
警察官が被疑者の弁護人依頼の意思を示している段階で「弁護士からの連絡がないと話し合いにならないのか」などと詰問を続ける行為は、弁護人依頼権の保障を規定する刑事訴訟法第34条に抵触する可能性がある。第34条は「逮捕又は勾留された被疑者は、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。この場合において、司法警察職員は、正当な理由がなければ、弁護人の助力を受ける機会を奪ってはならない。」と定め、被疑者が弁護人を介して対応する意思を示した以上、警察は直ちにその機会を保障しなければならないと規定している。ところが、弁護人との連絡を待つ市民に対して弁護人経由での取調べを認めず、直接的な質問を繰り返すことは、弁護人の助力権を事実上封じる行為であり、司法手続の公平性を欠く重大な瑕疵となる。憲法第31条にいう「法律の定める手続によらなければ、その生命、自由又は財産を奪われない」という適正手続の原則にも反し、弁護人依頼権を軽視する捜査手法は、被疑者の防御権を不当に制限し、後に行われる審理全体の信用性を揺るがす結果を招く。
威圧的取調べと職権濫用の法的評価
同一の市民に対して警察官同士が連携しながら執拗に同じ質問を繰り返す行為は、警察官職務執行法第2条が禁じる職権濫用のおそれを帯びる。第2条は「警察官は、その職権を行使する場合において、法令の定める職権を逸脱し、又は濫用してはならない」と規定し、必要かつ相当な範囲を超えた心理的圧迫を排除することを求めている。さらに、刑事訴訟法第197条第1項の暴行・脅迫等の禁止規定とも相まって、威圧的取調べは明確に違法行為として禁止される。これらの法規は、被疑者が自発的かつ自由な意思で供述することを保障し、捜査機関の過度な権力行使を抑制するために制定されたものである。したがって、警察官が「話し合いで今日来たんでしょ?」といった執拗な問いかけや弁護士連絡の詰問を続けることは、職務の限度を逸脱し、必要性・相当性を欠く違法な捜査手法と評価され得る。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察取調べ文化と人権軽視の構造的問題
- 社会的信頼の低下と司法機関への不信感
- 黙秘権尊重の制度的保障の課題
警察取調べ文化と人権軽視の構造的問題
日本の警察取調べにおいて黙秘を表明した市民に対し繰り返し「話し合い」を強要する行為は、個人の自由と尊厳を軽視する構造的問題を示している。このような取調べ文化は権力と市民との間に過度な上下関係を生み、市民の自主的な意思決定を阻害する傾向がある。警察組織内で黙秘の意思を共有しつつも強引な質問を継続することで、取調べの透明性と公正性が損なわれ、被疑者の精神的負担が増大する。さらに、警察官の職務執行法や憲法に定められた基本的人権尊重の原則よりも内部慣行が優先されることで、違法な取調べ手法が黙認されやすい土壌が形成されている。この問題を放置することは警察への信頼を揺るがすのみならず、司法制度全体の正当性を損ねる深刻な社会問題となる。
社会的信頼の低下と司法機関への不信感
市民が黙秘権を行使しても警察が執拗に話し合いを強要する姿勢は、社会全体における司法機関への信頼を著しく低下させる。民主社会においては法の支配と権力の行使が適正に担保されることが前提であるが、市民が自己の権利を主張してもそれが軽視される事実が広く知られると、法の下の平等や適正手続への疑念が生じる。司法機関への不信感が拡大すると、被害を受けた市民が警察や検察への相談を躊躇し、犯罪被害の報告率が低下する懸念がある。結果として公権力による治安維持と市民の安全保障との間に大きなギャップが生まれ、社会全体の安心感が損なわれる。このような負の連鎖を断ち切るためには司法制度の透明化と市民参加型の監視メカニズムが不可欠である。
黙秘権尊重の制度的保障の課題
黙秘権の尊重を制度的に保障するためには、警察官や検察官に対する教育・研修の充実が求められる。現状では黙秘権の意義や法律上の位置付けが組織文化として十分浸透しておらず、「話し合い」を強要する取調べ手法が暗黙的に許容されている。これを是正するためには、法曹関係者や法学者、市民団体による定期的な検証と監査を導入し、違反事例を公表することで抑止効果を高める必要がある。また、録音・録画の義務化や外部立会人制度の拡充により取調べの可視化を進め、市民が安心して権利を行使できる環境を整備しなければならない。さらに、違反行為には明確な責任追及と処分を伴う法整備を行い、制度の実効性を担保することが急務である。
まとめ
警察官が市民の黙秘権を明確に行使しているにもかかわらず「話し合い」を繰り返し強要する行為は、日本国憲法第38条や刑事訴訟法第197条第1項が禁じる自白強要や暴行・脅迫に該当するおそれがある。また、弁護人依頼権を保障する刑事訴訟法第34条や適正手続を定めた憲法第31条にも違反する可能性が高く、警察官職務執行法第2条が規制する職権乱用のおそれも指摘される。このような取調べ手法は被疑者の心理的負担を著しく増大させるのみならず、司法制度への信頼を毀損し、犯罪被害の相談抑制や報告率低下といった社会的影響をもたらす。制度的改善策として取調べの録音録画義務化、外部立会人制度の拡充、定期的な教育研修や第三者監査の導入、違反時の責任追及強化が急務である。