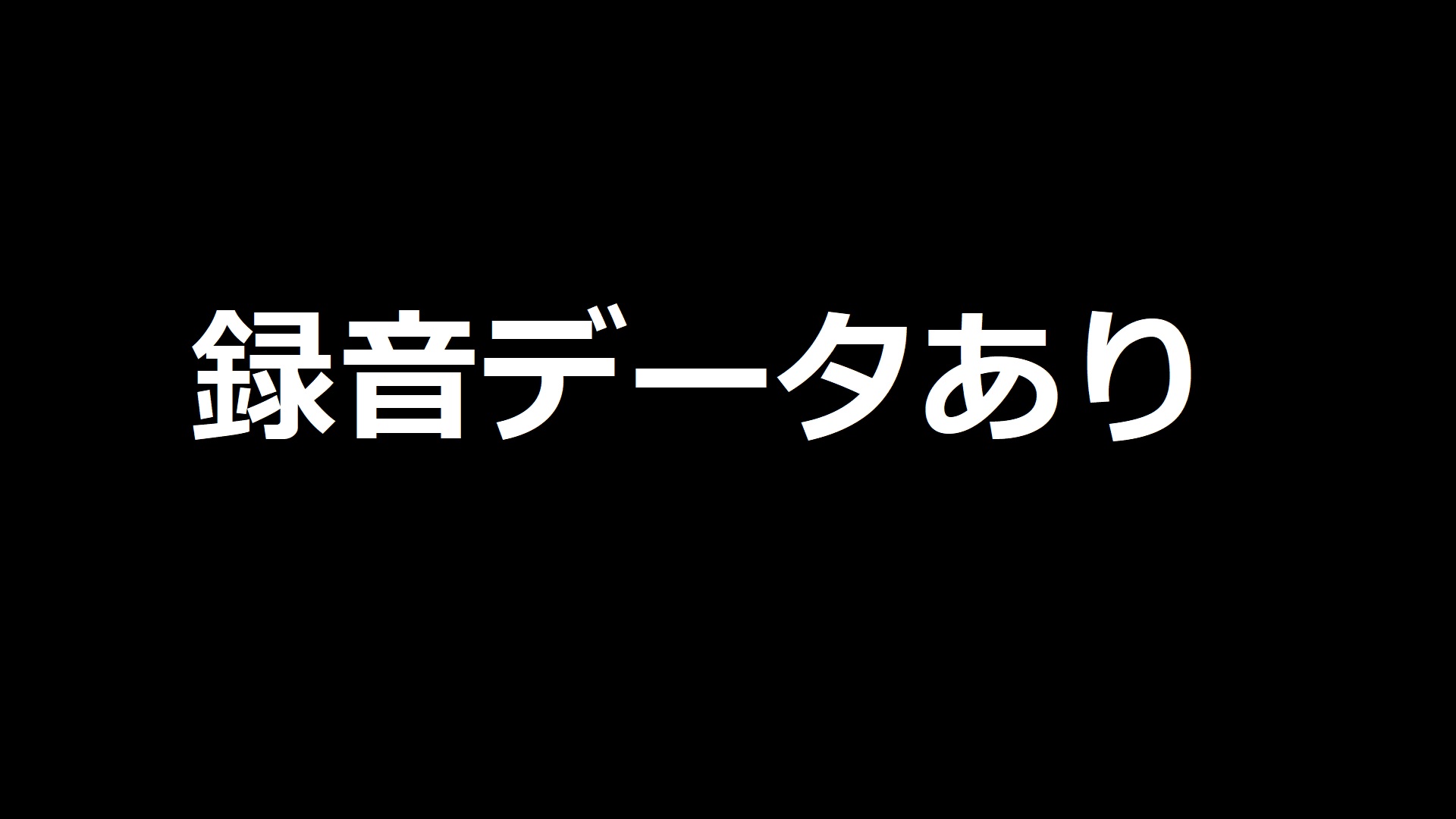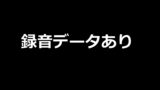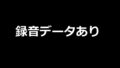警察官が装着するウェアラブルカメラの運用が、一部の都道府県警で先行して始まっている。透明性や証拠保全の名目で導入される一方、肝心の内規や利用目的の明示がないまま現場での運用が先行し、市民のプライバシー権や表現の自由を侵害する可能性が指摘されている。本稿では、法令・判例の観点からその違法性や社会的問題点を検証する。
警察官、撮影するな!で撮影してる?論理破綻の圧力警察官
- 経緯
- 警察官、撮影するな!で撮影してる?論理破綻の圧力警察官
- 考察:警察官、撮影するな!で撮影してる?論理破綻の圧力警察官
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定が交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
隣のご主人は「知らない」と答えた。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定は確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく夫人は言い返すさないと気が済まない。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう、お決まりの反論が続く。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしているこちらが不当、不法な保護される危険性がある。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを持ってきた。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護され、精神病院への強制入院へ向かうか。それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院へ入院させられる。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであり、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物と考えないと危険である。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉を発したり、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
その後、もう一人の警察官がパトカーで現れ、隣人夫婦、町内会長、若い警察官の集団に加わった。しばらくすると、2人目の警察官がこちらに近づいてきた。
情報が伝達されているはずなのに、私がスマホで録画している様子に気づいた警察官は、
「ちょっとお話いいですか?」
「あっ、撮影ダメです」
「警察官の・・・、あの・・・、撮影やめてください」と話しかけてきた。
この言い方を聞くと、この時点でこの警察官は理解していたはずである。
警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”。
その後マウントを取って現場の支配権を強引に握ろうとする警察官は、スマホを手で遮って圧力をかけてくる。
名前を連呼して、黙秘の意志を明確に示しているのにも関わらず、口を開かせようとする。
さらに、警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”知っていながら、「撮影やめてください」「撮影やめてください」と義務のない”命令”で圧力を強める。
やがて、仕方なく二度目の主張をした。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
警察官、撮影するな!で撮影してる?論理破綻の圧力警察官
この一連の出来事をYouTubeに投稿しようと編集していたところ、警察官の肩に装着されているカメラのような機器の存在に気がついた。
そこでGoogle検索を使って調べてみたところ、以下の記事を発見した。


(出典:jiji.com)
警察庁は17日、警察官が制服の胸部などに装着するウエアラブルカメラを来年度、一部の都道府県警で試験導入すると発表した。職務質問や交通違反の取り締まりなどの際、職務が適正に行われているか検証するのが主な目的という。
今後、運用要領を策定し、導入する警察を選定する。試行結果を踏まえ、全国での導入についても検討する。
運用案によると、対象となるのは、パトロールや職務質問に当たる地域警察官▽交差点などで交通違反を取り締まる警察官▽花火大会などの雑踏警備をする警察官。
撮影は任意の警察活動として行い、装着したカメラの赤いランプを点灯させたり、腕章を着けたりして相手に撮影していることを知らせる。場所は屋外や不特定多数が出入りする場所に限定。被害相談を受ける際や、個人宅に入る際などは撮影しない。
(出典:jiji.com)

(実際の対応警察官のウェアラブルカメラ)
撮影は任意の警察活動として行い、装着したカメラの赤いランプを点灯させたり、腕章を着けたりして相手に撮影していることを知らせる。場所は屋外や不特定多数が出入りする場所に限定。被害相談を受ける際や、個人宅に入る際などは撮影しない。
(出典:jiji.com)
記事内には上記の内規(まだ策定されていない)のような文言も見受けられるが、これまでの西入間警察署の対応を考えると、それを守るとは到底思えない。
つまり、「撮影やめてください、撮影やめてください、撮影やめてくださいって言っています警察官」
「お巡りさんに
2回くらい
言われましたよね」
と、東京高等裁判所 平成26年(ネ)第577号 平成26年10月29日判決、日本国憲法 第21条において、判例及び法令で、「一般市民が公務中の警察官を撮影することは、正当な行為である」と定められているのにもかかわらず、撮影の中止を強要。
一方、「警察官が公務中に市民を撮影する場合、原則として市民の同意は不要」ではあるものの、「撮影の目的が曖昧、または威圧・監視の意図が疑われるような場合」は、違法性を問われる可能性が極めて高いのにも関わらず、警察官が市民を撮影している。
また、「撮影は任意の警察活動として行い、装着したカメラの赤いランプを点灯させたり、腕章を着けたりして相手に撮影していることを知らせる。場所は屋外や不特定多数が出入りする場所に限定。被害相談を受ける際や、個人宅に入る際などは撮影しない。」という内規(まだ策定されていない)にも従っていない。
つまり、撮影はする。しかし撮影されるのは圧力で封じる。ということが見て取れる。
考察:警察官、撮影するな!で撮影してる?論理破綻の圧力警察官
この一連の出来事を第三者の視点から俯瞰すると、警察という公的機関が本来守るべき透明性と公平性の原則を自ら損なっている構図が浮かび上がる。
以下、その構造を冷静に考察する。
まず、市民がYouTube投稿に向けて映像を確認・編集する中で、警察官の肩に装着されたウェアラブルカメラの存在に気づいたことは、単なる偶然ではあるが、警察側の行動に対する市民の監視という重要な契機となっている。
その後に発見されたjiji.comの記事では、警察庁が一部の都道府県警においてウェアラブルカメラを試験導入し、今後全国導入も検討していることが明記されている。運用案には、撮影の範囲と方法について一定の指針が設けられており、具体的には赤いランプや腕章によって撮影中であることを知らせ、市民への不意打ちや秘密録画を避ける配慮がうかがえる。さらに、被害相談や個人宅での撮影は行わないとされている点からも、プライバシー保護と職務執行のバランスが意識された運用基準であることが読み取れる。
しかし、問題はその「内規(まだ策定されていない)」が現場レベルで適切に遵守されていない疑いが極めて濃厚であるという点にある。現場の警察官が市民に対して「撮影やめてください」と繰り返し要求している場面は、東京高等裁判所 平成26年(ネ)第577号判決や、日本国憲法第21条の趣旨と明確に矛盾している。これらは、一般市民が公務中の警察官を撮影することが正当な表現行為であることを確認したものであり、警察官の「撮影中止の強要」は、憲法の保障する表現の自由への干渉とみなされ得る。
さらに深刻なのは、警察官自身はウェアラブルカメラによる市民の撮影を実施しているにもかかわらず、同時に自らの撮影を拒む姿勢を見せているという、明白なダブルスタンダードである。しかもその撮影が、運用案にあるような「赤いランプの点灯」や「腕章の明示」などを行わずに、事前告知もない形で実施されているのであれば、それは内規(まだ策定されていない)違反であるだけでなく、市民に対する無通知・一方的な監視行為として、違法性が問われる余地も出てくる。
この構図は、「警察による撮影は正当である」「市民による撮影は妨害される」という、力関係に基づいた一方的な撮影権限の主張にほかならず、本来、行政機関としての中立性・公平性を保つべき警察が、自らの立場を利用して「撮る自由」と「撮られる拒絶」を恣意的に使い分けている様子が見て取れる。
総じてこの状況は、制度としての警察の正当性そのものが疑問視されかねない深刻な構造的問題をはらんでおり、単なる一現場の問題として片付けられる性質のものではない。市民の目からは、「撮影という手段を使った権力の行使と抑圧」という印象を与えかねず、信頼回復のためには、一貫したルールの明示と厳格な現場運用の徹底が求められる。これは単なる倫理や配慮の問題ではなく、憲法が保障する表現の自由と監視の正当性の、根源的な対立構造である。
関係する法令
- 個人情報保護法 第16条(利用目的の特定)
- 憲法第13条(個人の尊重・プライバシー権)
- 民法第709条(不法行為)
- 憲法第21条(表現の自由)
個人情報保護法 第16条(利用目的の特定)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用の目的をできる限り特定しなければならない。
憲法第13条(個人の尊重・プライバシー権)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
民法第709条(不法行為)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
憲法第21条(表現の自由)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
関係する判例
- 東京高等裁判所 平成26年(ネ)第577号(平成26年10月29日判決)
東京高等裁判所 平成26年(ネ)第577号(平成26年10月29日判決)
公務中の警察官を市民が撮影した行為について、裁判所は「撮影行為は違法でない」と判断し、警察官のプライバシー侵害の主張を認めなかった。市民の撮影行為は表現の自由の範囲内として保護されるとした。
専門家としての視点
- 利用目的が未特定の撮影は違法か
- 警察官の同意なき撮影行為におけるプライバシー侵害の構造
- 市民の撮影を制止する警察官の発言と憲法21条の抵触可能性
利用目的が未特定の撮影は違法か
個人情報保護法第16条は「個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、利用の目的をできる限り特定しなければならない」と規定しており、行政機関としての警察もこの義務を免れない。ウェアラブルカメラによる市民の撮影が実施される際、撮影行為それ自体が個人情報の取得にあたる場合、当該取得には利用目的の明示とその特定が事前に必要である。現実には警察庁の内規すら策定されていない段階で、現場の警察官が市民の容貌や言動を記録していたとすれば、それは利用目的の特定なき個人情報取得に該当し、違法性を有する。特に警察の活動は公的機関としての権限に基づくものであり、私人間の同意とは異なり、明確な法的根拠がなければ強制力は持たない。警察が撮影行為を遂行しながら、その目的や映像の扱いを市民に対して説明せず、明示的に同意も得ない状況で個人情報を取得すれば、それは個人情報保護法第16条違反となり、将来的に訴訟リスクや不服申し立ての対象となる。さらに、撮影された映像に保存・管理のルールが設けられていない場合には、第20条(安全管理措置)にも抵触する可能性がある。撮影機器の導入がモデル事業であれ、現場の執行が法令に準拠しない限り、行政処分としての違法性は免れず、制度設計が追いつかない段階での実施は法的にも極めて脆弱な立場に置かれている。
警察官の同意なき撮影行為におけるプライバシー侵害の構造
憲法第13条は「すべて国民は、個人として尊重される」と定め、人格権の核心としてプライバシー権が確立されている。警察官がウェアラブルカメラを用いて市民を撮影する行為は、仮に公共空間であったとしても、被撮影者の同意や撮影目的の明示がないままに一方的に記録を行えば、プライバシー侵害の構成要件に該当し得る。特に、赤色ランプや腕章の非表示などにより撮影されている事実を市民が認識できない状態で行われた記録は、外形的には通常の行動の延長であっても、内在的には監視行為として市民の自由行動に心理的制約を与えるものであるため、人格権の侵害として評価される。これに民法第709条が適用されるとすれば、「故意または過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、損害賠償の責任を負う」とある通り、違法な撮影によって精神的苦痛や不利益を受けた市民は不法行為に基づく損害賠償を請求する正当な根拠を有する。警察は公益目的を理由に行為を正当化するが、公益といえども憲法上の権利を制限するには明文の根拠と必要性・相当性の原則を満たさねばならず、それを欠いた撮影は違法である。市民の行動・発言が一方的に収集・蓄積される構造は、立法による明示的統制がない限り憲法13条に反する国家行為となる。
市民の撮影を制止する警察官の発言と憲法21条の抵触可能性
憲法第21条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と定め、撮影行為が公務員の職務を記録するものである場合には、この表現の自由の範囲に含まれる。東京高等裁判所平成26年(ネ)第577号判決では、市民が交番内で警察官を撮影した行為について、プライバシー侵害や業務妨害の主張は退けられ、「違法性は認められない」と明示されている。この判例は、市民が公務中の公務員を記録することは原則自由であり、それを制止するためには極めて限定的かつ明確な法的根拠が必要であることを示すものである。警察官が「撮影はやめてください」と繰り返すだけであれば、それ自体が物理的強制を伴わなくとも、威圧的態度や命令口調で発せられた場合には、事実上の圧力・抑圧と認定され得る。撮影の自由は表現の自由の中核に位置づけられ、言論・報道・監視といった機能的側面を有しているため、これを公権力が制限する場合は、その必要性と相当性を具体的に立証しなければならない。公務中の警察官が市民の撮影を制度的根拠なく妨げる発言を繰り返した場合、国家権力による違憲行為として構成される危険性が高く、裁量権の逸脱あるいは濫用として行政法的にも違法性を帯びる可能性がある。
専門家としての視点、社会問題として
- 運用基準なき監視機器の現場導入がもたらす構造的不信
- 警察による撮影と市民の撮影をめぐる権力関係の非対称性
- 行政の透明性を装いながら監視社会に傾斜する危険
運用基準なき監視機器の現場導入がもたらす構造的不信
警察官が装着するウェアラブルカメラは、もともと証拠保全や職務適正化を目的として期待される技術であるが、その導入が明確な法的枠組みや内規を欠いたまま現場で先行して実施されている現状は、社会的に看過できない重大な構造的不信を生んでいる。特に問題となるのは、警察庁が「運用要領を今後策定する」としていながら、地方の現場レベルで既に録画運用がなされている点であり、これは行政の説明責任と手続的正当性を根本から欠く状態である。警察による市民の撮影は、表面上は任意の職務執行であると装いながら、実態としては法的手当てのない状態で個人情報を収集・保管し、管理対象として市民を取り込むことに等しい。これにより、監視機器の技術的発展が市民の自由を静かに制限し、常時記録されているという感覚が日常生活の行動や発言に対する自己抑制(チリング効果)を引き起こす。本来、監視技術の導入は、制度設計が先行しなければならないが、現在の順序は明らかに逆であり、民主的統制を受けるべき警察権力が、技術という手段を先に握り、市民がそれを後から追認させられる構造は極めて危うい。これは制度の不備ではなく、構造的な責任回避とみなされるべきであり、立法機関による緊急の制度的介入が求められる。
警察による撮影と市民の撮影をめぐる権力関係の非対称性
現代社会において、撮影は情報の記録手段であると同時に、権力の行使手段でもある。公務中の警察官が市民を撮影する一方で、市民がその様子を撮影しようとした際に「やめてください」と制止されるような場面が多発しているとすれば、そこには明確な非対称的権力関係が存在している。警察による撮影は、証拠保全の名目の下で合理化されるが、市民の撮影は秩序妨害や名誉毀損といった枠組みに押し込められ、潜在的に違法視される傾向がある。だが憲法第21条が保障する表現の自由は、市民による公権力の監視行為を明確に含んでおり、市民が公務員の行動を記録することは違法ではないという判例も存在する。それにもかかわらず、現場では警察官が市民のカメラに対して強い反発を示し、場合によっては威圧的に制止するという事実があるならば、それは表現の自由に対する実質的な抑圧と解されるべきである。このような状況が常態化すれば、市民は公権力を可視化する機会を失い、片方向的にのみ「記録される側」に立たされることになる。それは監視と自由の均衡を根本から破壊するものであり、制度上の規律が存在しない現場対応を警察権の拡張と認識せざるを得ない。
行政の透明性を装いながら監視社会に傾斜する危険
行政がウェアラブルカメラの導入を「透明性の確保」や「職務適正化」として打ち出す一方で、実際にはその映像が内部管理され、一般市民のアクセスや照会が一切担保されていないのであれば、それは透明性の仮面をかぶった閉鎖的監視体制である。映像は一方通行で収集され、市民がそれに反論したり異議を申し立てたりする手段が存在しない状況では、行政に都合の良い記録だけが残り、反証の機会が制度上排除される。市民の行動が常に撮影され、記録されるという構造のもとで、警察だけが映像を所有し、その使用や廃棄を恣意的に管理できる状況が放置されることは、明確な情報の非対称性を生み出す。さらに、こうした映像は将来的に誤用、漏洩、あるいは不当利用の温床ともなり得るが、制度上の外部監査や独立機関による検証がない限り、それを抑止する手段も存在しない。現時点ではモデル事業と称して段階的導入が進んでいるが、その裏で映像収集の常態化と記録による行動監視が日常生活に組み込まれつつある。このような傾向が制度的に放置されれば、社会全体が「記録されることを前提とした行動様式」へと変質し、表現の自由や行動の自由が無意識のうちに制約を受ける構造が固定化する。
まとめ
警察官がウェアラブルカメラを用いて市民を撮影する運用が、一部の現場で既に開始されているにもかかわらず、その根拠となる内規は未策定であり、撮影された映像の利用目的や管理方法も明示されていない現状は、個人情報保護法第16条が求める「利用目的の特定」に反する可能性が高い。また、撮影の際に市民の同意を得ず赤ランプや腕章による告知も行われていない場合には、憲法第13条に基づくプライバシー権の侵害と評価され、民法第709条により不法行為責任を問われることも想定される。一方、市民による警察官の撮影は憲法第21条で保障されており、東京高裁平成26年判決により適法性が明示されているにもかかわらず、現場ではその行為を制止しようとする発言が繰り返されている。こうした一方通行的な撮影体制は、監視する側とされる側のバランスを崩し、表現の自由の実質的な抑圧を生む構造となっている。制度整備が追いつかない段階で技術だけが現場運用されている現状は、権力行使の不透明さを生み出し、行政の信頼性を根底から揺るがす要因となる。