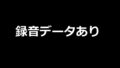防犯カメラはこれまで主に犯罪の証拠確保や犯罪抑止の手段として扱われてきたが、公務中の警察官の行動についても客観的に記録される装置として機能している。この視点が広がれば、防犯カメラの社会的意義は大きく変化する。今回の事例では、スマートフォン映像と防犯カメラ映像を比較・同期することで、警察官の接近行動や発言の正確な記録が確認され、市民の主張の裏付けとなっただけでなく、記録の存在そのものが警察官に対する抑止力としても作用していたことがわかった。これは単なる証拠装置ではなく、公権力の行使が可視化される時代の要請である。
防犯カメラは警察官にも有効か?
- 経緯
- 防犯カメラは警察官にも有効か?
- 考察:防犯カメラは警察官にも有効か?
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定が交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
隣のご主人は「知らない」と答えた。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定は確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく夫人は言い返さないと気が済まない。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう、お決まりの反論が続く。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしているこちらが不当、不法な保護される危険性がある。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを持ってきた。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護され、精神病院への強制入院へ向かうか。それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院へ入院させられる。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであり、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物と考えないと危険である。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉を発したり、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
その後、もう一人の警察官がパトカーで現れ、隣人夫婦、町内会長、若い警察官の集団に加わった。しばらくすると、2人目の警察官がこちらに近づいてきた。
情報が伝達されているはずなのに、私がスマホで録画している様子に気づいた警察官は、
「ちょっとお話いいですか?」
「あっ、撮影ダメです」
「警察官の・・・、あの・・・、撮影やめてください」と話しかけてきた。
この言い方を聞くと、この時点でこの警察官は理解していたはずである。
警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”。
その後マウントを取って現場の支配権を強引に握ろうとする警察官は、スマホを手で遮って圧力をかけてくる。
防犯カメラは警察官にも有効か?
この一連の出来事について動画作成及び検証を重ねてきたが、ふと「防犯カメラにも写っているのでは?」と気づき、防犯カメラの録画を確認してみた。防犯カメラの録画映像には一部始終が撮影されていた。今回の動画はスマホの動画と防犯カメラの動画を同期させたものだ。
もちろん先述のとおりスマホでの撮影は行っていたが、スマホでの撮影が主観的と捉えられやすいと思われる一方、防犯カメラは客観的、第三者目線、俯瞰的であるのではないだろうか。
警察官の発言は当然どちらからであっても同じであるが、行動は市民自らに向かってくる警察官、詰め寄る警察官と、客観的に市民に近づいていく警察官、詰め寄る警察官というように違う視点を観察することができる。
このことは、市民にとっての証拠としての映像だけでなく、固定カメラ(防犯カメラ)の存在が警察の行動抑止力になる可能性を感じさせる。
「防犯」とは本来すべての不当行為から身を守る手段であり、それが警察官であっても例外ではないということだと思う。
防犯カメラは一方的に市民を監視するものではなく、公務員の不適切な行為を抑止・記録する「対抗証拠」としても機能すると言ってもいいのではないだろうか。つまり記録する「対抗証拠」としても機能するということだ。
「防犯カメラは警察官にも有効である」と確信したという主観的結論である。
考察:防犯カメラは警察官にも有効か?
防犯カメラは、一定の位置に固定され、人物の意図や動きを伴わずに自動的かつ継続的に映像を記録する装置である。この録画機能は、撮影者の感情・立場・意図が一切介在しないという点において、記録手段としての中立性を備えている。また、映像は時間軸に沿って保存され、再生時には改変がなく、事象の経過・人物の動き・相対的な距離感などを検証可能な状態で示す。これらの機能は、防犯カメラが証拠性の高い記録手段として扱われる根拠となっている。
今回の事例では、防犯カメラが警察官の接近行動、位置関係、距離の変化、滞留時間などを継続的かつ明確に映しており、映像は警察官自身の発言とも一致している。特定の主張に依存せず、映像を見た第三者が事実関係を判断可能な情報が含まれていることから、その記録は信頼性のある客観的資料と認められる。また、行動の記録が残ることで、警察官が現場で取る態度や物理的接触の有無についても、後日検証が可能となる。
これにより、防犯カメラは民間人だけでなく、警察官の行動も同等に記録対象とし、後の検証や評価に用いることができる。事実として、防犯カメラはその場に存在する全ての人物の行動を平等に記録するため、対象者の職務や身分に関係なく、記録の適用範囲は等しい。したがって、防犯カメラが警察官の行動に対しても有効に機能していることは、構造的・技術的・運用上の性質から明確である。
以上により、客観的に見て「防犯カメラは警察官にも有効である」と断言できる。これは装置の仕組み、記録の性質、映像の検証可能性、対象者の限定なき記録対象化という事実の積み重ねにより導かれる、客観的結論である。
関係する法令
- 刑事訴訟法 第197条 第1項
- 刑法 第130条(不退去罪)
- 地方公務員法 第32条(信用失墜行為の禁止)
- 国家公務員倫理法 第3条(基本理念)
- 刑事訴訟法 第189条(検察官の捜査義務)
- 警察法 第36条(監察制度)
- 刑法 第193条(特別公務員職権濫用罪)
刑事訴訟法 第197条 第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人、証拠等を発見するため、必要な捜査をすることができる。
刑法 第130条(不退去罪)
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
地方公務員法 第32条(信用失墜行為の禁止)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
国家公務員倫理法 第3条(基本理念)
国家公務員は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、その職務の遂行に当たっては、職務に対する国民の信頼を損なうことのないようにしなければならない。
刑事訴訟法 第189条(検察官の捜査義務)
検察官は、犯罪があると思料するときは、捜査をしなければならない。
警察法 第36条(監察制度)
警察庁に監察官を置き、都道府県警察に係る業務について、必要な監察を行うものとする。
刑法 第193条(特別公務員職権濫用罪)
裁判、検察若しくは警察の職にある公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
専門家としての視点
- 防犯カメラ映像の証拠能力と刑事訴訟法における適用可能性
- 警察官による接近行動の法的限界と職権濫用の成否
- 防犯カメラがもたらす抑止効果と地方公務員法上の義務
防犯カメラ映像の証拠能力と刑事訴訟法における適用可能性
防犯カメラによって得られた映像記録は刑事訴訟法において証拠としての性質を備えている。特に刑事訴訟法第197条第1項は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人、証拠等を発見するため、必要な捜査をすることができる」と規定しており、証拠の収集過程において違法性がない限りその資料は捜査における有効な構成要素となる。防犯カメラは撮影者の恣意的な介入が存在せず、定点で継続的に映像を記録するという技術的特性から、記録内容に対する中立性・連続性・客観性が確保されており、刑事手続きにおける信頼性の高い証拠資料として活用される場面が多い。実務上も、被疑者の行動を明確に示す証拠映像が存在する場合、供述証拠の裏付け資料または供述と矛盾する事実資料として重視される。例えば、警察官が市民に接近する場面やその際の言動、接触の有無、距離感、周囲の状況などが明確に記録されている防犯カメラ映像は、その行動の正当性や必要性を検証する上で重要な判断資料となりうる。また、その記録が継続的で編集の痕跡がない限り、映像資料の信憑性を争う余地は乏しい。したがって、警察官による公務執行に対する市民側からの疑義が生じた際に、当該現場の防犯カメラ映像が存在するならば、それを証拠として収集・保全することは刑事訴訟法上の正当な捜査行為に該当し、それを無視・未提出・黙殺することは刑事訴訟法189条「検察官は、犯罪があると思料するときは、捜査をしなければならない」に反する捜査不履行としての問題を孕む。このように、防犯カメラ映像は証拠収集の面においても刑事訴訟法上の実効的根拠を持っており、警察官の行動に対しても法的評価を下すための客観的資料として十分に活用されるべきである。
警察官による接近行動の法的限界と職権濫用の成否
警察官が公務中に市民に対して接近し、距離を詰める行動は、その目的と方法、状況に応じて法的評価が分かれる。刑法第193条は「裁判、検察若しくは警察の職にある公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する」と定めており、警察官が本来許容されている職務範囲を超えて、市民に対して不必要かつ威圧的な行動を取った場合、これに該当する可能性がある。特に、防犯カメラ映像により、その接近が一方的であり、また発言や表情、身体の動きなどが威圧的であったことが記録されていれば、それは「職権の濫用」にあたる実質的根拠となり得る。刑事訴訟法第197条第1項が規定する捜査権限も、任意捜査においては市民の意思を尊重しなければならず、これを逸脱して行動の自由を事実上制限するような態度をとった場合、それは違法捜査として評価される可能性が高い。さらに、刑法第130条が定める不退去罪との関連において、警察官が市民の明示・黙示の意思に反して長時間その場に滞留し続けた場合、私有空間またはそれに準ずる場において不法に居座ったと見なされるリスクもある。これらはすべて、映像記録という客観資料によって裏付け可能であるため、警察官の行動が職務の範囲内であったか、あるいはその職権を超えたものであったかを明確に判断する基礎資料となり、防犯カメラの記録が果たす法的意義は極めて大きい。
防犯カメラがもたらす抑止効果と地方公務員法上の義務
防犯カメラの存在は、単に事後的な検証資料としての役割にとどまらず、現場での行動に対する抑止力としても機能する。特に警察官のように強い権限を行使する立場の公務員においては、自らの行動が記録されているという認識が不適切な言動を抑制する効果を持ちうる。地方公務員法第32条は「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と規定しており、公務員は常にその行動が社会的に見られていることを前提に職務を遂行しなければならない。さらに国家公務員倫理法第3条においても「職務に対する国民の信頼を損なうことのないようにしなければならない」とされており、記録の有無にかかわらず、職務中の態度には厳格な注意義務が課されている。したがって、防犯カメラが設置されている場面において、公務員がその存在を意識せず、通常の注意義務を怠った結果として市民に不安・威圧・不信を与えるような態度を取った場合、映像の存在はその行為を裏付ける証拠となると同時に、当該職員が自らに課された職務倫理を軽視した証左ともなり得る。警察官が防犯カメラに自らの不適切行動を記録された場合、それは職務違反とされるだけでなく、監察対象としての法的根拠を構成し、警察法第36条に基づく監察制度の適用が妥当となる。結果として、防犯カメラは記録装置であると同時に、公務員の行動に対する制度的な牽制装置としての役割を果たしうることが、法令上からも明確である。
専門家としての視点、社会問題として
- 防犯カメラ映像の公的活用と透明性確保の制度的不備
- 警察権行使の検証装置としての映像記録の不平等な運用
- 映像記録の存在が公務員の行動に与える社会的抑止力
防犯カメラ映像の公的活用と透明性確保の制度的不備
近年、公共空間に設置された防犯カメラの映像が刑事事件の立証や事故の原因解明において有効に機能する一方で、その活用にあたっての制度的透明性が極めて乏しいことが社会問題として浮上している。防犯カメラの映像は一方では「証拠」としての価値を持ちながら、他方では恣意的な運用、特に行政機関や警察に都合の良い場面だけが切り取られ、開示される傾向がある点が問題である。とりわけ、警察官自身の行動が撮影されている場合、当該映像が外部に公開されないまま内部処理にとどまり、監察・検証・説明責任の実効性が確保されていないという実態は看過できない。情報公開制度の枠組みにおいても、防犯カメラ映像の開示請求はプライバシーや公務執行妨害等の名目で拒否される例が多く、市民が警察官の行動を外部から客観的に検証する機会を著しく制限している。これは「行政に対する信頼性の確保」という近代的行政の基本理念に反し、むしろ市民と公的権力との間に不信の壁を築く要因となっている。また、法的にも、防犯カメラ映像の管理・保全・提供に関する統一的な規範が存在せず、各都道府県警察が独自の運用方針を設けているのが現状である。このような運用の恣意性と非公開性は、透明性原則に基づく民主的統治の原則と明確に衝突しており、特に警察官が市民に対して権限を行使した場面については、少なくとも当事者および監察機関が映像を検証できる制度設計が不可欠である。透明性確保の観点から、防犯カメラ映像は行政文書として一元管理されるべきであり、その保存期間、改ざん防止措置、開示要件を法令レベルで整備する必要がある。このような制度的基盤が欠如している現状は、映像の存在が証拠として機能し得る一方で、不当な権力行使の温床ともなり得る社会的リスクを内包している。
警察権行使の検証装置としての映像記録の不平等な運用
防犯カメラやスマートフォンなどによって現場の様子が映像として記録される事例が増加する一方、それらの映像が警察官の行動に対する検証手段として適切に機能していない点が構造的な問題である。一般市民による撮影は監視の手段として評価される一方で、警察側の保有する映像記録は捜査上の理由、プライバシー保護、公務の円滑な遂行といった名目の下、公開されることは極めて稀であり、明らかに運用が不平等である。例えば、警察官が市民に接近・詰問・接触する様子が映像に記録されていても、それが市民からの苦情に基づく証拠として採用されないケースがあることは、既に複数の報道や判例によって確認されている。これは、映像の「記録性」よりも「運用主体」がその活用範囲を支配している実態を示しており、警察という行政権力の内部で記録された映像が、外部の監視や是正のツールとして用いられていないという点で、証拠資料としての公平性が損なわれていると言える。とりわけ、事件性が明確でない接触事案や、公務執行妨害などの判断においては、映像の存在そのものが恣意的に黙殺される傾向にあり、これが警察権の行使に対する客観的検証の障壁となっている。記録媒体の存在が行動の正当性を支えるどころか、逆に運用側の裁量によって情報が遮断され、警察官による違法行為の立証が困難になる構造は、社会的にも深刻な問題である。これを是正するためには、映像が存在する限り、その存在自体を申告・記録する制度の導入と、映像の提供・保存・開示に関する運用基準を外部機関が監査可能とする仕組みが必要である。
映像記録の存在が公務員の行動に与える社会的抑止力
映像記録、特に防犯カメラや市民のスマートフォンによる動画は、現代社会において単なる記録手段を超え、現場における行動の抑止力として機能するようになっている。警察官のように強い公的権限を持つ者が、その行使を行う際に録画されているという状況は、行動に対する抑制的効果を生む。これは制度設計や法制度に基づく制約ではなく、社会的・心理的な制御である点において注目される。警察官が防犯カメラの存在を知りつつ、市民に接近・詰問・接触した場面が記録されていたとすれば、その行動の正当性や適法性が後に検証される可能性を常に意識せざるを得ず、そのこと自体が不要不急な介入や威圧的な態度を防止する効果を持つ。こうした抑止効果は、地方公務員法第32条が規定する「職の信用を傷つけてはならない」という条文とも連動し、公務員が社会的に監視されていることを前提に職務を遂行すべきであるという原則を支える根拠ともなる。市民からの視線、メディアの報道、SNS上での拡散など、映像の波及力は既に制度外のチェック機能として定着しており、逆に映像が存在しなければ一部の違法行為は黙認・隠蔽されかねないという社会的不安を生んでいる。こうした状況において、防犯カメラは単に「防犯」装置ではなく、「抑権」装置としても機能しており、その存在が公務員の行動全体を規律する間接的な法的拘束力となりつつある。公務員、とりわけ現場対応に携わる警察官がこの現実を認識し、自らの行動が常に記録・検証・拡散の対象となることを理解することが、公的権力に対する信頼を維持する最低限の条件となっている。
まとめ
防犯カメラの存在はこれまで主に犯罪抑止や証拠収集といった目的で語られてきたが、公務中の警察官の行動に対しても同等に有効であるという点はあまり論じられてこなかった。実際にスマートフォンによる主観映像と防犯カメラによる固定映像を比較した結果、警察官の接近行動や発言が異なる視点で客観的に記録されていたことから、防犯カメラは事実確認における公平な資料として機能することが明らかになった。またその存在は、警察官自身の行動に対する抑止力としても作用するため、市民に対してだけでなく、権限を持つ側の行動にも間接的に制約を加える装置としての意味を持つ。映像があることで、その場に居合わせなかった第三者でも後から検証可能となり、主張の正当性を裏付ける材料ともなり得る。記録媒体としての性質において、防犯カメラは主観の混入を排除し、位置や時間が特定可能な証拠を提供するという点で、非常に高い信頼性を有する。したがって、防犯カメラは警察官による公務執行の適法性を可視化し、市民の権利保護にも寄与する制度的要素として、今後ますますその意義が問われることになる。