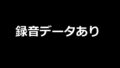警察官の現場対応は中立性と迅速性が求められる一方で、実際には「喧嘩両成敗」や「通報者優位」、「高齢者優位」、「多数優位」といった処理傾向が日常的に存在している。これらの傾向は、一見場を穏便に収めるための手法に見えるが、刑事訴訟の基本原則に照らせば重大な逸脱であり、加害者と被害者の峻別、供述の中立的評価、属性に依らない対応という基本が破壊されていることを意味する。制度疲労ともいえるこの構造的問題を直視し、今後の改善の糸口とする必要がある。
警察官の喧嘩両成敗、通報者優位、高齢者優位、多数優位について考える
- 経緯
- 警察官の喧嘩両成敗、通報者優位、高齢者優位、多数優位について考える
- 考察:警察官の喧嘩両成敗、通報者優位、高齢者優位、多数優位について考える
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定が交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
隣のご主人は「知らない」と答えた。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定は確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく夫人は言い返さないと気が済まない。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう、お決まりの反論が続く。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしているこちらが不当、不法な保護される危険性がある。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを持ってきた。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護され、精神病院への強制入院へ向かうか。それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院へ入院させられる。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであり、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物と考えないと危険である。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉を発したり、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
その後、もう一人の警察官がパトカーで現れ、隣人夫婦、町内会長、若い警察官の集団に加わった。しばらくすると、2人目の警察官がこちらに近づいてきた。
情報が伝達されているはずなのに、私がスマホで録画している様子に気づいた警察官は、
「ちょっとお話いいですか?」
「あっ、撮影ダメです」
「警察官の・・・、あの・・・、撮影やめてください」と話しかけてきた。
この言い方を聞くと、この時点でこの警察官は理解していたはずである。
警察官が“公務で撮影されても文句を言えないことを”。
その後マウントを取って現場の支配権を強引に握ろうとする警察官は、スマホを手で遮って圧力をかけてくる。
警察官の喧嘩両成敗、通報者優位、高齢者優位、多数優位について考える
すでに2023年2月9日のひき逃げ事件、保護問題も含めて、警察官のトラブル対応は、喧嘩両成敗、通報者優位、高齢者優位、多数優位だということについては認識していた。
今回の近隣トラブルについても、警察官のトラブル対応が、喧嘩両成敗、通報者優位、高齢者優位、多数優位になることはおおよそ想定していたし、予想通りであった。
結果的に案の定予想通りの結果となった。
1人目の警察官は、最初に相手方に近づき話を聞く。そしてこちらに来る。
2人目の警察官は、まず1人目の警察官と話をする。その後”隣人が呼んだ”町内会長と話し込む。そして隣人と話し込む。
”十分に集団に取り込まれ”、偏った意見、考え方を吸収した上で、”単独の市民”に近づいてくる。
「撮影禁止」を手掛かりに、黙秘を貫く”単独の市民”の口を開かせることに注力し、”話し合い”に持ち込もうとした。
考察:警察官の喧嘩両成敗、通報者優位、高齢者優位、多数優位について考える
本件は、過去に複数回の警察対応を経験した当事者が、警察官の現場対応に対して一貫した傾向を認識・記録していたという経過を前提としている。
2023年2月9日のひき逃げ事件および保護事案など複数の事案を通じて、「喧嘩両成敗」「通報者優位」「高齢者優位」「多数優位」といった傾向が制度的または慣習的に存在すると見なしていたことが文中に明示されている。
今回の近隣トラブル発生時にも、その傾向が再現されることを当事者は事前に想定しており、結果的にそれに近い対応がなされたと受け止めている。現場に到着した警察官の行動順序(1人目が相手方から聞き取り、2人目が町内会長および隣人と先に接触)を時系列で記述しており、これは「警察官がすでに集団側と接触・調整を済ませたうえで、単独の市民に接触してきた」という構造の再確認につながっている。
また、当該市民が黙秘姿勢を維持するなかで、警察官が「撮影禁止」という論点を契機に接近し、「話し合い」の枠組みに引き込もうとした行動が観察されている。この点は、当事者が「構造的な誘導」と見なしているが、俯瞰的には「警察官が複数の関係者と接触しながら、全体の状況を整理しようと試みた」とも読み取れる。ただし、聞き取りの順序や滞在時間の偏りがあることから、「集団側との関係性の強さ」が疑念として記録されていることも事実である。
総じて、本記録は当事者による一貫した観察と、過去経験を踏まえた行動予測の的中を示しており、個別事象にとどまらず、一定の処理傾向の存在を裏付ける主観的証拠として機能している。
関係する法令
- 刑事訴訟法第1条
- 刑事訴訟法第189条
- 刑事訴訟法第197条第1項但書
- 日本国憲法第38条第1項
- 警察官職務執行法第2条
- 行政手続法第5条
- 国家公務員法第99条
刑事訴訟法第1条
この法律は、刑事事件につき、事実の真実を発見し、これに基づいて適正な裁判をすることを目的とする。
刑事訴訟法第189条
司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、直ちに捜査をしなければならない。
刑事訴訟法第197条第1項但書
捜査は、強制の処分をすることができる場合を除いては、任意にこれをしなければならない。
日本国憲法第38条第1項
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
警察官職務執行法第2条
警察官は、その職務を執行するに当たっては、必要な限度をこえて人の権利を制し、又は義務を課してはならない。
行政手続法第5条
行政機関は、行政指導をするに当たっては、相手方の任意の協力によることを基本として、その趣旨及び内容を明確にし、かつ、相手方に対して一定の義務を課すような指導をしてはならない。
国家公務員法第99条
すべての職員は、職務の遂行に当たっては、法令及び上司の職務上の命令に忠実に従い、かつ、公正にこれを行わなければならない。
専門家としての視点
- 喧嘩両成敗処理の違法性と構成要件判断義務の放棄
- 通報者優位構造と捜査中立性の崩壊
- 高齢者優遇対応がもたらす平等原則違反と行政処分の偏向
- 多数優位判断がもたらす証言評価の歪曲と捜査機能の形骸化
喧嘩両成敗処理の違法性と構成要件判断義務の放棄
警察官が現場で当事者双方に形式的に非があるかのような扱いをし、事実上の責任の有無を問わず「双方に注意する」などの対応を取る行為は、刑事訴訟法第189条の捜査義務および構成要件該当性の認定義務に違反する。刑事訴訟法第189条は「犯罪があると思料するときは、直ちに捜査をしなければならない」と規定しており、警察官には加害性の有無を的確に判断し、必要な捜査に着手する義務がある。加えて刑事訴訟法第1条は、「事実の真実を発見し、これに基づいて適正な裁判をすることを目的とする」と定めており、形式的処理によって実質的な被害申告や違法行為の存在を曖昧にするような行動は、この法目的に真っ向から反する。また、「喧嘩両成敗」処理は、加害と被害の峻別をあえて避けることで場を収める目的に流される傾向があるが、これは刑法上の構成要件に照らして適法性を判断すべき職責を果たしておらず、事実上の不起訴的処分を現場レベルで恣意的に行っている点において、違法である。特に一方が黙秘権を行使しており、もう一方が通報側である場合、警察官のバランス感覚が大きく問われるが、そこで均衡処理を優先する姿勢は、黙秘者に対する不当な圧力と見なされ得る。喧嘩両成敗という形式に逃げる警察官の行動は、刑事手続の実質を破壊し、被害者の法的保護を構造的に無視する制度的失態である。
通報者優位構造と捜査中立性の崩壊
通報した側の主張を起点に捜査を進め、後から事情を聴取する側を事実上の被疑者として扱う構造は、捜査の中立性と任意性を破壊するものであり、刑事訴訟法第197条第1項但書に反する。同条文では「捜査は、強制の処分をすることができる場合を除いては、任意にこれをしなければならない」と明記されており、警察官が通報者の視点を前提として相手方への追及を行うことは、捜査の任意性を欠く不当な処分に該当する可能性がある。さらに、警察官職務執行法第2条により、警察官は中立的かつ必要最小限の権限行使が義務付けられているが、通報者の証言を無批判に信用し、それに基づく誘導的な対応を取る行為は、この義務に明確に反する。警察実務において「通報者=被害者」という暗黙の前提が作られることがあるが、これは裁判所の判断を代替する不当な権限行使であり、明確に違法である。刑事訴訟法上、警察官は事実関係を一から再構成する立場であって、通報者の主張を鵜呑みにする立場にはない。通報者優位という構造は、特に精神的に冷静でない通報者や、虚偽申告の可能性がある場合に重大な冤罪リスクを発生させる。警察が通報者を起点に場面を構成するかぎり、黙秘を貫く者、あるいは冷静に抗弁する者が常に不利となり、制度そのものが通報主導型の偏向処理へと転落していく構造問題を孕んでいる。
高齢者優遇対応がもたらす平等原則違反と行政処分の偏向
高齢者であることを理由に警察官が配慮的態度を取り、その主張を実質的に優遇する行為は、行政手続法第5条に規定される「相手方の任意の協力によることを基本とする」原則に反し、また国家公務員法第99条に定める「公正な職務執行義務」に違反する。高齢者だから穏便に、あるいは体力的・感情的な理由で詳細な追及を避けるという対応は、若年者や単独者に対して相対的に不利益な立場を強いる処分であり、実質的には行政判断に年齢差別を持ち込む行為に等しい。年齢は刑事責任能力や量刑判断においては考慮され得るが、事実の認定段階、特に初動捜査においてはそのような考慮は不要かつ有害である。高齢者が町内会などの社会的構造において影響力を持っている場合、その発言は無批判に受け止められがちであるが、それを理由に発言の真偽を検証しない行為は、平等原則の侵害である。警察実務においては「高齢者にはあまり強く出ない」という慣習的対応が存在するが、これが制度化されていれば、違法な行政慣行として直ちに是正されるべきである。若年者や弱者の意見が排除される結果につながる高齢者優位の構造は、適正手続を破壊し、事実解明を不可能にする偏向行為であり、その放置は明確な制度崩壊の兆候である。
多数優位判断がもたらす証言評価の歪曲と捜査機能の形骸化
複数人の証言が同一内容であることを理由に、それを無条件で信用する構造は、供述の独立性と内容による信用性評価という証拠法の基本原則に反する。刑事訴訟法第189条において、警察官には犯罪を認知した場合に速やかに捜査する義務があるが、その際に証言の数をもって判断の基礎とすることは、この義務の履行方法として重大な誤りである。さらに、警察官職務執行法第2条には「必要な限度をこえて人の権利を制してはならない」とあるが、少数の側に不利な判断を下すことは、この制限を逸脱する権限行使である。集団が一致した証言を行った場合、それが事前に打ち合わせた虚偽の可能性や、心理的同調に基づく内容であるかどうかの確認が不可欠である。多数側の証言が信頼され、単独の市民の主張が軽視されるという多数優位の処理は、捜査における判断の本質を放棄する行為であり、警察権の恣意的運用に直結する。証言数の多寡で処理が決まるのであれば、捜査の実効性は失われ、少数派にとっての法的保護は絵空事となる。証言の評価は数ではなく質によって行うという原則に立ち返らなければ、制度全体が市民の信頼を喪失し、捜査機関としての社会的機能が崩壊する。
専門家としての視点、社会問題として
- 現場警察官による形式的平等処理がもたらす司法機能の空洞化
- 通報制度の構造的欠陥と冤罪リスクの増幅
- 人口構成・地域力学に依存した警察判断の制度的危険
現場警察官による形式的平等処理がもたらす司法機能の空洞化
喧嘩両成敗という処理方式は、一見すると公平な判断であるかのように装うが、実態としては警察官が事件の実質を見ず、責任判断を放棄しているに等しい行為である。現場で一方的に加害があったとしても、両者に「話し合い」を促し「双方に非がある」として処理することで警察官は苦情を回避でき、事件も表面上は沈静化する。しかしこの対応は、刑事司法制度の根幹である加害と被害の峻別を放棄し、結果的に被害者の救済機会を奪い、加害者に実質的な免責を与えることとなる。特に近年、SNSや動画などによる記録が当たり前になった社会においては、現場対応が可視化され、喧嘩両成敗型処理の不当性が公に検証される機会も増えている。にもかかわらず、この処理傾向が温存されている背景には、警察内部での苦情回避、事案増加による負担回避、形式的公平性を維持するという事務的都合が存在する。この傾向が制度として蔓延することで、刑事司法機関全体の信頼性は大きく損なわれる。形式上は双方に非があるかのように扱いながら、実際には証拠も検討せず、一方の訴えを封じるこのような対応は、事実上の不起訴処理を現場警察官が恣意的に行っている構図であり、法治国家の基盤を根底から揺るがす深刻な社会問題である。形式的平等という名のもとに、実質的不平等が拡大していることを、制度的に直視する必要がある。
通報制度の構造的欠陥と冤罪リスクの増幅
通報者優位の構造は、本来は迅速な警察出動を可能にするために設計された制度的仕組みであるが、運用の現実では通報を行った側が事実上の「被害者」として固定され、その主張が捜査の出発点となることで、相手方の言い分は後回しにされる。この構造が固定化されることで、冷静に対応したり、黙秘を行う人物が加害者のように扱われ、過剰な疑念や圧力を受ける事例が少なくない。通報という手段は容易に虚偽申告や誇張された訴えに使われ得るものであり、警察が初動でこれを前提に動いた場合、証拠や証言の収集自体が偏る。結果として、加害者ではない市民が不当な取り調べや社会的非難に晒されるリスクが高まる。これは冤罪の構造的誘因であり、捜査が中立であるという前提を崩壊させる危険を持つ。社会的にも「通報すれば勝ち」という風潮が生まれ、トラブル対応の健全な対話文化を損ない、法制度が対立構造を助長する装置へと変質する。とくに精神的に不安定な通報者や、対人関係において優位性を取ろうとする人物によって制度が悪用された場合、結果として何もしていない側が常に疑いの目で見られ、自己防衛的に警察との接触を避けるという歪な社会構造が形成される。通報はあくまで一つのきっかけであり、警察官はその真偽をゼロから公平に検証する義務を負うことを、制度の根本から再確認しなければならない。
人口構成・地域力学に依存した警察判断の制度的危険
高齢者優位および多数優位という傾向は、現代の人口構成と地域力学において特に顕著であり、行政や警察対応に深刻な偏向を生んでいる。高齢化が進む社会においては、町内会や地域団体の中核を担うのは主に高齢層であり、その発言が「地域の声」として無条件に尊重されやすい。多数の意見がまとまっている場合、それが事実であるかどうかの精査を経る前に、警察官の判断が「空気を読む」形で多数側の意向に沿って決定される例も多い。これにより、単独で抗弁を行う若年層、障害者、外国人、あるいは地域に馴染みのない転入者が常に不利な立場に置かれる構造が温存されている。行政の現場では「波風を立てない」処理が優先され、長年地域に居住し、顔の広い高齢者や役職経験者の言動が実質的な証言の優劣を左右する。その結果、制度上は平等をうたっていても、運用上は地域構造に組み込まれた権力構造が個人の権利を圧倒する事態が発生している。特に警察官が「町内会長がそう言っている」「皆がそう言っている」といった根拠を持ち出す場面では、もはや事実認定よりも社会的立場や数の論理によって対応を決めているといわざるを得ず、このような偏向的処理は法の下の平等という憲法原則に反するだけでなく、個人の尊厳を破壊する重大な制度的病理である。
まとめ
警察官による現場対応において「喧嘩両成敗」「通報者優位」「高齢者優位」「多数優位」といった処理傾向が制度として常態化していることは、刑事手続の中立性、公平性、実体的真実の発見という基本原則を大きく損なう問題である。とりわけ初動における接触順序、通報を起点とする一方的捜査、社会的属性による扱いの違い、人数による証言評価といった構造的偏向は、警察権の行使が合理性と証拠に基づくものではなく、場の空気や力関係、地域構造に左右されている実態を露呈している。これらの処理が黙認されることで、被害者の保護は後回しにされ、黙秘や沈黙という正当な権利行使が不利に評価されるなど、制度本来の機能が形骸化している。今後、真に中立な警察実務を確立するためには、こうした処理構造を明確に可視化し、行政手続と刑事捜査の境界を厳密に監視し直す必要がある。