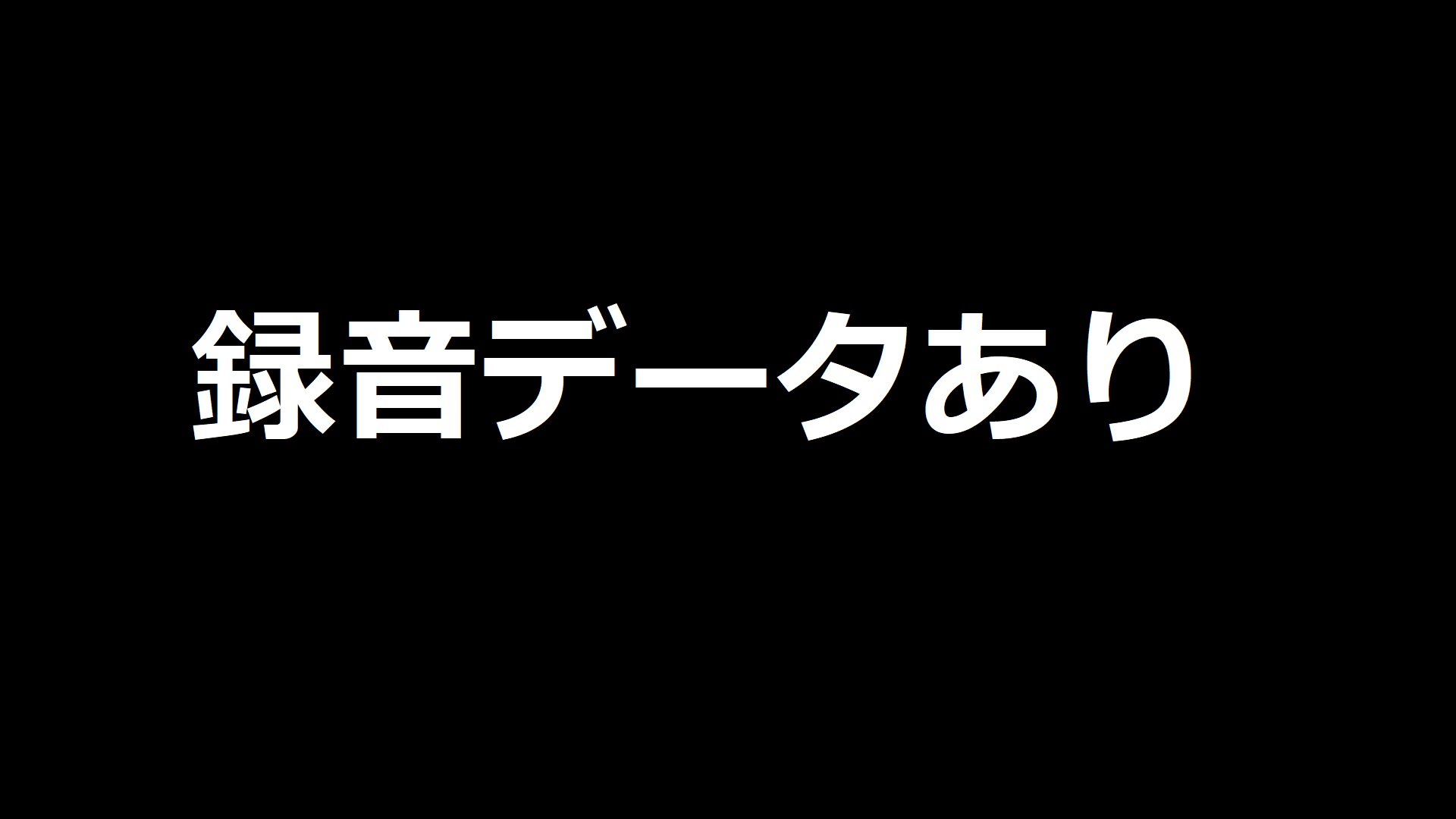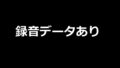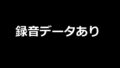警察官の現場対応における「連携」は、市民の権利保護や適正手続の実現にとって極めて重要である。にもかかわらず、現実には情報共有が不十分なまま、複数の警察官が同一の市民に対して繰り返し質問や圧力的言動を行う場面が確認されている。これは精神的負担を助長し、自己防衛としての録画や沈黙の権利を侵害しかねない構造である。特に、警察官が「撮影をやめろ」と繰り返し主張しながら、一方で「話を聞かせろ」と迫る場面では、対等な対話の前提が崩れ、結果的に市民側が不利な立場に追い込まれていく。今回の事例を通じて、警察内部の連携不足と、市民の基本的権利が現場でいかに軽視されているかを明らかにし、制度と運用の両面から再考を促す必要がある。
警察官連携とれてますか?
- 経緯
- 警察官連携とれてますか?
- 考察:警察官連携とれてますか?
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定のような取り決めが交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、いつものことではあるが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
相手は「知らない」と答え、「それは役場の誰かが勝手に言ったことじゃないのか」などと口にした。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定のような取り決めは確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく、まずは言い返すことが前提のような応対。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」──お決まりの反論が続く。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
私がまず思ったのは、保護される危険性があるということだった。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしている側が一方的に「保護」という名目で排除されかねない。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを手に取った。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護という名のもとに強制的な処置へと導かれるか──それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院への入院という「お決まりのコース」が待っている。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであるとみられており、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物として慎重に扱わなければならない。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
私はすぐに伝えた。
「私は弁護士に連絡をしました。現在、その折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
警察官連携とれてますか?
若い警察官は、私が弁護士への連絡を伝えた直後、すぐに私から離れて隣人夫婦のもとへ向かった。しばらくして、1台のパトカーが現場に到着した。降りてきたのは2人目の警察官である。彼は到着後、隣人夫婦、町内会長、先に到着していた警察官としばらくやり取りを交わした。その後、私の方へ向かって歩いてきた。
「ちょっとお話いいですか」と話しかけてきた警察官。しかし、すでに先に来ていた警察官に対し、弁護士に連絡を取り、折り返しの電話を待っている旨を伝えてある。そのため、新たに話しかけられる理由は見当たらなかった。私は警察官に対して問いかけた。
「連携してますか?」
「はい?」
「連携してますか?」
「なんですって?」
「連携をしてますか?きちんと」
「連携ってなんですか?」
「警察官同士で連携してますか?」
「連携というのは?
「お話聞いたらどうですか?」
「今聞きましたよ、私は○○さん・・・」
「私の、私の話したことをあの人に聞くべきなんじゃないですか?」
「聞きましたよ」
「警察官同士で聞きましょうよ」
「聞きましたよ」
「だったら何も言うことはないです」
「なんでですか?」
「言いましたよ、さっき」
「撮影やめてください。お巡りさんの話も聞いてますよね。撮影やめてくださいって、今2回ぐらい言われてますよね。なんでお巡りさんの話を聞かないのに、あなたの話を一方的に言うんですか?お話にならないじゃないですか。お話にならないじゃないですか、それじゃ。話し合いにしましょうよ」
「わかりました。じゃあもう一回いいますね。和たちは今、弁護士に連絡と取っていて、弁護士の連絡を待っています。私は何にもしゃべる気はないです。で、弁護士と話をしたいならしてください。以上です。それ以上何もしゃべりません」
考察:警察官連携とれてますか?
若い警察官が一人、住民と話をしていた男性から離れ、隣人夫婦のもとへと歩を進めたのは、彼が「弁護士に連絡した」と伝えられた直後のことだった。その場の空気が一変したのは、それから間もなくもう一台のパトカーが現場に到着した時である。降車してきたのは別の警察官であり、現場にいた隣人夫婦、町内会長、先着の警察官と一通り言葉を交わしてから、静かに彼のもとへ向かって歩いていった。
「ちょっとお話いいですか」そう声をかけた警察官に対し、彼は一歩も引かずに問いを返した。すでに別の警察官に同様の説明を済ませており、新たに話す理由が見つからなかったからである。返ってきた問いは簡潔だった。「連携してますか?」警察官の反応は曖昧で、質問の意図を測りかねている様子が見てとれた。言葉を繰り返しながら確認する彼と、要領を得ないまま応じようとする警察官。会話は噛み合わず、同じ言葉が幾度となく交わされた。「私の話したことをあの人に聞くべきなんじゃないですか?」「聞きましたよ」「だったら何も言うことはないです」やり取りは次第に平行線をたどり、警察官は撮影の中止を求める言葉を繰り返した。彼はそれに対しても動じることなく、明確な姿勢を示す。「もう一回いいますね。私たちは今、弁護士に連絡を取っていて、その返答を待っています。私は何もしゃべる気はないです。弁護士と話をしたいならしてください。以上です。それ以上何もしゃべりません」その言葉には、現場における主導権を明け渡すつもりのない、確固たる意思が込められていた。周囲が思惑を交錯させる中、彼の立ち位置は揺らぐことなく、静かにその場に留まり続けていた。
関係する法令
- 日本国憲法 第38条第1項
- 警察官職務執行法 第2条第1項
- 国家賠償法 第1条第1項
- 刑法 第104条の2
- 日本国憲法 第34条
日本国憲法 第38条第1項
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
警察官職務執行法 第2条第1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、何らかの犯罪を行おうとしていると疑うに足りる相当な理由がある場合に限り、停止させて質問することができる。
国家賠償法 第1条第1項
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。
刑法 第104条の2
公務員に対してその職務の執行を妨害する目的をもって、録音、録画、写真撮影その他これらに類する行為をし、又はこれを強要した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
日本国憲法 第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、拘禁されない。
専門家としての視点
- 現場における警察官間の情報共有の不備がもたらす緊張構造
- 弁護士対応中の被疑者に対する過剰接触の問題
- 記録行為に対する抑止的言動の違法性
現場における警察官間の情報共有の不備がもたらす緊張構造
警察官が複数現場に出動した際に、到着順によって得られる情報には時差が生じるが、その情報を適切に共有し、全体の対応方針を整合させることは極めて重要である。本件においては、先着の警察官に対して「弁護士と連絡中であるため、応答を控える」という明確な意思表示がされていたにもかかわらず、後から到着した別の警察官が再度同様の問いかけを行っている。この行動は、組織内での「指揮命令系統」や「情報共有体制」の不備を示唆しており、警察法第2条に定められた「適正な警察活動の遂行」の理念に反する。特に、刑事訴訟法第198条第2項に基づく黙秘権の尊重を無視した継続的な接触は、刑事訴訟法の趣旨にも反する行為であり、仮に精神的威圧を伴うものであれば、刑法第223条の強要罪や同法第194条の特別公務員職権濫用罪の構成要件に該当する可能性も否定できない。
弁護士対応中の被疑者に対する過剰接触の問題
弁護士に連絡を取っており、その折り返しを待っていると明示的に伝えられている状況において、繰り返しの問いかけや発言の強要は、刑事訴訟法第39条が保障する「弁護人との秘密交通権」に実質的な干渉をもたらす。特に、当該者が「これ以上は話さない」と明確に発言しているにもかかわらず、「話し合いましょうよ」「お話にならないじゃないですか」といった言葉を重ねる行為は、事実上の強制的な事情聴取と同義であり、任意捜査の限界(判例:最大判昭和63年3月8日)を超えるものである。このような態度は、被疑者の防御権を実質的に侵害し、刑事手続の公正を害するおそれがある。
記録行為に対する抑止的言動の違法性
警察官が「撮影をやめてください。お巡りさんの話も聞いてますよね」などと複数回にわたり発言し、撮影行為に対して事実上の中止圧力を加えた点は、重大な法的問題を含む。平成29年6月1日の最高裁判例を含め、公務中の警察官の撮影自体を禁止する法的根拠は原則存在せず、撮影が業務を著しく妨害しない限り、表現の自由(日本国憲法第21条)として保障される。よって、警察官が自身の発言を根拠に市民の記録行為を制限しようとする行為は、法令に基づく正当な職務権限の範囲を逸脱しており、国家賠償法第1条に基づく損害賠償責任の対象となる場合がある。
専門家としての視点、社会問題として
- 現場対応における警察官間の情報伝達と組織的意思決定の欠如
- 正当な抗議行動に対する制度的不信と排除構造の再生産
- 記録行為への抑圧と市民の萎縮効果がもたらす公共空間の劣化
現場対応における警察官間の情報伝達と組織的意思決定の欠如
本件のやりとりにおいて顕著であったのは、警察官間の連携の欠如である。先に現場に到着した警察官が、当事者から「弁護士と連絡を取っており、折り返しを待っているため、それまで一切話さない」という意思を明確に伝えられていたにもかかわらず、後に到着した警察官が再び一方的に「ちょっとお話いいですか」と問いかけ、さらにはその返答を得られないことに対して感情的な対応を重ねた点は、組織としての一貫性を欠く対応であった。これは警察法第2条が規定する「適正かつ能率的な警察の運営」の理念に反し、警察官個々の判断による分断的な対応が市民との間にさらなる不信を招く原因となる。現場対応において警察官同士が互いの認識を共有せず、二重の尋問や不必要な接触が生じれば、それは結果的に当事者に過度な精神的圧力を与えると同時に、警察組織への信頼を著しく損なう。特に、意思表示が明確に成されている状態であれば、再度の接触は合理性を欠き、任意捜査の範囲を逸脱した強要行為として捉えられかねない。このような状況が放置される限り、現場における警察の対応は市民の視点から見て一貫性を失い、組織的対応という本来の機能が形骸化する恐れがある。
正当な抗議行動に対する制度的不信と排除構造の再生産
市民がトラブルや違法行為に対して抗議の意思を表明することは、民主主義社会において正当な行動であり、法的にも制限されるべきではない。しかし、実際の現場では、110番通報があった側に対し機械的に警察が出動し、抗議を行っていた当事者の方が「保護対象」とされる構造が存在している。このような構造は、過去に「保護」という名目で一方的に排除された経験を持つ市民にとっては極めて脅威的であり、制度そのものへの不信を助長する。今回もまた、先に行動を起こした側があたかも「対応されるべき問題人物」として扱われ、その態度や応答をもってさらなる警察的介入が正当化されかねない状況に置かれていた。このような介入の連鎖は、被害を受けていた側が制度に対して信頼を寄せることが困難となり、警察や行政に対する敵意を生む温床となる。また、町内会長や周囲の関係者が数的優位によって一方の当事者に圧力をかける構図は、警察対応が中立的に機能していないことの象徴でもある。この構造を是正せずに繰り返すことは、市民の正当な抗議権を侵害するばかりか、制度的な排除を常態化させ、社会的分断を深める重大な問題となる。
記録行為への抑圧と市民の萎縮効果がもたらす公共空間の劣化
警察官による「撮影をやめてください」「警察官が言っていますよ」という発言が、現場での記録行為を実質的に妨害する圧力として機能した場合、それは重大な社会問題である。市民による記録は、公共空間における権力の行使が適正であるかを監視する最も基本的な手段であり、憲法第21条に定められた表現の自由にもとづく行為として尊重されるべきである。最高裁平成29年6月1日判決においても、公務中の警察官の撮影を禁止する法的根拠は認められず、撮影が妨害とされるには業務遂行に対する実質的な支障が明示的に立証されなければならない。本件において、録画行為が業務妨害に該当したとする客観的事実は示されておらず、むしろ警察官側の「指導」的な言動が撮影中止への心理的圧力として作用したと見るのが自然である。このような抑圧が常態化すれば、公共の場において市民が自らの身を守る記録手段を封じられることとなり、警察官による権力行使がブラックボックス化していく。記録への圧力は単なる発言ではなく、制度と自由の間に横たわる「監視の監視」を巡る対立の象徴であり、社会全体として看過すべきでない。
まとめ
本件は、警察官間の連携不足が市民との間に重大な摩擦を生んだ事例であり、現場対応の一貫性の欠如が当事者に過度な圧力を与え、不必要な対立を生じさせた典型といえる。また、撮影行為に対する警察官の発言は法的根拠に乏しく、その言動が記録行為への抑圧として機能していたことも問題である。さらに、弁護士連絡中という意思表示があったにもかかわらず再度の接触を試みるなど、警察組織としての意思共有が行われていなかった点は、警察法が求める適正かつ効率的な執行体制に反している。記録の自由と意思尊重を妨げるような運用は、市民の警察不信を加速させ、法の支配に基づく民主社会の土台を揺るがす重大な社会課題である。