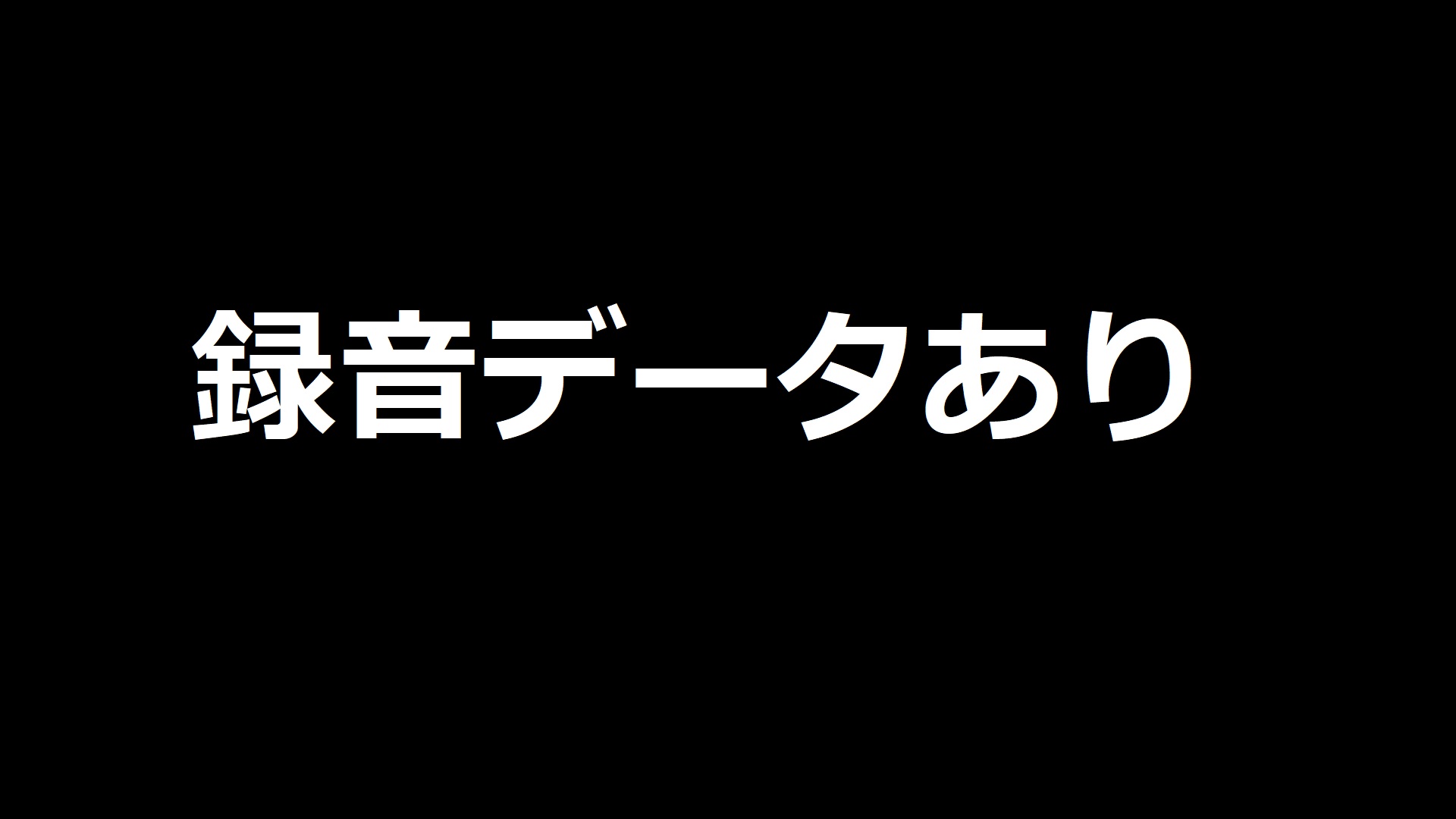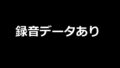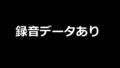公務中の警察官による「忠告しましたよ」という発言が、市民の撮影行為に対してどのような心理的影響を与え、法的にどのような構造を持ち得るかについて、制度面・社会的受容構造・判例との関係性をもとに検討する。本来であれば市民の側に法的な制限が存在しない撮影行為が、警察官の言葉ひとつで抑止される構図が常態化することの危険性と、それに付随する表現の自由の萎縮効果について明確に捉える必要がある。表現の自由、任意捜査の原則、そして公務員の発言責任の問題を複合的に読み解くことで、現場対応の限界と制度的課題が浮き彫りになる。
撮影禁止を”忠告”する警察官
- 経緯
- 撮影禁止を”忠告”する警察官
- 考察:撮影禁止を”忠告”する警察官
経緯
50年以上、隣の家の騒音に悩まされてきた。
様々なトラブルを経て、約5年前、問題の解決を目的として鳩山町役場の仲裁のもと、こちらは隣の家の前を通らず、隣は当方の家の前を通らないという、紳士協定が交わされた。
それから約5年間、大きなトラブルもなく平和に過ごしていた。
ところが、外出して帰宅すると、隣のご主人がクルマで当方の家の前を通っていた。
「また始まった。いったい何回蒸し返せばいいのか?」という憤りが込み上げた。
カーポートの上に防犯カメラを設置し、隣の家が外出する際には、確実に視界に入る位置に「防犯カメラ設置中」のステッカーも貼った。
それからおそらく1ヶ月ほどが経った頃、隣のご主人が出かけていくのが見えたため、しばらく様子をうかがった。
なんと、こちらの家の前を歩いて通っていった。
流石に腹が立ち、思わず声を上げた。
しかし、聞こえていないのか、あるいは無視しているのか、反応はない。
すぐに家を出て追いかけ、追いついたところで苦情を伝えた。
隣のご主人は「知らない」と答えた。
しかし、そんなはずはない。
1ヶ月前までの5年間、紳士協定は確かに守られていたのだから。
やがて夫人が現れた。
この場で「すみませんでした。気をつけます」と一言でもあれば、それで終わっていたはずだし、実際それほど騒音や行動が気になるわけでもない。
しかし、いつものごとく夫人は言い返さないと気が済まない。
「そんな約束なんか知らない」「ここは公道だから、何をしても構わない」。おそらく誰かの入れ知恵なのだろう、お決まりの反論が続く。
そして挙句の果てに、夫人は110番通報をした。
私が思ったことは、まず保護される危険性があるということ。
そこで家に戻りスマホを持ってきた。
過去の経験からして、110番通報により警察官が来れば、正当な抗議をしているこちらが不当、不法な保護される危険性がある。
そのため、いったん家に戻り、スマートフォンを持ってきた。
このときの方針は、明確に定まっていた。
・弁護士に電話をかける。
・通話がつながれば、そのまま警察官と話をしてもらう。
・もしつながらなくても、折り返しを待ち、警察官に取り次ぐ。
・それまでの間、とにかくスマートフォンで録画を続ける。
・そして、何を聞かれてもこう繰り返す。
「弁護士に連絡をしています。折り返しの電話を待っています。それ以上のことは一切話しません。」
すでに、2023年2月9日に同様の経験をしている。
どんな言葉が、どのように都合よく転換され、保護され、精神病院への強制入院へ向かうか。それはもはや予測不可能だ。
しかも、仮に逮捕であれば弁護士への連絡が認められているが、保護となれば、弁護士への連絡すら許されないまま、精神病院へ入院させられる。
さらに現在、私は事件の犯人との民事訴訟を控えている状況にある。
その犯人は、警察OBであり、事件に至るまでに行われた嫌がらせ行為が、西入間警察署および鳩山町役場との連携のもとで行われた可能性が高い。
となると、今回現場に来る西入間警察署の警察官も、単なる第三者ではなく、
加害者側の関係機関に属する人物と考えないと危険である。
つまり、「対応のフリをして、保護にすり替える」こともあり得るという前提で臨まなければならない。
この現実を踏まえ、私は自らに言い聞かせた。
余計な言葉を発したり、余計な行動は、絶対にしてはならない。
すべてが相手の都合のいいように解釈される恐れがある。だからこそ、録画し、記録し、発言は最小限に抑えるしかない。
隣の夫人が呼んだ町内会長が来た。
彼は完全に隣の味方であり、人数合わせと同調圧力の象徴のような存在だった。
この構図だけで、すでに「一対多」の構造が出来上がっていた。
ほどなくして、警察官が到着した。若い警察官だった。
撮影禁止を”忠告”する警察官
あまりに強烈な印象の警察官②にすっかり気を奪われ、警察官①(若い警察官)の対応を忘れていた。あらためて他の動画を作成しようと編集していると、警察官①もそれなりに問題のある発言をしていることに気が付いた。
「撮るのやめてもらっていいですか!」。これを2回。これについては威圧的とは言えず、お願いレベルだと評価できる。
問題は、「忠告しましたよ!」。この発言である。
今動画を見直してみて、この発言を聞いてみても、警察官から発せられたこの「忠告しましたよ!」は、市民レベルからすると、「動画を撮影すると、”何か罪に問われて例えば最悪逮捕されるのでは?”そこまでに至らずとも”トラブルに関してなんらかの不利益を被るのでは?”」と感じさせるに十分な威圧感を感じる。
結局、警察官②は強烈な個性で、そしてスマホのレンズに掌を限界ギリギリまで近づけるという、まさに緊迫した状況を作り出した。一方、警察官①も物腰は柔らかくとも「忠告しましたよ!」という一言を捉えてみると、さも”忠告”が警察官の職務として法的に正当なものであり、また”法的に撮影行為は禁止されている”と誤認させるに十分な”言い方であったということである。
問題は、「忠告しましたよ!」という言葉によって、忠告された側の市民がどういう行動にでるかである。おそらく何か強い信念を持っていなければ、前述のとおり「”忠告”が警察官の職務として法的に正当なもの」、「”法的に撮影行為は禁止されている”と誤認」し、その場で撮影をやめるであろう。
つまり警察官に忠告された市民は、撮影をやめるのである。
警察官に忠告された市民は、撮影をやめるということは、警察官の忠告は市民への「お願い」ではなく、“強制”であるということを意味する。
警察官が市民に、義務のないことを強制した。こう言っても過言ではないだろう。
さらに言えば、警察官が市民に、法や判例に基づかない行為を強要した。ということである。
つまり、これは警察官による明白な違法行為だ。
素人の市民はこのように結論付けた。
考察:撮影禁止を”忠告”する警察官
この一連のやり取りは、街頭での動画撮影という市民の行動に対し、2人の警察官がそれぞれ異なる接触方法を取った場面を記録・分析したものである。警察官②の対応は、身体的にスマートフォンへ掌を近づけるなど、視覚的・心理的に強い圧を伴うものであり、第三者の目から見ても、相手に直接的な威圧感を与える典型的な行為として映る。一方で、警察官①は口調も柔らかく、あくまで丁寧な言い回しで接しているように見える。
しかしながら、動画内での「忠告しましたよ!」という発言には、形式的にはお願いに近い表現でありながら、文脈と立場の非対称性により、受け手が「何かしらの法的根拠があって止めなければならない」と誤解する可能性が生じている。市民側が「法に基づかない任意の要請」であることを即座に判断できない限り、警察官の発言は結果として「実質的な命令」として作用する。特に現場という緊張感のある状況では、肩書きと制服の持つ権威性が、市民の判断を鈍らせる作用を持つ。
このように、「忠告」という言葉一つが、実際には撮影という行為を止めさせる直接的な力となっている点が重要である。つまり、警察官本人が「お願い」のつもりで言ったとしても、受け手の市民がそれを「強制」として受け取って行動を変えたのであれば、事実上、誤った警察権力が行使されたことになる。そしてその指示が、法的根拠や判例に基づかないものであった場合、警察官が職務権限を逸脱して市民の行動を制限したと評価されうる。
この事案は、口調や態度といった表面上の柔らかさに隠れた構造的な力の行使を浮き彫りにしている。形式上の「忠告」や「お願い」であっても、実際に相手の自由を制限する結果となれば、それは公権力の発動とみなされる。市民が「撮影は違法かもしれない」と誤認し、任意の行動を中断する可能性があったという事実は、警察官の発言が客観的に見て過剰であったことを示唆している。
全体として、この場面は「明白な暴言や物理的圧力」がなくとも、言葉と肩書きが市民の行動を拘束しうることを示しており、その影響は強い信念を持たない市民にとっては重大である。撮影行為自体に違法性がない限りにおいて、その自由は守られねばならず、それを覆すような発言がなされたとすれば、構造的には違法性の認定を含む事態となりうる。これは、当該警察官の行動を軽視することができない理由のひとつである。
関係する法令
- 刑事訴訟法 第197条第1項
- 刑法 第193条
- 日本国憲法 第21条
- 国家賠償法 第1条第1項
- 東京地裁平成20年6月23日判決(平成19年(ワ)第24785号)
刑事訴訟法 第197条第1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、捜査をすることができる。
刑法 第193条
裁判、検察若しくは警察の職務を行う公務員が、その職権を濫用して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。
日本国憲法 第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
国家賠償法 第1条第1項
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる。
東京地裁平成20年6月23日判決(平成19年(ワ)第24785号)
警察官はその職務の公共性に照らし、職務中の姿を撮影されることについて原則として容認すべき立場にある。よって、職務中の撮影は肖像権の侵害に当たらない。
専門家としての視点
- 警察官による「忠告」という発言の法的構造と任意捜査原則の緊張関係
- 表現の自由の侵害としての構造的違法性と国家賠償の成立可能性
- 職務中の撮影に対する抑止発言と判例における警察官の肖像権否定
警察官による「忠告」という発言の法的構造と任意捜査原則の緊張関係
警察官が公務中に市民の動画撮影に対して「忠告しましたよ」と発言した場合、その言葉は形式上の注意喚起であるように見えても、実質的には公権力を背景とした心理的制止に該当する構造を持つ。刑事訴訟法第197条第1項は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、捜査をすることができる」と定め、任意捜査の原則を前提としている。しかし、この原則は市民の自由を尊重したうえで捜査の開始や接触が行われるべきものであり、違法性のない撮影行為に対して「忠告」という語を用いて抑制しようとする行為は、任意捜査の限界を逸脱するおそれがある。市民にとっては警察官からの発言というだけで法的強制力があると誤認しやすく、「撮影をやめなければ違法な結果があるかもしれない」との恐怖心から自発的に行動を制限することに繋がる。このような状況が生じた場合、発言自体は「命令」や「措置要求」ではなくとも、実質的に市民の行動に影響を与えており、任意の域を逸脱した事実上の強制と解される構造がある。特に、撮影されているのが公務中の警察官自身である場合、その行為には自己の職務に対する不都合を回避する意図が含まれる可能性が否定できず、警察活動の透明性や市民の監視機能との緊張が顕在化する。したがって、「忠告しましたよ」という発言の背景には、任意捜査原則と権力的圧力の境界における深刻な問題が存在する。
表現の自由の侵害としての構造的違法性と国家賠償の成立可能性
公務中の警察官が市民による撮影行為に対し「忠告しましたよ」と発言した事例において、その発言が市民に対し行動制限を促す効果を持ち、結果として撮影継続に対する心理的萎縮をもたらした場合、憲法第21条が保障する「表現の自由」に対する実質的侵害となりうる。日本国憲法第21条は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定しており、市民が公的空間において公務員の職務執行を記録・公開する行為は、公共の利益に資する表現行為として強く保護されるべきである。このような文脈で、警察官の発言が抑止的な意味合いを持ち、行動変更や中断を誘発した場合、発言内容の形式ではなく結果としての市民の行動抑制に着目し、憲法上の権利侵害としての評価が成立する構造を有する。さらに、国家賠償法第1条第1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体がこれを賠償する責に任ずる」と定めており、発言が法的根拠なく表現行為の自由に干渉し、精神的萎縮や公的活動の妨害といった損害を発生させた場合、違法な公務執行として国家賠償の要件を満たす可能性がある。警察官の発言が行政指導の域を超えて市民の自由意思を実質的に奪う構造が確認された場合、その違法性の判断は形式ではなく実質に基づいて行われるべきであり、発言の影響力を過小評価することは許されない。
職務中の撮影に対する抑止発言と判例における警察官の肖像権否定
警察官が「忠告しましたよ」と発言し、職務中の撮影を制止または抑止しようとする行為については、肖像権やプライバシーの観点からの正当化が試みられることがあるが、東京地裁平成20年6月23日判決(平成19年(ワ)第24785号)はこれを明確に否定している。同判決は「警察官はその職務の公共性に照らし、職務中の姿を撮影されることについて原則として容認すべき立場にある。よって、職務中の撮影は肖像権の侵害に当たらない」と判断しており、撮影行為が公務の監視という社会的機能に基づく限り、その自由は制限されるべきではないという司法判断が存在する。このような判例の下では、警察官が市民に対して撮影をやめるよう発言すること自体が、判例上の価値判断と抵触する構造を持つ。警察官の発言が「お願い」や「配慮の依頼」としてなされた場合でも、市民の多くは制服と権力の象徴としての肩書きに圧倒され、命令として受け取ることがあるため、結果的に判例が示す「撮影の自由」の保障に対する実質的な侵害となりうる。したがって、職務中の警察官による抑止的発言は、肖像権保護を理由とする正当化が認められないばかりか、判例に基づき明確に違法性の判断対象とされる余地がある。
専門家としての視点、社会問題として
- 警察官の発言が生む市民の萎縮と公的空間における表現の後退
- 公務員の言葉が信頼される社会における誤解の構造と責任の所在
- 撮影を巡る対立が示す法理解の乖離と警察教育の制度的限界
警察官の発言が生む市民の萎縮と公的空間における表現の後退
公務中の警察官が市民の撮影に対して「忠告しましたよ」と発言する行為は、形式的には柔らかい言い回しであっても、現場においては国家権力の象徴を背負う者の発話として市民に強い心理的影響を与える。特に日本のように公務員の言葉が事実上の命令として受け止められやすい社会においては、法的拘束力のない発言であっても、受け手にとっては「今ここで撮影を続けることはトラブルになるのでは」「従わなければ法的な不利益を被るのではないか」といった恐怖や萎縮を引き起こしやすい。これは撮影行為が表現行為であり、公共空間において公務執行中の職員を撮影する自由は、日本国憲法第21条が保障する「表現の自由」の範疇に含まれるという前提に立てば、警察官の一言がその自由を事実上制限する力を持っていることになる。市民がカメラを構える自由、記録する自由は、公的権力を監視し、透明性を確保するために不可欠な民主社会の機能であり、それが公権力側の言動によって萎縮させられる構造が存在するならば、それは単なる現場対応の問題ではなく、制度としての民主性の後退と捉えるべきである。「忠告」という言葉がもつ柔らかい表現に隠れて、実質的な制止や抑圧の意図が入り込む余地が制度的に温存されている限り、言論と記録の自由を担保する社会的基盤は常に脅かされる。特に、法的には何ら違法性のない市民の行動が、現場対応によって制限される構図が常態化すれば、それは警察行政の問題ではなく、社会全体の表現空間における後退と見るべきである。
公務員の言葉が信頼される社会における誤解の構造と責任の所在
警察官が発する「忠告しましたよ」という一言が、市民にとってどのような意味を持つかを考察する場合、それは単に言語表現の問題ではなく、言葉が発せられる社会的文脈に強く依存している。日本社会において公務員の言葉は高い信頼性を前提とされており、たとえそれが任意の案内やお願いであっても、市民はしばしばそれを義務や命令として受け止める傾向にある。このような状況で「忠告」という語が使われると、市民はそこに法的根拠や罰則の示唆を読み取り、自らの行動を控えるようになる。だが、実際にはそのような発言が法的拘束力を持たない場合、市民の自由が誤った印象によって制限されたことになる。この構造は、発言を行った警察官個人の問題に還元すべきものではなく、公務員の発言がどのように受け取られるかという社会全体の受信構造と制度の設計に関わる。警察官が「丁寧な注意喚起」を意図していたとしても、その言葉が制度的に命令と誤解される文脈で発せられた以上、その結果生じた誤解の責任は、個人ではなく制度側にある。この構造を正さずに放置すれば、公務員の発言は形式的には任意を装いつつ、実質的には強制の手段として機能し続けることになり、任意と強制の区別は現実的に意味を失っていく。言葉の選び方の問題に見えて、実は受け手の判断構造と制度設計の不備が露呈しているのが「忠告しましたよ」という発言に含まれる社会的問題の本質である。
撮影を巡る対立が示す法理解の乖離と警察教育の制度的限界
公務中の警察官が市民の撮影に対して抑止的な言葉を用いる事例が後を絶たない背景には、法の文理と現場実務とのあいだに深刻な乖離が存在しているという制度的問題がある。判例上、警察官は職務中の姿を撮影されることについて原則的に容認すべき立場にあるとされており、東京地裁平成20年6月23日判決(平成19年(ワ)第24785号)はそのことを明確に示しているにもかかわらず、現場では未だに撮影を「やめてください」「忠告しました」といった言葉で抑止しようとする対応が繰り返されている。これは、警察官個人の知識不足というよりも、警察教育制度全体において、判例・憲法・市民権の意義が現実的な訓練内容として十分に浸透していない証左である。現場における撮影は、しばしば対立や緊張を生むが、それは「撮影=敵意」といった誤解が警察側にあるからであり、本来は市民が公務を監視する手段として当然のものであるという法的認識が共有されていないことが根本原因である。撮影行為が市民の側から行われるたびに緊張が生じるという現実自体が、制度が正常に機能していないことの証左であり、これは警察内部の研修制度、評価制度、苦情処理制度にまで遡って構造的に再検討されるべき問題である。「撮影を抑止したい」という反応が反射的に現れること自体、警察機関における人権感覚の後退と制度疲弊の兆候と見なすべきであり、個々の言動を叩くよりも教育体制の抜本的見直しが優先されるべきである。
まとめ
公務中の警察官が市民による撮影に対し「忠告しましたよ」と発言する行為は、表現の自由を侵害する可能性を孕みながらも現場では軽視されがちである。任意捜査の原則からすれば、違法性のない行為に対して公権力が心理的制止をかけることは、本質的に問題であり、場合によっては特別公務員職権濫用や国家賠償の構成要件に接近しうる。また判例上、職務中の警察官には肖像権の主張は原則として認められず、市民の撮影は合法であるにもかかわらず、抑止的発言が常態化する現状は制度としての教育・運用の欠陥を示す。警察官の一言が、市民の自由な行動を制限し、民主社会における監視機能を損なう構造に接続していることは見過ごされるべきではなく、個人の資質ではなく制度と社会全体の受け取り方の問題として捉えるべきである。