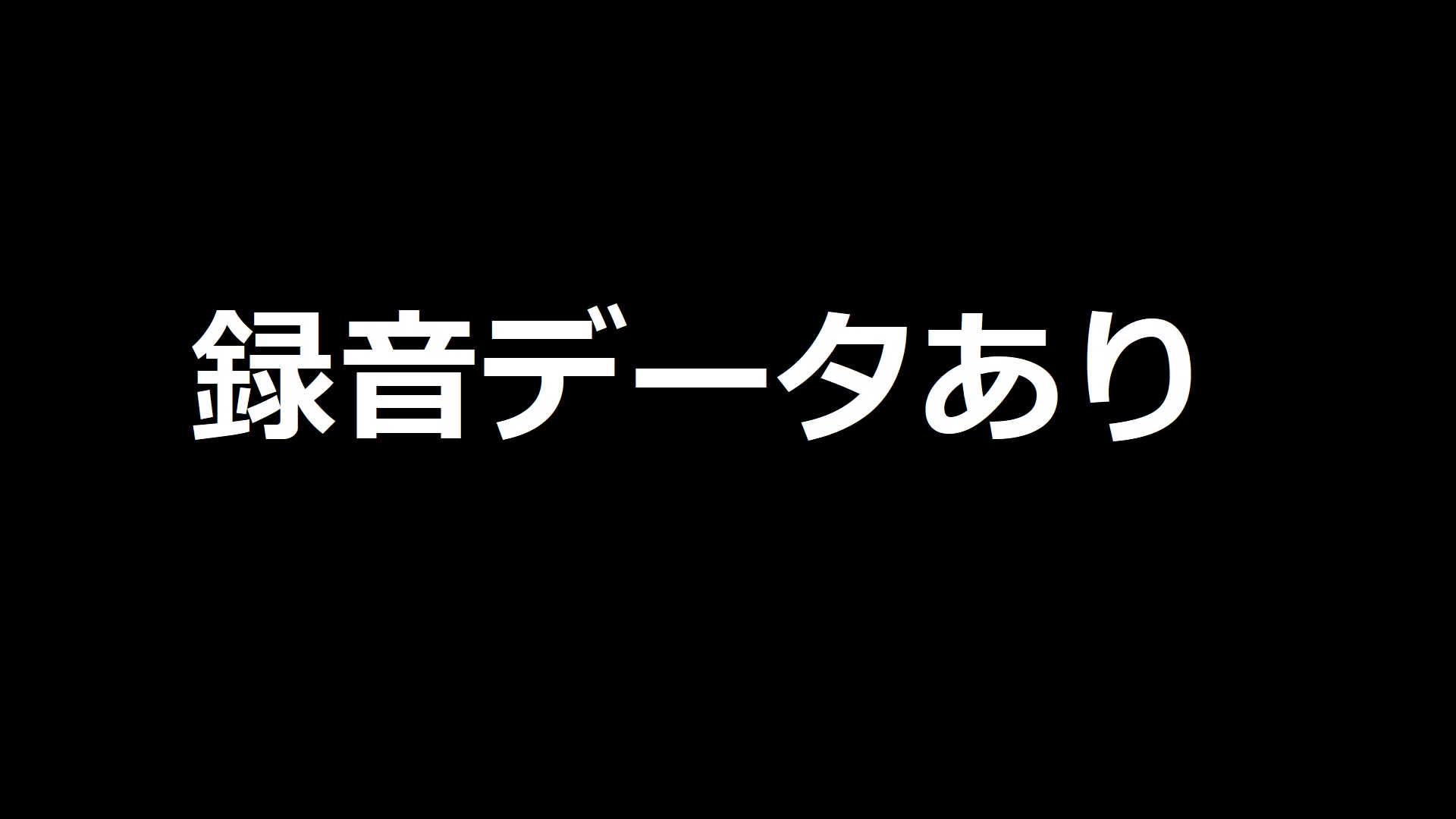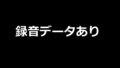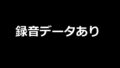警察官職務執行法に基づく「保護」制度は、公共の安全を目的とする一方で、その運用の実態は一般にはほとんど知られていない。被害者はある日、突如として警察による「保護」の対象となり、その瞬間から一連の対応を経験することとなった。警察の判断で行われるこの「保護」は、単なる一時的な措置ではなく、社会的に都合の悪い人物を排除する手段として機能しているのではないかと疑問を抱かざるを得ない。保護の瞬間、何が起こったのか。警察の対応はどのようなものであったのか。現場の状況やその後の経過を詳細に記録し、この制度の持つ問題点を浮き彫りにする。今回の記事では、被害者自身が体験した「保護」の瞬間を実況し、そこから見える警察制度の課題について考察する。
「保護」の瞬間を振り返る 実録・警察の対応とその問題点
- 「保護」に至る経緯
- 「保護」が決定された瞬間
- 「保護」によるその後の処遇
「保護」に至る経緯
4年間にわたる西入間警察署及び犯人、そして鳩山町役場長寿福祉課による嫌がらせ、嫌がらせをやめさせようとして起こった傷害事件(のちに過失運転致傷、救護義務違反で告訴)。110番通報、119番通報し、警察による現場検証が行われた。
被害者はパトカーに乗せられ東松山警察署へ。これまでの諍いから被害者はことある毎にスマホで録音をするようにしていた。この時も「一応」と思いスマホの録音を始めていた。
東松山警察署に着く直前、東松山警察署の玄関が見えた。玄関には生活安全課のK氏が立っていた。案内されるまま、怪我をした足を引きずりながら聴取室に入る。
最初はI刑事であった。
事件であるわけで、なぜそこにいたのか、どうしてそのクルマに近づいたのか、そのあたりの説明をしていく。説明をしていくというよりも、聞かれたから答えたという方が正確だろう。事件が起こるには原因、経緯、きっかけなどそれまでの過去の状況が必ず必要になるはずだ。
被害者がなるべく詳細にと説明をしていると、I刑事は突然それを遮って、「まっさらに」して考えろという。つまり原因、経緯、きっかけなどなく「まっさらに」して考えろと。
つまり、これまで4年間にわたり嫌がらせを受けてきたこと。その嫌がらせを受ける原因となったこと。その嫌がらせがどのようなものであったかということ。それらを一切無しにしてこの事件を取り扱うというのだ。確かにI刑事の言う通り、「まっさらに」して考えたら、ただクルマをとめていた高齢者カップルのクルマに近づき運転席のドアの横に立った。犯人がパワーウィンドウを一番下まで下げ、被害者がそこに手を入れた。犯人は恐怖を感じてクルマをフルスロットルで急発進させた。
そういうことになる。
次にS刑事と話した。S刑事は「今どきは煽り運転が世間を騒がせている。手を入れた方が悪いことになるんだ。きっかけを作ったのはあなただ。これまでの経緯もおかしいと思う」と、「これまでの原因、経緯、きっかけなどは”おかしいこと”であり、手を入れた被害者が悪い。」と言った。
「保護」が決定された瞬間
突然S刑事が「あなたの言っていることはおかしい。あなたのやった行動はおかしい。両親に手を出すかもしれないという発言、このまま放置できない。保護する。」I刑事は「クルマの中に手を入れた。他人の生命身体に危害を与える恐れがあるから、保護する。」
被害者は被害者として犯人が逮捕されるであろうから、その事情聴取を受けていたと思っていた。それが保護という行為をされたのだ。被害者は保護というものを知らなかった。いったい何なのだろう?これからどうなるのだろう?と被害者は感じた。
まず、おそらく犯人は警察OBであろうと思われる。そしてまず4年間に渡り被害者を騙して家から追い出そうとしていたのは鳩山町役場長寿福祉課。そして嫌がらせをしていたのは西入間警察署。犯人は西入間警察署か鳩山町役場長寿福祉課から依頼を受けて、被害者に嫌がらせをしていたのだろう。
どうやら被害者が自らその嫌がらせに終止符を打つべく、犯人をそこに引き留め110番通報をするということは想定していなかったようだ。そして結果的には傷害事件(のちに過失運転致傷、救護義務違反で告訴)となってしまったのだ。
この状況を専門家に言わせると、まず手を入れた被害者は犯人に危害を加えようとしたわけではなく、第三者を介して問題を解決しようとしたのだが、手を入れたと言う行為は過失にあたり過失相殺になる可能性がないこともないとのこと。その場合、過失割合は1対9もしくは2対8であろうとのことであった。
さらに担当弁護士によると「クルマの運転席に手を入れる行為は犯人ではない」とのこと。
状況からすると、おそらく警察OBの犯人を犯人としないために、被害者が悪いということで喧嘩両成敗、少なくとも被害届を出させないようにした。もしくは、はじめから西入間警察署はこのようなチャンスを狙っていて、どこかの時点で被害者を保護しようとしていて、東松山警察署から連絡を受けた西入間警察署の指示で被害者を保護したのかもしれない。
最近のXでの情報提供や埼玉県精神医療人権センターの方の話によると、被害者怨(つまり父)から依頼されて被害者を保護、そして精神病院に入院させようとしたとのことである。
今、音声データを聞きなおしても、被害者が自分から近づき、運転席に手を入れたとはいえ、ひき逃げをされ、こちらは負傷している状況で、「手を入れたおまえが悪い」というのはあまりにも強引すぎる話の持っていき方だ。
「保護」によるその後の処遇
この後、留置所の一番奥にある保護室に18時間拘禁され、翌日に措置入院判断のために2つの病院に行く。2人目の医師に「措置入院の必要なし」と診断され開放される。そこから2年間刑事事件として犯人を処罰させるべく戦い続けた結果、被害届で不起訴、告訴で不起訴、どちらも検察審査会で不起訴相当の結論が出て、刑事事件としてはこの事件は終了した。
ただし、弁護士の薦めで事件後すぐに日弁連人権擁護委員会に申し立て、その後埼玉弁護士人権擁護委員会に移送された。その結論はまだ届いてはいない。
関連する法令
- 警察官職務執行法
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
- 日本国憲法
警察官職務執行法
第三条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。
一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第二十九条 都道府県知事は、精神障害者であって、そのまま放置すれば自傷他害のおそれがあると認められる者について、二人以上の指定医の一致した診察の結果に基づいて、入院させなければそのおそれを防止することができないと認めるときは、その者を指定入院医療機関に入院させる措置をとらなければならない。
日本国憲法
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されない。
専門家としての視点
- 警察官職務執行法における「保護」の基準と適用
- 精神保健福祉法に基づく措置入院との関連
- 憲法上の人権保障と「保護」の限界
警察官職務執行法における「保護」の基準と適用
警察官職務執行法第3条に基づき、警察官は異常な挙動を示す者が自己または他人に危害を加えるおそれがあると合理的に判断した場合、その者を警察署や医療機関に保護することができる。この保護措置は犯人捜査とは異なり応急の救護を目的とするものであるが実際には長時間の身体拘禁を伴うことが多く実質的な自由の制限と捉えられる場合がある。一 精神錯乱又は泥酔のため自己又は他人の生命身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者という条文に基づき警察官の判断で保護が行われるがこの判断基準が明確ではなく適用に恣意性が生じる可能性がある。さらに警察官職務執行法に基づく保護は二十四時間を超えてはならないとされるが裁判官の許可状があれば最長五日間の延長が可能でありこの期間中に保護の適法性が問われることはほとんどない。そのため適切な司法審査が行われないまま警察官の判断のみで自由が奪われることがあり人権侵害の問題が生じる。警察の保護は社会秩序維持の観点から重要であるがその適用が広範囲になりすぎると不当な拘禁につながる可能性があり今後の制度改正が求められる。
精神保健福祉法に基づく措置入院との関連
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条により都道府県知事は精神障害者であってそのまま放置すれば自傷他害のおそれがあると認められる者について二人以上の指定医の一致した診察の結果に基づいて入院させなければそのおそれを防止することができないと認めるときはその者を指定入院医療機関に入院させる措置をとらなければならないと定められている。警察官職務執行法に基づく保護がそのまま措置入院につながるケースがあり実際には警察の判断が措置入院の決定に大きく影響する。問題はこのプロセスが本人の意思とは無関係に進められる点であり精神疾患の診断が誤っていた場合でも入院措置が維持される可能性があることである。また措置入院中は家族や弁護士との連絡が制限され外部との接触が困難になることがあり適正な監視機能が働かない場合がある。精神保健福祉法では入院の必要性を慎重に判断することを求めているが現場の運用では行政や警察の判断が優先されることが多く本人の権利が十分に保障されていないケースが散見される。こうした状況を改善するためには保護措置と措置入院のプロセスの透明性を高めるとともに本人が異議を申し立てる機会を拡充することが必要である。
憲法上の人権保障と「保護」の限界
日本国憲法第34条では何人も理由を直ちに告げられ且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されないと規定されている。しかし警察官職務執行法に基づく保護は刑事手続における抑留や拘禁とは異なるとされているため憲法の適用範囲が曖昧になる場合がある。特に警察の判断で一方的に保護が決定されることが多く憲法が保障する適正手続の要件を満たしているとは言い難い。さらに保護された者が精神疾患の疑いをかけられた場合適正な審査を受ける機会が与えられないまま措置入院に移行することがあり憲法上の人権保障の観点から問題となる。第三十四条何人も理由を直ちに告げられ且つ直ちに弁護人に依頼する権利を与えられなければ抑留又は拘禁されないという規定があるが保護措置が実質的な拘禁となる場合この権利が実効性を持たないことが多い。実際には警察の保護が長期間に及ぶこともあり憲法の理念と矛盾する状況が生じている。このため警察官職務執行法に基づく保護措置の適用基準を厳格に定めること適正な監査制度を設けることそして本人が速やかに異議を申し立てることができる仕組みを整えることが求められている。
専門家としての視点、社会問題として
- 社会的影響
- 国際比較
- 今後の課題
社会的影響
警察官職務執行法に基づく「保護」は、公共の安全と個人の人権のバランスを問う社会問題として大きな関心を集めている。この制度は精神錯乱や泥酔などの理由で個人を一時的に保護することを目的としているが、実際には不当な拘禁や人権侵害の問題が頻発している。特に、警察の判断による保護措置が、本人の意思を尊重せずに強制的な入院や拘禁へとつながるケースがあり、適用のあり方が問われている。日本では、精神障害を理由にした強制的な措置入院が年間多数発生しており、警察による保護がその前段階として機能している。この仕組みが適正に運用されているかどうかについては、専門家の間でも意見が分かれており、法的な手続きの透明性や市民の監視が不十分であるとの指摘がある。また、社会的影響として、警察による保護が特定の社会的立場の人々に偏って適用される可能性も指摘されている。例えば、ホームレスや貧困層の人々が不当な理由で保護されるケースが報告されており、社会的弱者が制度の乱用によって過剰に影響を受ける可能性がある。さらに、警察の権限が広範囲にわたることで、恣意的な運用のリスクも高まり、市民の信頼を損なう要因となっている。このように、警察による保護は公共の安全を守る目的がある一方で、運用の透明性や人権保障の観点から重大な社会的課題を含んでおり、適切な監視機構の確立が不可欠である。
国際比較
日本における警察の「保護」制度は、海外の同様の制度と比較しても独自の特徴を持つ。例えば、アメリカでは、精神疾患を理由とした保護や強制入院は裁判所の許可が必要であり、即時の法的審査を受ける権利が保障されている。イギリスでも、精神衛生法に基づき、強制入院には医師の診断と裁判所の判断が必要であり、警察が単独で判断することはできない。しかし、日本では警察官の判断のみで一時的に保護が行われ、その後の措置入院がほぼ自動的に進行するケースが多く、本人が異議を申し立てる機会が十分に確保されていない点が問題とされている。また、欧米諸国では精神疾患を持つ人々の権利保護のための監視機関が整備されているのに対し、日本では独立した監査機関が存在せず、警察や自治体の裁量が大きいことが課題となっている。さらに、北欧諸国では、精神疾患を抱える人々への支援が社会福祉の一環として行われ、警察による強制的な介入は最小限に抑えられている。例えば、スウェーデンでは、地域医療機関が主体となって精神的に不安定な人々を支援する仕組みが整っており、警察が直接介入するケースは極めて少ない。これに対して、日本では医療機関と警察の連携が十分でなく、警察が第一対応者として関与することが多いため、人権侵害のリスクが高まっている。こうした国際比較から、日本における警察の保護制度の問題点が浮き彫りとなり、制度の改善が求められている。
今後の課題
日本における警察の「保護」制度は、法的正当性や人権保障の観点から見直しが求められている。第一に、警察官職務執行法第3条に基づく保護の適用基準を厳格化し、警察の裁量を制限する必要がある。現在の制度では、警察官の主観的な判断で保護が行われるため、誤った適用が発生するリスクが高い。これを防ぐためには、保護の実施に際して医療専門家の関与を義務付けるなど、独立した第三者の判断を導入することが有効である。第二に、保護措置を受けた者が迅速に異議を申し立てることができる仕組みを整備することが重要である。例えば、欧米のように裁判所の監視を強化し、即時の審査を受けられるようにすることが考えられる。現在、日本では保護の適法性が十分に審査される機会が少なく、本人の権利が制限される可能性があるため、司法審査を強化することが望まれる。第三に、精神保健福祉法と警察官職務執行法の連携を見直し、警察が第一対応者として過度に関与しないような仕組みを構築する必要がある。例えば、地域の医療機関や福祉機関が主体となって精神疾患を持つ人々を支援し、警察の介入を最小限に抑える仕組みを作ることが求められる。加えて、警察の保護が差別や社会的偏見を助長するものであってはならず、特定の社会的弱者が不当な取り扱いを受けないような監視体制を強化することも不可欠である。以上のような課題に対処することで、警察の保護制度をより公正で透明性のあるものとし、人権を尊重する社会の実現につなげることができる。
アクセス(日本全国各地主要都市より)
①航空機でのアクセス
- 北海道(新千歳空港):新千歳空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 東北(仙台空港):仙台空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 北陸(小松空港):小松空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 中部(中部国際空港):中部国際空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 近畿(関西国際空港):関西国際空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 中国(広島空港):広島空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 四国(松山空港):松山空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 九州(福岡空港):福岡空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 沖縄(那覇空港):那覇空港 → 羽田空港 → 東京駅(JR)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
②新幹線でのアクセス
- 北海道(新函館北斗駅):新函館北斗駅 → 東京駅(東北・北海道新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 東北(仙台駅):仙台駅 → 東京駅(東北新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 北陸(富山駅・金沢駅):富山駅・金沢駅 → 東京駅(北陸新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 中部(名古屋駅):名古屋駅 → 東京駅(東海道新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 近畿(新大阪駅):新大阪駅 → 東京駅(東海道新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 中国(広島駅):広島駅 → 東京駅(東海道・山陽新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
- 九州(博多駅):博多駅 → 東京駅(東海道・山陽新幹線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
③電車でのアクセス
- 東京駅 → 池袋駅(JR山手線)→ 東武東上線 東松山駅
- 大宮駅 → 川越駅(JR川越線)→ 東武東上線 東松山駅
- 新宿駅 → 池袋駅(JR山手線)→ 東武東上線 東松山駅
- 横浜駅 → 東京駅(JR東海道線)→ 池袋駅 → 東武東上線 東松山駅
④バスでのアクセス
- バス路線なし(東松山駅から徒歩20分)
まとめ
警察官職務執行法に基づく「保護」は、公共の安全と個人の人権のバランスを問う重要な制度であるが、実際の運用では恣意的な適用や人権侵害のリスクが指摘されている。特に、精神保健福祉法の措置入院と密接に関連し、警察の判断のみで強制的な入院措置が行われる場合がある。国際比較では、日本の制度は欧米諸国に比べて裁判所の監視が弱く、司法審査の機会が限られている。今後の課題として、適用基準の厳格化、異議申し立ての手続きの確立、医療機関や福祉機関との連携強化が求められる。