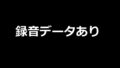鳩山町の長寿福祉課長が電話応対中に発した「死なないでね~」という言葉は、単なる冗談では済まされない。これは、住民から繰り返し指摘された過去の不適切発言に対する逆上と報復の言葉であり、制度内部から市民の声を封じる構造を象徴している。地方自治体における職責の自尊が過剰に肥大化し、それを咎める住民に対し制度的優位の立場から嘲笑をもって応じる――この発言が示すのは、地方行政の現場に潜む支配構造と公共性の喪失である。役場職員としてあるまじきこの言動が、なぜ社会的に許容されないのか、そしてなぜ今なお問題視され続けているのかを明確に掘り下げる必要がある。
「死なないでね~」
- これまでは
- 「死なないでね~」
- 考察「死なないでね~」
これまでは
2023年2月9日、4年間およぶ鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせの結果、ひき逃げ事件に発展し、被害者は被害者として東松山警察署に行った。東松山警察署に向かうパトカーの中でスマホの録音を始めた。事情聴取中に謎の警察による不当な保護(警察官職務執行法第3条)。18時間拘束された挙句、2つの精神病院に措置入院判断のために連れていかれ、結果的には開放された。
鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせが行われた理由としては、幼少期からの父によるDV、パワハラ、モラハラがあり、離婚後「これ以上人生を狂わされたくない」という思いから同居を拒否するも、母からの「二度とそのようなことは起こらない」との言葉を信じて、また「今度は何があろうと絶対に家から出ていかない」と心に決める。
同居をはじめてしばらくすると、相変わらずはじまる父のパワハラ、モラハラ。「出ていかない」ための抵抗により、父は警察、役場を利用して追い出そうとする。
鳩山町役場長寿福祉課、精神保健福祉士の不手際により、父の目論見を知った被害者は父を家から追い出す。
精神保健福祉士の行動はその後も不審極まりなく、やがて母も去ることとなる。
ひとり残された被害者は一時、精神保健福祉士を唯一の頼りとするが、やがてその目論見が自己の、所属組織、さらには警察へのアピールであったことを知る。
精神保健福祉士との関係を遮断すると、西入間警察署、鳩山町長寿福祉課、犯人による嫌がらせが始まる。
一方、精神保健福祉士の行動を追及し始めた被害者は、省庁を含むあらゆる組織に問い合わせを重ね、やがて二巡目で鳩山町長寿福祉課長にたどり着いた。
被害者は長寿福祉課長と6か月にわたり面談を重ねたが、その最中、課長は被害者に対し、冷徹に「孤独死とか大丈夫か?」と発言した。
さらに、その後も電話での会話の中で「本人が楽になるならそれもひとつの手だ」との持論を展開・・・。
「死なないでね~」
さすがに、「行政職員」、「役場職員」、「福祉課職員」、ましてや「福祉課部門の長」の発言としての、彼の今後を心配し、「持論を持つことは構わないと思うが、対外的にその発言は許されるものではない」と忠告すると・・・。
あろうことか、鳩山町長寿福祉課長は、被害者との電話中に、口を受話器に押し当て、
「死なないでね~」
被害者が感じ取ったのは、田舎町の役場の課長職が、とてつもなく名誉な職責であって、町民であっても、その名誉な職責を傷つける発言、つまり課長の発言をたしなめる発言を、行ってはならない。
それが町民に対し、役場職員、福祉課長が死を軽んじた発言をした、つまり「孤独死とか大丈夫か」、「本人が楽になるならそれもひとつの手だ」という発言をしたということについて、たとえ町民であっても、いや、さらに言えば町民であろうとなかろうと、田舎町の役場の課長職の名誉を傷つけてはならない。
田舎町の役場の課長職というのは、その職責に見合っているとは言えない発言をしても、町民ごときにとやかく言われる筋合いはない。
さらに言えば、田舎町の役場の業務は町民へのサービス(住民サービス)ではなく、町民は田舎町の役場の職員のように、田舎町の役場の課長にひれ伏すべき立場であると言いたいのだ。
と感じた。
考察:「死なないでね~」
「死なないでね~」
鳩山町の長寿福祉課長が、町民との電話の最中に、受話器に口を押し当てて、冗談めかした調子でこう発言した。
公務としての電話対応中に、町の福祉行政を担う課長職が町民に向けて発した一言である。
しかもこの発言は、相手から課長自身の発言姿勢について忠告を受けた直後に行われた。
発言の語調は明らかにふざけており、受話器に口を押し当てるという行為もまた、通常の応対では見られない演出的なものだった。これは偶然や無意識ではなく、意図的に行われた挑発的動作である。
「死なないでね~」という言葉は、表面的には軽く聞こえるかもしれない。だが、この場面において発せられたそれは、町民に対する嘲笑と圧力の象徴として理解されるべきである。
行政職員が、批判や異議の声に対し、冗談を装った言葉で応じるという態度は、倫理上重大な逸脱である。
特に福祉を担当する部署の責任者が、生命や死を軽く扱うような言葉を発することは、組織の信頼性そのものを損なう行為である。
この一言は、個人の資質に還元されるべきではない。
制度の内側にいる者が、制度に対して抗議する市民に向けて、どう振る舞うか。
その一端が、電話の受話器越しに現れたということに他ならない。
記録すべきは、「死なないでね~」という言葉だけでなく、それが発せられた状況と態度、そして発言者の立場である。
ふざけた一言であっても、それが制度の側から発せられたものである以上、町民にとっては明確な言語的暴力であり、絶対に見過ごされてはならない。
関係する法令
- 地方公務員法
- 国家賠償法
- 民法
- 障害者虐待防止法
地方公務員法(第33条)
すべての職員は、全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
地方公務員法(第35条)
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
国家賠償法(第1条)
国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、故意又は過失により違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
民法(第709条)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
障害者虐待防止法(第2条)
この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者に対する虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者に対する虐待及び使用者による障害者に対する虐待をいう。
障害者虐待防止法(第7条)
市町村は、障害者に対する虐待を受けたと思われる者を発見したときは、これを通報し、及び必要な対応を行わなければならない。
専門家としての視点
- 制度的自尊と咎めへの報復構造としての「死なないでね~」
- 福祉課長という立場に固執する者の言語的復讐
- 公共発言における権力者の逆上と失言の本質
制度的自尊と咎めへの報復構造としての「死なないでね~」
「死なないでね~」という言葉は、鳩山町長寿福祉課長が町民から繰り返し咎められた結果として発せられたものであり、偶発的な発言でも感情的な失言でもない。前提として課長は、「孤独死とか大丈夫か」「本人が楽になるならそれもひとつの手だ」といった極めて不適切な発言を公務中に重ねていた。これを町民から明確に指摘され、忠告されたとき、彼は制度内部の自尊心と自己正当化の欲求からくる防衛反応として、言語による報復手段を選択した。「死なないでね~」という表現には、相手を気遣う意図は一切含まれておらず、批判を封じ、矮小化する意図が明確に読み取れる。これは制度の側が、市民の異議申し立てを抑え込む際に使う言語的抑圧の典型例であり、福祉課長という立場の者が発することで、構造的暴力の象徴となっている。地方公務員法第35条が定める「職員の信用保持義務」に明確に違反しており、制度の外部に対する敬意を欠いた姿勢が如実に表れている。地方自治体の行政職員は市民への奉仕者であるべきところ、課長は職責を自己の権威として捉え、その権威に対して市民が咎めを行うこと自体を「許せない無礼」として認識していた。そのため、「死なないでね~」は、制度的優越に浸る者が、市民に向けて仕掛けた報復であり、制度内の序列意識が生み出した言語による黙殺命令である。
福祉課長という立場に固執する者の言語的復讐
この言葉がもつ核心的な意味は、「町民ごときが、制度の長である自分を指導・忠告してよいはずがない」という上下意識に基づく言語的復讐である。特に「死なないでね~」は、相手を気遣う形を借りながら、その実、言語的主導権を取り戻し、相手の抗議を無効化しようとする攻撃的言葉である。しかも、この発言が課長という制度的肩書をもつ者の口から、意図的な演出を伴って発せられた点を考慮すると、その言語は明らかに市民への抑圧と嘲弄を含んでいる。地方公務員法第33条は職務への誠実性と奉仕義務を規定するが、このような発言は職務遂行ではなく、立場の誇示と自己防衛に過ぎない。さらに国家賠償法第1条は、公務員が「故意または過失」によって他人に損害を与えた場合、その所属自治体が損害賠償責任を負うと定めており、本件のように明確な意図に基づいた発言が精神的損害を与えた場合には、町が責任を問われうる。課長は福祉の専門性ではなく、「田舎町の役場の課長である」という職責的名誉を優先し、住民の声を聞くよりも、その発言権を打ち砕くことを選んだ。ゆえにこの言葉は、「行政職員として許される表現の範囲を超えているか否か」ではなく、「行政職員であるからこそ絶対に許されない発言」であり、もはや懲戒処分や訓告で済む次元の問題ではない。
公共発言における権力者の逆上と失言の本質
「死なないでね~」という発言の本質は、公共の場における権力者が、自身の発言を正当化できなくなったときに示す逆上と、統制を失った言語行為である。この言葉は、表面上のふざけた語調とは裏腹に、制度的立場の喪失を避けようとする強い動機から発せられた防衛反応である。批判に耐えられなかった行政職員が、自らの上位性を言葉によって再構築しようとし、結果として人間の尊厳を踏みにじる言語攻撃を選んだ。民法第709条の「故意または過失による法律上保護される利益の侵害」は、こうした公共の場での発言にも適用され、市民が受けた精神的苦痛は明確に損害として評価されるべきである。さらに、障害者虐待防止法第2条において定義される精神的虐待の一類型としても、このような言語行為は軽視できない。制度的立場にある者が、制度の批判に対し言葉で応じるのではなく、揶揄や侮辱で応答した場合、その構造は明確に「制度の内部からの暴力」として成立する。しかも5年経った現在でも嘲笑の的となり続けているのは、それが偶発的な失言ではなく、制度意識に基づいた必然的発言であったからである。この発言は、行政制度が市民の声を敵視し、封じようとする時にどのような形をとるかを端的に示すものであり、それゆえに風化させてはならない。
専門家としての視点、社会問題として
- 地方行政における「役場階級意識」の固定化と住民軽視
- 田舎行政における閉鎖性と言語的報復の構造
- 公務員制度が生む「内部者による公共空間の私物化」問題
地方行政における「役場階級意識」の固定化と住民軽視
「死なないでね~」という言葉に象徴されるのは、地方行政に根深く存在する「役場階級意識」の固定化である。特に小規模自治体では、役場内の肩書がそのまま社会的身分として流通しやすく、それが住民との間に垂直的な力関係を生み出している。住民の苦情や指摘を「町民ごときが」という視点で捉えたとき、その反応は制度の保守ではなく自我の保守へと移行し、職責を盾にした排他的態度が出現する。「死なないでね~」という言葉は、忠告を受け入れるべき立場の者が、逆にその忠告者を嘲弄し、自らの制度的優位性を誇示し直そうとした行為である。これは「全体の奉仕者」としての職務観が喪失し、「全体を管理する者」という誤認識にすり替わっていることを意味している。このような権力構造が日常的に維持されている場合、住民は制度に対して声を上げること自体を萎縮し、行政との関係は一方的な支配と服従へと変質する。社会学的に見れば、こうした言語による侮辱は「象徴的暴力」として定義され、市民社会の健全性を損なう要因となる。つまりこれは一職員の問題ではなく、制度的上位に位置する者が制度を私物化することで、町全体の公共性が損なわれるという社会問題にほかならない。
田舎行政における閉鎖性と言語的報復の構造
小規模自治体における行政組織は、内部構造の閉鎖性が高く、外部からの批判を敵視しやすい傾向にある。とりわけ役場という空間は、住民が訪れる窓口でありながら、職員にとっては「自分たちの職場」であるという内向きの認識が強く、結果として市民との対話は上下関係の中で処理されがちである。「死なないでね~」という発言は、その閉鎖性から生じた内部者意識が、批判を受け入れられず、逆にその批判者に報復するという言語的暴力として顕在化した事例である。この報復は、職員個人の資質というよりも、組織文化に根差す対外姿勢の問題であり、住民に対する言語の選択が抑止されない環境が常態化していることを示す。公共組織においては、制度への異議申立てが保障されてこそ公共性が維持されるが、閉鎖的な役場文化ではそれが敵意とみなされやすい。その結果として、制度の内側から「ふざけた口調」で語られる言葉が、外側の市民に対しては明確な威圧となる。このような発言が長く記憶され、問題視され続けるのは、それが単なる失言ではなく、田舎行政が抱える社会構造的問題、すなわち「制度が外部の声に耳を塞ぐ構造」を象徴しているからである。
公務員制度が生む「内部者による公共空間の私物化」問題
本件における「死なないでね~」という発言は、公務員制度に内在するもうひとつの問題、すなわち「公共空間の私物化」が起こる構造を示している。制度的立場にある者が、制度そのものを自己の名誉の源泉として扱い、それに異を唱える外部の住民に対して攻撃的態度をとる時、その瞬間から公共空間は内部者の私物と化す。このような言語行動は、公的立場を使って私的感情の報復を行うという点で、制度そのものへの重大な背信である。「死なないでね~」は、批判を受け入れる器量のない行政職員が、自身の優越性を誇示するために発した言葉であり、同時に公共の場を私的な舞台に変える暴挙であった。公務員制度の本質は、個人が制度の顔としてふるまう責任と抑制を要請するものであり、その制度を武器として市民に向けることは、制度の存在意義を根本から破壊する行為である。また、このような発言が「冗談」や「軽口」として処理される風潮もまた、公共空間における権力不均衡を助長する。公共は誰のものか。それは制度を管理する者のものではなく、制度に参加するすべての市民のものである。この問いを突きつける出来事として、「死なないでね~」という言葉は社会問題として認識されなければならない。
まとめ
「死なないでね~」という発言は、単なる軽口や冗談ではなく、制度的優越意識に基づく明確な報復表現であり、町民からの正当な忠告に対し、制度の内側から言語的優位で抑え込もうとする行為である。課長という職責に過度に自尊を抱いた結果、咎められること自体に強い拒否反応を示し、その拒否が言葉による嘲弄として表出した。「孤独死とか大丈夫か」「本人が楽になるならそれもひとつの手だ」といった本来発してはならない言葉に対する市民の指摘に対し、それを謝罪も撤回もせず、むしろその指摘を侮辱的に笑い飛ばすかたちで「死なないでね~」と返す態度は、制度的暴力の典型である。この発言は新採用の役場職員でさえ慎むべきものであり、課長職がそれを口にした時点で、個人の資質を超えた組織的な問題へと拡大する。制度の名誉を守ることを優先し、制度の対象である町民を見下すその構造は、地方行政が抱える根本的課題であり、「死なないでね~」という言葉を通じて社会が直面するべき問題として浮かび上がったのである。