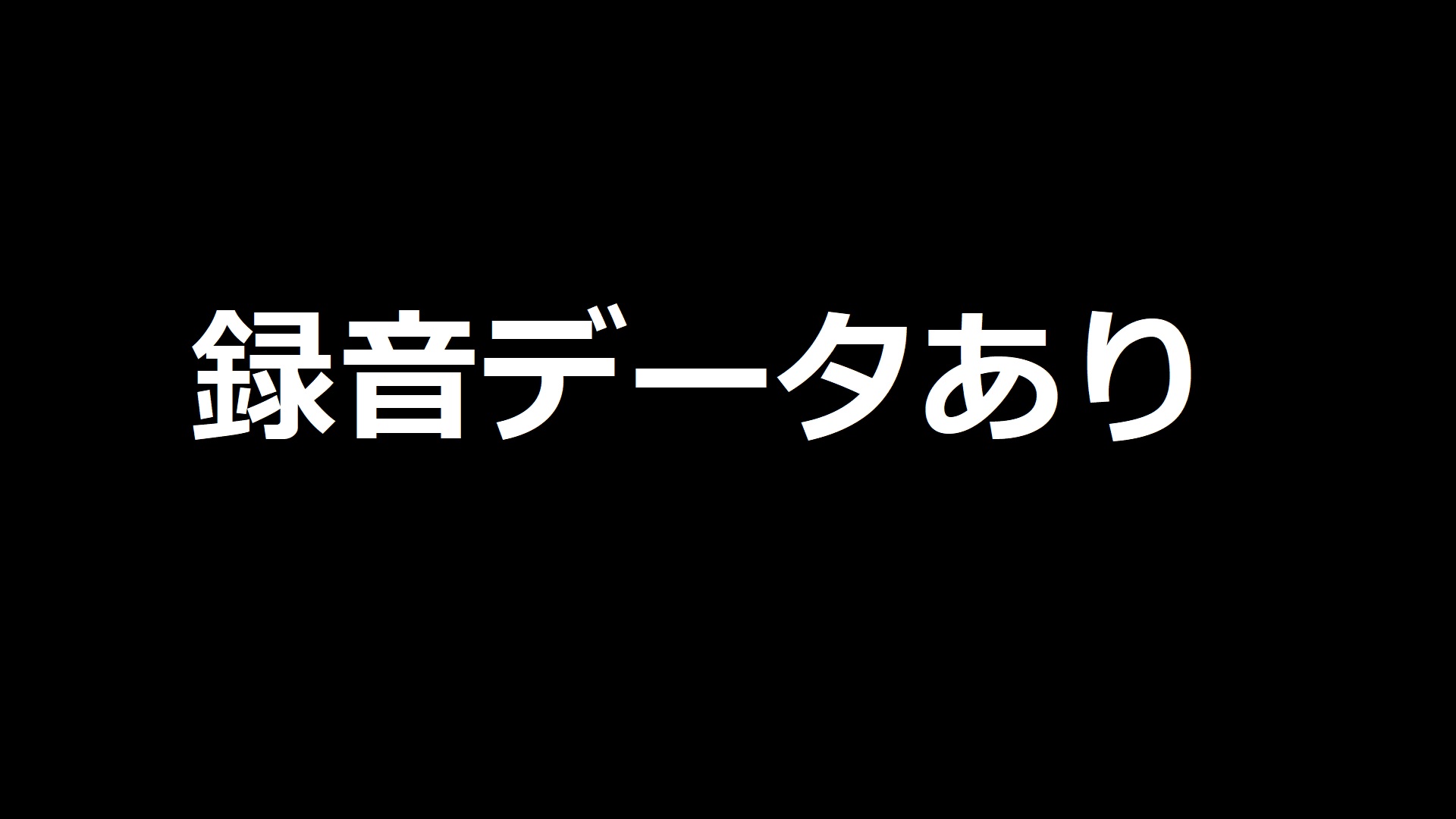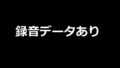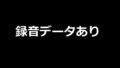家庭内での暴力や心理的虐待は、単なる家庭の問題ではなく、社会全体が向き合うべき課題である。児童虐待防止法や刑法においても、家庭内での暴力や精神的支配は問題視されるが、多くの場合、被害者は外部に助けを求めることが難しい状況にある。特に成人した子供に対する親の過干渉や強要は、法的にどのように位置付けられるのか。今回の記事では、法的視点から家庭内支配の問題を分析し、解決策を探る。
父の横暴は続く
- DVが終わるとモラハラ、パワハラ
- 結婚してからも干渉してくる迷惑親
- 引きこもりにもグラデーションはある
DVが終わるとモラハラ、パワハラ
2023年2月9日、被害者はひき逃げ事件の被害を受けた。110番通報、119番通報、実況見分の後、パトカーで東松山警察署に連れて行かれる。そのパトカーの中からスマホで録音を始めたことにより録音データが残っている。その後謎の警察による不当な保護措置を受けるが、刑事は客観的に考えると、クルマに近づき手を入れた被害者が悪いと言う。
しかし、そこには理由があった。鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人から4年間にわたる嫌がらせを受けていた。その嫌がらせの理由は、父との確執であった。前回に続いて、事件、保護の根本にある父の横暴について、ここに書き記していく。
やがて被害者が肉体的に父を上回るようになると、今度はパワハラ、モラハラだ。父の思い通りにならないことがあると、怒鳴る、物を投げつける。また人生は父の描いたとおりに歩むべきとされ、かつ父を上回ってはならない。
一例を挙げると、父が風呂に入ると、風呂の中でタオルで身体をぬぐう。すると風呂は垢だらけになる。被害者たちはその垢だらけの風呂に入らなければならないのだ。とある年末、さすがに年末くらいはきれいな風呂に入ろうと湯を入れ替えて風呂に入ると、父は激怒。大声でわめきながら風呂の蓋を湯船に叩きつける。その蓋のひび割れは、今も残っている。
被害者が就職をして、過酷な労働環境の中で椎間板ヘルニアを患い、1ヶ月入院した。退院間近になり、病院の外を歩いていると、足がつってしまった。医師に相談すると、1週間退院を延ばそうということになった。父にそのことを電話で報告すると、そこから1時間以上にわたる説教。寒い病院の1階の待合室で1時間以上立ちっぱなしという状況であった。
結婚してからも干渉してくる迷惑親
被害者は就職して赴任先が長野であった。そこで結婚したのだが毎週末に父と母が埼玉から来る。そしてある日被害者が帰宅すると、父が家に帰ると言う。聞いてみると父が元妻とケンカをしたのだと言う。人の新婚家庭に毎週末現れ、そして挙句の果てに元妻とケンカをして帰る。
その後埼玉の実家で同居をするが、またここで父と元妻の諍い、母の金への執着。そんなことなら同居などしなければよかったという状況で、結局1年で被害者たち家族は元妻の実家へと移転する。ここで両親とは縁を切る。
被害者は父母と縁を切ったのである。これは自分の新しい家族、元妻、2人の子供との4人での家庭を守る目的であった。
引きこもりにもグラデーションはある
よく引きこもり、家庭内暴力などと地上波テレビなどのオールドメディアの情報番組などで、勧善懲悪的論調で言っているが、まるで被害者のような人間がただただ親に甘えてそのような状態になっていると思われがちである。しかし、同じ引きこもり、家庭内暴力であってもグラデーションというものがある。
親からのDV、モラハラ、パワハラ、新婚家庭への過剰な干渉、同居でのトラブル、そして元妻、元妻実家とのトラブル、家庭を守ろうとすればするほど、他者からの圧力は強まり、また自分の人生の方向性までも自分で選択できなくなる。やがて心は病み、さらにそのことを咎められ孤立を深める。
鬱病、双極性障害と病状は悪化し、やがて社会からのドロップアウト。そんな境遇の中、自ら立ち上がろうとしても、父からの父の常識である「雇用されて働く」という道に無理やり引き戻されようとする。
続く父の支配と家族の苦悩
- 身体的暴力から精神的支配へ
- 結婚後も終わらない干渉
- 社会から孤立する人生の背景
身体的暴力から精神的支配へ
この家庭では、父の支配が長年続いていた。かつては身体的暴力が日常だったが、子が成長し力関係が変化すると、暴力はモラハラやパワハラへと形を変えた。怒鳴る、威圧する、物を投げるといった行為が続き、家族は常に父の機嫌を伺いながら生活を送ることになった。例えば、父は風呂の中で体をタオルで拭く習慣があり、その結果湯が垢だらけになっていた。しかし、それを指摘すると激昂し、風呂の蓋を湯船に叩きつけることもあった。そのひび割れは今も残っている。さらに、子が就職し過酷な労働環境で椎間板ヘルニアを患い1ヶ月入院した際、退院直前に足がつり、医師と相談して1週間退院を延ばすことになった。そのことを父に報告すると1時間以上にわたり電話で説教を受け、寒い病院の待合室で立たされ続けることとなった。父の支配は身体的暴力から精神的支配へと変化しながらも続いていた。
結婚後も終わらない干渉
この家庭では、結婚後も父母による干渉が続いた。子は就職を機に長野へ赴任し、そこで結婚したが、毎週末のように父母が埼玉から訪れた。新婚家庭に両親が頻繁に押しかけるだけでなく、ある日には父が「帰る」と突然言い出し、理由を尋ねると元妻と口論になったとのことだった。新婚家庭であるにもかかわらず、元妻と父の争いが繰り返され、家庭の安定は阻害されていった。その後、埼玉の実家に戻り、両親との同居を始めるが、ここでも父と元妻の争いが絶えなかった。さらに、母の金への執着も家庭の問題を深め、結果として1年で元妻の実家へ移り住む決断をする。この時、子は両親と完全に縁を切ることを決意する。自らの家庭を守るために必要な選択であったが、それでも父の影響は完全には消え去らなかった。
社会から孤立する人生の背景
世間では引きこもりや家庭内暴力が一方的に語られることが多いが、その背景には複雑な事情がある。この家庭では、親のDVやモラハラ、新婚生活への過剰な干渉、同居でのトラブル、さらには元妻やその実家との軋轢といった要因が積み重なり、家庭を守ろうとするほど他者からの圧力が強まっていった。その結果、本人の選択肢は次第に狭まり、精神的な負担が増していった。やがて心は病み、鬱病や双極性障害を発症し、社会との接点を失うことになる。それでも社会は本人を「甘え」として扱い、厳しい視線を向ける。そんな状況の中で立ち上がろうとすると、父は「雇用されて働くことが正しい」という自身の価値観を押し付け、再び支配を強めようとする。引きこもりという言葉では片付けられない背景があり、そこには長年の家庭内の抑圧と社会的な孤立が深く関係していた。
関係する法令
- 児童虐待防止法
- 刑法(暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪)
- 不法行為(民法第709条)
児童虐待防止法
(第2条) 児童虐待とは、親権を行う者その他の監護する者がその監護する児童(18歳未満の者)に対し、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト(養育放棄)、心理的虐待を加えることをいう。
刑法(暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪)
(第208条) 暴行を加えた者が、人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(第204条) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(第222条) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(第223条) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処する。
不法行為(民法第709条)
(第709条) 故意又は過失により他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
家庭内支配と法的視点
- 親による心理的虐待と法的対応
- 家庭内暴力がもたらす法的責任
- 過干渉と法的境界線
親による心理的虐待と法的対応
児童虐待防止法第2条では、親権者や監護者による心理的虐待も児童虐待と定義されている。例えば、「お前は価値がない」「何をやっても無駄だ」といった言葉を繰り返し浴びせることは、心理的虐待に該当し得る。また、刑法第222条の脅迫罪も関連する。生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。親が子に対し恐怖を与え、意のままに操ろうとする行為が、法的に問題となる可能性がある。さらに、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求も検討できる。精神的苦痛を与えた行為により、精神疾患を発症した場合、加害者に対して損害賠償請求が可能となる。家庭内での心理的虐待は密室で行われることが多く、被害者が外部へ助けを求めることが難しいという特徴がある。そのため、児童相談所や警察への相談が困難な状況も生じやすい。日本では、家庭内の問題として軽視されがちだが、法律上は明確に保護される権利がある。虐待が日常化している場合、児童相談所や専門機関に相談することで、法的措置を講じることが可能である。虐待を受けた子供は成人後もその影響を受けることが多く、精神的負担を抱えるケースが少なくない。虐待の証拠を残すことも重要であり、録音や日記の記録を行うことで、法的手続きにおいて有効な証拠となる場合がある。
家庭内暴力がもたらす法的責任
刑法第204条では、故意に人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されると定めている。家庭内であっても、身体的暴力はこの傷害罪に該当する可能性がある。また、暴行罪(刑法第208条)も考慮される。人を傷害するに至らなかった場合でも、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処される。親が子に対して暴力を振るう行為は、家族内の問題ではなく、刑事事件となる可能性がある。また、DV防止法が適用される可能性もあり、裁判所により接近禁止命令などが出される場合がある。家庭内の暴力は外部に知られにくいため、警察への通報が遅れる傾向があるが、暴力を受けた場合には速やかに警察に相談し、被害届を提出することが望ましい。身体的暴力だけでなく、継続的な威圧行為や精神的な圧迫も違法となる場合がある。日本では家庭内の問題として処理されがちだが、刑事事件として対処することが可能であり、適切な法的措置を講じることで、被害者の保護が図られる。加害者が暴力を認めない場合でも、怪我の写真や診断書を証拠として提出することで、法的手続きを進めやすくなる。
過干渉と法的境界線
民法第709条に基づき、故意または過失によって他人の権利を侵害した場合、加害者には損害賠償の責任が発生する。過度な干渉が原因で精神疾患を発症した場合、親に対して賠償請求が可能となる。また、刑法第223条の強要罪も関連する。生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせた者は、3年以下の懲役に処される。親が成人した子に対し、自身の価値観を強要し、自由を奪う行為は、法律上問題となる場合がある。特に日本では、親の意向が強く反映される文化があるため、過干渉が問題になりやすい。過干渉が精神的苦痛を伴う場合、それが継続的に行われることで、生活の自由が制限される可能性がある。法的に独立した成人であれば、親の干渉から逃れる権利を有するが、親が支配的な関係を強要する場合には、法的手続きを検討する必要がある。過干渉が生活に支障を及ぼす場合、弁護士や専門機関に相談することで、対応策を見つけることができる。精神的負担が大きい場合には、医療機関で診断を受けることも重要であり、診断書が証拠となる場合もある。
家庭内支配の深刻化と社会的課題
- 心理的虐待の連鎖と社会的影響
- 家庭内暴力の実態と法の限界
- 親の過干渉が生む社会的孤立
心理的虐待の連鎖と社会的影響
家庭内における心理的虐待は、被害者に深刻な精神的ダメージを与えるだけでなく、その影響が世代を超えて受け継がれることが社会問題として指摘されている。児童虐待防止法第2条では、親権者または監護者が児童に対し心理的虐待を加えることを虐待として定義しているが、これは単なる家庭内の問題ではなく、将来的な社会全体への影響を考える必要がある。心理的虐待を受けた子供は、自己肯定感の低下や対人関係の不適応を引き起こし、ひいては社会的孤立を深めるリスクが高まる。さらに、成長後に親になった際に同様の行為を繰り返す可能性があるため、社会全体でこの問題を認識し、早期介入が求められる。現在の日本社会では、家庭内の問題が「親子の関係」として処理される傾向が強く、被害者自身が問題を表面化しづらい状況にある。心理的虐待を受けた者が相談できる環境の整備や、家庭外での支援体制の充実が不可欠であり、自治体やNPOの役割がより重要になっている。虐待の証拠が残りにくいことも問題であり、加害者が責任を問われる機会が少ない。録音や日記などの記録が、法的手続きの中で有効な証拠となるため、被害者自身が自衛手段を持つことも必要となる。家庭内の支配構造が社会全体に与える影響を考えたとき、単に法律を強化するだけではなく、教育や啓発活動による意識改革が必要不可欠である。
家庭内暴力の実態と法の限界
家庭内暴力は、単に個人的な問題ではなく、社会全体に影響を及ぼす犯人行為であるにもかかわらず、現在の法制度では被害者が適切に保護されないケースが多い。刑法第204条に基づき、他者に傷害を負わせた場合には15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるが、家庭内での暴力は外部に知られにくいため、適用される機会が少ない。また、刑法第208条により、傷害に至らない暴行も処罰の対象となるが、家庭内の問題として処理されるケースが多く、被害者が警察に相談できない状況が続いている。DV防止法の枠組みの中で保護命令が発令されることもあるが、親子間の暴力に対しては適用が難しく、実際には法の空白地帯となっている。親からの暴力を受けた被害者は、精神的なダメージを抱えながらも加害者である親との関係を維持しなければならない状況に陥ることが多い。社会全体として、家庭内の暴力を犯人として捉え、被害者が迅速に支援を受けられる仕組みが求められている。警察の対応の強化や、シェルターの拡充、第三者機関による早期介入が不可欠であり、暴力の連鎖を断ち切るための包括的な施策が必要となる。
親の過干渉が生む社会的孤立
日本社会における親の過干渉は、単なる家庭内の問題ではなく、若者の社会的孤立を深刻化させる要因の一つとなっている。民法第709条では、故意または過失により他人の権利を侵害した者は損害賠償の責任を負うとされているが、親の過干渉が精神的苦痛を与えた場合にも適用される可能性がある。特に、成人した子供が親の意向に逆らえず、自分の進路や生活を自由に選択できない状況は、精神的圧迫として問題視されるべきである。刑法第223条の強要罪では、義務のないことを行わせる目的で脅迫や暴力を用いた場合に処罰の対象となるが、家庭内での圧力は外部から見えにくく、実際に刑事事件として扱われることは稀である。親の過干渉によって自立を阻害された若者は、社会との接点を失い、経済的にも依存を余儀なくされることで、社会的孤立を深めるリスクが高まる。日本の文化的背景には「親の言うことを聞くのが当然」という価値観が根強く、過干渉が問題視されにくいという現状がある。しかし、精神的な支配が続けば、被害者は自らの人生を自由に選択できず、精神疾患のリスクが高まるだけでなく、将来的な社会復帰も難しくなる。現状を改善するためには、家庭内の問題を外部に相談できる環境の整備や、法律の適用範囲を拡大し、過干渉による精神的な被害も法的に認められる仕組みを作ることが重要である。
まとめ
家庭内における心理的虐待や過干渉、暴力は単なる個人的な問題ではなく、社会全体に影響を及ぼす深刻な課題である。児童虐待防止法では18歳未満の子供に対する心理的虐待を禁止しているが、成人後の親子関係における精神的支配や暴力もまた、刑法や民法の観点から問題視されるべきである。特に親の過干渉が成人後の社会的自立を阻害し、精神的苦痛を引き起こす場合、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性がある。家庭内暴力についても、刑法第204条の傷害罪や第208条の暴行罪が適用されるが、家族間の問題として軽視されがちな現実がある。社会全体として家庭内の人権侵害を問題視し、被害者が支援を受けられる体制を強化することが求められている。親子関係における権力の乱用を防ぐためにも、法的知識の普及と、適切な相談機関の利用が必要不可欠である。