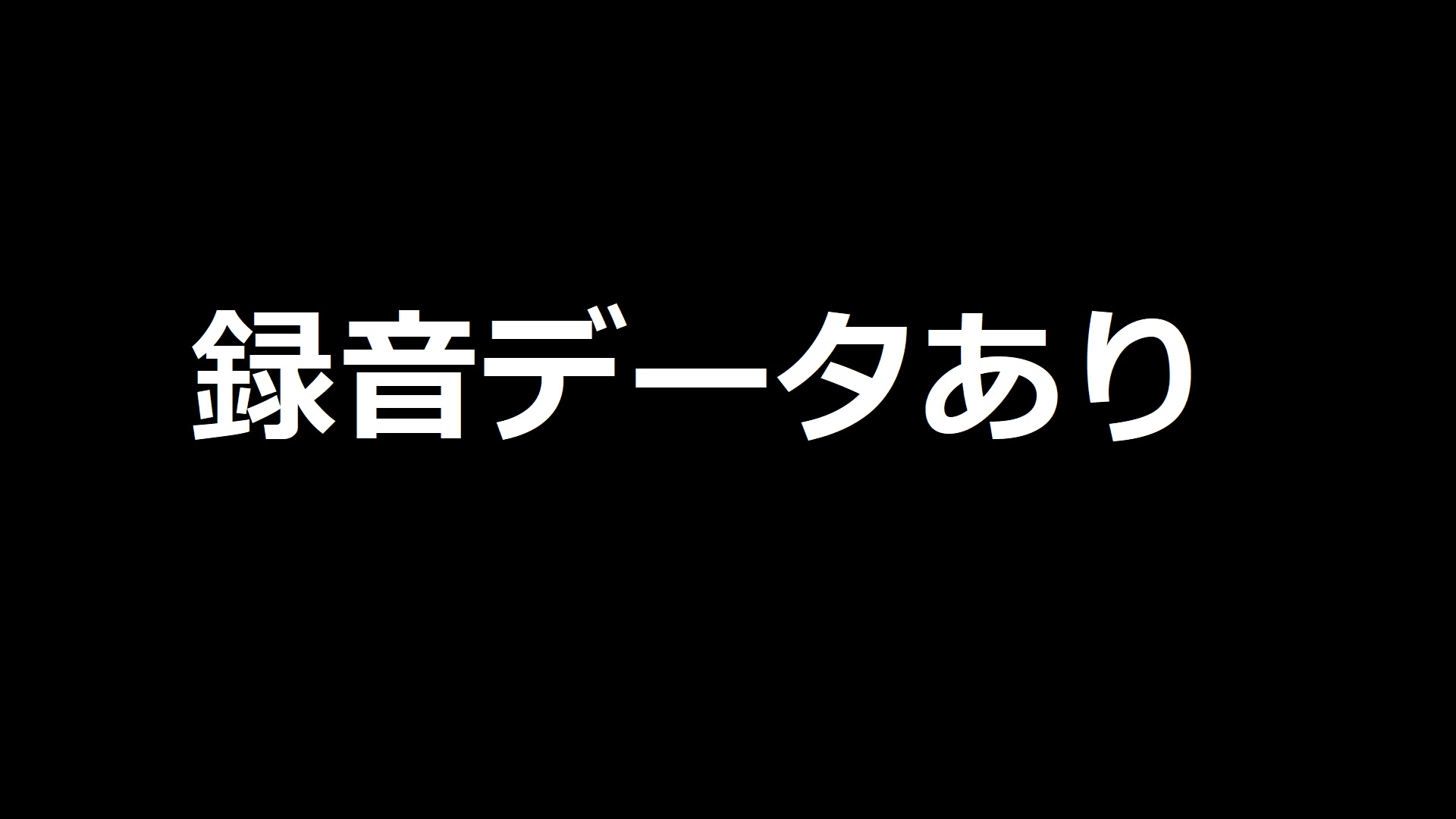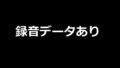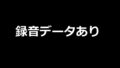親子の関係は幼少期の影響が大きく、成人後もその影響を受け続けることがある。特に親が強い支配的な傾向を持つ場合、子供が独立した後もその影響から完全に逃れることは難しい。家庭内の支配構造が続くことで、自由な意思決定が阻害され、親の意向に従わざるを得ない状況が生まれる。家族の中で築かれた力関係が、社会的な問題へと発展するケースもあり、このような状況から抜け出すには心理的な認識の変化と外部からの支援が必要となる。
断ち切れない父との関係性
- 事件、保護
- これまでの経緯
- 離婚から再度同居へ
事件、保護
2023年2月9日、被害者は4年間に及ぶに鳩山町役場長寿福祉課、西入間警察署及び犯人からの嫌がらせの末、ひき逃げ事件に会う。被害者として東松山警察署に向かうが、事情聴取中に謎の警察による不当な保護をされる。
18時間東松山警察署の保護室に拘禁された挙句、2つの病院の措置入院判断を受け、最終的には開放される。
これまでの経緯
その事件に至るまでには経緯がある。
幼少期から父親のDV、パワハラ、モラハラを受けてきた。そして成人し、結婚してからもパワハラ、モラハラは続いた。一時同居したが、結果1年で同居生活は破綻し、元妻の実家へ転居することとなる。
離婚から再度同居へ
さらに元妻の実家から転勤の都合で横浜へ転居するが、ここで元妻及び元妻両親と揉める。離婚話となるが、一番関わってほしくなかった父を母が連れてきた。結局元妻と子供たちと別居する。
結果的に元妻とは離婚することとなるが、ここで被害者は「これ以上自分の人生を父に左右されたくない」という思いから、すでに会社から近い場所でアパートを探していた。
そこに母の「家に帰って来なさい。そういうことはもう2度とないから」。被害者はこの発言に当然父とのコンセンサスが取れているものと考えた。後に結果的に実家に帰っても同じような問題が起こったことを考えると、コンセンサスが取れていたわけではないだろうことを知る。
母のその言葉を信じて、被害者は実家に戻った。そして今度こそはどんなことがあっても家から出ていかないと心に決めたのだ。それが今の状況になっている。
断ち切れない父との関係
- 事件と不当な保護
- 家庭内で続く支配
- 離婚と再同居の経緯
事件と不当な保護
2023年2月9日、この家庭において、長年にわたる父の支配と外部からの圧力の中で、ついに大きな事件が発生した。この家庭の一員は、4年間にわたる役場や警察署、さらには特定の人物からの執拗な嫌がらせの末、ひき逃げ事件の被害に遭った。負傷した状態で東松山警察署に赴き、被害者として事情を説明していた最中、突如として警察による不当な保護を受けることとなった。この家庭の一員は何の前触れもなく18時間にわたり保護室に拘禁され、2つの病院で措置入院の判断を受ける事態となる。最終的には開放されたものの、警察の介入により、事件の被害者であるにもかかわらず自由を奪われるという矛盾した状況に置かれた。なぜこのような事態が起こったのか、それは家庭内の長年の支配構造と無関係ではない。この事件の背景には、父親の強権的な影響力があり、さらに地域社会の一部の人間がその支配に加担する形で、この家庭の一員を孤立させようとした構造がある。この出来事が象徴するのは、単なる事故や誤解ではなく、この家庭の中で続く長年の圧力と抑圧の結果であった。
家庭内で続く支配
この家庭における父の影響力は、単なる親子関係の枠を超えていた。幼少期から続く暴力、言葉による支配、そして精神的な圧迫は、大人になってからも続いた。結婚して家庭を持った後も、父の影響は消えることなく、一時的に同居することになった際には、わずか1年で関係は破綻した。父は絶えず力関係を維持しようとし、その場にいる全員を支配しようとする姿勢を崩さなかった。この支配の構造は、単なる家族間の意見の対立ではなく、父が家庭のすべてを自らの支配下に置こうとすることによって生じる問題であった。その影響は結婚生活にも及び、最終的に夫婦関係の破綻をもたらすこととなる。父の存在が関係の維持に影を落とし、夫婦間の意思決定にまで干渉し続けた結果、家庭内での生活は次第に耐え難いものとなった。この家庭の一員は、父の支配から逃れるために距離を取る選択をしたが、結局のところ、それは一時的なものに過ぎなかった。
離婚と再同居の経緯
離婚を決意したこの家庭の一員は、元妻の実家から転居することとなったが、そこでも新たな問題が発生した。転居先の横浜で元妻およびその両親と衝突し、離婚の話が持ち上がった際、最も関わってほしくなかった父が母によって呼ばれることとなった。この結果、元妻と子供たちとは別居することとなり、最終的には離婚が成立した。その後、この家庭の一員は自らの意志で会社の近くにアパートを探し、新たな生活を始めようとしていた。しかし、母からの「家に帰ってきなさい。そういうことはもう二度とないから」という言葉に動かされ、実家に戻ることを決意する。しかし、それは父とのコンセンサスが取れた上での決断ではなかった。結果的に、実家に戻った後も同じような問題が繰り返されることになった。この家庭の一員は、今度こそ家を出ることなく、そこで生き抜くことを決意したが、その選択は必ずしも自由への道ではなく、新たな戦いの始まりであった。
関連する法令
- 刑法第204条(傷害罪)
- 刑法第208条(暴行罪)
- 刑法第223条(強要罪)
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法第223条(強要罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
警察の保護権限とその濫用の実態
- 警察官職務執行法第3条の適用と問題点
- 民事不介入原則と警察の介入の矛盾
- 法的保護制度の機能不全とその影響
警察官職務執行法第3条の適用と問題点
警察官職務執行法第3条は「自己若しくは他人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するために緊急の必要があるとき」に警察官が保護措置を講じる権限を認めている。しかし、この条文の解釈と運用には大きな問題がある。本来、危険の存在は客観的に認められなければならないが、実際には主観的な判断に依存しやすく、警察の裁量が大きすぎる。その結果、正当な理由なく市民が拘禁されるケースが発生している。例えば、本件では当事者がひき逃げの被害者として警察署を訪れたにもかかわらず、保護の名目で18時間も拘禁された。これは「危険が存在する」との一方的な判断によるものであり、警察権限の濫用に該当する可能性がある。刑法第220条(逮捕監禁罪)は「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は3月以上7年以下の懲役に処する」と規定しており、適切な手続きなしに拘禁を続けた場合、警察自体がこの罪に問われる可能性がある。
民事不介入原則と警察の介入の矛盾
日本の警察は民事不介入の原則を掲げており、民間の争いには関与しないとされている。しかし、実際には一方の当事者の主張を根拠に介入する例が後を絶たない。例えば、本件では父親の主張が一方的に受け入れられ、行政や警察が当事者を排除しようとする動きがあった。これは実質的に民事介入にあたる行為である。刑法第223条(強要罪)では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせた者は3年以下の懲役に処する」と定められている。警察が一方的な判断で住居からの退去を促すなどの圧力をかけた場合、この強要罪に該当する可能性がある。警察が本当に民事不介入を貫くのであれば、どちらか一方の主張に基づいた対応をすべきではないが、現実には「介入する場合」と「しない場合」を恣意的に使い分けている実態がある。
法的保護制度の機能不全とその影響
本来、法律は弱者を保護するために機能すべきであるが、現実には制度が形骸化しており、むしろ権力が恣意的に運用される原因となっている。刑法第204条(傷害罪)では「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている。仮にDVや暴力が行われていた場合、本来であれば加害者に適用されるべき法令であるが、本件では警察が適用せず、むしろ被害者が保護の名のもとに拘禁されるという逆転現象が発生した。さらに刑法第208条(暴行罪)は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」としており、暴行があったにもかかわらず警察が取り合わない場合、それは権力による黙認とも言える。こうした制度の機能不全が続く限り、被害者が救済されず、加害者が放置される状況が続くことになる。
警察による「保護」の名目と社会的排除の実態
- 行政・警察の裁量と「保護」の悪用
- 民事不介入の原則と現実の矛盾
- 社会的孤立と国家権力の介入
行政・警察の裁量と「保護」の悪用
警察官職務執行法第3条は「自己若しくは他人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するため」に警察官が保護措置を講じる権限を与えているが、この裁量が広すぎることが問題視されている。本来ならば、現実的な危険性が認められる場合に限定されるべきだが、警察の主観的な判断で恣意的に適用され、結果として「保護」と名付けられた強制的拘禁が発生するケースが後を絶たない。今回の事例では、ひき逃げ被害者として警察署を訪れたにもかかわらず、被害者が18時間もの間、保護室に拘禁されるという矛盾が生じている。これは「現実的な危険が存在する」という一方的な解釈によってなされたものであり、警察権限の濫用とみなすべき事例である。さらに、刑法第220条(逮捕監禁罪)では「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は3月以上7年以下の懲役に処する」と定められており、適切な手続きがないまま長時間の拘禁が続いた場合、警察自体がこの罪に該当する可能性がある。こうした事例は全国的に見ても少なくなく、「保護」と称して実際には社会的排除が行われていることが問題視されている。
民事不介入の原則と現実の矛盾
日本の警察は原則として民事不介入を掲げているが、現実にはこれが恣意的に適用されることが多い。本来、民間人同士の争いに警察が介入することは制限されるべきだが、特定の一方の意見のみを根拠に介入し、結果的にもう一方の権利を侵害するケースがある。本件では、父親の主張が一方的に受け入れられ、行政や警察が当事者を社会から排除しようとする動きが見られた。これ自体が民事不介入の原則に反する行為である。刑法第223条(強要罪)では「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人に義務のないことを行わせた者は3年以下の懲役に処する」とされているが、警察が一方的な判断で住居からの退去を迫ったり、拘禁を強行する場合、この条文が適用される余地がある。警察が本当に民事不介入を徹底するのであれば、一方の言い分だけをもとに判断するのではなく、双方の主張を公平に検討すべきである。しかし、現実には「介入すべき場面では介入せず、介入すべきでない場面で積極的に関与する」といった恣意的な運用が続いている。
社会的孤立と国家権力の介入
日本社会において「家族」は強い結びつきを持つものとされているが、家庭内の権力構造がそのまま社会的な立場に影響を及ぼすことも多い。特に親子間の支配関係が行政や警察によって正当化される場合、被害者の社会的孤立が助長される結果となる。本件では、長年にわたる家庭内の問題が警察の関与によってさらに悪化し、行政の対応がむしろ当事者を排除する方向に進んだ。刑法第204条(傷害罪)では「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と明記されており、暴力があった場合には適用されるべきであるが、警察はこの適用を見送り、代わりに「保護」という名目で被害者を拘禁するという逆転現象が起きた。また、刑法第208条(暴行罪)では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」とされているが、実際には家庭内の支配が黙認されることで加害者が処罰を免れるケースが多い。結果として、社会的に弱い立場の者が救済されず、家族関係の名のもとに不当な扱いを受ける状況が続いている。
まとめ
父親との関係は幼少期からの影響が続き、成人後も支配と干渉が繰り返された。結婚後もその影響から逃れることはできず、家庭の決定にも父親が介入し続けた。離婚後、一度は独立を決意したものの、母親の説得を信じて実家へ戻ることとなり、結果的に父親との関係は再び固定化された。親子関係の中で権力の不均衡が長年続くことで、個人の意思や自由が奪われる状況が生まれ、家族の枠を超えた社会的な問題としても考えられる。この関係を断ち切るためには、心理的な支配構造の認識と、社会的なサポートの重要性が求められる。